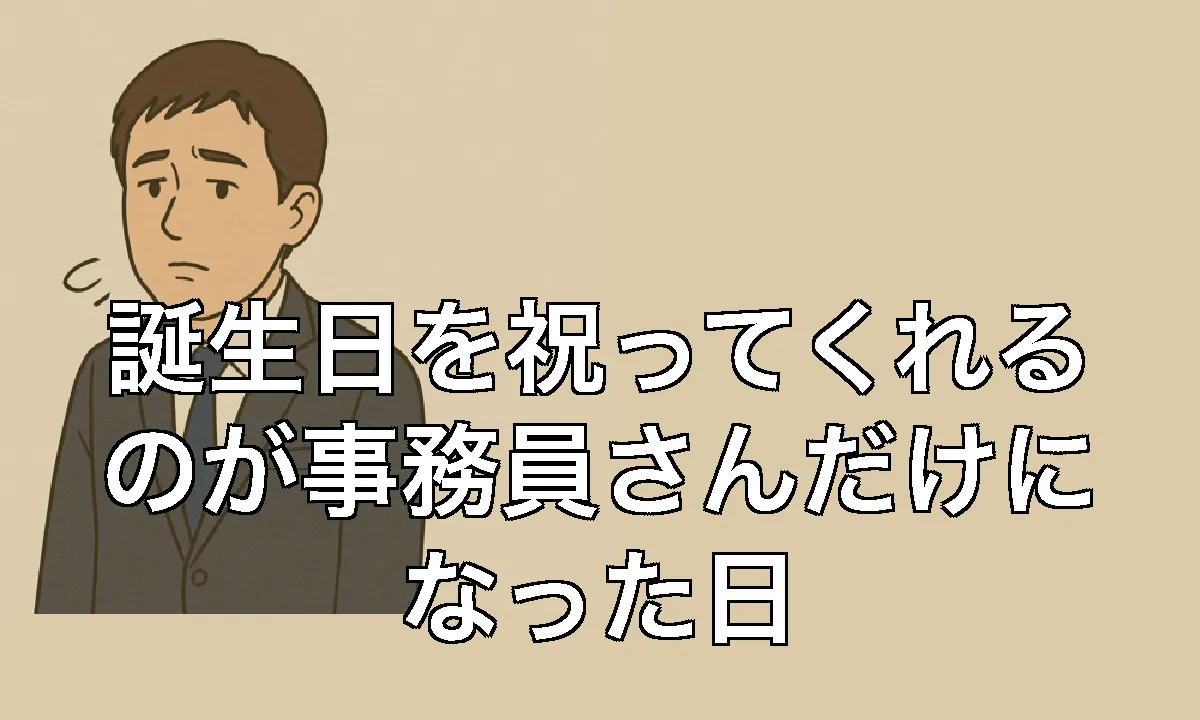誕生日に気づいたのは事務員さんだけだった
朝の出勤時、事務所のドアを開けたら「先生、お誕生日おめでとうございます」と言われた。正直、一瞬なんのことかわからなかった。カレンダーを見て「ああ、今日か」と思い出す始末。それくらい、自分の誕生日が特別な日ではなくなって久しい。でもその一言が、思った以上に心に染みた。誰にも祝われないと思っていたから、たった一人のその言葉が、妙に暖かく感じた。なんだか、自分がちゃんと“存在している”ってことを、少しだけ肯定された気がしたのだ。
おめでとうございますの一言が沁みた朝
その日、事務員さんは小さなコンビニのプリンと、100円ショップのリボンで飾られたメモ帳をプレゼントしてくれた。どちらも決して高価なものじゃない。でも、それがどれだけ嬉しかったか。家に帰れば誰もいないし、LINEも静まり返っている。SNSで繋がっているはずの人たちは、こちらの誕生日になど興味がない。だから、事務員さんのその小さな行動が、まるで心の中に小さな灯りを灯してくれたようだった。
ロウソクもプレゼントもないけれど
昔はケーキにロウソク立てて、誰かと笑っていた記憶がある。学生時代、野球部の仲間が誕生日を祝ってくれたあの夜。居酒屋で、先輩に無理やり日本酒を飲まされたことすら、今ではいい思い出だ。でも今は、ロウソクもないし、誰かと食べるケーキもない。食卓にはカップラーメンか、スーパーの半額弁当。誕生日だからといって何かが特別になるわけじゃない。だけど、心の片隅では「誰か祝ってくれないかな」と期待してしまうのが人間なのだ。
気づいてくれる存在がいるだけで違う
人間って、誕生日を祝われるかどうかで、自分の存在価値を確かめている部分がある気がする。実際、誰にも祝われない誕生日は、自分が透明人間になったような気持ちになる。でも、たった一人でも「おめでとう」と言ってくれる人がいるだけで、「あ、自分はまだここにいていいんだ」って思える。それがたとえ形式的な言葉でも、やっぱりうれしい。事務員さんの存在が、そんな心の支えになってくれている。
「誰かに期待する」のをやめたのはいつからか
昔は、もっと誰かに構ってほしかった。連絡が来るのを待って、メッセージの既読に一喜一憂していた。だけど、あるときから「どうせ誰も覚えてない」と、期待しなくなった。もしかすると、それは自分自身が人との距離を取ってしまった結果かもしれない。仕事にかまけて、休日も一人。そんな毎日を積み重ねていたら、自然と“祝ってくれる人”がいなくなっていた。
同級生のグループLINEは静か
高校の野球部のグループLINEはまだ残っている。けれど、最近は連絡も滅多に来ないし、誰かの昇進や子どもの誕生日の報告が流れてくるばかり。自分の誕生日に「おめでとう」の一言が来ることなんて、もう何年もない。誰が既婚で、誰がマイホーム建てて、そんな話ばかりの中、自分だけが取り残されているような気がする。既読スルーされる自分の存在は、やっぱり薄れているのだ。
元カノからの通知なんてもう来ない
昔付き合っていた人から、誕生日だけは毎年連絡が来ていた。たとえ終わった関係でも、その一言があるだけで、心が少しだけあたたかくなったものだ。でもその人も、もう結婚して子どももいるらしい。そんな通知はもう来ないし、自分のスマホは静まり返っている。通知が鳴るのは、せいぜいAmazonの発送連絡くらい。誰かに必要とされていない現実を、誕生日が改めて突きつけてくる。
事務員さんの気遣いに甘えてばかりかもしれない
事務員さんが気づいてくれるだけでありがたい。でも、それに甘えて、こちらからは何も返していない気がする。忙しさを理由に、感謝の気持ちすらちゃんと伝えていないかもしれない。それでも彼女は、朝早くから来て、事務所を支えてくれている。その姿を見るたび、自分は一体なにをしてるんだろうと、情けない気持ちになることもある。
コーヒーを淹れてくれるその手間を想像する
冬の朝、冷えた事務所に入ると、温かいコーヒーの香りが広がっていることがある。自分が席につく前に、湯を沸かし、コーヒーを淹れてくれている。そんな些細なことに、どれだけ助けられてきたか。けれど、自分はそれにどれだけ報いているのか。少しの「ありがとう」を言いそびれて、そのまま日にちが過ぎていく。気づいたときには、気遣いに甘えすぎていたことに、後悔するのだ。
こちらからは何も返せていない現実
事務員さんの誕生日を聞かれたら、自信を持って即答できない。プレゼントを渡したことも、ケーキを用意したこともない。それなのに、自分は祝ってもらってばかりいる。ありがとうの言葉すら、まともに伝えられていない。なんだか、自分ばかりが受け取って、相手には何も渡せていない。そんな不公平が、この年齢になってようやく重たく感じられるようになった。
感謝の言葉もつい後回しにしてしまう
「ありがとう」って、タイミングを逃すと本当に言いにくくなる。忙しくて、疲れてて、その一言すら言えなくなる日がある。だからといって、心の中で感謝していれば伝わるわけじゃない。むしろ、言葉にしなきゃ何も伝わらない。気づいてはいるのに、つい後回しにして、気づけば一ヶ月も経っていたりする。そんな自分が、やっぱり少し情けない。
司法書士という仕事は祝ってくれる人が減っていく
開業して十数年。最初は、友人や親戚からも祝福の連絡が来ていた。開業祝いに花が届いた年もあった。でも、年数を重ねるにつれて、それは次第に減っていった。忙しくなった分、関係が薄くなった人も多い。自分からも連絡を取らなくなり、結局、誕生日すら誰にも気づかれなくなった。事務所という小さな世界に閉じこもって、少しずつ“誰かに祝われる存在”から遠ざかっているのかもしれない。
独立すれば自由だと思っていたあの頃
20代の頃、「自分の城を持てたら自由になれる」と思っていた。上司に頭を下げる必要もなく、好きなように仕事ができる。そう信じていた。でも実際に独立してみたら、仕事は増える一方で、休みもなく、責任もすべて自分。自由なんて幻想だった。自由の代わりに手に入れたのは、終わりのない孤独だった。誰かと喜びを分かち合う時間も減っていった。
それでもこの仕事を続ける理由
そんな誕生日を過ごしても、結局次の日にはまた登記の準備に追われている。クライアントのこと、事務所のこと、やるべきことは尽きない。それでも、この仕事を続けているのは、どこかで「自分にもまだ役割がある」と信じたいからだと思う。誰かの人生の一部に関われることは、やっぱり小さな誇りだ。
誰かの役に立っているという実感
相談に来た方の不安な顔が、最後には少し笑顔になる。そんな瞬間に、ふっと報われた気持ちになることがある。登記なんてただの手続きかもしれない。でも、そこには人の想いや生活が詰まっている。そんな一つひとつに関われることが、続ける理由になっている。祝ってくれる人は少なくなったけど、誰かに感謝される場面は、まだちゃんと残っている。
忙しさの中にある小さな達成感
山のような書類に囲まれて、「もうダメだ」と思うこともある。でも、その一つを片づけ終えたときの、静かな達成感がたまらない。誰にも見られていないけど、自分だけはちゃんと知っている。「今日も一日、やりきった」と思える瞬間が、次の日の力になっている。地味で派手さはないけれど、そんな日々の積み重ねが、たぶん今の自分を支えている。
「ありがとう」の一言に救われる日もある
どんなに疲れていても、「助かりました」「ありがとうございます」と言われると、それまでの疲れが少し軽くなる。誕生日に誰も祝ってくれなくても、仕事の中で感謝されることがある。事務員さんの「おめでとう」も、依頼者の「ありがとう」も、どちらも心に染みる言葉だ。結局のところ、人は誰かの言葉に救われながら生きているのかもしれない。