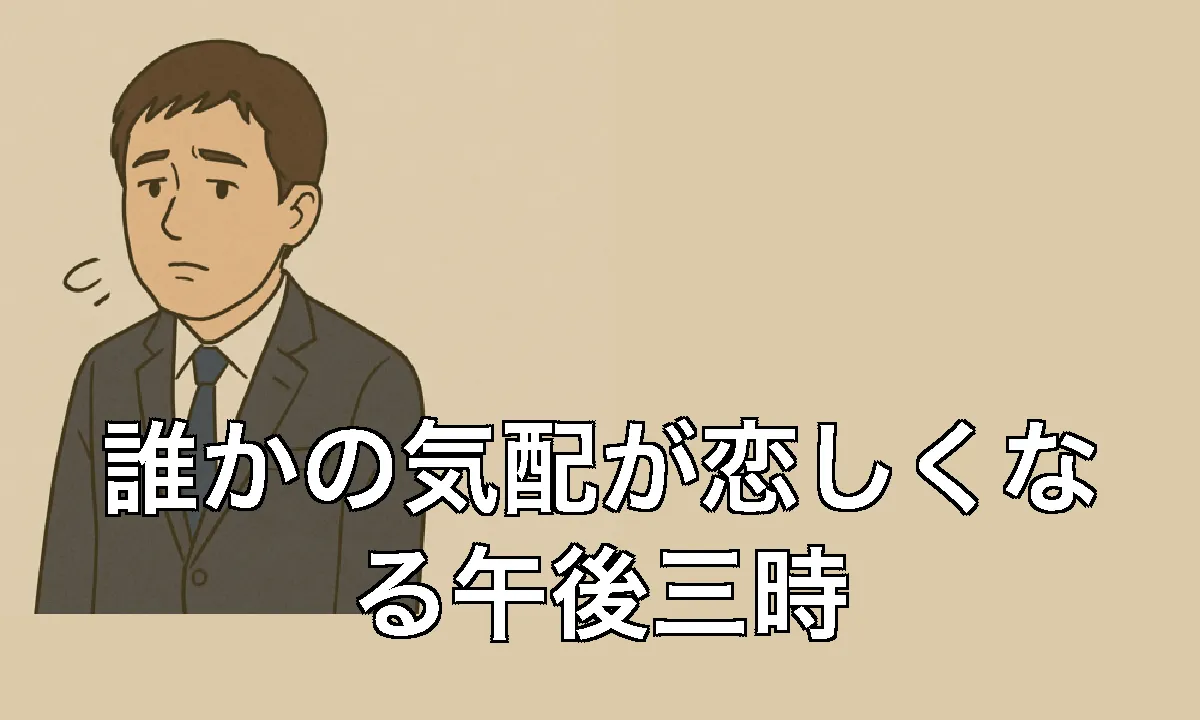静まり返る午後にふと思うこと
午後三時。ふと時計に目をやると、事務所には自分しかいないという事実が、妙に胸にのしかかる時間帯だ。昼休憩も終わり、電話も鳴らず、来客もない。そんな静けさが日常になりすぎて、逆に少し怖くなることもある。まるで図書館の閉館間際のように、音を立てることが悪いことのような空気が漂う。ここに誰か、たった一人でもいてくれたら、と思う瞬間が何度もある。
電話も鳴らない静寂の時間
仕事に集中できる環境というのは、ある意味ではありがたい。しかし、何も音がしない空間というのは、集中よりも孤独を感じさせる。電話が鳴れば少し気が紛れるし、お客様の声が聞こえれば、自分が「社会とつながっている」ことを実感できる。だが、そういった音が一切ない日は、まるで無人島に漂着してしまったような心細さがある。
プリンターの駆動音にすら安堵する
この静寂の中で、唯一安心できるのがプリンターの動作音だったりする。書類を印刷する「ウィーン」という音が聞こえると、少しだけ心がほぐれる。誰もいない部屋に自動で紙が吐き出される様子は、まるで機械が話しかけてくれているような錯覚すら覚える。そんな音に安堵している自分に気づいたとき、ちょっと切なくなるのだ。
カップ麺のお湯を注ぐ音が生活音になる
昼ごはんも独り。事務所の給湯ポットでお湯を注ぎ、カップ麺に注がれる音が「人間らしさ」の音に思えてしまう。ぐつぐつ鳴る音が、誰かと生活している感覚をかすかに与えてくれる。実家にいたころ、母が台所で立てていた音を思い出す。あの頃は、生活音なんて気にも留めなかったのに、今はそんな音にすら救われている。
誰とも喋らず終わる一日への虚しさ
特に忙しい時期が終わった直後は、ぽっかり穴が空いたように感じることがある。一人で業務をこなし、誰とも話さず一日が終わる。家に帰ってもテレビが喋るだけ。そんな日々が続くと、ふと「自分って本当に生きてるんだろうか?」と問いかけたくなる。喋ることのない一日は、どこか色のない白黒テレビのように感じるのだ。
事務所に人がいるという安心感
人がいる空間には、安心感がある。別に会話をしなくても、誰かの気配があるだけで、自分が「一人じゃない」と思える。以前、事務員さんが在籍していたころのことを思い出す。あの頃は、同じ空間にもう一人いてくれるだけで、仕事の疲れも少し和らいでいた。今思えば、それがどれだけありがたいことだったか身にしみる。
以前いた事務員の思い出
数年前に一緒に働いていた事務員さんは、明るくて、細かいところに気がつく人だった。朝「おはようございます」と声をかけられることが、どれだけ嬉しかったか、今ではその声が耳に残っている。ちょっとした雑談や、仕事終わりの「おつかれさまでした」が、当時は当たり前すぎて気づかなかったけれど、実はものすごく大事なことだった。
おはようございますの価値を噛みしめる
「おはようございます」たった一言の挨拶でも、人間関係があることを確認できる魔法の言葉だ。今の事務所では、朝来て自分がスリッパに履き替え、無言でパソコンを立ち上げるだけ。鏡に映るのも自分だけ。朝から誰とも目を合わせないまま一日が始まると、妙に体が冷える気がする。「おはよう」の一言で、室温が2度上がるような気がするのだ。
挨拶ひとつが生む空気の温度
人の声がある空間は、体温だけじゃなく心の温度も保ってくれる。挨拶を交わすことで、お互いの存在を認識し、孤独の膜が破れる。「いってきます」と言えば、「いってらっしゃい」と返ってくる。そんなやりとりがない今、日々の仕事がまるで無音の作業ゲームのように感じてしまう。感情がフラットになるのが、いちばん怖い。
誰かが座っているだけで違うもの
何も話さずに、ただ隣に人が座って仕事をしている。それだけで、部屋の空気はまるで違って感じる。キーボードを打つ音、書類をめくる音、椅子のきしむ音。それらがすべて、人間がここにいるという証明になる。仕事の効率うんぬんではなく、「一緒にいる」という事実が、これほどまでに大きいとは思わなかった。
退勤のおつかれさまが沁みる理由
一日の終わりに「おつかれさまでした」と言える相手がいるだけで、その日が報われた気がする。帰り際のひとことが、今日という一日の終わりをちゃんと実感させてくれる。今はそれがない。パソコンを閉じ、電気を消し、ひとりで事務所の鍵を閉めるとき、なんとも言えない空虚さが襲ってくる。「おつかれ」と言いたい相手がいない、それがいちばんこたえる。
誰かと働くという小さな希望
とはいえ、誰かと一緒に働くには、それなりの準備と勇気がいる。雇用には責任が伴うし、人間関係のリスクもある。でも、だからといってずっと一人で仕事をするのが正解かといえば、それもまた違う気がする。完璧な人材を求めすぎず、「一緒にいてくれるだけでありがたい」と思えるような関係性を、もう一度築いてみたい。
まずは半日からでもいいかもしれない
フルタイムでがっつり働いてもらうのは難しくても、週に数回、午前中だけでも誰かと一緒にいられたら、それだけでだいぶ違う。面接だって、堅苦しいものにせず、「一緒に雑談しながら決めましょう」くらいの気持ちで構えた方がいいのかもしれない。心のぬくもりを求めるなら、こちらも心を開いていく準備を始めるべきなのだ。
完璧な人材ではなく一緒にいられる人
求めているのは、スキルでも経験でもない。ただ、ここで一緒に机を並べていてくれる人。雑談に笑ってくれる人。たまにお茶を淹れてくれる人。そんな「存在」があるだけで、日々の事務所は確実に変わる。人のぬくもりというのは、温度や言葉だけでなく、「そこにいる」ということ自体に宿るものなのだと思う。
能力よりも相性と温度感
効率や成果を追い求めるよりも、自分と合う人と働く方が長続きする。それは、元野球部だったころの感覚にも近い。ポジションの上手い下手よりも、ベンチで冗談を言い合える奴と組んでいた方が、試合の緊張も和らいだものだ。司法書士事務所もある意味、チーム。一緒にいることが楽でいられる、そんな人と出会いたい。
無理しない雇用のかたちを探る
社会保険のこと、給与のこと、業務の切り分け…雇うって考えると大変なことばかり思い浮かぶけれど、最初からフル装備を目指す必要はない。業務委託でも、アルバイトでも、自分にとっても相手にとっても無理のない形で、まずは始めてみる。失敗してもまた考え直せばいい。完璧な体制なんて、誰も最初から持ってないのだから。
ぬくもりは贅沢ではなく必要なもの
ひとりで黙々と仕事をこなすことに慣れてしまった今だからこそ、もう一度人のぬくもりを思い出したい。それは決して「贅沢な願い」なんかじゃない。人間として、ごく自然な感情なのだと思う。人の気配があることが、こんなにも安心をくれるのだから。午後三時、誰かの笑い声が聞こえる日が、またいつか訪れることを願っている。