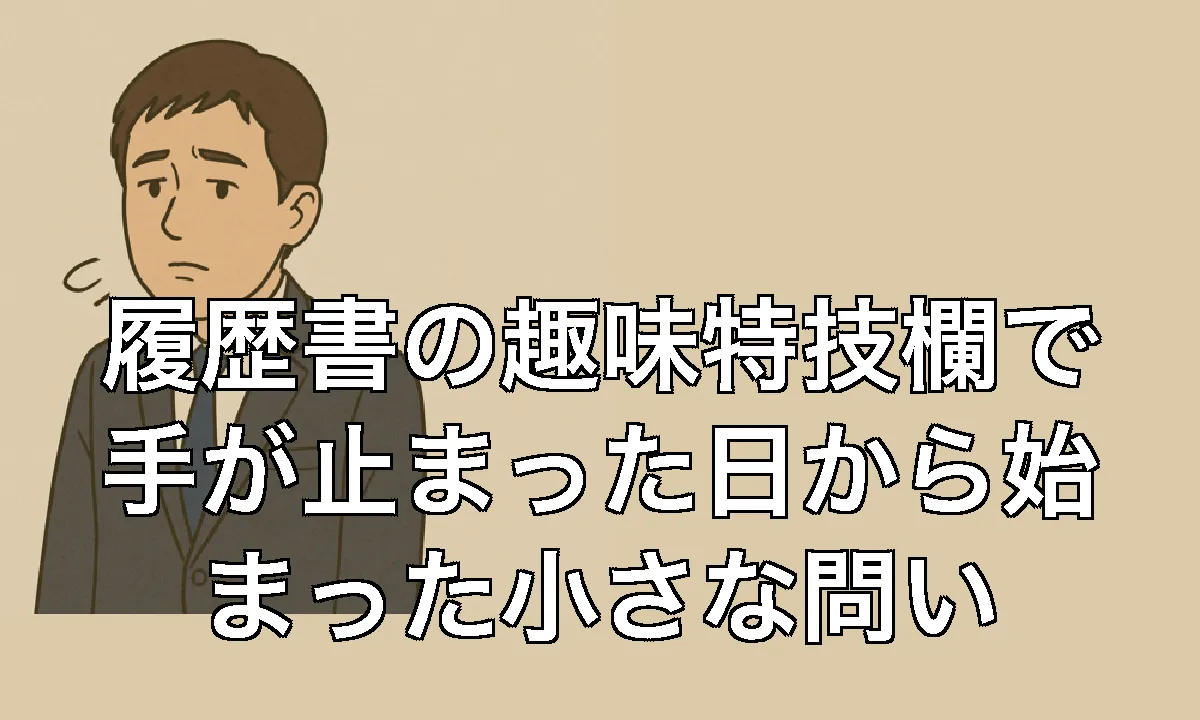履歴書と向き合ったあの静かな夜
あれは確か、司法書士試験に合格したあと、最初に就職活動を始めた頃だった。履歴書を書くために一人で深夜の自室に座り、ペンを手に取ったまま動けなくなった。「趣味・特技」の欄を前に、思いのほか長い沈黙が訪れた。真面目に見られたいけど、盛りすぎも嘘っぽい。でも何も書かないのも気が引ける。そんな葛藤に包まれながら、自分は一体何が好きで、何が得意なのかを自問し続けた。あの夜は単に履歴書を書く時間ではなく、思いがけず“自分を見つめ直す時間”だった。
何も書けない自分にじわじわと焦りがにじんだ
そのとき私は、驚くほど自分のことを知らなかった。資格の勉強には時間をかけてきたが、自分の「好きなこと」や「得意なこと」にはほとんど目を向けてこなかった。周りの友人たちは「料理」とか「映画鑑賞」とか、サラッと書いていたけれど、私はそれがうまくできなかった。どれも中途半端で、特別と言えるものがない気がして。履歴書の一欄が、こんなにも自分の空白を炙り出すものだとは思いもしなかった。書けないことに焦り、恥ずかしさを覚えた夜だった。
普通であることがこんなにも空っぽに感じた
「これといって趣味も特技もありません」。それをそのまま書くわけにはいかないと、思えば思うほど、何も書けなくなる。でも実際、毎日仕事や勉強に追われて、趣味に没頭する時間なんてなかったのだ。特別じゃない毎日を積み重ねる中で、誰かに誇れるような「何か」を持っていなかった自分。普通であることが、こんなにも自分の無個性を突きつけてくるとは思ってもみなかった。書けないというより、「自信がない」から書けない、という方が正しい感覚だった。
過去を振り返っても「これ」と言えるものがなかった
学生時代を思い返してみても、思い出されるのは部活と受験勉強ばかりだった。確かに野球部には所属していたし、ポジションはセンターだった。でも特別うまかったわけでもないし、補欠になったこともある。それに、「野球」と書いたところで、相手にどう思われるのかも不安だった。結局「これは趣味とは言えないな」と自分で却下する始末。自分の中で何かを誇ることができないというのは、履歴書を書く以上に、自尊心に静かに刺さる時間だった。
趣味も特技も人並みだった元野球部の視点
元野球部、とはいえ社会に出てから何かに活かされたこともないし、今では球を握ることもなくなった。かつての自分の一部だった活動も、ただの過去になってしまっていることに気づいたとき、少し寂しさも感じた。履歴書には、今の自分が書かれる。過去の肩書きや部活歴すら、「今の自分」と切り離されるような感覚になった。だからこそ余計に、何を書けばいいのかわからなくなったのだろう。
部活が終わったあとの空白の時間
部活を引退した高3の夏。そこから受験勉強に没頭したが、ふと手が止まるときはいつも「俺って何が好きなんだっけ」と思った。友人がゲームやアニメに夢中になる横で、私は特に何かに没頭することもなく、ただ淡々と毎日を消化していたような気がする。だからなのか、大学でも社会人になっても、明確な趣味を持てずにいた。「趣味のある人=余裕のある人」という印象があり、自分にはその余裕がなかったのだと思う。
「ただの好き」じゃダメなんだろうかという疑問
たとえば、YouTubeで野球の名場面を見るのは好きだ。でも「趣味」と書くには曖昧すぎる気がして書けなかった。「ただの好き」と「履歴書に書くほどの趣味」の間には、何か越えられない壁がある気がしていた。でも、今思えば、好きという気持ちがあるだけでも十分だったのかもしれない。「ちゃんとした趣味じゃないとダメ」と思い込んで、自分の小さな好きすら否定していたことに気づくと、あの頃の自分に「それでいいんだよ」と声をかけたくなる。
司法書士になった今でも続くあの空欄の呪い
司法書士として独立した今でも、自己紹介のたびに「趣味は何ですか?」という問いに詰まる自分がいる。お客様との雑談でもそうだし、事務員さんとの雑談でもそう。履歴書のあの欄はもう必要なくなったけれど、「趣味や特技がある人間」という社会の暗黙の基準は、今もなお自分にプレッシャーを与えてくる。司法書士としての実績よりも、ちょっとした人柄の方が大事にされる場面もあり、そのたびにまた「何か書けたらよかったのに」と思ってしまう。
事務員さんに「先生の趣味って何ですか」と聞かれたとき
ある日、事務員さんに「先生って趣味とかあるんですか?」と聞かれた。特に悪意のない雑談だったのは分かっているけれど、なぜかドキッとした。「うーん、特には…」と曖昧に答える自分に、情けなさが込み上げた。事務員さんは笑って「そうですよね、忙しいですもんね」とフォローしてくれたけれど、心の中では「忙しいから何もないって、ただの言い訳じゃないか?」と自分を責めていた。大人になっても、あの空欄の呪いは続いていた。
答えられないことで気づく自己紹介の苦手さ
趣味が言えないだけで、なぜこんなにも自己紹介が苦手になるのか。ふと考えると、それは自分という人間を言葉で語る訓練をしてこなかったからかもしれない。業務のことは話せても、自分のことになると急に言葉が出てこない。これはたぶん、司法書士に限らず、仕事一筋でやってきた人には多い悩みなんじゃないかと思う。自分の好きなことを言葉にできる人は、それだけで魅力的に見える。でも、自分にはその武器がない。それがコンプレックスにもなっていた。
お客さんの履歴書を見て思ったこと
相続や会社設立の手続きなどで、お客様から履歴書や経歴書を見せてもらうことがある。その中には、正直「えっ、これ趣味なの?」と思うような内容もあった。でも、それがまた良かった。ガーデニングとか、バイクツーリングとか、犬と遊ぶこととか。人それぞれの「好き」が詰まっていて、書いてあるだけで少しだけ人となりが見える。私は、それを見て「ちゃんとした趣味」じゃなくても、胸を張って書ける人になりたかったのだと、改めて思った。
「自分らしさ」って他人の言葉で語れない
履歴書の趣味欄は、実は“他人からどう見られたいか”を反映しやすい欄でもある。でも、それって結構しんどい。誰かの評価を気にして、ありもしない趣味を書いてみても、あとで自分が疲れるだけだった。結局のところ、自分らしさというのは他人の評価基準では語れないし、語る必要もない。今ではそう思えるけれど、当時の私はそれが分からなかった。だから、何も書けずにペンを握ったまま時間だけが過ぎていった。
もしもあの欄に本音を書けるなら
もし今、あの履歴書をもう一度書けるなら、きっと違うことを書くと思う。たとえば、「日々の業務に愚痴を言いながらも何とかこなすこと」とか、「一人事務所で毎日サバイバルしてること」とか。そんなのは趣味でも特技でもないかもしれないけれど、それが今の自分を一番表している気がする。人に誇れるようなことじゃなくても、自分の中で続けていることには、やっぱり意味がある。そう思えるようになったのは、やっぱり司法書士として生きてきたからかもしれない。
愚痴ること、耐えること、仕事を続けること
趣味ではないけれど、私の特技は「続けること」だと思う。文句を言いながらも、事務所を閉めることなく、地味にやってきた。大したことじゃないかもしれないけれど、同業の知り合いが辞めていく中で、自分はまだここにいる。それって、ある種の能力じゃないだろうか。誰かに語れるような立派な趣味がなくても、日々を積み重ねることができる。それが私の誇りかもしれない。
司法書士としての自分の「特技」はなんだろう
派手さはない。でも、地味な書類を確実に処理し、面倒なお客様にも誠実に対応する。それを毎日続けている自分を思うと、「これこそ特技じゃないか」と思うようになった。趣味はわからなくても、仕事をする姿勢や心構えは自分らしい。誰かの履歴書には書かれないような部分に、自分の「強み」があることに気づいた。そう思えるようになっただけでも、あの空欄と向き合った価値はあったのかもしれない。
それでも毎日やっていることが自分の一部になる
結局、人って「毎日やってること」が自分の一部になっていく。私は司法書士という仕事を毎日続けている。それだけで、もう十分じゃないかと思えてきた。履歴書の「趣味・特技」欄に詰まったあの夜も、いま振り返れば、自分を形作る大事な一歩だった。特別な何かがなくても、続けることに意味はある。これを読んでいる誰かが、「自分には何もない」と感じていたら、まずは続けていることを大事にしてほしい。きっとそれが、あなただけの特技になる。