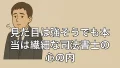一人きりの時間が多すぎると心が沈むこともある
司法書士の仕事は、一見すると静かな環境でコツコツと進めるのが理想だと思われがちだ。しかし、現実にはその「静けさ」がじわじわと心に堪えてくる日もある。朝から晩まで、事務所の中には時計の秒針の音と自分のキーボードを叩く音しか聞こえない。集中はできるけれど、ふと気を抜いた瞬間に襲ってくる孤独感。特に忙しさの波が過ぎた後の、ぽっかり空いた時間にそれはやってくる。誰とも話さずに一日が終わると、なんとも言えない虚しさが残る。
静けさは集中には向いているが
静かな環境は書類作成や登記の細かい確認には最適だ。誰にも邪魔されず、依頼者の人生の節目に関わる大事な仕事に集中できるという点では恵まれていると言える。でも、それが毎日続くとなると話は別だ。ふとした瞬間に、「この沈黙、今日もずっと続くのか」と感じてしまう。心の中でため息をつくことが、日に日に増えていく。
書類とにらめっこしているだけの一日
朝イチで不動産の登記申請書を作成し、次に相続の戸籍をチェックして、午後は商業登記の補正対応。黙々とこなしていくうちに、いつの間にか夕方になっている。頭はフル回転でも、心はどこか置き去り。まるで機械のように手だけが動いている感覚になる。目の前の仕事に没頭しながらも、ふと「誰かと会話したの、いつが最後だっけ」と思い出せないときがある。
電話が一本も鳴らない日もある
電話が鳴らないというのは、平和なようでいて、ある意味では不安になる。連絡が来ない=仕事が来ない。そう感じてしまうのは、小さな事務所を構える身としては避けがたい感情だ。音が鳴らない静けさの中で、ますます自分の存在が希薄に思えてくる。自分のやっていることに意味があるのかと、考え込んでしまう。
事務員がいても会話は少ない
ありがたいことに、事務員さんが一人いてくれる。でも、一緒にいるからといって会話があるとは限らない。お互いの役割はわかっているし、無駄なおしゃべりで仕事の邪魔はしたくない。そういう気遣いがかえって、静けさを強調してしまう。
相手に気を使いすぎてしまう自分
「いま声をかけたら迷惑かな」「何か話すネタあるかな」と考えているうちに、声をかけるタイミングを逃してしまう。特に年齢差や性格の違いがあると、なおさらだ。こちらとしてはフランクに話したいのに、相手に構えてしまわれたらどうしよう、と気にしすぎて結局何も言えない。気疲れだけが残っていく。
雑談一つにも遠慮が生まれる
雑談というのは、気楽なようでいて意外と難しい。たわいのない会話でも、タイミングや内容を誤ると空気が凍る。だからこそ、余計に話しかけづらくなってしまう。結局「何も話さない方が楽」と思ってしまい、沈黙が日常になる。でも、それが本当に楽なのかといえば、決してそうではない。
昼休みの沈黙が余計に堪える
仕事の合間にほっと一息つけるはずの昼休み。けれど、事務所の中は相変わらず静まり返っている。コンビニ弁当の包装を開ける音すら気を使ってしまうくらいだ。休憩なのに、気持ちは全く休まらない。むしろ、孤独感がより濃くなる時間帯だ。
コンビニ弁当と時計の針の音
チンという電子レンジの音と、カチャカチャという箸の音。そのほかは、ただ時計の針が進む音だけが響いている。誰かと一緒に「今日寒いですね」なんて他愛のない会話を交わせたらいいのに、と思いながらも口は動かない。ただ黙々とご飯をかきこみ、スマホを見るふりをして時間をやり過ごす。
ふと「何のために頑張ってるんだろう」と思う
お腹は満たされても、心はぽっかりと空いたまま。午前中に処理した案件の書類を思い出しても、達成感はあまりない。ただただこなした、という事実だけが残っている。そんな自分を「仕事は順調なはず」と励まそうとしても、納得はできない。「何のために頑張ってるんだろうなぁ」と、つぶやくことさえ虚しくなる。
テレビの音が恋しくなる午後
普段は気にならないテレビのワイドショーの音すら、恋しくなる。誰かが何かを話している、ただそれだけのことがありがたく思えてくる。自宅でテレビをつけっぱなしにしている人の気持ちが、ようやく分かってきた気がする。音があるだけで、なぜこんなにも気持ちが違うのだろう。
かつてのにぎやかな時間が懐かしい
昔のことを思い出すと、今の静けさとのギャップに愕然とする。特に高校の野球部時代、狭いロッカールームでわいわい騒いでいたあの時間が、今では夢のようだ。汗くさいけれど、あのときは孤独とは無縁だった。
野球部のロッカールームの騒がしさ
誰かが冗談を言えば、みんなが笑った。先輩に怒鳴られても、仲間がいるからこそ耐えられた。試合に出られずベンチで終わった日でも、帰り道にみんなで買い食いして笑って帰った。今のように、誰にも感情を共有せず一日を終えるなんて考えられなかった。
声を出して笑うことが減った
いつからか、声を出して笑うことが少なくなった。笑い声をあげる相手がいないし、そもそも笑うような出来事自体がない。テレビを見てクスッと笑うことはあっても、それは誰かと共感し合う笑いではない。感情の波が小さくなっていくのを感じる。
思い出話すら話す相手がいない
「昔はな…」と始める話も、相手がいなければただの独り言だ。野球の話、学生時代の失敗談、恋愛の苦い記憶。どれも誰かに聞いてもらいたい気持ちはあるけれど、話す場も相手もいない。それが一番しんどい。