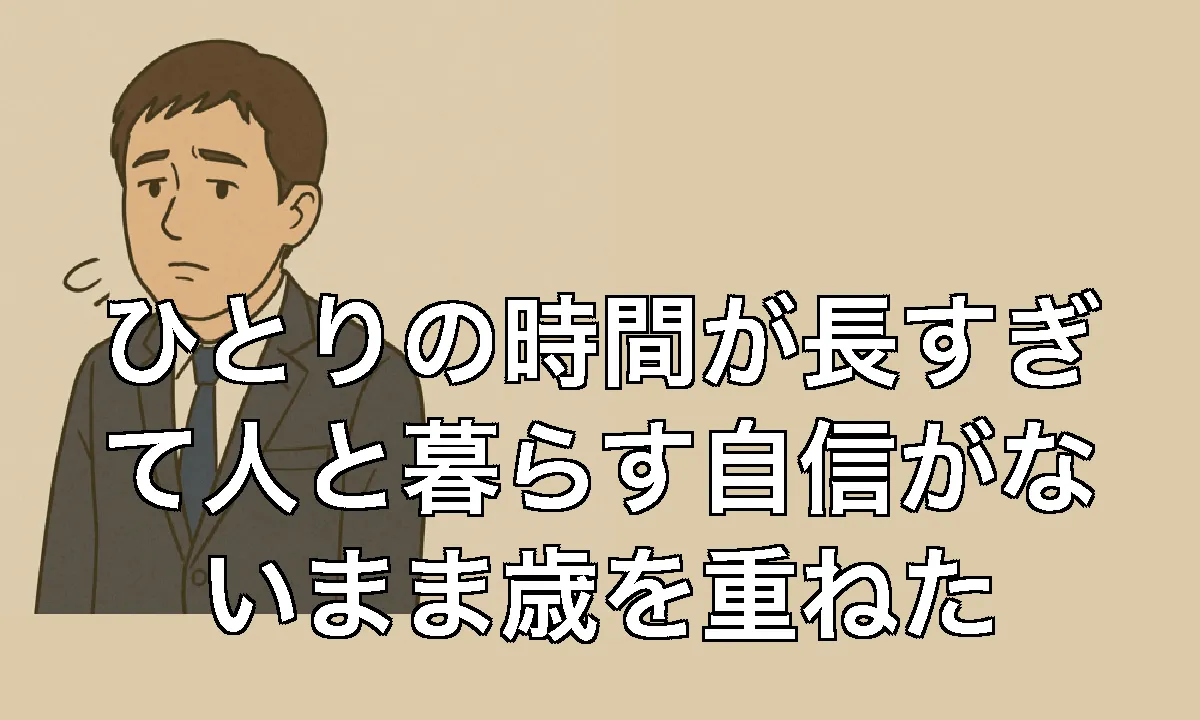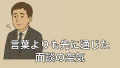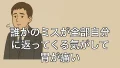人と暮らすという感覚を忘れてしまった
独身生活が長くなると、誰かと一緒に暮らすという感覚そのものが、遠い過去のものになってしまう。最初は自由を満喫していたはずが、気がつけば人との距離の取り方すら分からなくなっていた。司法書士という仕事はひとりで黙々と進める場面が多く、業務中の対話も形式的なものがほとんど。気を抜いた会話なんてここ数年、まともにしていない。そうやって少しずつ、自分だけの時間、自分だけの空間に慣れきってしまった。
「ただいま」に返事がない日常の安心感
家に帰って「ただいま」と言っても返事はない。でも、それが逆に安心だったりする。誰にも気を使わず、部屋着のまま冷蔵庫を開けて、テレビをつけて、気まぐれにビールを飲む。誰かと暮らしていたら、そうはいかない。「片付けてからにして」とか「今日の夕飯は?」とか、いちいち気配りを求められるかもしれない。それが面倒に思えてしまう。そんな風に思ってしまう自分に罪悪感を覚えることもある。でも、正直それが今の自分の“居心地のいい暮らし”なのだ。
誰にも気を遣わなくていいという自由
ひとり暮らし最大の魅力は、何よりも「気を遣わなくていいこと」。誰かの予定に合わせる必要もなければ、体調や機嫌を気にかける必要もない。これが本当に楽なんだ。たとえば、仕事帰りに急にラーメンが食べたくなったとしても、誰に気兼ねすることもなく直行できる。この自由を手放してまで、誰かと暮らす理由が見つからない。そう思いながらも、深夜に無音の部屋に戻ると、ふと空虚さに包まれることもある。
自分ルールが日常を支配していく
掃除のタイミング、洗濯の頻度、食事のメニューまで、自分ルールがすべてを支配している。誰にも否定されないし、正されることもない。だからこそ、この生活が長くなるほど、他人の存在が異物に思えてくる。学生時代の合宿のような共同生活は、今となっては想像すらできない。元野球部の頃は「風呂は15分まで」とか「食事は一斉に」なんてルールに従っていたはずなのに、それを思い出すだけで疲れてしまう。
気づけば会話のリズムが狂っていた
久しぶりに昔の友人と会って話すと、自分の言葉の間や反応が微妙にズレているのを感じる。相手が言葉を返す前に話をかぶせてしまったり、逆に間が持たず無言になってしまったり。以前は自然にできていた“会話のキャッチボール”が、今ではぎこちないピッチング練習のようだ。ひとりで過ごす時間が増えると、会話も鈍る。それは分かっていても、わざわざ会話の練習なんてしない。
話すという行為が少し怖くなっていた
電話が鳴ると、軽く身構える。誰からの連絡か、何を話せばいいのか、それを考える前に胸がザワつく。たとえ親しい人からでも、気軽なLINEで済めばいいのにと思ってしまう。話すことそのものが、少し怖いと感じている自分がいる。面と向かって相手と心を通わせるには、体力もいるし、気も遣う。そのハードルが年々高くなっている気がする。
沈黙のほうが落ち着くときがある
誰かと一緒にいて沈黙が続くと、「何か話さないと」と焦っていた若い頃。でも今は逆だ。沈黙のほうが落ち着く。喫茶店で黙ってコーヒーをすする時間。無言で事務所のデスクに向かう時間。そのほうがよっぽど楽だ。無理に言葉を紡ぐより、自分の中の静けさに身を委ねているほうが心地いい。もしかすると、これは人付き合いが下手になったというより、“人付き合いに疲れた”のかもしれない。
司法書士という仕事の性質も影響している
司法書士の仕事は一見「人と関わる仕事」に思われがちだが、実際はひとりで書類を整えたり、調べ物をしたり、パソコンに向かって黙々と作業する時間のほうが圧倒的に長い。お客様とは最低限のやり取りしかなく、それ以上踏み込むことは少ない。だからこそ、ひとりでいることに慣れてしまいやすい。これは業界全体に言えることかもしれない。
基本はひとりで完結する仕事
登記業務や相続関係の処理など、集中力を必要とする場面が多い司法書士の仕事。事務所内にいるときは、電話対応以外は完全に自分の世界に入っている。時折、事務員が声をかけてくることがあっても、つい「あとで」と返してしまう自分がいる。集中したい、邪魔されたくない。そんな意識が、ますます他人との距離を遠ざけているのかもしれない。
人と接しているのに心が開かれない
不動産業者や金融機関の担当者、お客様とは日々会話をしている。でも、それはあくまで業務の一部であり、心を通わせるような関係ではない。だから「人と接しているのに孤独」という感覚が拭えない。何気ない雑談や弱音を吐ける相手がいるわけでもなく、終業後に「今日はこんなことがあった」と言える人もいない。そういう積み重ねが、ひとりの時間をより当たり前のものにしていく。
それでも誰かと暮らしたい気持ちもある
ひとりが快適だと言いながらも、心の奥には「誰かと一緒にいたい」と思う気持ちもある。スーパーでふたり分の食材を買っているカップルを見ると、なんとも言えない感情が込み上げてくる。仕事が忙しく、孤独に慣れきってしまった自分にはもう手の届かないものかもしれないと思いながら、それでも“ちょっといいな”と思う瞬間がある。
コンビニの店員との会話が妙に嬉しい
「温めますか?」「袋にお入れしますか?」――それだけの会話なのに、妙にほっとする。名前も知らないコンビニ店員とのやり取りが、思いのほか心に染みる。人とのつながりがほとんどない日々において、そんな一瞬の会話が救いになることもある。自分はもう人と暮らせないんじゃないかと思いつつも、こうした瞬間に少しだけ“誰かと関わりたい”と思ってしまう。
たまに夢に出てくる「誰かの気配」
夢の中に見知らぬ女性が出てきて、隣に座って何かを話している。内容は覚えていないけれど、その「気配」だけがやたらとリアルで、目覚めた後の部屋の静けさに現実を突きつけられる。もう長い間、人と暮らしていないけれど、心の奥ではまだ誰かと一緒にいたいと思っているのかもしれない。そんな自分に気づいて、少しだけ切なくなる。
結婚だけが答えではないと分かっていても
誰かと暮らす=結婚という価値観がまだ根強く残っている。でも、本当に必要なのは「形」ではなく「関係性」なのかもしれない。無理に結婚という選択肢にしばられるのではなく、自分にとって心地よい距離感で人と関われる方法を見つけることが大事だ。そう頭では分かっているけれど、実際に動き出すのはやっぱり怖い。
人と暮らすこと=弱さを見せること
ひとりでいることに慣れすぎると、誰かに弱さを見せるのが怖くなる。「疲れた」「今日はしんどかった」と口にすることで、自分のバランスが崩れそうで避けてしまう。でも、本当はそういうことを分かち合える相手がいるからこそ、心は安定するのかもしれない。司法書士として強くあらねばならないと感じる日々の中で、自分の弱さに向き合うことが一番の課題かもしれない。
自立と孤独のバランスの難しさ
ひとりで生きる力を身につけることは大切だ。でも、それが行き過ぎると孤独に変わる。誰にも頼らず、誰にも頼られない関係性は、どこか寂しい。自立と孤独、そのバランスをどうとるか。それを模索する日々の中で、ふとした瞬間に「このままでいいのか」と自問自答している。きっと、それに明確な答えなんてないのかもしれない。