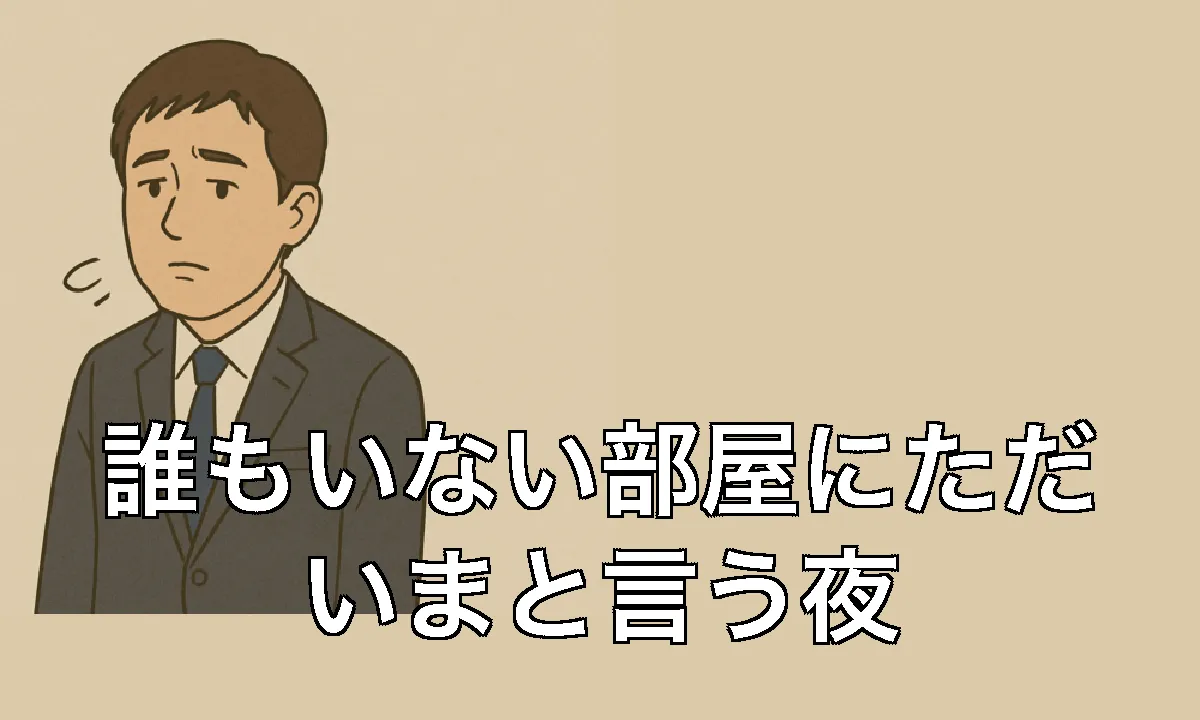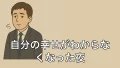仕事を終えて向かう先に誰もいないという現実
残業が終わり、事務所の明かりを落とすと、ふと気が抜けたようになる。もう夜の9時を回っている。事務員はとっくに帰宅し、近所のコンビニのレジすら他人行儀に思える。家に向かう道は、毎日通っているのに、どこか「寄りたくない」と思わせる空気がある。鍵を取り出して玄関を開けても、誰の声もしない。電気がついていないだけで、こんなにも寂しいのかと、自分でも驚くほどだ。
慌ただしい一日の終わりに押し寄せる静けさ
登記の締切に追われ、電話とメールの応対にぐったりする午後。それでもなんとか今日の案件を片付けて、やっと一息つく頃には、外はもう真っ暗だ。そんな日の帰り道、静けさが妙に身に染みる。繁華街のにぎわいもどこか遠く、誰とも話さないまま夜が終わるのかと、不意に虚しさがこみあげてくる。仕事で忙しいふりをしているが、心のどこかで「誰かに待っていてほしい」と思っているのかもしれない。
「もう帰っていいですか」と言う事務員との対比
夕方、「先生、今日はもう上がっていいですか?」と聞いてくる事務員の声に、いつも「もちろん」と答える。だが、心の中では少しだけうらやましい。彼女には帰る場所があるのだ。誰かが「おかえり」と言ってくれる場所が。その違いが、言葉にならない孤独として胸に残る。仕事をしている間は忘れていられるが、誰もいない部屋に帰ったとき、その差を痛感する。
帰宅途中に寄り道したくなる理由
たとえばスーパーに立ち寄って無意味に店内を歩いたり、コンビニで買わなくてもいいコーヒーを買ったりするのは、「誰もいない部屋にすぐに帰りたくない」という気持ちの表れだ。外にいる間はまだ“ひとり”じゃない気がしている。でも、レジを通過して店を出た瞬間、急に現実に引き戻される。寄り道は、ほんの少しでも「誰かと関わっている」気分になりたいための、ささやかな逃避行なのだ。
玄関を開けた瞬間の無音が心に刺さる
「ただいま」と小さくつぶやく声が、自分の耳にだけ届く。返事はない。無音の部屋がそこにある。電気をつけると、朝出たままの姿で部屋は沈黙を守っている。郵便受けに何か入っているか見てみるが、たいていはチラシか請求書。人とのつながりを求めたわけじゃないはずなのに、こうして何もないと、何かが欠けているような気がしてならない。
テレビもつけずに座り込む習慣
ソファに腰を下ろしても、テレビのリモコンには手が伸びない。音が鳴ると、かえって寂しさが強調されるような気がして、しばらく無音の中で座っていることが多い。携帯を見るのも億劫で、LINEは未読のまま。たまに母から「元気か」とだけ書かれたメッセージが来て、それに返信するのも何かが重たい。何も考えずにいる時間が、少しずつ心をすり減らしていく。
温かいごはんの匂いがしない夜
誰かが作ってくれた味噌汁の匂い、炊きたてのご飯、そんな記憶は遠い昔の話になった。コンビニ弁当を温めても、どこか「一人用」として用意された感が漂っていて、それがまた寂しい。せめて自炊でもすればいいのかもしれないが、気力が湧かない。食事は空腹を満たすだけの作業になり、楽しみにはならない。食べ終えた容器を無言で捨てる、その動作のひとつひとつが空しく感じる。
司法書士という仕事は、孤独とセットなのか
司法書士という職業は、想像以上に“ひとり”の時間が多い。もちろん人と会う仕事ではあるが、相談を受け、手続きをこなし、結果を出したあと、その感情を誰かと共有する場面は少ない。成果を誰かに褒められることもなければ、失敗を一緒に悔しがってくれる人もいない。淡々と、でも確実に責任を果たす。それがこの仕事の美学であり、同時に孤独でもある。
相談相手がいても心の中までは見せられない
お客様の相談に乗るとき、自分のことを語ることはほとんどない。相手に安心してもらうためには、こちらが“しっかり者”である必要があるからだ。心に抱えている不安や孤独を見せてしまっては、信頼が揺らぐように感じてしまう。結果的に、誰にも心のうちを明かせないまま一日が終わることになる。話すことで楽になるのに、それが許されない立場にもどかしさを感じる。
お客様に言われた「先生もおひとりなんですか」
ある日、相続の相談で訪れた中年女性に、世間話の延長で「先生もおひとりなんですか?」と聞かれた。何気ない一言だが、胸に刺さった。図星だからこそ、返す言葉に困った。「ええ、まあ」と笑ってごまかしたが、それがそのまま自分の現在地を突きつけてくるようだった。彼女は帰り際に「いい人、いないんですか」と続けてきたが、それに答える余裕すらなかった。
愚痴をこぼせる場所がない現実
事務員に仕事のことで愚痴を言うわけにもいかない。彼女には彼女の立場があるし、こちらのストレスをぶつけるわけにもいかない。結果、愚痴は自分の中で熟成され、重たくなっていく。仲のいい司法書士仲間も、遠方だったり忙しかったりして、頻繁には連絡できない。誰にも迷惑をかけず、でも誰かに甘えたい。そんな矛盾を抱えたまま、夜は更けていく。
元野球部仲間とのLINEが唯一のつながり
高校時代の野球部仲間とのグループLINEが、今でも細々と続いている。プロになった者はいないが、それぞれの人生で踏ん張っている。誰かが子どもの写真を送ってきたり、草野球の結果を報告したり、そんな何気ないやりとりが妙に救いになる。たまに「お前も来いよ」と言われても、仕事を理由に断ってしまう。でも、その誘いがあるだけで、まだ自分も誰かの記憶の中にいる気がして少し安心する。
仕事の話ができない飲み会は居心地が悪い
昔の友人と会っても、仕事の話ができないとどうしても浮いてしまう。「登記って何やってるの?」と聞かれても、説明するのが面倒で、「まあ地味な事務職みたいなもん」と答えてしまう自分がいる。本当は誇りを持っている仕事なのに、理解されないことが前提になっているから、つい自分から話を遮ってしまう。それがまた孤立を深めてしまっている気がする。
ひとりであることを否定しないで生きるという選択
誰かが待っている部屋がある人は幸せだと思う。でも、誰も待っていない部屋にも、自分なりの価値があるのかもしれない。静かな夜に自分と向き合う時間は、時に残酷だが、時に癒しでもある。誰もいないからこそ、誰にも気を使わずにいられる自由。寂しさと自由は、時として同じコインの裏表なのだ。
誰かが待っていないからこそ見える景色
夜の帰り道、住宅街の明かりや、団地の窓に映る家族の影を眺めながら歩くと、「ああ、自分は一人なんだな」と実感する。でもその一人であることが、逆に誰かの話をちゃんと聞ける力になっている気もする。司法書士という仕事は、相手の人生に深く関わる場面が多い。そのとき、自分が孤独だからこそ、誰かの孤独に寄り添えるのかもしれない。
夜の事務所に一人残って考える未来
事務員が帰ったあと、ひとりで事務所に残って書類を整理していると、不思議と落ち着く。机の上の蛍光灯だけが照らす小さな空間。誰にも邪魔されず、ただ仕事に没頭できる時間。結婚や家族があれば、きっとこういう時間は得られないだろう。寂しいけれど、だからこそ持てたものもある。その事実に、少しだけ救われる。
同じように頑張る人へ届けたい言葉
このコラムを読んでくれている人の中にも、似たような夜を過ごしている人がいるかもしれない。孤独や不安を抱えながら、それでも仕事を続けている。そんなあなたに言いたい。「自分だけじゃない」と。誰もいない部屋に帰る夜も、ただの通過点かもしれない。明日もまた、少しだけ前を向いて、一歩だけ進んでみようと思えるように、そんな夜の仲間として。