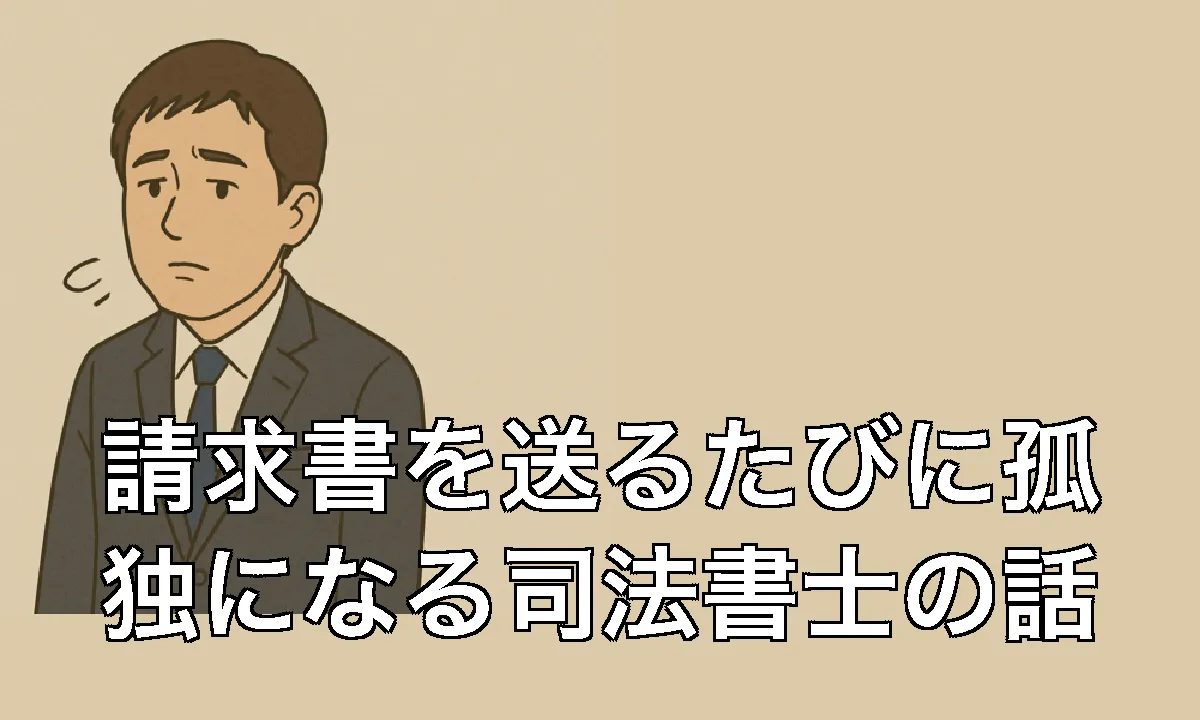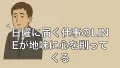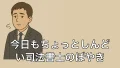請求書を送るたびに押し寄せるこの虚しさ
仕事を終え、請求書を作成し、送信する。その一連の作業が終わると、なぜか決まって心がぽっかり空くような気がする。業務はきちんと遂行したはずだし、トラブルもなく、むしろ順調に終わった部類なのに、どうにも晴れない。たぶんそれは、「完了」=「関係の終了」と感じてしまうからだろう。特に自分のような地方の小さな司法書士事務所で一人主軸となって動いている人間にとって、その“終了”の瞬間は、想像以上に孤独感を呼び起こす。
ひと仕事終えた達成感と比例しない心の空白
仕事が一段落したあとの「やりきった感」はある。だけど、どうにもそれが胸にじんわりと残らない。むしろ、空っぽになる感じが強い。例えるなら、野球部時代に大会が終わったあとのグラウンド。勝っても負けても、その場所を離れる瞬間のあの寂しさに似ている。やっている最中は夢中で、気持ちも高ぶっている。でも終わった瞬間、そこには静けさと虚しさしか残っていない。司法書士という仕事も、案件が一つ終わるたびに似たような喪失感がある。
達成感よりも「終わった感」が勝つ瞬間
案件が終わったら、それはそれで良いことのはず。だけど請求書を送った後に感じるのは、「達成」ではなく「終了」の重さだ。関係性もそこで一旦切れることが多いからだろう。感情を交わす暇もなく、書類と報酬だけが行き交う。終わった瞬間、次の案件に向かわなければならない。それが当たり前なのだけれど、どこか人間的な余白が抜けている気がして、寂しさばかりが残る。
数字だけのやりとりに感情が追いつかない
請求書に書かれているのは、報酬額や業務内容、日付や支払期日など、事務的なことばかり。それが大事なのはわかっている。でも、そこに人間味や思い出は一切ない。依頼者とのやり取りがどれだけ密だったとしても、最後に残るのは「数字の紙切れ」だけだ。それに自分の感情がどうしてもついていかないのは、たぶん、仕事に真面目に向き合っているからこそだと思いたい。
ありがとうも言われずに終わる現場も多い
司法書士の仕事は、感謝されないときも多い。何か大きな成果が目に見えるわけではないし、登記が終わっても「それが当然」と思われていることも多い。そういうとき、請求書だけが「あなたとの関係はこれで終わりです」と言っているように感じてしまう。何となく、こちらの存在が消えていくような、そんな気持ちになる。
淡々とした報酬請求という儀式
送る側も、受け取る側も、請求書というのはある意味で淡々としているべきものだ。でもだからこそ、そこに感情を持ち込むと浮いてしまう。自分の中にある「ありがとうございました」という気持ちも、フォーマットの中に閉じ込められて表に出ない。まるで手紙を書きたいのに、絵はがきの余白しか与えられていないような気分になる。
言葉のやりとりが少ないほど寂しさが増す
最近はメールでのやり取りが主流だ。電話よりも効率的で、証拠も残るし、便利だ。けれどその分、「やりとりの間(ま)」や、何気ない会話が削ぎ落とされていく。請求書を送るメールには、たいてい一文しか添えない。「ご確認のほどお願いいたします。」それだけ。そこに自分の温度や、気持ちなんて入り込む余地はない。
請求書を送るたびに「一人でやってるな」と実感する
どんなに忙しくても、どんなに依頼が続いても、最終的にすべて自分で判断し、処理し、完了させる。そのプロセスの最後に待っている請求書送信は、自分という存在が「個」であることを強く意識させられる瞬間だ。仲間と肩を並べて頑張った野球部時代とは真逆の景色で、そこで感じるのは誇らしさというより、やっぱり孤独だ。
忙しいのに、誰にも見られていない感覚
毎日が本当にあっという間に過ぎていく。登記の準備、面談、書類作成、期限対応……気づけば夜。なのに、誰に評価されるでもなく、誰かに見られている感覚もない。事務員はいてくれるけど、やっぱりこの業務の核心部分は自分一人で完結する。そうなると、どんなに忙しくても、自分の存在が誰にも映っていないような気がしてくる。
事務員はいるけど、共感までは届かない
一緒に働いてくれている事務員は本当にありがたい存在だ。でも、事務処理や電話対応を任せることはできても、業務全体の責任や感情の共有までは難しい。たとえば、自分が請求書を送る直前に感じるモヤモヤや、終わったあとの脱力感を分かち合うことはできない。それは職種の違いというより、責任の重みの違いなのだと思う。
わかってもらえない苦労は胸の中に溜まる
こういった「わかってもらえない系」の孤独は、本当に地味に効いてくる。誰かに「今日、請求書出したあと急に寂しくなっちゃってさ」と言ったところで、きっと「え、なにそれ?」で終わる。でも、そういう一言を飲み込む回数が増えるたびに、自分の中の孤独貯金がじわじわと溜まっていく。これは多分、誰にも見えないけど確実に溜まってる。
元野球部だった頃とは違う「孤独の種類」
学生時代、勝っても負けてもチームメイトと笑い合ったあの感覚が、今は恋しい。野球部の頃は、失敗も成功も分かち合えた。だが今は、成功も孤独、失敗も孤独。周りに人がいても、根っこの部分では常に一人。責任を持つということは、こういう孤独を抱えて生きることなんだと最近ようやく腹落ちしてきた。
仲間と喜びを分かち合った日々との対比
試合が終わった後、チームで飲んだ水の味。ベンチで応援したときの声の枯れ具合。そういう“みんなで作った記憶”があったから、結果がどうであっても満たされていたんだと思う。今の仕事では、それがない。実績や報酬が残っても、それを語る相手がいない。そういう日々の繰り返しが、静かな孤独を育てていく。
大人になってからの成果は一人で飲み込む
結局、報酬が振り込まれても、誰かと「やったな!」と祝杯をあげるわけでもない。せいぜい一人で夕飯をちょっと豪華にするくらい。それも、寂しさの上塗りになることがある。「おめでとう」とか「頑張ったね」とか、そういう言葉が欲しいわけじゃない。でも、何かこう、ちょっとでいいから誰かと“分かち合いたい”。それが本音かもしれない。