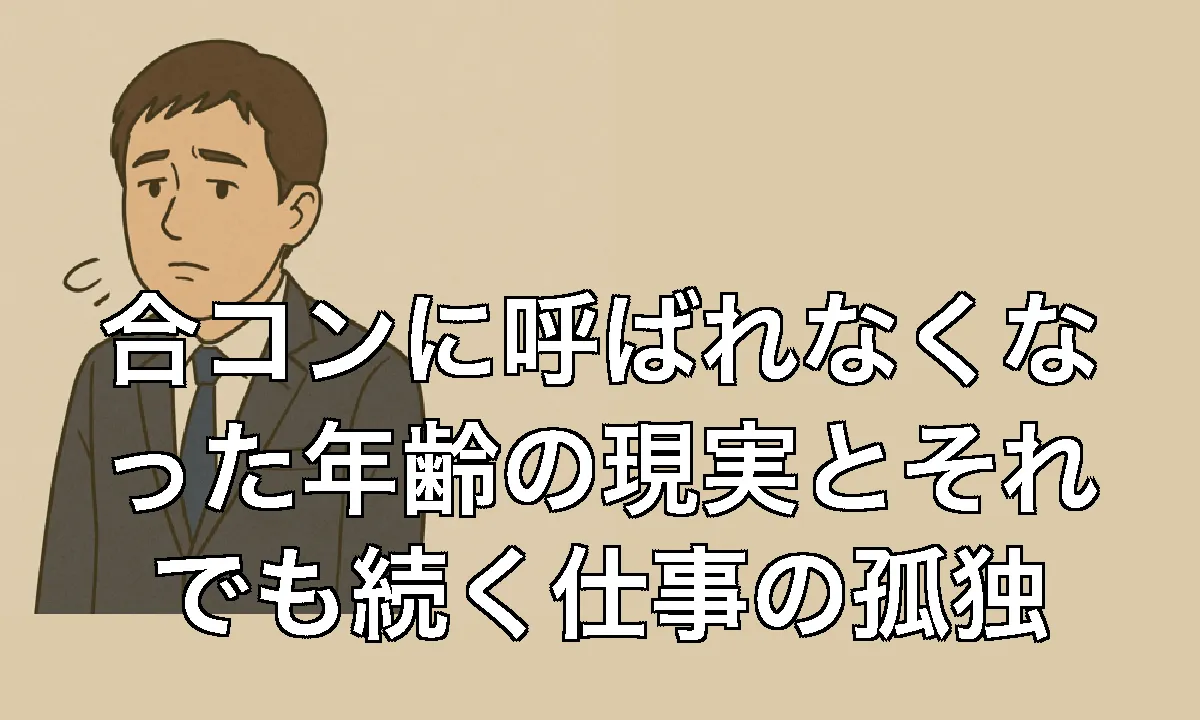合コンに呼ばれなくなったと気づいた夜
ある夜、LINEの通知を無意識に確認して「お、飲みの誘いか?」と思った自分に気づいた瞬間、なんとも言えない虚しさがこみ上げてきた。もう何年も、そんな連絡は来ていないのに。昔はちょっと暇だとすぐ誰かしら誘ってきてくれたのに、今じゃ仕事の連絡ばかり。合コンなんて、もう別世界の話みたいに感じる。いや、正確に言えば、「呼ばれなくなった」と気づきたくなかっただけなのかもしれない。
連絡は来ない でも通知はちゃんと見てる
未練がましくスマホの通知をチェックする自分が嫌になる。40代を過ぎて「飲み会」や「合コン」の文化から完全に外れたことは、わかっている。それでも、人と繋がる機会を期待してしまうのは、心のどこかがまだ満たされていない証拠なんだろう。通知の中に誰かからの誘いがあればいいな、と一日に何度も確認してしまう。今さらそんなことをしても無駄だとわかっていても、やめられない。
誰にも言えない寂しさの居場所
「寂しい」なんて、男のくせに言えるわけがない。仕事仲間にも、友人にも、そんな話はできない。でも、心の中では常に何かを求めている。寂しさって、黙っているとどんどん大きくなって、やがて自分の声すらかき消してしまう。テレビの音やラジオの声にすら、誰かと話しているような安心感を覚えることもある。話しかけられない日が続くと、人間は不安定になるんだと身にしみて感じる。
自分の存在価値がふとわからなくなる
仕事をして、家に帰って、誰にも会わずに寝る。その繰り返しの中で、「俺って何のために生きてるんだっけ」と思うことがある。お客様から感謝されても、それは業務に対するもの。個人として見られている実感は少ない。誰かに必要とされたい。でも、それがない現実に、価値を感じられなくなる夜もある。ただただ、空っぽの部屋で、過去の栄光にしがみついている自分がいる。
昔の仲間たちは家庭を持っている
久しぶりに連絡が来たと思えば、結婚式の招待状や出産の報告。昔の仲間たちは、みんなそれぞれの家庭を築いている。かつては夜遅くまで一緒に笑っていたメンバーが、今じゃ家族サービスに忙しい。自然と話す話題も変わってきて、どこか自分だけが取り残されたような気分になる。集まりにも呼ばれなくなり、「誘ってもどうせ来ないと思った」と言われたときの胸のざらつきは今も忘れられない。
「飲み行こうぜ」のノリも消えた
かつては、仕事終わりに「とりあえず一杯行こうか」となるのが当たり前だった。今ではそれぞれに事情があり、時間が合わない。自分だけが暇というわけではないが、誘われないという事実は変わらない。気づかないうちに、自分の周囲が静かになっていた。気のせいかと思っていたけれど、これはもう現実なんだと認めざるを得ない。
話題は子どもの習い事とローンの話
同世代の話を聞いていると、中心にあるのは子どもの教育や住宅ローンのこと。それはそれで立派な生き方だけど、自分にはその話に加わる資格がない。どう反応すればいいかもわからない。話を合わせて「へえー」と言ってみるけれど、実のところ心は別の場所にある。そういう瞬間が、思っている以上に人を孤立させる。
司法書士という仕事は誰も誘ってくれない
この仕事をしていると、人に誘われる機会が極端に少なくなる。平日も休日も、予定が読めないし、急な依頼も多い。友人たちからも「忙しいでしょ」と遠慮されて、気づけば孤立していく。それが積み重なると、仕事以外の人間関係がほとんどなくなってしまう。自分でもそうしてしまっているのかもしれないが、どこか寂しさが残る。
土日も緊急対応 曜日の感覚が崩れる
土日だからといって休めるわけではない。登記の締切、相談者の事情、急なトラブル。休日はあってないようなもの。結果、曜日の感覚が鈍り、生活のリズムはバラバラ。自分のための予定は後回し、気づけば誰かの都合に合わせる毎日になっていた。それを選んだのは自分だけれど、ふとした瞬間に「これでよかったのか」と考えてしまう。
気がつけば今年も花見に行けなかった
毎年、「今年こそは花見に行こう」と思うのに、気づけば桜は散っている。そういうことが積み重なって、季節すら忘れるようになる。仕事に夢中で時間が過ぎるのは悪いことではない。でも、何かを置き去りにしている感覚が残る。誰かと一緒に花を見て、何気ない話をして笑い合う。そんな普通のことが、今の自分には一番難しい。
誘われなくなったのではなく 忙しさで消えた
本当は誘われていたのかもしれない。でも、「どうせ無理だろう」と思われていたのかもしれない。忙しさで断る日々が続けば、自然と誘いは減る。それは仕方ないと頭では理解しているけれど、心はついていかない。いつの間にか「呼ばれない側」になっていた自分を、鏡の中に見つけるたびに、苦笑いしかできなくなっている。
夜の予定はすべてキャンセル要員
予定が入っていても、急な電話一本で全部キャンセルになる。それが当たり前になってくると、自分から予定を入れるのが怖くなる。どうせ守れないなら最初から断っておいたほうがマシだと考えてしまう。その結果、ますます人との繋がりが減っていく。まるで、仕事のために人間関係を犠牲にする人生を選んでしまったようだ。
どうせ無理だからと断る前提で話される
「どうせ無理でしょ?」と、最初から諦められているような声かけが増えた。「忙しいの知ってるから」と、気を遣ってくれるのはありがたい。でも、それは同時に「君はもう仲間じゃないよ」と言われているようで、なんとも言えない疎外感を感じる。そうやって一歩ずつ、社会から孤立していく感覚が積み重なっていく。
「また今度ね」が永遠の別れになる
「また今度飲もう」は、便利な言葉だ。でも、その「今度」が来ることは滅多にない。会いたいなら会う。誘いたいなら誘う。そうしなければ、時間は勝手に過ぎていく。「今度」は人間関係を終わらせる言い訳になってしまうことが多い。言葉の奥にある本音に気づくたび、自分がどこか遠い場所に立っている気がしてくる。
じゃあこの仕事を選んだのは正解だったのか
司法書士としての道を選んだのは、自分自身。後悔しているわけではない。でも、孤独に耐える覚悟が必要だとは思っていなかった。毎日誰かの手続きを支え、誰かの不安を解決している。それでも、自分の不安や孤独を支えてくれる人はいない。そう感じる瞬間が、年々増えていく。
毎日誰かの人生の一部に関わっている
登記も相続も、ただの事務手続きに見えるかもしれない。でも、その裏には必ず人の人生がある。別れだったり、始まりだったり。誰かの節目に立ち会っているという実感は、少なからず自分の誇りでもある。誰にも褒められなくても、自分だけはわかっている。それが唯一、今の自分を保ってくれている支えかもしれない。
誰にも感謝されなくても記録に残る
この仕事の多くは、感謝されることが少ない。むしろ、「当然」と思われることのほうが多い。それでも、法務局には自分の名前が残っている。記録として、確かに自分が関わった証が残る。それがせめてもの証明であり、ひとりの司法書士として生きた痕跡なのだと思っている。
人と距離を取りながら生きられる仕事
この職業は、適度に人と距離を取りながら関わることができる。人間関係が煩わしいと感じるときには、それが救いになる。でも、本当に心を開ける相手がいないというのは、やはりどこか寂しい。距離があるからこそ楽だけど、だからこそ孤独も深くなる。バランスの難しさを日々感じている。
それでも寂しさは書類の隙間から漏れてくる
どれだけ忙しくしても、ふとした瞬間に寂しさは顔を出す。封筒を閉じるとき、書類をファイリングするとき、その隙間からこぼれ落ちる感情は、自分でもコントロールできない。机に向かう背中が空虚に感じる日もある。それでも、明日もまた書類を積み重ねていくしかない。
ひとりで戦い続ける理由が見えなくなる
なぜこんなに働いているのか。誰のために、何のために。そう問いかけたくなる日がある。自分が選んだ道なのに、その道がどこに向かっているのか見えなくなる瞬間がある。ひとりで戦うことに意味を持てなくなるとき、それでも自分を支えてくれるのは、過去の自分の選択だけだ。
誰かに呼ばれたい気持ちは残ってる
合コンに呼ばれなくなったって、本当はどうでもいいのかもしれない。ただ、誰かに「お前も来いよ」と言ってもらいたいだけなのだと思う。必要とされたい。声をかけられたい。そういうささやかな願いが、まだ自分の中に残っている限り、この仕事も、この人生も、続けていける気がしている。