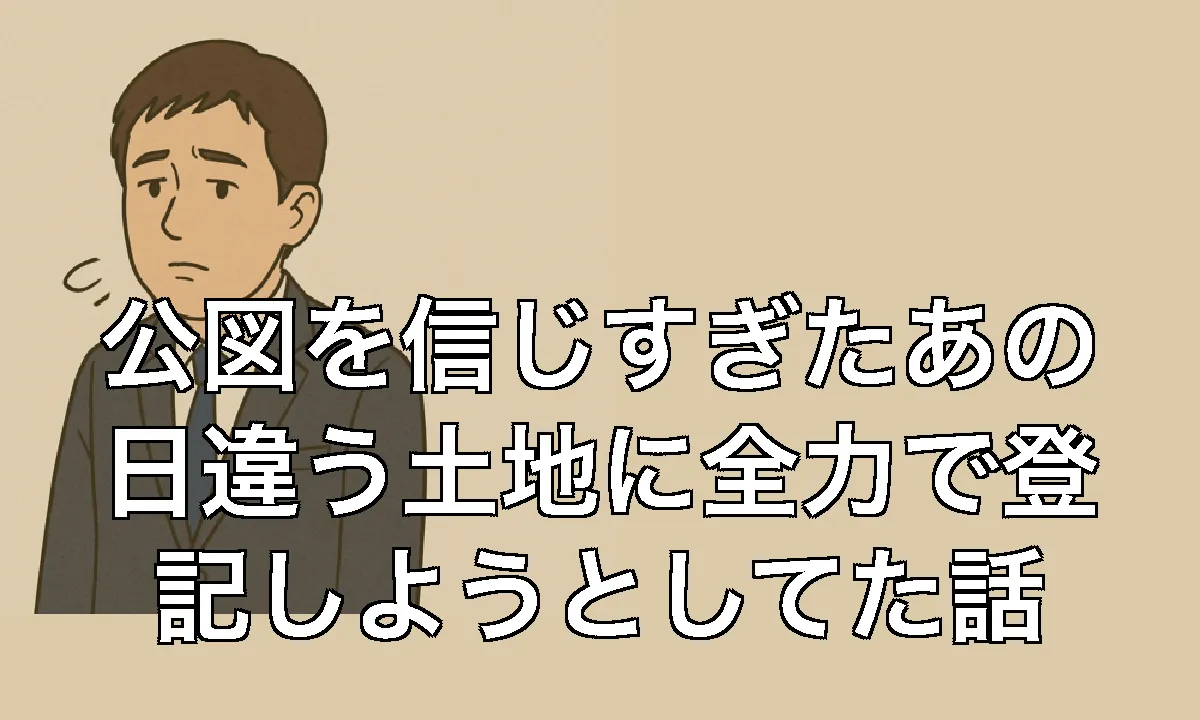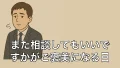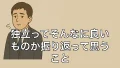あの日の登記ミスは突然に
この仕事をしていると、時折「なんでこんな初歩的なミスをしたんだろう」と自己嫌悪に陥る瞬間があります。その中でも、今回の「公図の見間違い」はかなり痛烈でした。まさか自分が、全く別の土地を登記しようとしていたなんて。今だから笑えますが、当時は頭の中が真っ白で、しばらく呼吸が浅くなりました。地方の小さな司法書士事務所で、日々の業務に追われながら、基本の“き”を怠った結果です。
依頼は普通の土地登記だった
その日はいつも通り、土地の名義変更の依頼が入りました。登記原因は相続。地番もはっきりしており、公図も法務局から取り寄せて一通りチェックしたつもりでした。依頼人も穏やかな方で、急ぎでもないとのことで、精神的には余裕があったはずです。にもかかわらず、どこかで「このくらい大丈夫」という慢心があったのかもしれません。作業を淡々と進め、事務員にも軽く説明して、申請準備に取りかかったのです。
ちょっとした忙しさに紛れて
その頃、相続登記の案件が立て続けに入っており、気づけばデスクの上が地番のメモと公図のコピーであふれていました。私の事務所は事務員が一人で、資料整理も全部自分でやらなきゃならない状況。そんな中で、見なきゃいけないものを見た“つもり”になってしまったのです。ほんの10分だけでも集中して見ていれば気づけたことを、私は「急いでいるから」の一言で流してしまいました。
「見たつもり」で確認を終わらせた
登記対象の土地は公図で確認済み、と自分では思い込んでいました。でも実際には、隣の地番の土地を見ていたのです。土地の形状が似ていたことと、住所表示が紛らわしかったことも拍車をかけました。けれど一番の問題は、自分の心の中にあった「こんなミスはしない」という過信でした。確認すべき現地写真やGoogleマップのチェックも省略し、「だいたいこんなもんだろう」と作業を進めてしまったのです。
公図と現地は似て非なるものだった
後から思えば、公図というのはあくまで目安であり、現況と一致するとは限らないという基本を忘れていました。特に地方では、地目や形状が公図と実際でズレていることも珍しくありません。それを完全に見落とし、しかも現地確認を怠ったのです。まさに「机の上の仕事」で完結させようとした結果、全く違う土地に登記の申請書を作ってしまいました。
現地を見に行かなかったことへの後悔
私はその案件で現地を一度も見に行きませんでした。なぜなら「わざわざ行かなくても大丈夫」と思ったからです。でも現地を訪れていれば、すぐにおかしな点に気づけたはず。登記対象の土地には古い納屋があると依頼人に言われていたのに、私が用意した申請書の地番は、何も建っていない空き地でした。こういう「ちょっとした違和感」に気づけなかった自分を、いまでも責めたくなります。
地番と地形が似てるだけで信じた自分
「地番が連番だから隣だろう」と勝手に解釈してしまったことも、失敗の原因でした。土地の形も似ており、「たぶんこれだな」と決めつけていたのです。でも法務局の職員でもない限り、そこまで地番の位置関係に詳しい人間なんていません。確認不足のまま申請を進めたことで、依頼人に迷惑をかけてしまいましたし、自分自身の信用も大きく傷つきました。
ミスが発覚した瞬間のあの冷や汗
間違いに気づいたのは、依頼人からの一本の電話でした。「先生、書類の住所、ちょっと違う気がするんですけど…」その言葉を聞いた瞬間、全身から血の気が引きました。すぐに資料を見返し、公図と地番を突き合わせて愕然。まったく違う土地を見ていたことに、そこでようやく気づいたのです。電話を切ったあと、しばらく椅子に座ったまま動けませんでした。
依頼人との電話で初めて知る事実
依頼人は優しい方でした。「先生も忙しいでしょうから…」と気を遣ってくれましたが、その言葉が逆に胸に突き刺さりました。プロとして信頼して任せてくれていたのに、私はその期待を裏切ってしまったのです。謝罪し、書類の差し替えと訂正申請を迅速に行いましたが、あの時の情けなさは今も忘れられません。たった一つの確認不足がどれだけの影響を与えるかを、骨身にしみて感じました。
頭が真っ白になるとはこのこと
登記の仕事はミスが許されない、とは常に思っていたはずなのに、まさか自分がこんな単純なミスをするとは思ってもいませんでした。公図の見間違い一つで、すべての段取りが崩れ、信用も大きく揺らぐのです。しかもそれを、他人に指摘されるまで気づけなかったという事実が、一番ショックでした。ミスを認めること自体もつらかったですが、それ以上に「自分は大丈夫」と思っていた過信が一番の敵でした。
なぜこんなミスをしたのかを振り返る
司法書士としての仕事は地味で確認作業の連続です。そんな中で、忙しさや疲れ、そして慢心が重なると、つい「まぁ大丈夫だろう」と手を抜いてしまう瞬間があります。今回の件は、その“少しの油断”が大きなミスを生むという、まさに典型的なケースでした。私は改めて、自分の仕事に対しての向き合い方を見直すきっかけを得たように思います。
忙しさを理由に基本を省略した結果
あの日の私は、まさに「やるべきことをやらなかった」だけです。言い訳はいくらでもできます。「相続案件が立て込んでいた」「相談者が多かった」「役所対応に追われていた」でも、それは言い訳にすぎません。地番の確認、公図と現地の照合、現況の写真確認といった基本のプロセスを怠った私の責任。それを“忙しさ”という言葉で誤魔化していた時点で、もうミスは始まっていたのだと思います。
自分が事務員だったら怒ってる
この件があったあと、自分が逆の立場だったらどう思うかを考えました。もし私が事務員で、所長がこんなミスをしていたら…正直、怒っていたと思います。「なぜ確認しなかったんですか?」って、聞きたくなったはず。だからこそ、今後は事務員に甘えず、自分の確認作業はしっかりやろうと心に決めました。自分に甘くなると、必ずそのツケは誰かに回る。それを思い知らされた出来事でした。
「確認した気になってた」怖さ
一番怖いのは「確認したつもり」になっていたことです。紙の上で見ただけで「わかった」と思い込んでしまう。それが公図の恐ろしさです。登記の現場では、ほんの小さな思い込みや見落としが致命的なミスにつながります。確認した“はず”が、確認していなかった。そうならないためには、どんなに忙しくても、どんなに面倒でも、声に出して、目で見て、体で確認することが大切なんです。
地方事務所の人手不足という現実
とはいえ、現実問題として、地方の司法書士事務所はどこも人手不足です。うちも事務員が一人しかおらず、繁忙期には回らない業務がどんどん増えていきます。そんな中で、「この程度なら」と判断してしまう場面は本当に多い。だけど、それでミスをしたら意味がない。やっぱり一人ひとりが、“確実な仕事”を心がけるしかありません。地道な仕事だからこそ、手を抜けない。そんな当たり前を忘れないようにしています。
一人事務員にすべてを任せきれない理由
事務員に任せられる範囲には限界があります。彼女もよく頑張ってくれているけれど、結局のところ、最後の責任は私が負うもの。だからこそ、自分で確認する癖をもっと徹底しないといけない。信頼して任せることと、丸投げすることは違います。このミスをきっかけに、私自身の働き方や判断基準も、少しずつ見直しているところです。
誰にも頼れないという慢性的な孤独
たまにふと、「ああ、誰かに相談したいな」と思うときがあります。でも、同業者に失敗を話すのは恥ずかしいし、かといって他に気軽に話せる人もいない。そういう意味では、司法書士という仕事はなかなか孤独です。だからこそ、自分自身で立ち止まり、振り返り、そして修正していくしかない。失敗から逃げず、ちゃんと向き合うこと。それができるようになって、ようやく一人前かもしれません。