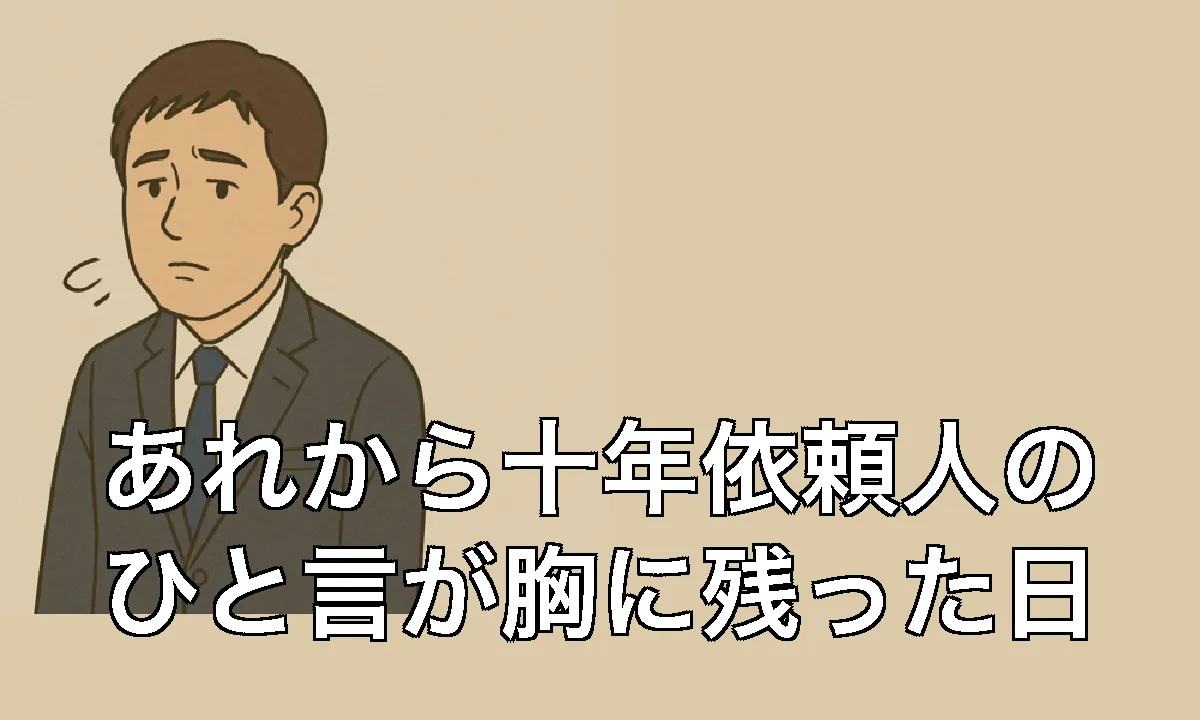忘れかけていた名前が届いた日
机の上に置かれた一通の封筒。その差出人の名前に、僕はしばらく目を奪われていた。「どこかで見たことがあるような……」と思った瞬間、十年前のある依頼が鮮明に蘇った。名前を見ただけで、当時の空気感ややりとりまで思い出せるようなことなんて、そうそうない。僕にとっては日々同じような案件を処理する中のひとつにすぎなかったはずのその人が、なぜ今、手紙をくれたのだろう。そう思いながら封を開けた。
封筒の筆跡に見覚えがあった
字は丁寧でまっすぐな書き方。女性特有の丸みを帯びた文字に、当時も少し驚かされたことを思い出す。依頼人は離婚に伴う不動産の名義変更の相談だった。事情は込み入っていたが、本人はどこか冷静で、それが逆にこちらの緊張感を増すようなタイプだった。文字にはその人の人柄がにじみ出るというが、当時の彼女の覚悟が字からも感じ取れたことを、今あらためて思い出した。
開けた瞬間に過去の記憶が押し寄せた
封筒を開けて最初に出てきたのは、一枚の便箋。そこに綴られていたのは、たった数行のメッセージだった。それでも僕の胸には強く響いた。「先生の言葉が、あのとき本当に支えでした」と。思わず手が止まり、しばらくじっと便箋を見つめていた。こんなにもシンプルで、でも心に響く言葉があるのかと驚いた。司法書士という職業で、こうして“ありがとう”をもらえる瞬間は、決して多くない。
当時の案件はさほど特別なものではなかった
僕の記憶の中でも、あの案件は「丁寧にやったつもり」程度だった。特別に困難でもなく、感情的なやりとりがあったわけでもない。ただ、時間通りに説明し、書類を整えて手続きを終えた、それだけの記憶だ。けれど依頼人にとっては、その時期が人生の分かれ目だったのだろう。こちらの言葉が、知らず知らずのうちに彼女を支えることになっていた。自分が思う以上に、誰かの人生に影響を与えていることがあるのだ。
久しぶりの面談に戸惑う気持ち
便箋の最後に「一度お礼が言いたくて、伺ってもいいですか」と書かれていた。正直、少し戸惑った。こういう“お礼の訪問”のようなものは、実はあまり得意ではない。何を話していいかわからないし、社交辞令のやりとりに疲れることもある。それでも予定を調整し、事務所で再会の日を迎えることにした。
十年分の時間が空気に漂っていた
事務所のドアが開いた瞬間、そこに立っていたのは、確かにあのときの彼女だった。だけど印象はまるで違って見えた。服装も、表情も、話し方も穏やかになっていて、あの頃の張り詰めた空気がすっかり抜けていた。時間というのは、こんなふうに人を癒やすものなんだと実感した。そして、十年間の重みは、僕自身にも確かに刻まれていたのだと気づかされた。
相手の変化と自分の変化を比べてしまう
彼女は新しい仕事に就き、子どももいるとのことだった。人生を切り拓いていった様子が話の端々から伝わってきた。一方で僕は、十年前とほとんど変わらぬ事務所で、変わらぬ作業をこなし、気づけば独り身のまま。この差を見せつけられるようで、内心ちょっと情けなくなった。もちろん彼女にそんな意図はないのだろうけど、勝手に自分を比べてしまうのが人間というものだ。
会話が弾むわけでもないのに居心地が良かった
たわいない話が中心だった。過去の手続きのことも、彼女の近況も。だけど、なぜか居心地が良かった。久々に“誰かとゆっくり話す”という感覚を思い出した。事務員さんとしか会話していない日もある中で、こうして旧知の人と再会することで、自分の感情が少しずつ解凍されていくようだった。
依頼人が語ったたったひと言
会話の終盤、彼女がポツリとこう言った。「あのとき、誰にも言えなかったんですけど、先生だけは普通に接してくれて、ありがたかったです」。なんてことないひと言。でもそれが一番グッときた。派手な感謝の言葉よりも、そういう“日常の延長にある気遣い”が、じわりと心に沁みた。
あのとき救われたと言われたけれど
自分が何を言ったのかなんて、もう思い出せない。ただ、決まり文句のように「大丈夫ですよ」とか「心配いりません」と言ったのかもしれない。でもそれだけでも、誰かの孤独を少しだけ軽くできたのだとしたら、司法書士という仕事にも意味はあるのだろう。評価されない仕事のなかに、こうして時折、宝物のような言葉が紛れている。
自分では覚えていない対応の数々
毎日同じような案件に向き合っていると、正直、記憶に残らない。誰のどの書類だったか、何度説明したか、そんなものはすぐに忘れてしまう。でも相手にとっては、その一瞬が人生の転換点だったりもする。そう考えると、日々のルーチンにも責任があるのだと、あらためて感じさせられる。
でもそれがこの仕事の本質かもしれない
人の人生の“はしっこ”に関わるのが司法書士の仕事だ。決して主役ではないけれど、だからこそそっと支える役割がある。目立たなくても、報われなくても、それでも時折こんなふうに感謝されるなら、この職業は捨てたもんじゃない。書類の山の裏に、人の人生が確かにある。そのことを、十年ぶりの再会が教えてくれた。
誰にも評価されない仕事の意味
誰も見ていないと思っていた。褒められることもないし、営業成績があるわけでもない。それでも、こうして時間を経て感謝の言葉をもらえるなら、やってきた意味はある。派手じゃない仕事にこそ、静かな価値が宿るのだと信じたい。
書類の山の向こうにあるものを見たい
目の前の案件に追われて、疲れて、愚痴って、それでも誰かのためになっているかもしれない。そう思える瞬間があるから、今日も机に向かえる。そうでなければ、とうに辞めていただろう。地味で孤独なこの仕事が、ほんの少しだけ輝いた日だった。
愚痴ばかりの日々にも意味があったと信じたい
今日も電話は鳴り止まず、事務員さんと手分けして対応に追われる。書類のミスもあるし、クレームもある。正直、投げ出したくなることのほうが多い。だけど、たまにこうして「先生にお願いしてよかった」と言ってもらえることがある。そのひと言で、また少し頑張ろうと思える。十年前の彼女のように、誰かの人生の片隅で、静かに役立てていたらいい。