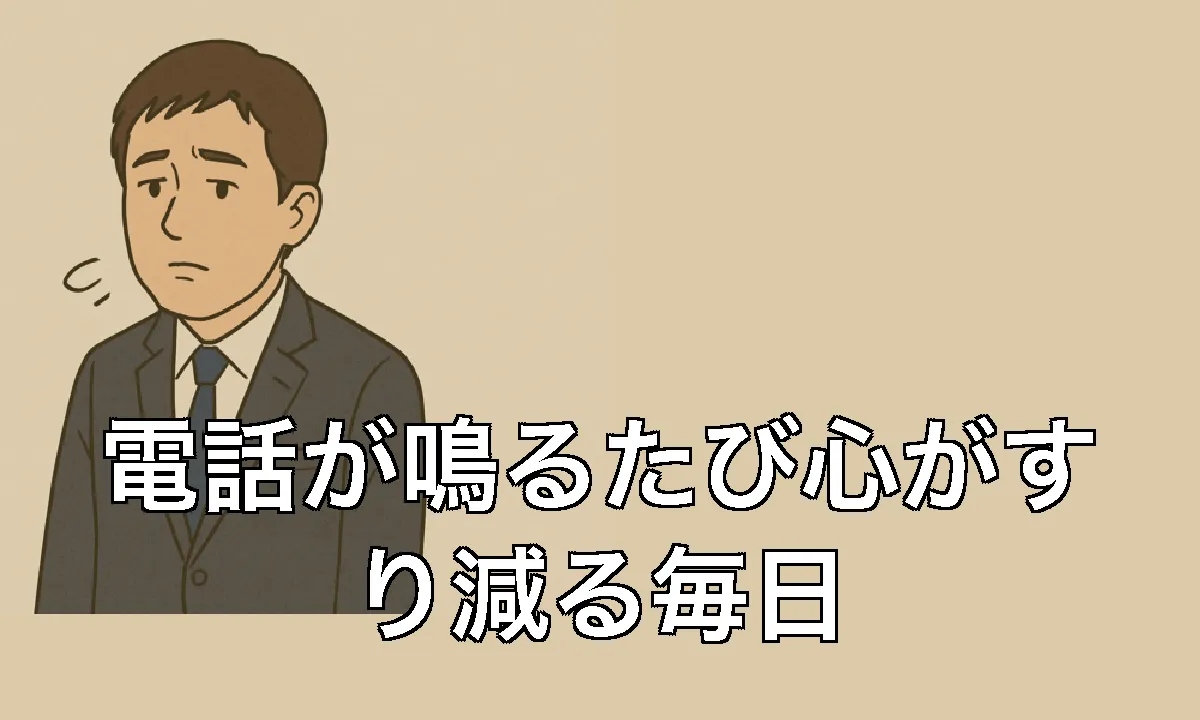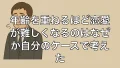静寂を破る着信音にびくつくようになった理由
司法書士として独立して十数年。最初の頃は電話が鳴るのが嬉しかった。「仕事が入ったかも」「問い合わせかも」なんて期待もあった。でも今は違う。電話が鳴るたび、心臓がドクンと鳴る。胃の奥がきゅっと縮む。鳴った瞬間、体が固まって動けなくなることもある。これはもう、条件反射に近い。事務所の静けさを破るあの着信音が、次の面倒やトラブルの合図に思えてしまうのだ。
一度の失敗で染みついた条件反射
ある日、遺産分割の相談で電話がかかってきた。その内容自体はよくあるものだったが、依頼人の親族同士の感情がこじれていた。こちらは丁寧に手続きを進めていたつもりだったが、突然相手方から「なんでこんな進め方をしたんだ」と怒号交じりの電話が入った。声を荒らげる相手に、言い訳も説明も通じない。その時の電話の衝撃は、まるで心臓に針が刺さったようだった。以来、「また何かミスしたかも」「怒られるかも」と構えてしまうようになった。
あの電話のあと全部が変わった
その電話を受けた直後、手が震えて書類も持てなかった。事務員にも心配された。「電話一本でこんなに動揺する自分って、情けないな」と思ったが、それが現実だった。夜になってもその声が頭に残っていて、夢の中でもうなされた。そこからだ。電話が鳴るたび、まず「怖い」が頭をよぎるようになった。以前のように淡々と電話に出ることができなくなったのは、この一件がきっかけだった。
笑って受けたふりの裏で手が震えていた
それ以来、なるべく落ち着いた声で「はい、○○司法書士事務所です」と受け答えする。でも電話が終わると、手汗びっしょり。相手に声が震えていたことを気づかれていないか、そればかりが気になって、しばらく仕事に集中できない。大した内容じゃなかったはずの電話にも、体が反応してしまう。電話対応って、地味だけど一番神経を使う業務なんじゃないかと、本気で思うようになった。
電話がトラブルの入り口に見える日々
電話の音に怯えるようになると、不思議なもので、電話=悪い知らせというイメージがどんどん強化されていく。着信履歴を見ただけで「あ、この人、前に揉めた相手かも」とか「なんかややこしいことになってそう」と勝手に構えてしまうようになる。冷静になってから確認すると、まったく問題ない内容だったりすることもあるのだが、その“直前の緊張”は何度味わっても慣れない。
良い話はメールで来る 悪い話は電話で来る
気づいたのは、褒められるような連絡はメールで届くことが多いということだ。「丁寧に対応していただきありがとうございました」とか「またお願いします」といった連絡は、たいてい文章。逆に、クレームや不満、誤解などは、だいたい電話で突然来る。だから、「電話=やばい話がくる装置」みたいなイメージが自分の中で出来上がってしまったのかもしれない。理屈じゃない、もう脳がそう覚えてしまっている。
「おかけになった番号は…」でホッとする瞬間
電話が鳴って出られなかったとき、「この番号は現在使われておりません」というアナウンスを聞くと、なぜかホッとする自分がいる。「なんだ、間違い電話か」と。通常ならなんとも思わないようなことに安堵してしまうのは、完全に神経がすり減っている証拠だと思う。自分でも笑ってしまうが、それくらい電話というものが怖くなってしまったのだ。
事務所の電話に誰よりも敏感な自分がいる
一人で事務所を切り盛りしていると、電話も業務の一部。分かってはいるけれど、それでも心のどこかでは、誰か代わってくれないかなと思ってしまう。事務員がいてくれて助かることは多いが、結局大事な電話は自分が出るしかない。誰よりも早く、反射的に電話に手を伸ばしてしまう自分がいる。それが習慣になってしまっている。
事務員さんより先に取らないと落ち着かない
本当は任せてもいいのに、電話が鳴ると「自分が出ないと」と反射的に思ってしまう。事務員さんが取ってくれるのを待つ間にも、「何の電話だろう」「どう対応してるかな」とそわそわしてしまう。結局、電話を終えた事務員さんに「何の件だった?」と聞いてしまい、安心したり逆に焦ったりする。出るにしても出ないにしても、電話は心の平穏を奪っていく。
鳴る前から気配でわかるようになった
静かな時間が続くと、なぜか「そろそろ電話鳴るかも」と身構えるようになった。妙に第六感が働くようで、電話の前にパソコン画面を整えたり、資料を手元に準備したりする自分がいる。仕事に集中していても、その予感だけで緊張してしまう。電話に生活リズムをコントロールされている気がして、なんだか悔しいし情けない。
本当は出たくないけど職業柄逃げられない
「電話苦手なんです」と言っても、司法書士という立場では通用しない。相手が高齢者ならなおさら、電話のほうが安心されることもある。だからこそ、出ないわけにはいかない。でも心では「どうか留守電にしてください」と願っている自分がいる。そんな自分にちょっと嫌気がさす。でも、これが今のリアルな姿なのだ。
電話=緊急対応という呪いの刷り込み
もう一つ大きいのが、「電話は緊急対応用」という考え方が根深いことだ。メールなら一晩寝かせてから返信できる。でも電話はそうはいかない。リアルタイムで答えを求められることが多く、その場で判断しなければならない。これは司法書士にとっては重荷になることが多い。たった5分の電話で、その日の気力が奪われることも珍しくない。
休日の着信履歴で血の気が引く
せっかくの休みにスマホを見ると、着信履歴に1件。「○○不動産」「○○銀行」なんて名前が並んでいると、それだけで血の気が引く。折り返すべきか、このまま知らないふりをするか。いや、どっちみち気になって休めない。休みの日まで気持ちを掻き乱されるなら、いっそ電源を切ってしまいたい。でも、それができないのが性分なのだろう。
無意識に「また何かあったのか」とつぶやいている
電話の着信を見るたび、口をついて出る言葉がある。「また何かあったのか」。この一言が癖になっていて、自分でもびっくりする。たとえそれが親戚や友人からの電話でも、まず疑ってかかってしまう。心がすり減るとはこういうことなのだろう。いつの間にか、音だけで心が反応してしまうようになってしまった。
同業者との会話でわかったのは自分だけじゃないということ
最近、同業の司法書士さんと話す機会があった。そこで「電話、怖くないですか?」と何気なく言ってみたら、思った以上に共感を得られた。みんな何かしらのプレッシャーや緊張を抱えているようで、それを聞いて少しだけ救われた。自分だけじゃない、と思えることが、これほど心を軽くするとは思っていなかった。
「あの音が嫌だよなあ」で始まる共感
「プルルルって鳴るたびにビクッとするよね」そんな会話が、深夜の居酒屋で交わされた。共感の輪が広がるほど、心の中の何かがほどけていった。同じように感じている人がいる。それだけで、「この感じは自分だけの弱さじゃないんだ」と思えた。誰にも言えなかった気持ちを、やっと言葉にできた気がした。
電話恐怖は珍しくないと知って救われた
その場にいた全員が「実は苦手なんだ」と口をそろえたとき、正直少し泣きそうになった。自分がダメなんじゃない、この仕事が、いや社会全体が、電話に過剰な期待をしてるのかもしれないとすら思えた。みんな忙しく、余裕がない中で、即対応を求められる。それが怖いのは当たり前だ。そう思えるようになっただけでも、少し気が楽になった。
でもやっぱり次の電話も怖いのが現実
どれだけ共感を得たとしても、次の日、また電話は鳴る。そしてやっぱり、動悸がする。人間ってすぐには変われない。でもそれでもいいのかもしれない。怖いと思いながらも、ちゃんと応対してる自分は、少しだけ誇ってもいいんじゃないか。そう思いながら、今日も電話の前で深呼吸をして、受話器に手を伸ばす。