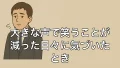忙しさに押しつぶされそうだったあの日
開業してから何年経っても、忙しさに慣れるということはない。特に年度末や不動産の動きが激しい時期には、仕事が重なるだけでなく、ひとつひとつの処理が複雑になる。あの日も、朝から嫌な予感がしていた。事務員が体調不良で休み、電話は鳴りやまず、メールも開くたびに新たな問題が待っている。自分が一人で対応できる範囲をとっくに超えていたのに、誰にも弱音を吐けず、ただただキーボードを叩いていた。
すべてが重なったタイミングでの不動産トラブル
そんなときに限って、不動産の登記に関するトラブルが発生した。書類に記載された地番に誤記があり、すでにお客様に説明済みだった内容と異なることが発覚。関係先にはすでに提出済みで、今さら修正するには手続きが煩雑になる。加えて、相手方の司法書士からの連絡も「こちらに過失はない」と冷たい一言。事態をどう収束させるか、頭の中で何通りもシミュレーションをしたが、答えは出なかった。
登記の修正、顧客からの催促、そして事務員の欠勤
顧客からは「まだか」「大丈夫か」と連絡が入り、電話に出るたびに胃がキリキリと痛んだ。訂正書の準備を進めようにも、事務員が不在で書類チェックやコピー作業すら手が回らない。普段なら他愛のない冗談を交わして和らぐ雰囲気も、今はまるで無風地帯。そんな中、一人で黙々と書類を見つめていたとき、ふと「これ、俺の限界かもしれない」と思ってしまった。
心の中では「もう辞めたい」がぐるぐるしていた
正直言えば、そのとき心の中では「司法書士を辞めたい」という言葉がぐるぐると渦を巻いていた。こんなに頑張っても、評価されるわけでもない。人に頼るのが苦手な性格なのもあって、自分だけで抱え込みすぎていた。結婚もせず、友人も少なく、ただただ仕事に向き合ってきた結果がこれなのかと、自問自答していた。
ふと思い出した、あの同期の存在
そんな重苦しい空気の中、ふと頭に浮かんだのが、司法書士試験の勉強時代に苦楽を共にした同期の顔だった。彼も同じく地方で独立開業していると聞いていたが、ここ数年は全く連絡を取っていなかった。電話番号も変わっているかもしれない。それでも、もう誰でもいいから助けてほしい、話だけでも聞いてほしい、そんな気持ちで電話帳を開いた。
司法書士試験の受験仲間だった彼
彼とは予備校の自習室で出会い、缶コーヒーを片手に愚痴をこぼし合う仲だった。合格発表の日には一緒に泣き笑い、開業後もしばらくは連絡を取り合っていた。ただ、お互いに仕事が忙しくなるにつれて、いつの間にか疎遠になってしまった。今さら連絡をして迷惑じゃないか、そんな不安を抱きつつも、手は勝手にダイヤルを押していた。
実務に出てから疎遠になっていた関係
電話のコール音が鳴る間、心臓の音が聞こえるようだった。だが、彼は変わらぬトーンで「おお、久しぶり」と応えてくれた。拍子抜けするほど自然なやりとりに、胸がじんわりと温かくなった。自分が仕事でどれだけ参っているかを素直に話すと、彼は真剣に耳を傾けてくれた。
ダメ元でかけた一本の電話がすべてを変えた
相談というより、ほとんど泣き言のような話を30分ほど聞いてくれた彼は、最後に「俺もあったよ、同じようなこと」と言った。その一言にどれだけ救われたか。自分だけじゃない、自分が特別にダメなんじゃない。そう思えるだけで、心がスッと軽くなった。
「ああ、それ俺もやったことあるよ」
専門職というのは、プライドが邪魔をして「助けて」と言いづらい。けれど、「俺もやったことある」という共感の一言は、何冊のマニュアルよりも心に効いた。同じ失敗をしたことのある人の声には、安心とリアリティがある。叱られたわけでも、叩かれたわけでもない。ただ共感してもらっただけなのに、泣きそうになった。
同じミスを経験していたという共感
「地番の間違い? ああ、俺もそれで客に怒鳴られたことあるよ」と彼は笑った。その笑いが、自分にとっては救いだった。司法書士という仕事は、ミスが許されないプレッシャーが常にある。でも、それでも人間なのだから、間違えることもある。そう言ってもらえたことで、ようやく自分を許せた気がした。
助言よりもまず「わかるよ」と言ってくれた
彼は「こうすればいい」とは言わなかった。ただ「わかるよ」と繰り返してくれた。その言葉がどれだけ沁みたか。人は理屈じゃなく、感情で動くものなのだと痛感した。「頑張れ」でも「大丈夫」でもなく、「わかるよ」が一番必要だった。
その一言で張りつめていた糸がゆるんだ
心の中にずっと張っていたピンとした糸が、「わかるよ」の一言でゆるんで、涙が出そうになった。電話を切った後、なぜか少しだけ笑えた。やることは変わらないけれど、気持ちがまるで違った。重荷を少しだけ降ろせたような感覚だった。
人はやっぱり一人ではやっていけない
独立してからというもの、全部自分でやらなきゃという思い込みに支配されていた。でも、頼るという選択肢もあるのだと、あの電話が教えてくれた。頼ることは甘えじゃない。誰かの存在を思い出すこと、それが生き抜く力になる。
独立開業の孤独に慣れすぎていた自分
開業してしばらくは、誰にも頼らずにやりきることがかっこいいと思っていた。でも現実は甘くない。失敗して、責められて、それでも誰にも言えなくて、気づけば笑わなくなっていた。そんな日々の中で、電話一本が心をほどいてくれた。
「頼ってもいい」ということを思い出した
人に頼ることがこんなに安心につながるとは、思ってもみなかった。小さな一歩が大きな救いになる。あの日の自分に言ってやりたい。「一人で頑張らなくていいよ」と。そう気づけたことが、何よりの収穫だった。
恥をかくのが怖くて相談できなかった過去
若い頃の自分は、相談することで「できない奴」と思われるのが怖かった。でも、歳を重ねた今ならわかる。恥をかいてでも誰かに頼る強さこそが、本当の意味での「かっこよさ」なのかもしれない。
助けてもらったことで生まれた「恩返し」の気持ち
あのときの出来事は、自分にとって忘れられない原点になった。今は、後輩や悩んでいそうな同業者からの連絡には、できる限り耳を傾けるようにしている。あの日、自分が救われたように、今度は誰かを救えたらいい。
自分も誰かの電話に応える覚悟ができた
あの一本の電話があったからこそ、今、自分は誰かの「一本」に応えられるようになった。何を言えばいいかはわからなくても、「わかるよ」と言ってあげられる。それだけで十分だと思えるようになった。
後輩からの相談にも、素直に耳を傾けるように
以前は「そんなの自分で考えろよ」と思っていた。けれど、今は違う。誰しも余裕がない時は判断力も鈍るし、弱音も出る。そんなときに話を聞いてもらえるだけで、人は前を向ける。そのことを自分が身をもって知ったからだ。
自分の弱さを見せられる人の強さ
弱さを隠して生きるよりも、弱さを見せて助けを求める方が、実はずっと難しい。そして、それができる人こそが、本当の意味で強い人なのかもしれない。そんなふうに思えるようになった自分を、少しだけ誇らしく思う。
結局、孤独な職業だけど孤立はしなくていい
司法書士という仕事は、どうしても一人で抱え込みやすい。でも、孤独であることと、孤立することは違う。助け合える関係があるだけで、仕事の重さも変わってくる。あの日の電話が、そのことを教えてくれた。
同業者同士で支え合うことの意味
競争相手でありながらも、同じ苦労を知る仲間というのは特別だ。どんな励ましよりも、同じ立場にある人の「共感」が、心を癒す。情報交換でもなく、技術の話でもなく、ただ「わかる」という言葉が最も価値がある。
競争よりも共感が必要な世界
成果や件数を競うよりも、お互いに支え合える関係が大切だと思うようになった。数字よりも気持ち。売上よりも信頼。その方が、長くこの仕事を続けていける気がしている。
地方だからこそ、なおさら大事になる横のつながり
都市部よりも、顔が見える関係が多い地方では、同業者との横のつながりが本当に大事だ。いざというときに助けてもらえる人がいること。それだけで、孤独な仕事にも安心感が生まれる。