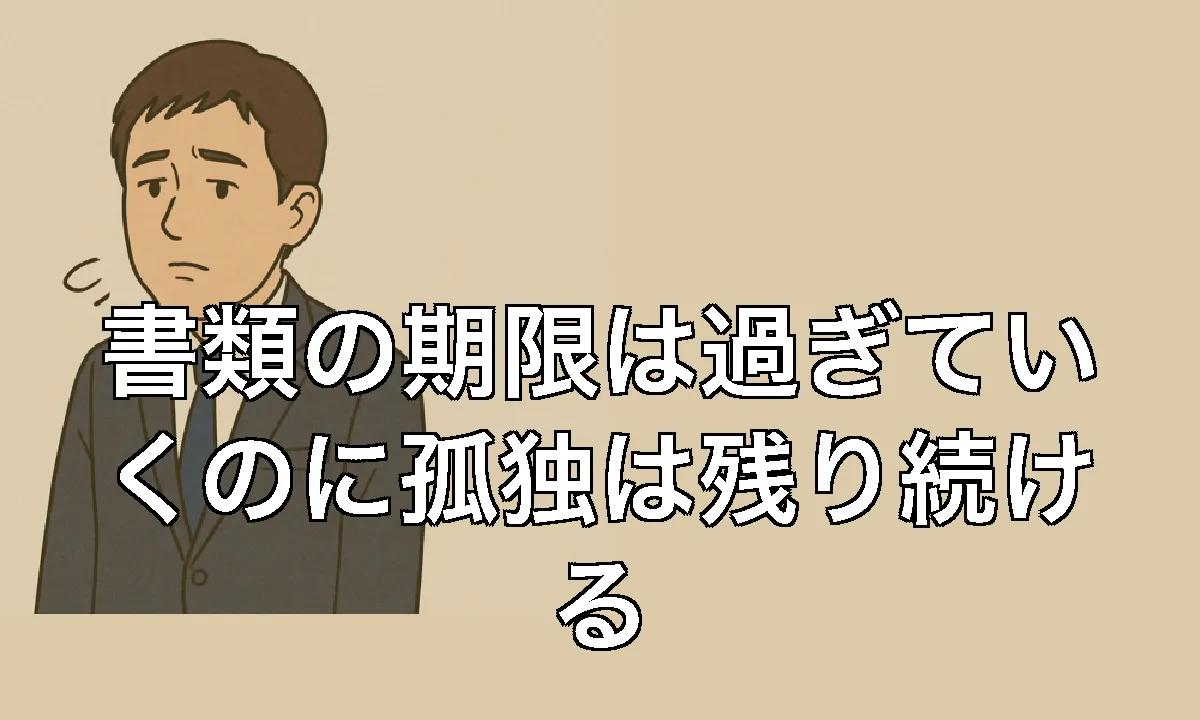書類に追われる毎日と心に残るもの
毎朝、事務所に入るとまず机の上の書類を確認する。登記の依頼、申請書類、期日の決まった案件……。ひとつひとつが期限付きで、放っておけばすぐにクライアントや関係機関に迷惑がかかる。でもふと、手を止めて思う。「こんなに期限に追われてるのに、自分の心のことはいつまで後回しにするんだろう」と。仕事は片付いていくのに、どこか胸の内にはぽっかりと穴が残る。その正体に向き合う暇もないまま、またひとつ締切がやってくる。
提出期限を守ることが仕事の基本
司法書士にとって、期日を守るのは信頼の基礎だ。登記申請の期限、決済日の調整、遺産分割協議の期日調整……。それらすべてに「この日までに」という数字がついてまわる。だからこそ、時間に対しては敏感になるし、自分の行動にもプレッシャーをかける。でも逆に言えば、「期限があるから終わらせられる」とも言えるのかもしれない。ゴールが明確に設定されているからこそ、人は走れるのだ。
カレンダーにびっしり書かれた予定と締切
私のカレンダーは、ほとんど白い隙間がない。打ち合わせ、申請準備、役所への提出、顧客への連絡…。スマホにも紙の手帳にも同じように詰まっていて、まるでそれが「生きてる証」のように感じてしまうことすらある。だが、その予定に「自分のための時間」はどこにもない。まるで他人のためにだけ時間が流れているような感覚になることもある。
終わる書類と終わらない感情の対比
書類はいつか片付く。印鑑をもらって提出すれば、それで一区切りがつく。でも、心の中にある孤独や焦燥感には終わりがない。誰かに相談したい、誰かと笑いたいという感情があっても、提出先もなければ締切もない。処理すべきフォーマットも、書式も、誰も教えてはくれない。だから、どんどん溜まっていって、気づいたら自分自身が置き去りになっている。
孤独には期限がないという事実
不思議なもので、孤独というのは「この日まで」と決められない。気づいたら始まっていて、終わったと思ってもまた戻ってくる。独身で、家に帰っても誰もいない。テレビがついているのに、音が壁に吸い込まれていくだけ。誰かに「寂しい」と打ち明けたくても、それすら躊躇ってしまう。司法書士という職業柄、人前では毅然としていなければならない、そんな無意識の縛りもあるのかもしれない。
気づけば誰とも話していない日
一度、気づいたことがある。朝から夕方まで、誰とも会話していない日があった。事務員は休みで、電話は留守電、訪問もゼロ。目の前の書類を淡々と処理するだけの一日。その日の終わり、ふと「今日は声を出してないな」と気づいたとき、背筋がゾッとした。まるで自分が存在していないかのような気持ちになった。
忙しさで埋まらない空白時間
よく「忙しくしていれば寂しさなんて感じない」と言う人がいるけれど、それは違う。むしろ忙しいときほど、ふとした隙間にぽっかりと孤独が顔を出す。クライアントとの電話を切った直後、帰宅して靴を脱いだ瞬間、コンビニのレジで「ポイントカードはお持ちですか?」と聞かれたとき。そういう何でもない瞬間に、「ああ、自分はいま一人なんだな」と突きつけられる。
仕事の中でふと感じる「虚しさ」
書類を整え、手続きを完了させる。それが司法書士の仕事だと割り切ってはいる。でも、機械的に処理しているだけの日が続くと、どこかで「これが本当に自分のやりたかったことだったのか」と虚無感に襲われる。感謝されることもあるけれど、それも一瞬のことで、すぐ次の案件に追われていく。やりがいという言葉が、どこか遠いものに感じてしまうのだ。
依頼人とは話すのに心は通わない
登記や相続の相談で、多くの人と接する。でもその大半は「業務のやり取り」だけに終始する。たとえ雑談を交わしても、それ以上踏み込むことはない。ある意味で、こちらも「距離を取ること」に慣れてしまっているのかもしれない。だが、そうやって人との関係を線引きしていくうちに、自分が誰とも深く関われなくなっていることに気づく。
形式的なやりとりに慣れすぎた結果
電話応対も、書面の送付も、挨拶も、すべて「業務の一部」として処理する癖がついている。だからこそ、心を込めたやりとりが苦手になってきた。若い頃はもっと人との関係に敏感だったはずなのに、今は「効率的なやりとり」が正しいと思い込んでいる自分がいる。そうやって人間らしさを削っていった先に、何が残るのだろう。
声をかけてほしいのはこっちかもしれない
ある日、相続の相談に来た高齢の女性が、「先生もお一人なんですか?」とぽつりと聞いてきた。そのとき、思わず「ええ、まあ…」と曖昧に答えたけれど、心の中では「本当は自分の方が話しかけてほしかったのかも」と気づいた。人に頼られる立場であるはずの司法書士だが、時には誰かに気づいてほしいと願っている自分がいる。
事務員との関係に救われる瞬間
たった一人の事務員がいてくれることで、日常が保たれていると感じることがある。業務的な話だけでなく、ちょっとした愚痴や冗談を交わせるだけで、心が軽くなる。もし彼女がいなかったら、仕事場がただの「作業空間」になってしまうだろう。たった一人でも、心を許せる存在がいるというのは、実はとても貴重なことなのかもしれない。
何気ない会話が唯一の人との接点
「先生、これってどう処理すればいいですか?」と声をかけられる。それだけのやりとりが、妙に嬉しかったりする。仕事の話ではあるけれど、「自分が必要とされている」という感覚を与えてくれる瞬間だ。お昼を買いに行くタイミングがかぶったとき、並んで歩きながらする他愛もない会話。ああ、今日も誰かとちゃんと会話できたな、とホッとする。
それでも距離は埋まらないこともある
事務員とはあくまで雇用関係だし、そこに甘えすぎてもいけない。向こうにも生活があり、人生がある。たとえ距離を感じる瞬間があっても、それを責めるわけにはいかない。ただ、その距離を意識するたび、自分の中にある孤独がよりはっきりと輪郭を持って現れてくる。
書類の山の先に何があるのか
ひたすらに業務をこなし、書類を積み上げていく。その先に何があるのか、自問自答する日々がある。司法書士として生きる以上、ある程度の孤独や責任は仕方ないと理解しているつもりだ。でも、それだけで人生が終わってしまうのはどこか虚しい。もう少し、自分の心と向き合う時間を持たなければ、何のためにこの仕事をしているのか、わからなくなってしまう。
数字と手続きに追われて見えなくなる本質
登記簿の番号、提出日、登録免許税…。そうした数字に囲まれていると、「人間の営み」というものを忘れてしまいそうになる。司法書士は本来、誰かの人生の節目に関わる存在だ。結婚、相続、事業承継…そうした背景にこそドラマがあるはずなのに、数字と書式だけで捉えてしまうと、その大事な部分を見落としてしまう。
誰かの人生に関わっているという重み
ある日、不動産の名義変更に来た若い夫婦の笑顔を見て、はっとしたことがある。「この手続きは、ただの登記じゃない。新しい生活の始まりなんだ」と。その瞬間、少しだけ心が温かくなった。そういう瞬間をもっと大切にしていけば、業務にも少しずつ意味が感じられるのかもしれない。
でもそれを感じる余裕がない
問題は、その「温かさ」を感じる余裕が、日々の業務に追われる中ではなかなか持てないということだ。時間に追われ、数字に追われ、次の依頼に追われていく中で、心を動かす余白がどんどん削られていく。そんな日々が続くと、やりがいの源すらわからなくなってしまう。
心の締切を意識して生きるということ
書類のように、孤独にも「締切」があったらいいのにと思うことがある。でも、そんな都合のいい話はない。だからこそ、自分自身で「ここまでに何か変えよう」と心に区切りをつけていくしかない。誰かに頼ることを怖れない、弱さを隠さない、それが「心の締切」になるのかもしれない。
自分の感情にも区切りをつけてみる
一日一日、仕事に追われていく中で、たまには自分に問いかけてみる。「今日はちゃんと笑えたか」「誰かにありがとうと言えたか」。そんな小さな振り返りでも、心の整理につながる。感情を垂れ流しにせず、きちんと折りたたんでしまうこと。書類のように、自分の気持ちにも整理整頓が必要だ。
孤独に慣れすぎる前にできること
孤独は、気づけば染みついてしまう。でも、それに慣れすぎる前に、何かアクションを起こした方がいい。友人に連絡する、誰かのSNSにいいねを送る、あるいはこの記事のように、文章にして自分をさらけ出す。そうやって誰かに届くことを信じるだけで、孤独はほんの少し軽くなるのかもしれない。