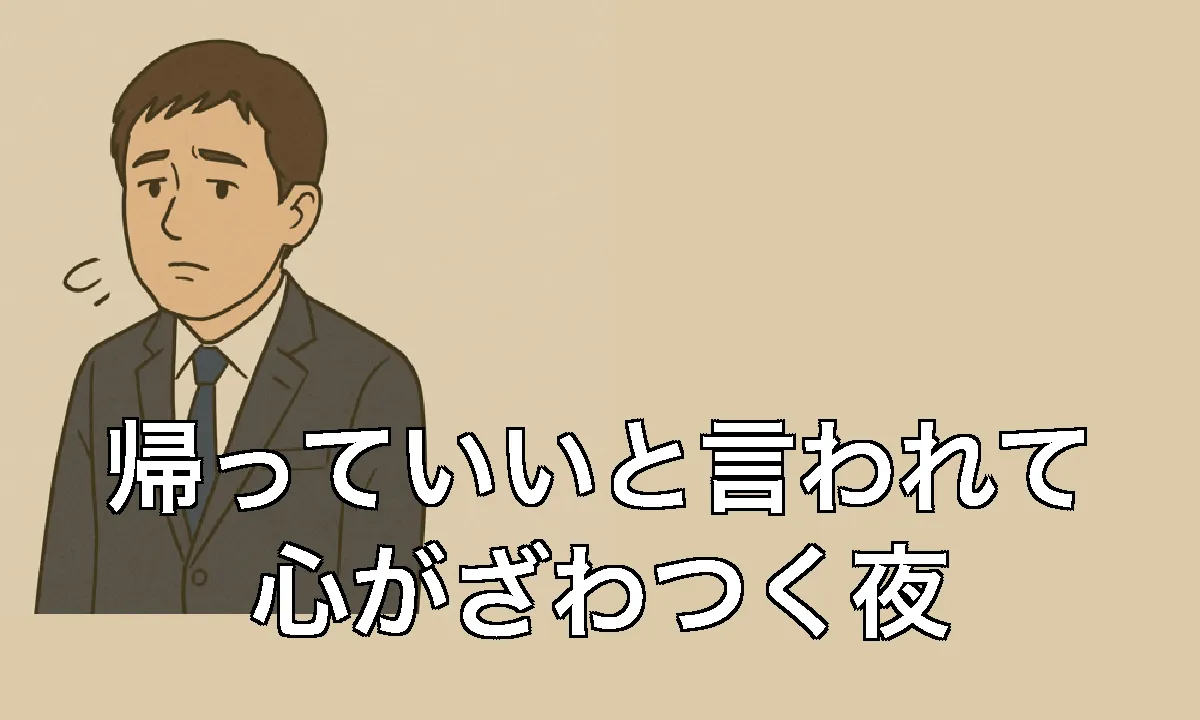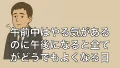一言の優しさが心に重くのしかかる夜
「もう帰っていいですよ」。その言葉は、たしかに優しさでできている。でもなぜか、心に重くのしかかってくる。あの一言で、急に自分が不要な存在になったような気がするのはなぜだろう。事務所で一緒に働いてくれている事務員さんが僕を気遣ってくれて発するその言葉に、むしろ深くえぐられるような感覚すらある。たぶん、自分のなかにある「役に立たなければ存在価値がない」という呪いのような感情が顔を出すのだと思う。疲れているのに、帰れない夜がある。それは物理的に帰れないのではなく、気持ちが帰ることを許してくれない夜だ。
帰っていいですよの破壊力
その日も残業が続いていた。夕方を過ぎ、少し早めに切り上げようとしていたところに、事務員さんが言った。「先生、もう帰ってください。私やっときますので」。ありがたい。その言葉だけで救われるはずだった。けれど、心は妙にざわついた。まるで、グラウンドからベンチに下げられたときのような感覚だった。元野球部の僕にとって、「役に立たない」と思われるのが何よりもきつい。彼女の言葉に悪意などないのはわかっている。それでも、どこか自分が戦力外通告を受けたような寂しさを感じたのだ。
感謝と虚無が同時に押し寄せる瞬間
彼女には心から感謝している。毎日黙々と働いてくれて、僕よりも細かく気を回してくれることもある。その彼女が僕を思って言ってくれる「帰ってください」は、ありがたすぎるほどの言葉だ。ただ、感謝の気持ちと同時に、「じゃあ、俺いなくても平気か…」という虚無感が押し寄せる。事務所のドアを開けるその瞬間まで、ずっと心の中で揺れている。ありがたい。でも、寂しい。必要とされていないようで、胸がチクチクする。
仕事が終わったはずなのに気が抜けない
いざ帰っても、頭の中では仕事のことがグルグル回っている。登記漏れがないか、連絡を忘れていないか、郵送物の確認は済んでいるか。気にしだすと止まらない。頭の中では帰宅したはずなのに、心はまだ事務所に置きっぱなしだ。だから、帰宅してもテレビをつけっぱなしにして、ソファでそのまま眠ってしまう。なにかを考える余裕も、手を動かす気力もない。あの「帰っていいですよ」が、僕を一日中支配しているように感じる。
置いていかれたような孤独感
たとえ先に帰っても、心が晴れることは少ない。むしろ、「俺だけ何もしてない」という罪悪感が残る。何もしてないどころか、朝から晩まで働いていたはずなのに。たぶんこれは、司法書士という職業にある種の「使命感」や「責任感」が染みついてしまっているからかもしれない。事務員さんがまだ作業をしている姿を想像すると、そわそわしてしまう。誰かを置いて帰ることも、誰かに置いていかれることも、同じくらい居心地が悪い。
事務所に一人取り残された感覚
逆に、事務員さんが先に帰って自分が残るときもある。そのときの静けさが、また堪える。カチカチというキーボードの音も、電話のコール音もなくなった事務所は、まるで真空状態のようだ。そんな中でパソコンに向かいながら、「何のためにこんなに遅くまで…」とつぶやいてしまう。声に出してみても、誰も返事をくれない。無音が、仕事へのやる気だけでなく、自分の存在までも吸い取っていくような気さえしてくる。
誰にも求められていない気がしてくる
「先生いなくてもまわりますよ」と冗談まじりに言われたことがある。それは気遣いの言葉だったはずなのに、なぜか今でも頭に残っている。役に立つために働いているのに、役に立たないと感じると、急に立ち位置を失う。特に、家庭があるわけでもなく、誰かに必要とされている感覚が希薄な日々の中では、職場だけが自分の居場所になっている。だからこそ、「もう帰っていいですよ」の一言に、自分の居場所が一瞬で崩れるような錯覚に陥るのだ。
司法書士という役回りの不器用さ
人の手続きを支えるのが司法書士の仕事だ。だけど、自分自身の感情の手続きには妙に不器用だと思う。誰かに喜ばれると、うれしい。それは本当。でも、感謝されてもどこか満たされないような、自分の中の空白に気づいてしまう日がある。誰かにやさしくすることはできる。でも、自分にやさしくするのは苦手だ。
優しさを与える側の孤独
相談者や依頼者には、できるだけ丁寧に向き合いたい。事務員さんにも負担をかけすぎないようにしたい。だからこそ、こっちが苦しくても、つい「大丈夫ですよ」と言ってしまう。そうしているうちに、自分だけがずっと後回しになってしまう。優しさを与える側にいることで、逆に自分の孤独が強調される瞬間がある。
誰かを労う言葉が自分には届かない
「先生も大変ですね」と言われることがある。でもそれは社交辞令のようにも聞こえて、素直に受け取れない。むしろ、「大変そうに見せてしまってるのか」と自己嫌悪に陥る。人に気を遣わせないようにと頑張ってきたけど、気づかぬうちに自分自身が孤立していたのかもしれない。人を気遣えば気遣うほど、自分への言葉が遠く感じる。
役割に埋もれる自分
「司法書士として」という言葉に、自分の人格がどんどん押し込められていく感覚がある。プライベートでさえ、「先生」と呼ばれたり、法律の相談を受けたりする。それはありがたいことだ。でも、いつの間にか、自分がただの“機能”になってしまったように思える瞬間がある。役割に応じて振る舞ううちに、本当の自分がよくわからなくなる。