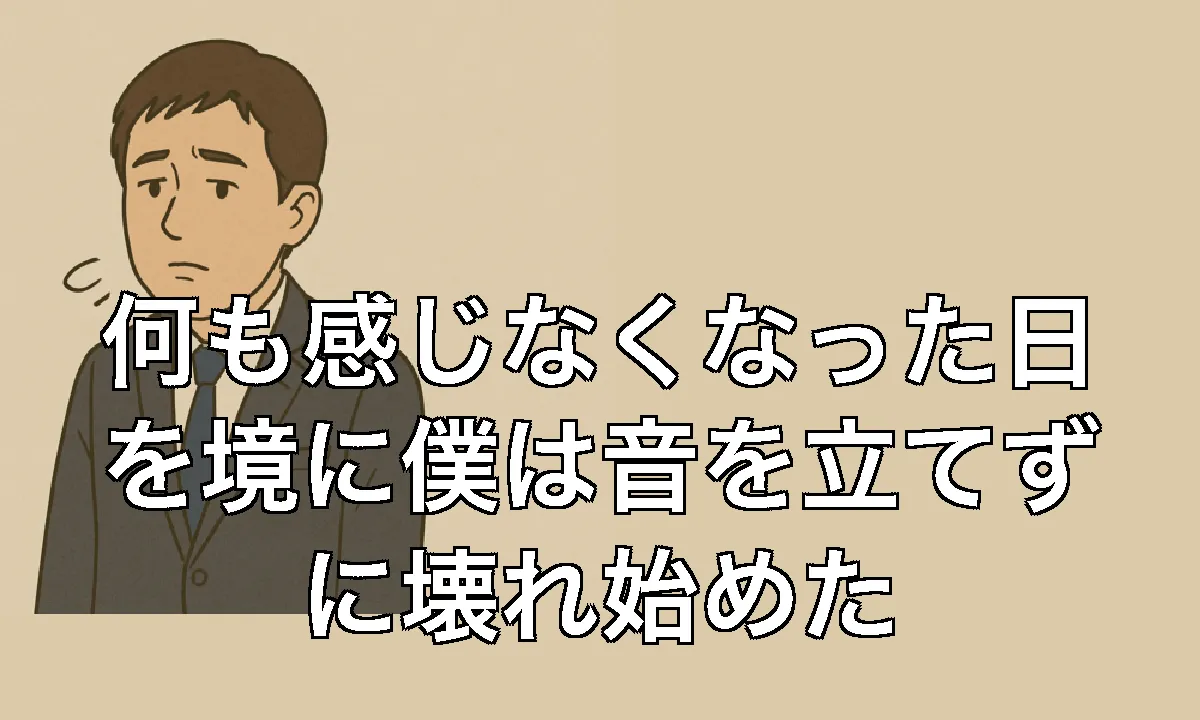朝起きても何も感じないという異常
毎朝のルーティンは変わらない。アラームが鳴り、目を覚まし、顔を洗ってスーツに袖を通す。けれどある日、ふと気づいた。胸の中にまるで何もないのだ。焦りも不安も、昨日の出来事の名残も、何も。単なる疲れかと思ったが、そんなレベルではなかった。感情のスイッチそのものが壊れてしまったような無音の世界が、僕の朝に広がっていた。これは危険なサインだったのかもしれない。
昔は仕事のことで胃が痛くなった
司法書士として開業して10年。最初の数年は、登記のミスや相談者の言葉ひとつひとつに神経をすり減らしていた。寝る前に明日の申請内容を何度も確認し、胃がギュッと締め付けられるような感覚に苦しんでいた。あの頃はしんどかったけど、少なくとも「感じて」いたのだ。今となっては、そんな自分が少しだけ羨ましい。何かを恐れ、何かを考えられる自分が、まだそこにはいたのだから。
今は痛みすらないことが怖い
今は、どんなに厄介な案件が入ってきても動じない。クレームを受けても、「はいはい」と流せるようになってしまった。そうなることが「慣れ」だと思っていた。でも、違った。それは、感情の死だ。痛みも怒りも、感謝すらも感じられない自分に気づいたとき、僕は震えた。「こんな自分が、誰かの大事な手続きを扱っていていいのか?」。そう思ったとき、初めてまた少しだけ「感じた」気がした。
感情が抜けていく日常
忙しい日は続く。朝から晩まで、電話とメール、書類の確認と押印。目の前の作業をこなすことだけに集中していると、気づけば一日が終わっている。ふと、夕方の窓に映る自分の顔が無表情であることにゾッとする。何も感じずに一日が終わる。その繰り返し。こうして少しずつ、自分の中の何かがすり減っていくのを、誰も教えてくれない。だからこそ、自分で気づかなければならないのだ。
登記も相続もこなせるようにはなったけど
技術的な面では、だいぶ慣れてきた。不動産の名義変更も、会社設立の登記も、相続案件も、ある程度の流れとパターンで回せるようになった。けれど、便利になればなるほど、そこに人間味がなくなっていく感覚があった。依頼者の事情に心を寄せる余裕がなくなり、ただ「処理」するだけの毎日。効率化の裏側で、心の温度はどんどん下がっていった。
効率化の果てにあったのは虚無だった
一つひとつの業務を効率的にこなすこと。それが目標だったはずだ。けれど、効率だけを追い求めると、心がついてこなくなる。「早く終わらせること」が最優先になると、誰かの不安に寄り添う余裕などなくなる。たしかに、効率は上がった。でも、代わりに得たのは虚無だった。笑顔で感謝されても、自分の心には何も響かない。これは本当に、望んでいた未来だったのだろうか。
書類の山は自分の気持ちを埋めるものではなかった
事務所の机には、今日も書類が積まれている。達成感ではなく、義務感で処理しているだけ。それでも、「忙しくしていれば何も考えなくて済む」と思っていた。けれど、埋めようとしていた心の隙間は、書類では埋まらなかった。ただただ紙が増えていくだけだった。重ねられた書類の厚みは、心の空洞の深さを示しているようで、目を背けたくなった。
「大丈夫?」と聞かれても反応ができない
久しぶりに知人に会ったとき、「元気?」と聞かれて、答えに詰まった。「大丈夫」と口では言うけれど、本当にそうなのか自分でもわからない。感情の回路が鈍くなっていると、人の言葉にもどう返せばいいのかわからなくなる。会話が苦手になったわけではない。ただ、言葉が胸に届かないだけ。そんな自分に気づいて、さらに落ち込んでしまう。
優しさにすら鈍感になってしまった
ある日、事務員さんがコーヒーを買ってきてくれた。「先生、疲れてそうだったから」と笑いながら。昔なら「ありがとう」と自然に言えた。でも今は、その優しさを受け取ることすらどこか億劫だった。「気を使わせてしまった」と感じるだけで、感謝の気持ちすら湧かない。それが一番しんどい。人の気持ちに反応できない自分は、どんどん壊れているんだと思った。
誰かの気遣いすら負担に感じてしまう
本来なら嬉しいはずの気遣いが、なぜか重く感じる。自分の中の感情の回路が詰まっているせいで、素直に喜べないのだ。「また何か返さなきゃ」とか、「どう思われてるんだろう」とか、考えすぎてしまう。相手はただの親切のつもりでも、自分の中では処理しきれない。そうして、人との関わりがどんどん面倒になっていく。それが悪循環を生むとわかっていても、止められなかった。
事務員さんの笑顔に救われる瞬間
何も感じない毎日でも、唯一、ふとした笑顔に救われるときがある。事務員さんがコピー機の前で小さく笑ったとき、なぜか涙が出そうになった。些細な瞬間に心が反応する。感情は死んだわけじゃない。眠っていただけなんだと、その時初めて気づいた。誰かの自然な表情が、自分の心をノックしてくれることがある。その扉を、閉じたままにしてはいけない。
心が壊れる音は静かだった
ドラマみたいに突然泣き崩れるわけでもないし、叫ぶこともない。ただ、静かに、何も感じなくなる。それが一番怖い。壊れる音はしない。でも確実に、何かが崩れている。その兆候を、自分だけが気づけない。だからこそ、こうして言葉にして残しておくことに意味があるのかもしれない。少しでも誰かの心に届けば、自分の鈍くなった感情にも、何かが戻ってくるような気がする。