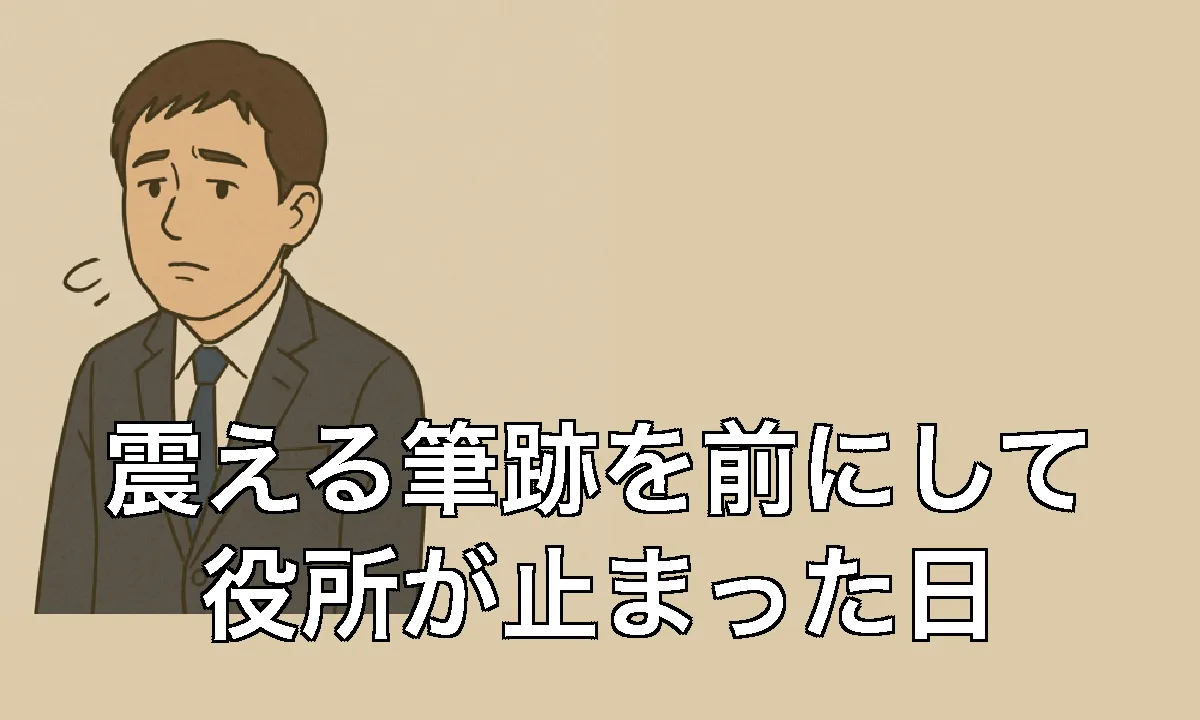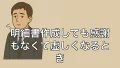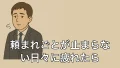高齢の依頼人が書いた一通の書類
その日、ひとりの高齢の依頼人が、手を震わせながらも何とか書いた遺産分割協議書を持参された。紙いっぱいに広がった文字は、まるで波打つように揺れていて、正直なところ読むのも大変だった。でも、そこには彼女なりの「家族への想い」と「きちんと終わらせたい」という気持ちが、にじみ出ていた。筆圧の強弱も、行のズレも、機械的なフォントでは表せない人間らしさそのものだった。
文字が揺れる それでも本人の意思は揺らがない
その依頼人は80代半ばの女性で、数年前に夫を亡くして以来、ひとりで暮らしていた。相続手続きをきちんとやっておきたいという意思は強く、何度も通ってきてくれた。ペンを持つ手が震えるたび、「これでもいいかしら」と聞かれたが、その表情には覚悟があった。本人が自分の意志で書いたこと、それが何よりも大事だと、僕は思っていた。
書類を突き返した役所職員の一言
提出したその書類を見た役所の担当者が、まるで埃でもついているような目で言った。「これ、読めないですね。再提出でお願いします」。その瞬間、頭の中でブチッと何かが切れそうになった。形式的な基準は大事だと分かっている。でも、その書類には、たったひとりの人生の集大成が詰まっていたんだよ。読めないのは努力が足りないんじゃなくて、心が足りないんじゃないか。そんな思いがこみ上げた。
現場の柔軟さと窓口の硬直さ
司法書士として仕事をしていると、役所や法務局の対応にため息が出ることも多い。柔軟に考えてくれる人もいる一方で、書式や文字の「正しさ」だけを見て、背景を想像しようともしない人もいる。もちろん「読めないものは受け取れない」という理屈も理解はする。でも、せめてその人がどんな気持ちで書いたのかくらい、見てやってほしいと願う。
書類を読む側の都合 書く側の現実
そもそも高齢の依頼人が自筆で書類を用意するのは、かなりハードルが高い。認知機能が衰えていなくても、視力や手の力が落ちていれば、まっすぐな文字を書くのは至難の業だ。それでも自分で書こうとする姿勢にこそ、敬意を払うべきじゃないかと思う。私たちが見るのは、ただの文字ではなく、その背景にある生活と人生なのだから。
筆跡が読めないからといって無効なのか
実務上は、文字の可読性が判断のポイントになることはある。でも、「読めない=無効」という単純な判断が、どれだけ依頼人を傷つけるかを考える人は少ない。例えるなら、耳の遠いお年寄りに小さな声で話しかけて「返事がないから無視された」と言うようなものだ。読み取る側の工夫や努力を、もっと評価される仕組みにしてほしい。
形式を守るあまり壊れていく本人確認
最近では「本人確認」が厳格化される傾向にあるけれど、機械的な基準だけで「本人らしさ」を測れるわけじゃない。震える筆跡も、実印のわずかなズレも、むしろそれが「本人の証」であることがある。決まった枠に当てはめることでしか確認できないなら、それは本来の目的から外れている。誰のための制度なのか、原点に立ち返って考えたい。
司法書士としてのジレンマと葛藤
こういう場面に出くわすたび、「俺、何のためにこの仕事してるんだろうな」と考え込んでしまう。依頼人のために戦いたい。でも、ルールを破っても意味がない。間に立つ司法書士は、感情を飲み込みながら手続きを前に進めなければならない。黙っていた方が円滑に進むと分かっていても、心がついてこないことがある。
依頼人のために怒るべきか冷静であるべきか
怒りの感情が湧いても、そこで声を荒げたところで物事が進展するわけではない。むしろ状況を悪化させることもある。でも、何もしなければ「この人は何も言わない」と見られるのもまた事実。毎回、自分の中で葛藤する。「言うべきか、言わざるべきか」。それは、まるでストライクかボールか微妙な球を見逃すような感覚に近い。
怒鳴ったところで変わらない でも黙っていられない
何度も役所に掛け合い、丁寧に説明しても結局「前例がないので無理です」と断られることもある。そのたびに、「こんなに頑張ってるのに…」という虚しさが襲ってくる。怒っても変わらない、でも言わないと自分が壊れる。そんな気持ちで、何度も書類を見直して、代替案を考える日々。ああ、誰かに聞いてほしい。
自分の立ち位置がぐらつく時に思い出すこと
迷ったときに思い出すのは、過去に「ありがとう」と言ってくれた依頼人の顔だ。制度に負けそうになっていた私を支えてくれたのは、結局その一言だった。仕事の成果が見えにくいこの世界で、そうした言葉が一番の救いになる。だから今日も、「誰かの役に立ってるはず」と自分に言い聞かせながら、机に向かっている。
元野球部としての我慢強さに救われる瞬間
地味なルーティンや、理不尽に耐える日々。こんなのは高校時代の部活と変わらない。炎天下でノックを受け続けたあの頃が、今の我慢の源になっている。踏ん張りどころでは、いつも心の中で「ここが9回裏だ」と唱えている。独身だしモテないけど、せめて自分の背中には恥じないように、立ち続けたいと思う。
書類とは誰のためのものなのか
役所に出す書類は、ただの紙ではない。それは人生の節目に寄り添う「証」であり、本人の想いの詰まった「声」でもある。そんな大切なものを、「読みにくいから」と突き返すのは、あまりにも機械的すぎる。形式と人の想い、その間をつなぐ存在として、司法書士の役割は本当に重い。そして、誇りに思いたい。
本人の意思が込められた一筆の重み
依頼人が震える手で書いたその文字は、決して美しくなかったかもしれない。でも、そこにこそ「本人の意思」があった。機械で打った文字では出せない、想いの重さがにじんでいた。その一筆がある限り、私たちはその人の人生に寄り添っているという実感を持てるのだ。効率だけでは測れない価値が、そこにある。
パソコンのフォントにはない温度
最近の若い依頼人は、全部Wordで済ませようとする。でも、それが悪いとは言わないけれど、手書きの文字には不器用なりの「温度」がある。それを感じられるかどうかで、対応も変わってくる。効率重視の時代だからこそ、非効率に宿る人間らしさを、もう少し大切にしたいと思っている。
綺麗でなければ通らないという不文律に抗う
「読みやすい字でお願いします」と言われるたびに、「じゃあ、誰が決めたんだよ」と思う。最低限の可読性は必要だ。でも、それを盾にして依頼人の声を無視するのは、プロのすることじゃない。司法書士として、自分なりの矜持を持って、不条理と戦っていくしかない。たとえ結果が同じでも、心の持ちようは違うから。
最後に押されたのは 震える手の実印だった
その書類に、最後に押されたのは、小さく震える手による実印だった。朱肉が少し滲んで、印影も少しずれていた。でも、それが本人の手で押された確かな証だった。きっとこの仕事は、派手なことも感動的な瞬間も少ない。だけど、そのひとつひとつの「証」に立ち会えるという意味では、悪くないなと思う日もある。