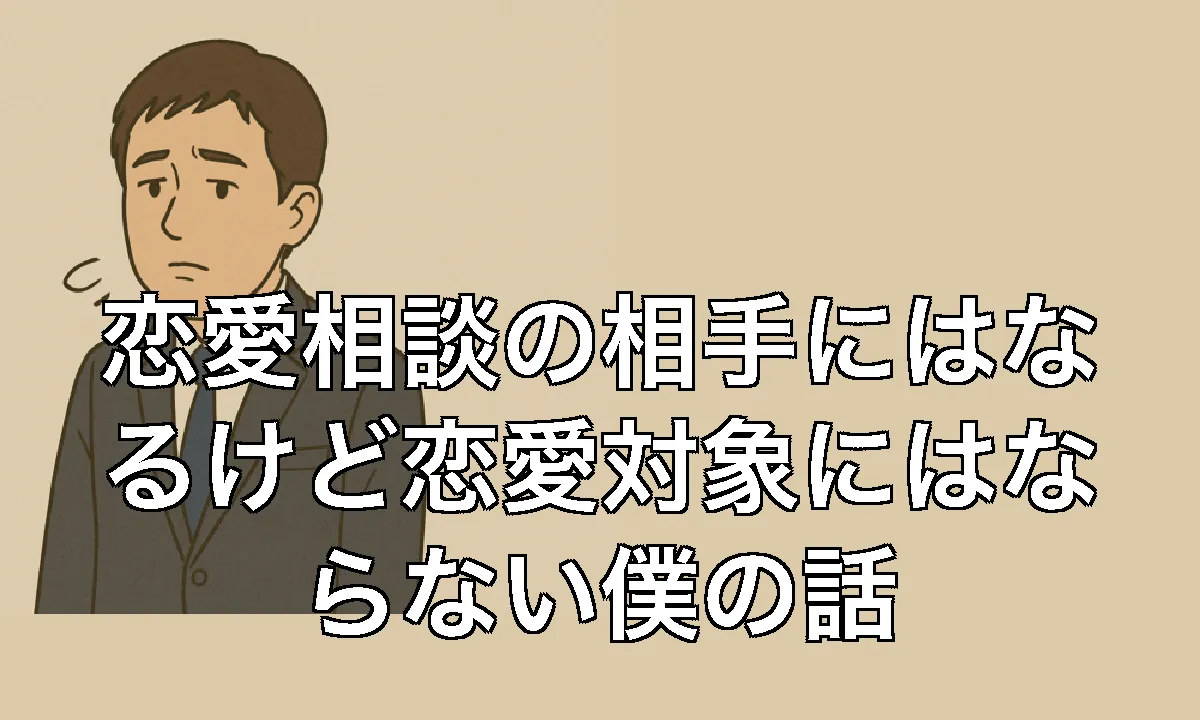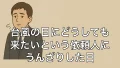恋愛の話は聞けるのに恋は始まらない
学生時代から、なぜか恋愛相談を持ちかけられることが多かった。真面目で優しそう、話しやすい…そんな評価はいつしか僕の定位置になった。でも一度も「好きになった」とは言われたことがない。相談を真剣に聞けば聞くほど、「この人は頼りになる」と思われて終わる。特に司法書士として日々人の相談を聞く今、プライベートでも「聞く側」に徹してしまいがちだ。
いつの間にか「話しやすい人」枠に収まっていた
司法書士になってからも、友人や知人、はたまた依頼人の家族からまで「ちょっと相談していいですか」と言われることがある。相談内容は仕事ではなく、恋愛や家庭の話。聞いているうちに「私、今の彼とはどう思いますか?」なんて展開になる。そして気づくと、彼女たちは誰か別の男性と付き合っていく。僕はただの通過点だったのだ。
「優しそう」って便利な言葉
「優しそうですね」って褒め言葉だと思っていた。でもそれは、壁がなさそう、安全圏、つまり「異性としてのドキドキはないですよ」という遠回しな拒否なんじゃないかと感じるようになった。学生時代の合コンでも、社会人になってからの飲み会でも、言われるのは決まって「安心する人」。恋のスタートラインには立っていなかった。
元野球部の肩幅は恋には使えない
昔、野球部だったことがあって、肩幅は人並み以上にある。でも、恋愛では筋肉も努力も通用しない。むしろ「体育会系なのに優しいって珍しいね」なんて言われて、また安心枠へ。高校時代の後輩から「お兄ちゃんみたい」なんて言われたのが決定打だった気がする。恋愛対象にはならない、でも心の荷物は置いていける存在。それが僕のポジションだ。
アドバイスをすればするほど遠のいていく距離
真剣に相談に乗ると、距離が縮まるどころか、どんどん「兄貴」みたいな立場になっていく。ある時、ある女性から彼氏の浮気について相談された。親身になって話を聞き、どうすべきか一緒に考えた。でも数週間後には「彼、やっぱり反省してくれて…」と笑顔で報告されて終わった。僕はただの無料カウンセラーだった。
「そういうとこがいいんだけど…」の破壊力
決まって言われるのが、「そういうとこがいいんだけど、なんか違うんだよね」。何が違うんだ。そこがわからないからこそ、こっちは延々と「ただのいい人」に甘んじるしかない。きっと彼女たちが求めていたのは、ドキドキする恋であって、安心できる恋ではなかったのだろう。理屈じゃなく、感情の問題だというのはわかっている。
対象外の人にばかり話しやすくなる構造
自分でも気づかないうちに、「恋愛対象外の安心感」を醸し出すようになっているのかもしれない。笑顔、相槌、話の広げ方、そして何より否定しない姿勢。それが司法書士としてのスキルでもあるからこそ、プライベートでもそのまま出てしまう。結果、また「話しやすいね」と言われて、恋は始まらない。
独身司法書士のリアルな日常
この歳になると、恋愛云々の前に、日常を回すのが精一杯になる。朝から書類、役所、電話、時にはトラブルの火消し。終わるころには夜。隣の席の事務員さんは気を遣ってくれるが、あくまで「職場の関係」。仕事は積み上がり、私生活はどんどん削れていく。
仕事では頼られるけどプライベートは空洞
依頼人から感謝されることはある。「先生のおかげです」と言われるときは、やりがいを感じる。けれども、仕事が終わってドアを閉めた瞬間、誰とも共有できない「空っぽさ」が胸に広がる。家に帰っても、誰かが待っているわけでもない。スマホの通知も営業メールばかり。気づけば、土曜の夜も机の上の残り香だけが友達だった。
登記よりも自分の未来を整理したい
登記簿の名義変更はスムーズにできても、自分の人生の方向は全然見えてこない。「このままでいいのか」と思いつつも、日々に追われて何も変わらない。新しい出会いもない、行動力も失われる。もう一度、誰かと深くつながるには、何かを変える勇気が必要なのだろうが、それが難しい。
一人事務所の帰り道が長く感じる夜
仕事が終わり、鍵を閉めて帰路につくとき、ふと空を見上げる。田舎の星空はきれいだ。でもその美しさすら、誰かと共有できないと虚しくなる。「先生、今日も遅くまでお疲れさまです」と自分に言い聞かせながら歩く足取りは、少し重たい。誰かにおかえりと言ってもらえる日が来るのか、正直わからない。
愚痴になるけど誰かに届いてほしい
日々の中で、自分の気持ちを吐き出す場所がないと、どんどん心が沈んでいく。司法書士という肩書きの下には、一人の不器用な人間がいて、時には弱音も吐きたくなる。今回の記事も、そんな想いから書き始めた。誰かに共感してもらいたいのかもしれない。
「人を支える仕事」の裏側の孤独
士業って、誰かを支えるのが仕事だ。困っている人を助けるために、知識と時間を使う。それは誇らしいことだと思う。でもその裏で、支える側が誰にも支えられずに消耗していることもある。僕は多分、そんな典型なのかもしれない。声にならない声を飲み込んで、また次の日に備える日々だ。
感謝されるけど満たされない現実
「先生がいてくれて本当に助かりました」と言われると、救われた気になる。でも、それは一瞬。感謝の言葉と引き換えに、またひとつ自分の時間と心を差し出している。誰かに何かをしてもらう、という経験が減り続けていることに気づいたのは、つい最近だった。ずっと「与える側」でいると、空っぽになる。
相談を聞いてもらえる側になりたい
誰かに恋愛相談をされたとき、「俺の話も聞いてよ」と言えたらいいのに。そう思っても、口には出せない。変に意識させてしまうのも怖いし、何より「そんなキャラじゃないでしょ」と笑われそうだ。でも、本音を言えば、ただ誰かに聞いてほしいだけなんだ。そういう気持ち、きっと誰にでもあると思う。