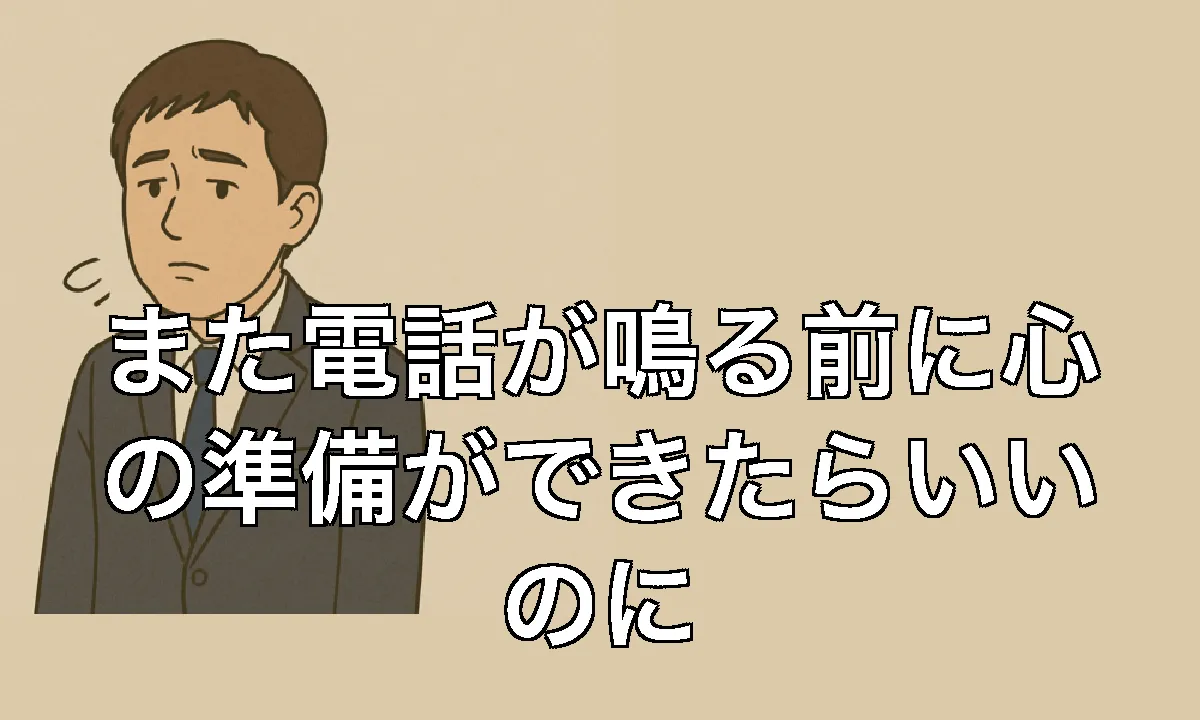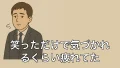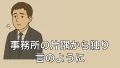一日の始まりが憂鬱な理由
朝、まだエンジンがかかっていない状態で、最初に聞く音が電話の着信音というのは、正直つらい。司法書士という職業柄、電話の一本が依頼の入口であることもわかっている。それでも、受話器を取るまでのあの妙な緊張感がたまらなく苦手だ。何が飛び出すかわからない会話、トラブルの予感、急なスケジュール変更……。まるで、目を覚ました直後にいきなりマウンドに立たされるようなものだ。
朝のコーヒーより先に鳴る電話
たとえば、まだ湯を沸かしている途中、寝癖もそのまま、そんなときに限って電話が鳴る。「ああ、また今日も始まったな…」と深いため息が出る。電話を取るか否か、数秒の間に頭の中で会話の予測をフル回転させるけれど、結局どんな内容がくるかなんて読めないのが現実だ。大したことのない問い合わせのときもあるが、たいていは重たい相談や急なトラブル。朝の時間に心の余裕がないこちらの状態など、お構いなしに電話の相手は本題に入ってくる。
着信音が胸をざわつかせる
携帯の着信音も固定電話の呼び出し音も、どこか苦手になってしまった。ピリリと響くその音に、条件反射のように胸がザワザワしてしまう。これがトラウマというやつかと、苦笑いすら出る始末だ。昔、野球部の試合前、サイレンが鳴る直前のような不安感がある。でも違うのは、あの時は仲間がいたが、今は基本的に一人で対応しなければならない。誰かに代わってもらうこともできず、無理してでも出なきゃというプレッシャーだけが残る。
内容が読めないから余計に怖い
電話の内容がメールのように最初から文字で伝わってくれば、こんなに構えずに済むのにと思う。メールなら、じっくり読んで、考えてから返せる。でも電話はそうじゃない。相手の声色やテンション、言葉の選び方から瞬時に情報を読み取り、自分も即座に応えなければならない。たった数秒で、誤解が生まれることもある。だから、相手の第一声が妙に高圧的だったり、急ぎの内容だと、こちらの心の準備がまるで追いつかない。
電話対応がもたらすストレスの正体
電話対応は、単に「出る」「話す」「終わる」ではない。実際はその前後に膨大な精神的プロセスがある。出るまでの葛藤、話しながらの気遣い、切った後のモヤモヤや対処の段取りなど、見えない部分が多すぎるのだ。中でも一番きついのは、「また何か言われるんじゃないか」「苦情じゃないか」という先入観に自分が縛られていること。気を抜けないという緊張が、慢性的なストレスにつながっている。
要件が複雑な場合の時間の奪われ方
一見シンプルな相談内容でも、話が進むにつれてどんどん複雑になっていくことがある。「少しだけお時間いいですか?」の一言が、1時間の拘束になることも珍しくない。途中で「あとで折り返します」と言えればいいのに、真面目な性格が邪魔して、つい最後まで聞いてしまう。そしてその後、別件の処理が遅れる。スケジュールにズレが出て、結局夜遅くまで仕事をする羽目になる。そんな日が続くと、電話に出ること自体が怖くなる。
感情をコントロールする難しさ
どんなに疲れていても、どんなに気が乗らなくても、電話口では一定のトーンを保たねばならない。それが「仕事」だとわかっている。でも正直、感情の起伏を抑えながら話すのは相当な技術がいる。怒っている相手には下手に出て、急いでいる相手には焦らずに対応し、初対面の相談者には安心感を与える。まるで役者のような切り替えが求められる。でも、切った後にどっと疲れが押し寄せてくる。
事務所における電話の立ち位置
電話は便利で欠かせないツールだというのは百も承知。でも、司法書士事務所において、その「便利」がストレスの種になっているという矛盾も存在する。メールやチャットが普及している今でも、やはり電話でしか伝えられない空気感や確認事項があるのも事実だ。それでも、電話を受けるたびに心が削られていく感覚は、きっと電話を取る人にしかわからない。
「問い合わせ」という名の地雷原
「ちょっと教えてほしいんですけど」という入りで始まる電話、これが厄介だ。法的な相談と単なる質問の境目が曖昧で、無償対応の範囲なのか判断に迷うことが多い。しかもその曖昧な状態で30分も話し込むと、後悔しか残らない。「これって無料相談で済む話じゃないですよね…」と、言いたいけど言えない。結局、損した気分で電話を切るのが日常になってしまっている。
軽い気持ちでかけてくる相手との温度差
かける側は「思い立ったから聞いてみよう」くらいの温度感だと思う。でもこちらは、仕事の手を止めて、資料を閉じて、頭を切り替えて対応している。その温度差が、じわじわと心を疲弊させていく。相手に悪気はないのだろう。でも、「こっちも今、別件で手一杯なんですよ…」と伝えられないもどかしさが、どこにもやり場がないストレスとなって積み重なる。
本当はメールで済ませてほしい
「この内容ならメールで送ってくれたら助かるのに…」と思うことはよくある。特に、確認事項が多いケースでは電話だと漏れも生じやすいし、後で「言った言わない問題」にもなりやすい。実際、以前それで一度トラブルになったことがある。だからこそ、できるだけ文面に残してもらいたい。でも現実には、電話が“早くて確実”だと思っている人もまだまだ多いのが悩ましい。
事務員との分担と心苦しさ
事務員がいるとはいえ、すべての電話を任せるのは気が引ける。複雑な内容やクレームっぽいものはどうしても自分が対応せざるを得ない。事務員に負担をかけたくない気持ちもあり、自分で抱え込みすぎてしまう。結局、心のどこかで「また自分が出なきゃ」と思い込んでしまい、それが電話恐怖を助長しているのかもしれない。
事務員に任せることへの罪悪感
忙しい時でも、無理に電話に出るのは、事務員への気遣いもある。怒鳴られたり面倒な案件に巻き込まれるのは、やっぱり自分が…という意識が強い。結果、自分の業務が滞る。でも、任せる勇気が出ない。だからこそ、職場内での「電話の分担」についても、もう少し柔軟に考えられたらと思う。
「先生お願いします」と来る恐怖
事務員が「先生、○○の件で…」と保留にする声を聞いた瞬間、胸がざわつく。いよいよ出番か、と思いながら、深呼吸をして受話器を取る。でも、心はすでに緊張でいっぱい。特に相手の名前に見覚えがあると、「またか…」という気持ちも湧いてくる。そんな感情の繰り返しが、日々の仕事の疲れに拍車をかけているのは間違いない。