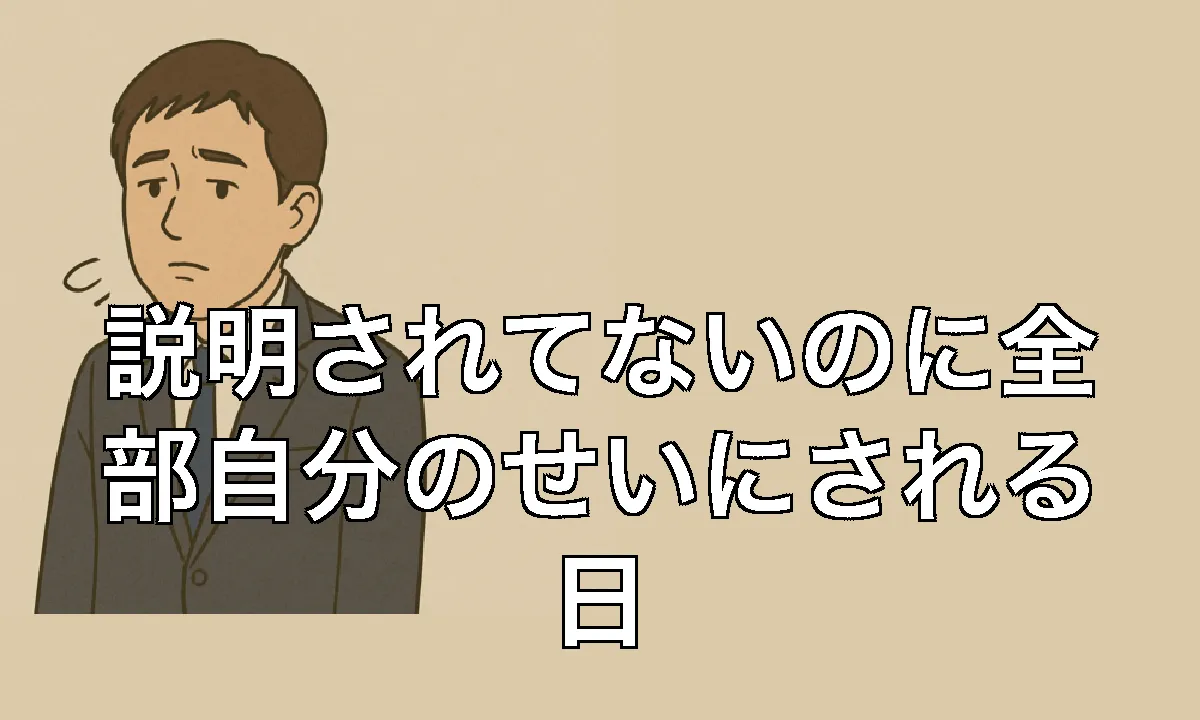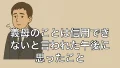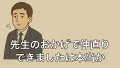司法書士という仕事は説明される側ではなく説明する側
司法書士の仕事というのは、基本的に「説明する側」に立たされる職業です。登記の意味、手続きの流れ、必要書類の趣旨。全てこちらが噛み砕いて伝えなければなりません。ところが相手の理解度や前提知識にはバラつきがある上、時間がない中でのやりとりが多い。結果として、「聞いてない」「知らなかった」という反応に直面することも少なくありません。にもかかわらず、そのフォローも含めて結局こっちの責任という構図。説明が足りなかったんじゃないかと、自分で自分を責めることが日常になってしまっています。
「聞いてない」では済まされない立場
先日、ある相続の案件で書類の提出漏れがありました。ご依頼主には事前に説明していた内容でしたが、「そんな話、聞いていません」とのこと。こちらとしては記録も残していたのに、それでも相手がそう言えば、もうそれ以上どうすることもできません。結局、「わかりにくく説明してしまってすみませんでした」と謝る羽目に。こういったことが続くと、どこかで「本当に自分が悪かったのか?」と感覚が麻痺していきます。
責任だけが降ってくる構造
司法書士は、「正しく説明し、正しく手続きを進める」ことが仕事です。でも現実には「正しく聞いてもらえるかどうか」はコントロールできないんですよね。たとえば書類のサインひとつにしても、場所を間違えて書かれてしまえば、「説明が足りなかったのでは」と突き返される。そうなると、こちらがその書類を補正して、また時間をとって再度手配して…と、責任だけがどんどんこちらに積み重なっていきます。
自分だけが理解しておかねばならないという圧力
司法書士としての役割を果たすためには、全体を俯瞰して進める必要があります。依頼者が気づかないポイントまで想定し、必要書類を先回りして揃え、何を質問されても答えられる準備が求められます。まるで自分だけがこの案件全体を理解しておかないと崩壊してしまうようなプレッシャー。誰かに頼ることもできず、相談相手すらいない日々が続くと、「一体誰のための仕事なのか」と虚しさがよぎる瞬間もあります。
なぜか先回りして謝る癖がついた
もう謝らなくてもいい場面ですら、「すみません」と口にしてしまう癖がついてしまいました。これも多分、説明責任が全部自分にくる立場に長くいるせいでしょう。ミスの有無に関係なく、とりあえず謝っておけば場が収まるということがわかってしまうと、謝罪が習慣になってしまう。けれどそれって本当に健全なのかと、ふと我に返る瞬間もあります。
自分が怒られないための予防線
昔、野球部でキャッチャーをやっていた頃、ピッチャーの暴投も自分のせいにして「俺が構えた場所が悪かった」と言ってました。今思えば、それと同じことをしているのかもしれません。トラブルを未然に防ぐには、まず自分がクッションにならなきゃいけない。でも、何でもかんでも自分が背負ってしまうと、だんだん心がすり減っていくのも事実です。
誰かを守るためでもあるが結局自分を守っている
自分が責任を引き受けるのは、相手を守るためであると同時に、自分がもっと大きな面倒を避けるためでもあります。怒らせない、クレームにならない、評判を落とさない。そうやって一見「誠実」に見える対応の裏側には、「面倒ごとは起こしたくない」という消極的な動機がある。それに気づいてしまうと、自分がなんとも情けなく思えてきます。
説明不足な相手でも責められない現実
そもそも、説明されていないことが原因でも、こちらがそれを指摘するのは難しい立場です。「ちゃんと聞いてください」と言えればどれだけ楽か。でも司法書士というのは、サービス業でもあり、士業でもあり、ちょっと微妙な立場なんです。言いたいことを言えば角が立つ。結局、やんわりとこちらが折れるしかないという現実があります。
立場上口ごたえすらできないジレンマ
相手が感情的になっているときほど、事実よりも感情の収拾が優先されます。こちらに非がなくても「すみません」と言わざるを得ない。逆に、「そちらが確認していなかったのでは」と言えば、「上から目線だ」と反発されるだけです。司法書士という仕事の性質上、「お客様」という言葉を使わないまでも、実質的には常に低姿勢が求められています。
ミスの原因がどこにあっても気づかなかった自分が悪い
誰かがミスをしても、「こちらで確認が甘かったですね」とつい言ってしまう。実際には、事前に何度も説明していても、向こうが覚えていなかったり、書類を読んでいなかったりする。でも、そういうことを声に出すと関係が壊れる。だから、「全部自分の責任」と言ってしまったほうが簡単で、すべてが早く収束する。そんな理不尽な選択を、いつの間にか受け入れている自分がいます。
でもたまにはちゃんと言ってくれと叫びたい
「それ、先に言ってくれよ…」と叫びたくなる場面が、本当にたくさんあります。小さなことから大きなことまで、こちらの知らないうちに状況が変わっていて、しかも「対応できていないこちらが悪い」とされる。もう、超能力者じゃないんだから…と自分に突っ込みを入れつつ、今日もまた説明責任の塊のような仕事に向き合っています。
孤独な責任感をどうやって消化しているのか
説明して、謝って、処理して、また謝って…そんな日々の中で、ふと立ち止まって考えることがあります。この重たい責任感、どこかに逃がせる場所はないのか。結論から言えば、正解なんてない。でも、一人で抱えすぎない工夫だけはしないと、自分が壊れてしまう。
野球部時代の無言の連帯感とは違う
学生時代、ミスしても誰かがすぐに声をかけてくれました。「ドンマイ」「次いこうぜ」って。今は違います。仕事ではミスした瞬間に信頼を失う危険がある。フォローの言葉もなければ、連帯感もない。ただ、黙って結果を出すしかない。その孤独がいちばんこたえます。
同じグラウンドに立つ仲間がいない
司法書士は基本的に一人仕事。現場で一緒に戦ってくれる人はいません。事務員さんはいるけれど、責任の矢面に立つのは常に自分。トラブルがあっても相談相手もいないし、アドバイスをくれる上司もいない。独立開業って聞こえはいいけど、実際には誰も助けてくれないんです。
ひとりで背負うことが習慣化してしまった
怖いのは、この孤独な状態に慣れてしまったことです。誰にも頼れないことが普通になって、弱音を吐くことすら忘れてしまう。「自分さえ我慢すれば」と思っていたら、それが当たり前になっていた。気づけば、ずっと肩に力が入りっぱなしの生活です。
それでも続ける理由はあるのか
こんなにしんどいのに、なぜこの仕事を続けているのか。自分でもたまにわからなくなります。でも、思い出すんです。たった一言の「ありがとう」が、どれだけ救いになるかを。理不尽な責任を押しつけられても、それを乗り越えた先に見える、たった一人の満足そうな笑顔。それが、この仕事の報酬です。
誰かの役に立てている感覚だけが支え
すべての手続きが終わったあとに、「助かりました、本当にありがとう」と言われた瞬間。それだけで、積もりに積もったストレスが少し和らぐのです。この仕事をしていて良かったと心の底から思える、数少ない瞬間です。
感謝の一言に救われた記憶
かつて、とても複雑な相続案件で長期間関わったお客様がいました。その方から最後に「先生がいてくれて、本当に助かった」と言われて、涙が出そうになりました。自分の苦労が誰かの役に立っていたのだと実感できた、忘れられない一言です。
ありがとうがある日は全部許せる気がする
結局、誰かに感謝されると、今日もまた頑張ろうと思えるんです。不思議なものです。説明責任が全部こっちにきても、怒られても、文句を言われても、たった一言の「ありがとう」で、心が報われる。そんな日がある限り、まだこの仕事を辞めるわけにはいかないんだと思っています。