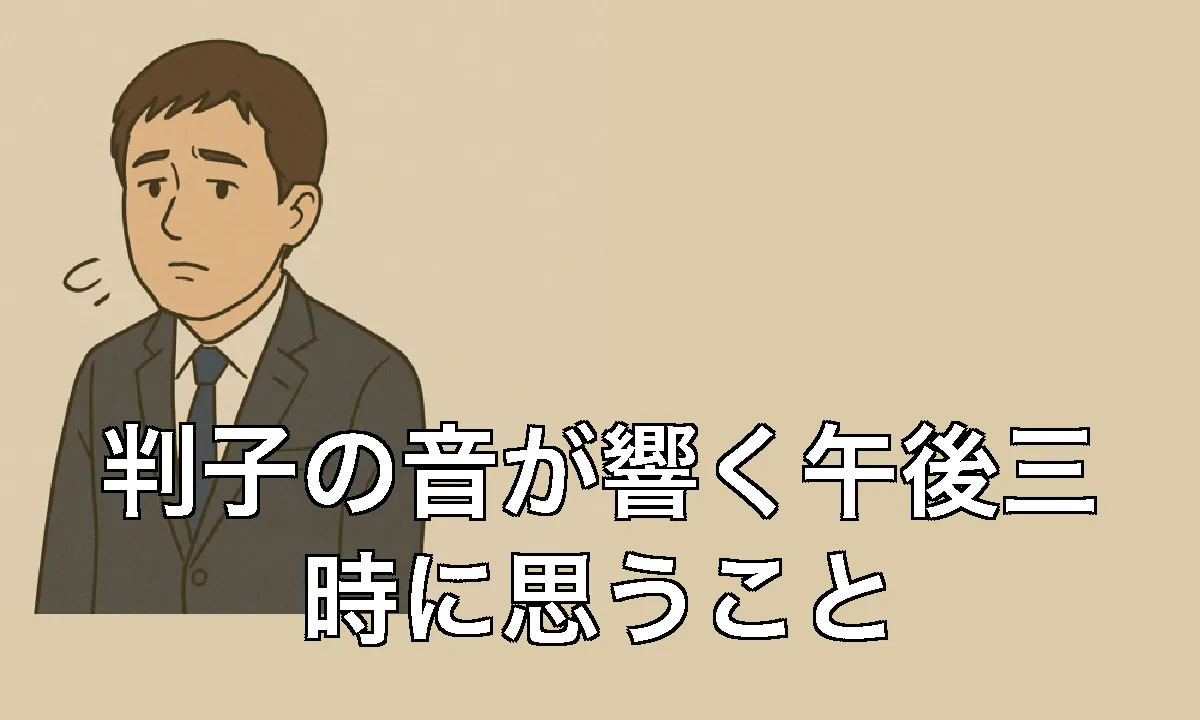午後三時の事務所に響く音
午後三時。世間では一息つくティータイムかもしれないが、僕にとっては妙に心がざわつく時間帯だ。外からの電話も一旦落ち着き、事務員も銀行に出ていて、事務所には僕一人。そんな静けさの中、登記書類に判子を押す音だけが「カツン」と響く。耳慣れたはずのその音が、なぜか今日は心に残る。誰に聞かせるでもなく、ただ自分のために押す判子。書類の山を前に、音だけが時間の経過を告げてくる。
判子を押すという仕事の重み
司法書士にとって判子は単なる印鑑じゃない。そこには「この内容を確認しました」「責任を持ちます」という覚悟が詰まっている。毎日何十枚と押しているはずなのに、時々ふと手が止まる。これで本当に間違ってないか?と。依頼人の人生に関わる内容もあるだけに、緊張が走る。ミスは許されない。どんなに疲れていても集中力を切らしてはいけない。
単なるルーチンでは終わらない
「ただ書類に印を押すだけでしょ」と言われたこともある。でも、その一押しに至るまでには何度も確認し、細かい点をチェックし、場合によっては法務局や依頼人とのやり取りもある。自分が思っているより、ずっと神経を使っている作業なのだ。手が勝手に動くようになっても、気持ちのどこかにピリッとした緊張感を持ち続けないと、いざという時に足をすくわれる。
音に込めた責任と緊張感
カツンという音は、小さな鐘のように自分にプレッシャーを与える。その一瞬で「よし、大丈夫だ」と心の中で自分に確認する。音の中には僕の覚悟が詰まっているのだ。だからこそ、その音がやけに大きく感じる日は、心のどこかで何かが揺れている証拠なのかもしれない。
誰も見ていない静けさの中で
午後三時の事務所は、妙に音が反響する。事務員がいない時間帯は特に、コピー機の音、マウスのクリック、そして判子の音が、まるで自分の孤独を強調するように響いてくる。この仕事、ひとりでやる時間が長いとはわかっていたけど、静かすぎると不安になることがある。
事務員も外出中のひととき
いつもは隣でカチャカチャとキーボードを叩いている事務員も、この時間だけはいない。たった一人になると、やたらと集中力が乱れる。「誰かに見られている」と思うと背筋が伸びるのに、それがないと途端に気が緩む自分がいる。独立してから何年経っても、まだこの感覚には慣れない。
音だけが自分の存在を証明する
カツンという音が鳴るたびに、「今、仕事をしている」と自分に言い聞かせているような気がする。誰かに評価されるわけでもなく、淡々と自分で自分を支えていく作業。それが司法書士の仕事なのかもしれない。見えない相手に向けて、静かに責任を積み重ねている。
なぜこの時間が苦しくなるのか
午後三時は、不思議と精神的な谷間になる。午前中の勢いが切れ、夕方にはまだ早い。やらなきゃいけないことは山ほどあるのに、手が止まる。そして、自分の置かれた状況や孤独を急に意識してしまう時間でもある。僕だけかと思っていたが、他の士業仲間も同じようなことを言っていた。
一日の中で最も集中が切れる瞬間
昼食の後、少し落ち着いたころにやってくる午後三時。この時間帯は本当に集中力が切れやすい。特に単調な作業が続いていると、気づけば手が止まり、窓の外をぼんやり見てしまっている。そんな自分に気づいては、「まだ今日もあと数時間あるのか…」とため息が漏れる。
昼過ぎの倦怠感と焦燥感
眠気まではいかないけど、体が重い。書類は溜まっているし、登記の期日も迫っているのに、どうにも気持ちが前を向かない。焦っても進まないことに苛立ち、かといって休むわけにもいかない。そんな午後三時は、まるで足に重りをつけたまま走らされているような気分になる。
やることはあるのに進まない
ToDoリストはびっしり埋まっていて、明らかに「暇」ではない。むしろ追われている。でも、その追われていることすら、もうどうでもよく感じる瞬間がある。そうなると、気持ちだけが焦って、実際には何も進まないという悪循環。頭ではわかっているのに体がついてこない。
ふと湧き上がる孤独の正体
静けさが心にしみる時間。誰とも会話せず、誰からも連絡が来ない午後に、急に「俺、何やってんだろう」と思う。普段は考えないようにしているけど、ふとした瞬間に浮かぶこの疑問が、妙にリアルで怖い。仕事をしていても、どこか満たされない感情がそこにはある。
誰とも話さないまま進む時間
午前中に数件の電話応対をし、それ以降ずっと無言のまま仕事をしていることも多い。夕方まで一言も発さずに終わる日も珍しくない。そんな日は、自分がだんだん透明になっていくような気がしてくる。声を出さないというだけで、こんなにも気持ちが塞ぐとは思わなかった。
人恋しさと虚しさの間で
別に誰かと話したいわけじゃない。でも、完全なひとりは辛い。誰かがそばにいるだけで、こんな気持ちは少しは和らぐんじゃないかと思う。けれど、実際にはそう簡単に人を呼べる仕事でもない。人恋しさと煩わしさの狭間で、心が揺れる。結局、またカツンと判子の音が鳴る。
過去の自分に話しかけたくなる
午後三時の沈黙の中、ふと過去の自分を思い出す。なぜこの道を選んだのか、何を目指していたのか。司法書士になったあの頃の理想や、もっと若かった自分が持っていた熱量。そんなことを考えながら、今の自分と静かに向き合う時間になる。
元野球部だった頃の午後三時
高校時代、午後三時はグラウンドで声を張り上げていた時間だった。汗だくでボールを追いかけ、練習メニューをこなしていたあの時間帯。声を出し、走って、全身で自分の存在を示していた。今は、その時間に椅子に座って判子を押している。まるで別人のような静けさが、時折心を締めつける。
声を出して走っていたあの時間
「声が出てないぞ!」と先輩に怒鳴られながら、息が切れるまで走っていた。周囲とぶつかり合いながらも、仲間がいて、敵がいて、目指すべきものがあった。あの頃は孤独とは無縁だった。今、誰にも怒鳴られず、誰にも応援されず、ひとりで机に向かっていると、あの喧騒が少し恋しくなる。
今とのギャップに戸惑う
まさか自分が、午後三時に静かな部屋で黙々と書類を処理するようになるなんて、あの頃の僕は想像していなかっただろう。けれど、そのギャップを「だからダメだ」と否定することもできない。野球をやっていた頃と同じように、今も目の前のことを必死にこなしている。方向は違っても、気持ちは変わっていないはずだ。
それでも判子を押す理由
どんなに静かでも、どんなに孤独でも、僕は今日も判子を押す。誰かの登記のため、誰かの未来のために。その音が響くたびに、自分が「ここにいる」と確認できる。大げさかもしれないけど、その小さな音に、僕の今が詰まっている。
誰かの人生に触れているという実感
判子を押すことで、契約が成立し、登記が動き、人の人生が進んでいく。自分の名前は出ないかもしれないけど、確実にその裏には自分の仕事がある。直接感謝されることは少ないけれど、誰かの役に立っているという実感が、僕を支えてくれる。
ほんの数秒に込める信頼
「お願いします」と渡された書類に対して、しっかりと内容を確認し、カツンと判子を押す。たったそれだけの行為に、依頼人は僕を信じてくれている。その期待に応える責任が、プレッシャーであり誇りでもある。だからこそ、判子を押す音が、時に自分を励ますように感じるのだ。
この仕事を選んだ意味を思い出す
大変なことも多い。孤独もある。うまくいかない日もある。それでも、ふとした瞬間に、「この仕事をしていてよかった」と思える出来事がある。判子の音が、そんな記憶を呼び起こす。午後三時の静けさの中、今日もまたひとつ、確かな仕事を積み重ねていく。