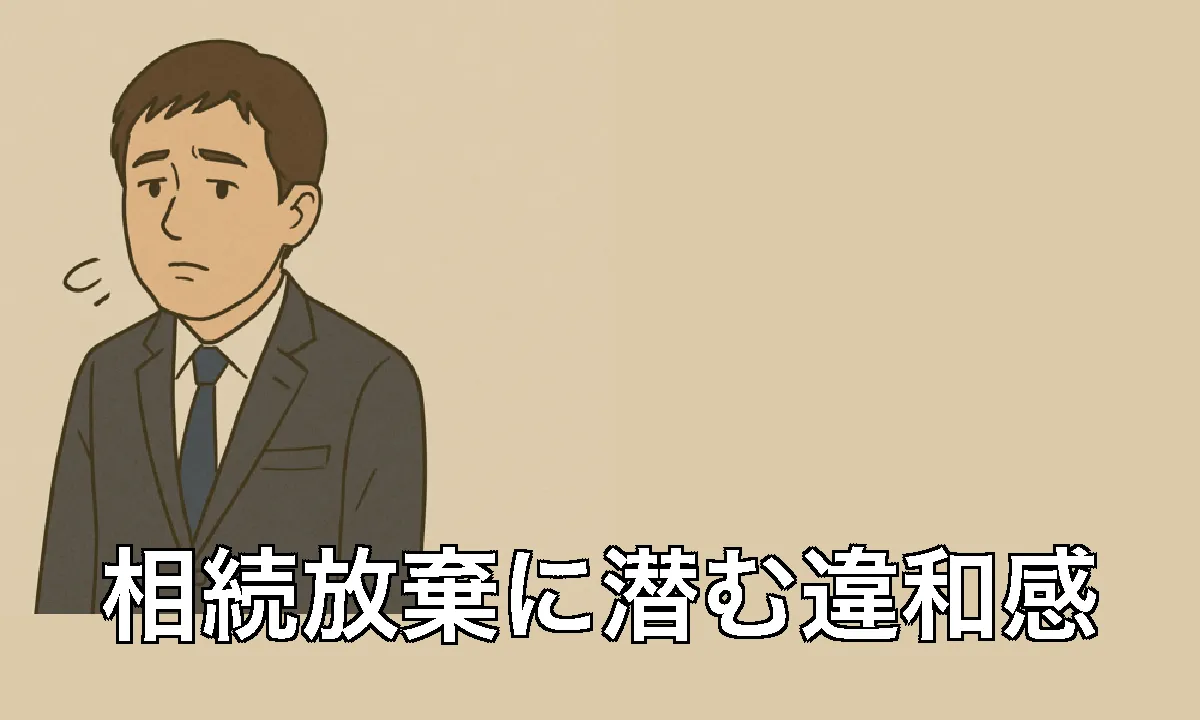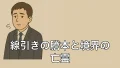相続放棄に潜む違和感
その日も朝から電話が鳴りっぱなしだった。年配の女性の声が受話器越しに震えていたのは、冬の寒さのせいではないと直感でわかった。彼女は「相続放棄をお願いしたい」と言い切ったあと、まるで罪を告白するように沈黙した。
相談室に来たのはその翌日だった。彼女の目は赤く、袖口に握りしめられたティッシュがしわくちゃになっていた。遺産は預金が少しあるだけ、と説明されたとき、なぜかその言葉が妙に引っかかった。
依頼者は泣きながら印鑑を押した
「ご親族とは疎遠で?」と問いかけると、彼女は黙って頷いた。印鑑を押す指先が震えていたのは、単なる高齢のせいではないだろう。戸籍関係の書類を確認しながら、私は何かが噛み合わない感覚にとらわれていた。
遺産額が少ない割に、彼女の表情はまるで命を削っているかのようだった。相続放棄にしては感情の揺れが大きすぎる。書類を提出することで何かを守ろうとしている――そんな印象を受けた。
遺産はわずかな預金だけのはずだった
預金通帳の写しを見て、私は首をかしげた。あまりに端数が揃いすぎている。まるで誰かが意図的に残高を調整したようだ。故人の過去の住所や職歴も調べてみたが、謎が深まるばかりだった。
「隠し口座とかってあるもんなんですか?」と私が口にすると、隣のサトウさんが顔も上げずに「預金じゃなくて戸籍を見た方が早いです」とつぶやいた。なるほど、やっぱり只者じゃない。
古い戸籍に隠された名前
さっそく本籍地から取り寄せた戸籍の束。明治時代に遡るまで確認していくと、見慣れない名前が浮かび上がってきた。依頼者の兄として一度だけ記載され、数年後に除籍されていた男の存在。
この兄の存在を、依頼者は一言も口にしていなかった。戸籍上は「生存していたことがある」という事実だけがそこに刻まれていた。だが、住所が特定できない。まるで煙のように消えていた。
誰も知らない兄の存在
もしこの人物が生きているなら、相続権は彼にもある。そして、依頼者が相続放棄を急いだ理由も、つじつまが合ってくる。彼女は兄を庇っているのか、それとも兄から逃れているのか。
まるで劇場型犯罪だ。自分の存在を隠すために、他人を使って相続放棄させる。いや、そこまでは行かなくとも、意図的な“排除”は疑ってかかるべきだった。
サトウさんの冷静な一言
「この兄、昭和58年に住所不定で失踪扱いになってますね」とサトウさんがさらりと言う。たしかに戸籍の欄外にそう記されていた。しかも、行方不明の届け出は依頼者本人だった。
「じゃあ、この兄が生きてる可能性は…」とつぶやくと、サトウさんは「ゼロじゃないし、ゼロにしたいんでしょうね」と冷たく言い放った。やれやれ、、、また厄介な案件だ。
謄本に映らない家族の影
調査を続けると、ある小さな手がかりが浮かび上がってきた。故人がかつて住んでいた町内で、近所の八百屋が語った噂だった。「あの人、戦後に誰かを養子にしたって聞いたよ」
謄本にはその情報は載っていない。しかし、実際には認知されなかった血縁が存在する可能性もある。その人物が、今なお戸籍の外で暮らしているのかもしれない。
近所の八百屋が語った噂
「昔、戦争孤児みたいな子を連れてた」と八百屋のご主人は語った。もしそれがこの“兄”なら、依頼者との関係性が変わってくる。兄ではなく、赤の他人。だが“家族”として扱っていたなら、それだけで人は揺れる。
見えない家族。記録されない血縁。システムが見落としたその関係が、今の相続放棄の根底にある気がしてならなかった。
お彼岸の墓に刻まれたもう一つの名字
調査の末にたどり着いた墓地には、依頼者と異なる名字が並んで刻まれていた。どうやらその兄は、別の姓で養子縁組された可能性が高い。にもかかわらず、依頼者がわざわざ行方不明届けを出していた――。
それは、家族としての責任か、それとも名義上の整理のためだったのか。いずれにせよ、彼女が言わなかった“兄の真実”がそこに横たわっていた。
断絶の理由と嘘の同居
最終的にわかったのは、兄とされていた人物は実子ではなかったということ。だからこそ、彼を相続から外したいという気持ちはわからなくもない。だが法は感情を考慮しない。
依頼者が相続放棄を選んだのは、彼に一切の干渉を許さないためだった。彼女の目には、静かな怒りと深い哀しみが浮かんでいた。
親族間で交わされた秘密の書類
最後の手がかりは、古い納戸から出てきた「養育契約書」の写しだった。それは兄とされた人物が一時的に家庭内にいた証拠だった。だが、法的な効力は持たない紙だった。
あくまで人情としての関係であり、法としての家族ではなかった。それが、今回の“放棄”の根拠だったのだ。
争族を避けた“演技”
サトウさんがぽつりと言った。「これは家族じゃない者を、家族だったと認めさせないための芝居だったんでしょうね」。それは冷たいようでいて、優しさでもあったのかもしれない。
人はときに、家族だったことを忘れることで自分を保とうとする。法を扱う私には、それが一番切なかった。
真実の放棄か仕組まれた除外か
最後に私は依頼者に問いかけた。「この兄と、何か話したいことはありますか?」 彼女はゆっくりと首を横に振った。「もう十分です」と。
その静かな決断は、長い時間と葛藤の末に辿り着いたものだったのだろう。
過去の事件記録を掘り起こす
かつて、その兄とされる人物は補導歴があった。警察の古い記録をサトウさんが見つけてきた。非行と縁を切るために、依頼者が戸籍の整理を急いだ可能性もある。
人が人を守るために、あるいは遠ざけるために取る行動は、紙の上では読みきれない。司法書士としての私は、そこに“正義”ではなく“整合性”を見いだすしかないのだ。
司法書士シンドウ、墓場までの証明義務
「先生って、たまに探偵みたいですよね」とサトウさんが書類を綴じながら言った。まるで怪盗キッドを追い詰めるコナンのような気分ではあるが、こちらは帽子もなく、ただのスーツ姿だ。
やれやれ、、、どうせならもう少しカッコいい仕事をしたかったもんだ。だが結局、私の仕事は“納得”を形にすることに尽きるのかもしれない。
相続放棄届の裏に書かれたメモ
帰り際、依頼者が忘れていった相続放棄届の控え。裏にはこう書かれていた。「もう一度家族になれる日は来ない。それでも、ありがとう」。
私はそっとメモを伏せて、机の引き出しにしまった。たとえそれが証拠にはならなくとも、それはたしかな“想い”だった。
そして、決断は依頼者に戻された
法はすべてを許してくれるわけではない。だが、法の隙間に人間の感情があることを忘れてはいけない。依頼者の放棄は、拒絶ではなく、和解の形だったのかもしれない。
私は書類に最後の印を押し、静かに机に置いた。もう、これ以上詮索する必要はなかった。
やれやれ、、、それでも書類は正直だ
机の上に並んだ書類はすべて整っていた。だが、それらの裏にある物語を知る者は、私とサトウさんだけだ。やれやれ、、、司法書士というのは、つくづく影の職業である。
私たちは黙って窓の外を見た。冬の光が、静かに地面を照らしていた。