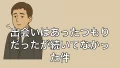判子より重い心と偽造の契り
朝の判子が告げた違和感
「あれ、なんか今日の印鑑、重たくないですか?」
事務所の静寂を破るようにサトウさんが言った。彼女は朝から届いた新しい依頼の委任状を手にしていた。いつものように判子を押す段になって、何かが引っかかったらしい。
俺はコーヒーを啜りながら、彼女の眉間の皺を見て思った。
「サザエさんの波平が髪一本でバランスを取ってるように、こういう細かい違和感って、意外と大ごとの前触れだったりするんだよな……」
依頼人の震える手元
依頼に来たのは、40代の男性。見た目は落ち着いていたが、印鑑を取り出す指先が微かに震えていた。俺はその細部に妙な既視感を覚えた。元野球部のクセで、人の手元の動きには敏感だ。
いつもと違う委任状の質感
委任状の紙質もおかしかった。やたらと新しい。役所が出すものにしては、コピー用紙の匂いがする。裏を見ると、かすかにインクジェットのにじみ。
サトウさんの静かな指摘
「シンドウ先生、これ、書体が微妙にズレてます。市販のテンプレートを加工したような……」
彼女はパソコンのフォント一覧を開きながら言った。やれやれ、、、また厄介な依頼の匂いがする。
戸籍謄本に滲んだ疑惑
俺たちは確認のため、依頼人が持参した戸籍謄本を調べ始めた。表面上は問題なかったが、細かく見ると、印字のフォーマットが最新のものと微妙に違う。
修正液と年月日の微妙なズレ
「あ、ここ。見てください、昭和62年がちょっと薄い。しかも“年”のフォントだけが浮いてます」
まるでルパン三世が偽造書類で税関を突破するときのトリックみたいだ、と俺は苦笑した。
「昭和か平成か」迷う不自然さ
文字の一部だけが古臭い。あえて古く見せているような手間のかけ方。そこに違和感と同時に悪意を感じた。
シンドウの経験が揺さぶられる瞬間
この手の書類を10年も扱ってると、正直飽きる。でも、こうやって“気づいてしまった瞬間”の心拍の上がり方だけは、いつまで経っても慣れない。
元野球部が見抜いたフォームの乱れ
依頼人が別紙に署名したとき、ペンの運び方が印鑑の筆跡と違った。利き手も逆だ。
筆跡鑑定士より先に気づいた癖
「この線、途中で手首を返してますね。印鑑のときとまるで違う。」
高校時代のキャッチャーとしての観察眼が、まさかここで生きるとは思わなかった。
グローブではなく印鑑を握る手
「フォームが崩れてると、球もブレる。印も同じですね」
なんて言ったらサトウさんに「比喩が昭和です」と呆れられた。
投球フォームと筆圧の一致
印影を重ねてみると、筆圧の掛かり方に矛盾があった。捺印は明らかに別人。俺の中で“黒”が確定した。
偽造の奥に隠された家族の闇
調査を進めると、亡くなったはずの親族が実は生きている可能性が浮上した。依頼人はその資産を騙し取るため、偽造書類を作ったらしい。
依頼人の過去と封印された遺産
事情を聞けば、家庭内での深い確執。遺産の名義を巡って、心に刻まれた恨みと執着。
隠された戸籍と2通目の遺言書
役所から正規の戸籍を取り寄せると、別の遺言書が見つかった。それには、生きている親族の名が記されていた。
サトウさんの鋭いプロファイリング
「人を騙そうとしても、書類は嘘をつけないですね」
彼女の冷静なひと言に、依頼人は黙ってうつむいた。
真実の判子が押される瞬間
その後、依頼人は正式に自白し、偽造の責任を取る形で和解交渉に入った。俺たちは必要な書類を用意し、今度こそ真正の手続きを進めた。
全ての証拠を並べた静かな説得
「この印鑑、重かったでしょう?あなた自身の心の重さだったんです」
そう告げたとき、依頼人の目から静かに涙がこぼれた。
心で押す最後の印
最後の書類に印を押すとき、依頼人の手は震えなかった。そこに込められたのは、ようやく自分を許すという気持ちだったのだろう。
「やれやれ、、、」と独り言をこぼしながら
「やれやれ、、、これでまた月末の申請ラッシュだよ」
と呟く俺に、サトウさんは一言。
「感動のラストに愚痴って入れられるの、シンドウ先生くらいですよ」
俺は肩をすくめ、コーヒーを飲み干した。