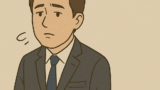根より深く縛られたもの
朝の来客と重たい空気
朝のコーヒーが冷めかけた頃、事務所のドアが静かに開いた。年の頃は五十手前と見える女性が、遠慮がちに中へ入ってきた。 口元に緊張がにじむその様子は、明らかにただの相談者ではなかった。
登記相談という名の沈黙
女性は開口一番、ある土地の根抵当権について相談したいと言った。だが、それは古い登記簿を調べれば済む話のはずだった。 彼女が何度も「その土地には思い出がありまして」と繰り返すたび、話の本筋は次第に霞んでいった。
抵当権の記録に残された違和感
調べてみると、根抵当権の設定者が既に亡くなっていることがわかった。だが、何かがおかしい。解除登記がされていないだけでなく、住所移転の記録もない。 このパターン、前にもあったな――確かあの時も、表に出せない何かがあった。
相続か恋か不審な継承の構図
亡くなった設定者は独身だったというが、その土地はある若い男性に引き継がれていた。相続の記録もなければ、売買もされていない。 まるで恋人にそっと残した、秘密のプレゼントのようだった。
サトウさんの冷静な指摘
「これ、恋愛感情絡んでますね」とサトウさんは言った。書類の束を眺めながら、まるで犯人の心を読み解く探偵のように淡々と。 僕が何か言いかける前に、「昭和の未練、令和に持ち越されてるだけですよ」と切り捨てた。
昭和の契約と令和の執着
調査を進めると、故人が生前に何度も同じ女性名義の口座に送金していた事実が判明した。記録は残っていないが、贈与の意志があったことはほぼ確実だった。 その女性が、今朝の相談者だったのだ。
名義変更に隠された愛憎劇
女性は涙ながらに語った。「あの人は、誰にも知られたくなかったんです。私との関係を」。 それでも、最後に彼女はその土地の名義を別の若者に変えた――かつての亡き人の弟子だったという。
根抵当は誰のためのものか
名義人の若者は、故人の思いを「受け継ぐ」とだけ言った。登記上の法的整合性はなかったが、感情的には筋が通っていた。 やれやれ、、、登記よりも重たい感情が、時には法をも超えてしまうのだ。
土地の裏で囁くもう一人の存在
調査中、サトウさんがぽつりと漏らした。「こういう話、案外多いんですよ。登記簿に出てこない関係って」。 たしかに、土地には登記されない想いが眠っていることがある。むしろ、そちらのほうが根が深い。
実印が語る最後のメッセージ
故人が残した実印が、机の奥から見つかった。押された紙には、こう記されていた。「この土地を、君に託す」。 法的には無効でも、それは彼の遺志であり、想いの証だった。
勘違いと直感が交差した午後三時
僕は最初、女性を詐欺まがいの相談者かと思っていた。だがそれは違った。彼女の言葉は、最初から最後まで本物だった。 信じられたのは、サトウさんの直感と、たまたま僕がコーヒーをこぼした書類の一枚だった。
真実は法務局の外に落ちていた
一枚の古い写真が、すべてを物語っていた。そこには、笑顔で並ぶ故人と女性、そしてまだ幼い若者の姿があった。 法では結べない、けれど確かに存在していた家族のような関係だった。
サトウさんのひとことと僕のうっかり
「シンドウさん、結局またうっかりで解決しましたね」とサトウさん。 僕は苦笑いを浮かべつつ、机の引き出しにしまった実印をもう一度見た。
解決はしたが心は登記できない
根抵当権は正式に解除された。でも、それだけじゃない。そこにあった想いは、解除できないものだった。 紙の上の問題は解決しても、人の気持ちはそう簡単には割り切れない。
夕暮れの事務所と変わらぬ日常
カーテン越しに差し込む夕陽の中、サトウさんが無言でファイルを閉じる。今日も一日、事件は解決した。 僕はため息をついて立ち上がる。「さて、晩飯どうするかな……サザエさんにはカツオがいるけど、俺にはいないからな」