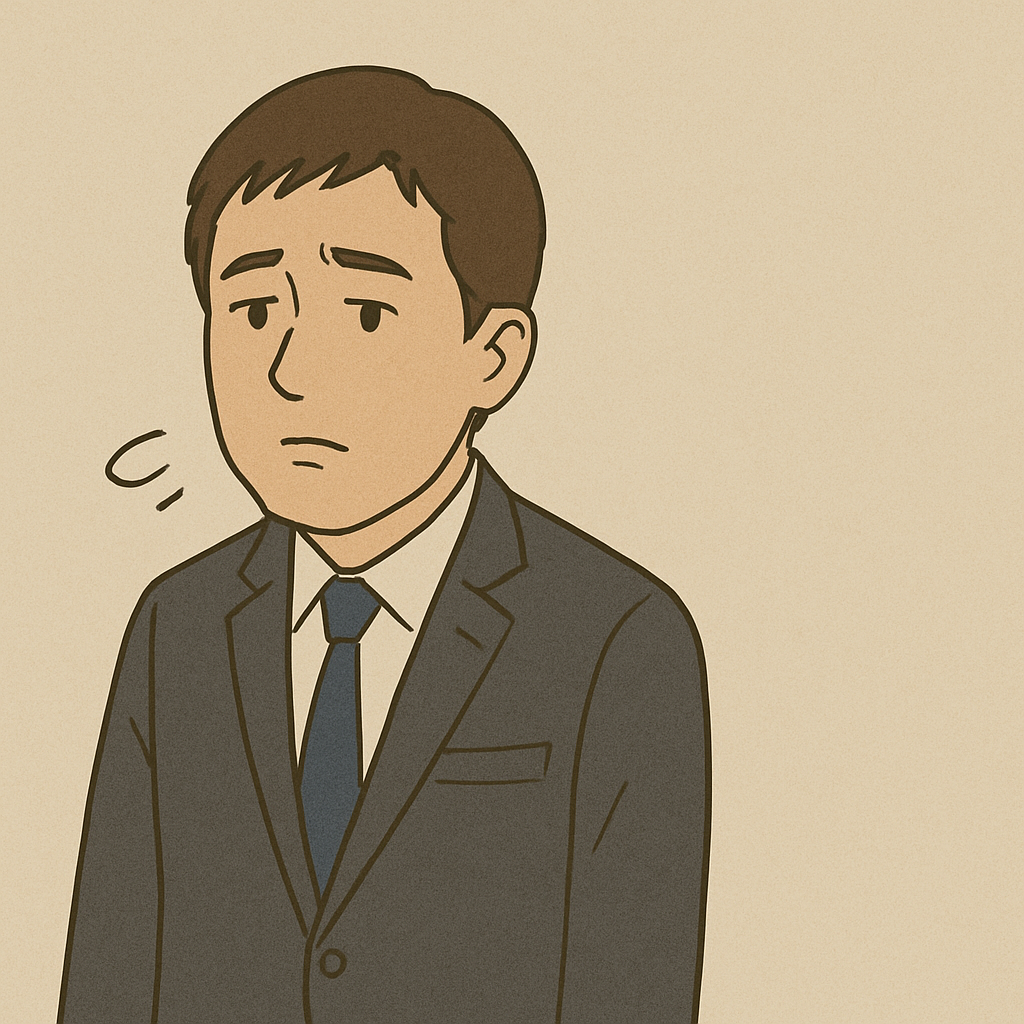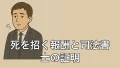登記簿の中の違和感
朝からどんよりとした空模様。湿った空気と一緒にやってきたのは、一本の登記簿の写しだった。 古い物件の名義変更について相談したいという依頼だったが、ぱらぱらとページをめくっているうちに、俺はある一文に目を止めた。 「地役権の目的に供する土地に関する制限事項あり」──そう、やけに曖昧で、通常書かれない表現だった。
数字の羅列に混じった一文
登記簿は基本的にフォーマットが決まっていて、そこに書かれる文言は法律に沿ったものばかりだ。 なのに、この一文はまるで手書きの注釈のように、欄外に滑り込んでいた。 これは誰かの手によって、意図的に残された痕跡なのかもしれない──そんな予感がした。
サトウさんの冷静な指摘
「これ、おかしいですよね」 俺の横から無遠慮に伸びた手が、問題の一文を指差した。いつの間にかサトウさんが背後に立っていた。 「通常、制限事項があるなら具体的な条項が書かれるはずです。これじゃ意味がわかりません」──冷静で、的確。まるで、銭形警部が部下を叱るときのような声だった。
依頼人は突然に
午前11時、約束の時間より30分早く、依頼人の老人が現れた。 少し腰が曲がりながらも、目だけは妙に鋭かった。「昔、父がここを持っていたんです。でも、なんだか妙なんです」 彼が差し出したのは、昭和50年代の茶封筒。中には数枚の古びた写真と、黄ばんだ謄本の原本が入っていた。
古びた茶封筒の中身
封筒の中の写真には、木造の平屋と、その前に立つ男たちの姿が映っていた。 その一人が依頼人の父だという。写真の裏には「昭和五十二年 地役権協定締結」と鉛筆で書かれていた。 だが、その協定に関する登記はどこにもない。登記簿はまるで、その事実ごと削除されていたかのようだった。
記憶にない過去の登記
謄本の履歴を追っていくうちに、ある時期だけポッカリと空白になっていることに気づいた。 前の名義人から依頼人の父への所有権移転が、なぜか5年も後になって登記されていた。 しかも、その間の取引記録も、法務局の閲覧記録にも存在しなかった。これは……隠されている。
旧法務局跡地の調査
俺たちは旧法務局の倉庫に保管されていた登記原票の写しを見に行くことにした。 さすがに古くて埃まみれだったが、係の人が好意で探してくれた。 「これ、該当しそうですね」──そう言って差し出されたファイルの一つが、明らかに異質だった。
シンドウのうっかりと泥だらけの資料
ファイルを受け取ろうとした瞬間、俺は足を滑らせて棚に膝をぶつけ、資料一式を床にぶちまけた。 サトウさんがため息をつく。「ほんと、野球部時代から変わってないんですね」 泥のついた資料の中に、ただ一枚だけ赤い付箋が貼られた紙があった。それが全ての鍵になるとは、このときはまだ知らなかった。
一文が示す隠された関係
赤い付箋のページには、地役権設定契約に関する記録が走り書きでメモされていた。 「未登記にて合意済 昭和五十三年」──つまり、公的な手続きを経ないまま、口約束で済まされた契約だった。 誰かが、それを秘密裏に記録だけ残したのだ。しかも、それが表に出ないように。
元所有者の足取り
元の所有者について調べたところ、地元の名士で、当時かなりの土地を所有していた人物だった。 だが彼は、数年後に急死している。そしてその相続は複雑で、揉めに揉めていたという。 この地役権の一文は、誰かが意図的に削除せずに“匂わせる”形で残したものだったのかもしれない。
司法書士の直感が動く
登記の空白期間と、記載された一文。そして、依頼人の父の写真と地役権。 全てがつながりそうで、あと一歩足りない。だが、何かが引っかかっていた。 俺はその日の夜、再び登記簿を最初から読み直した。
ファイルの隅にあった赤鉛筆の印
ようやく見つけた。謄本の写しの下部、余白に赤鉛筆で書かれた小さな矢印。 その矢印の先には、わずかに違うフォントの一文が紛れ込んでいた。 「現所有者は地役権を承継せず」──それが、全ての説明だった。
サトウさんが告げた決定的な一言
「つまり、これは誰かが地役権の存在を意図的に消そうとした、ってことですよね」 サトウさんは眉一つ動かさずに言った。俺は思わず背筋が凍る。 「そして、例の一文は……それを訴えた最後の抵抗だったんじゃないですか?」
地元新聞の過去記事にヒントが
1978年の地元紙を調べると、小さな記事に目が止まった。 「登記ミスで土地売却が無効に 法務局が謝罪」──場所も時期も一致していた。 おそらく、その件を誰かが記録として残し、密かに訴えようとしたのだ。
見落とされた事故の記録
更に調べると、その土地で火事が起きていたことも分かった。 原因不明の出火で、一人が亡くなった。相続が揉めたのも、そこに理由があったのかもしれない。 過去の不正登記と、家族の争い。全てが一文に凝縮されていたのだ。
再び謄本と向き合う
俺は依頼人に、改めてすべてを説明した。 「法的にはもう無効かもしれませんが、事実として残しておくことはできます」 彼は静かに頷いた。「父は、きっとそれを望んでいたと思います」
登記内容の空白期間
あの5年間の空白は、単なる怠慢ではなく、意図的な操作だったと今では確信している。 そしてその操作が、家族に分断を生み、長い時間を奪った。 俺たち司法書士が扱う登記は、ただの書類ではない。人生そのものだ。
全てをつなぐ最後のピース
サトウさんが、最後に言った。「シンドウ先生、これでひとまず終わりましたね」 俺は書類の山を見ながら、ふぅ、とため息をついた。 「やれやれ、、、もう少し肩の力を抜きたいもんだ」
故人の遺志が語るもの
結局、登記の中の一文が語っていたのは「忘れないでくれ」という遺志だったのかもしれない。 たった数文字で、人の思いは残る。記録というものの重さを、俺は改めて知った。 事務所に戻ると、雨は止んでいた。
結末と静かな報告書
数日後、修正された登記の写しと報告書を依頼人に送った。 「助かりました」とだけ書かれた小さなメモが返ってきた。 俺たちの仕事は地味だ。でも、誰かの人生を守っているのだと思う。
登記の裏にあった家族の秘密
今回の件で学んだことは一つ。謄本の一文を、ただの“文字”と侮ってはいけない。 そこには、争いも、痛みも、時には希望も潜んでいる。 司法書士として、俺はそれに耳を傾け続けるしかない。
やれやれと帰り道の独り言
コンビニで買った肉まんをかじりながら、俺はぽつりとつぶやいた。 「やれやれ、、、今度は登記じゃなくて、俺の人生に誰か一文足してくれないかな」 すると、後ろから塩対応の声が飛んできた。「その一文、誤字だらけになりそうですね」