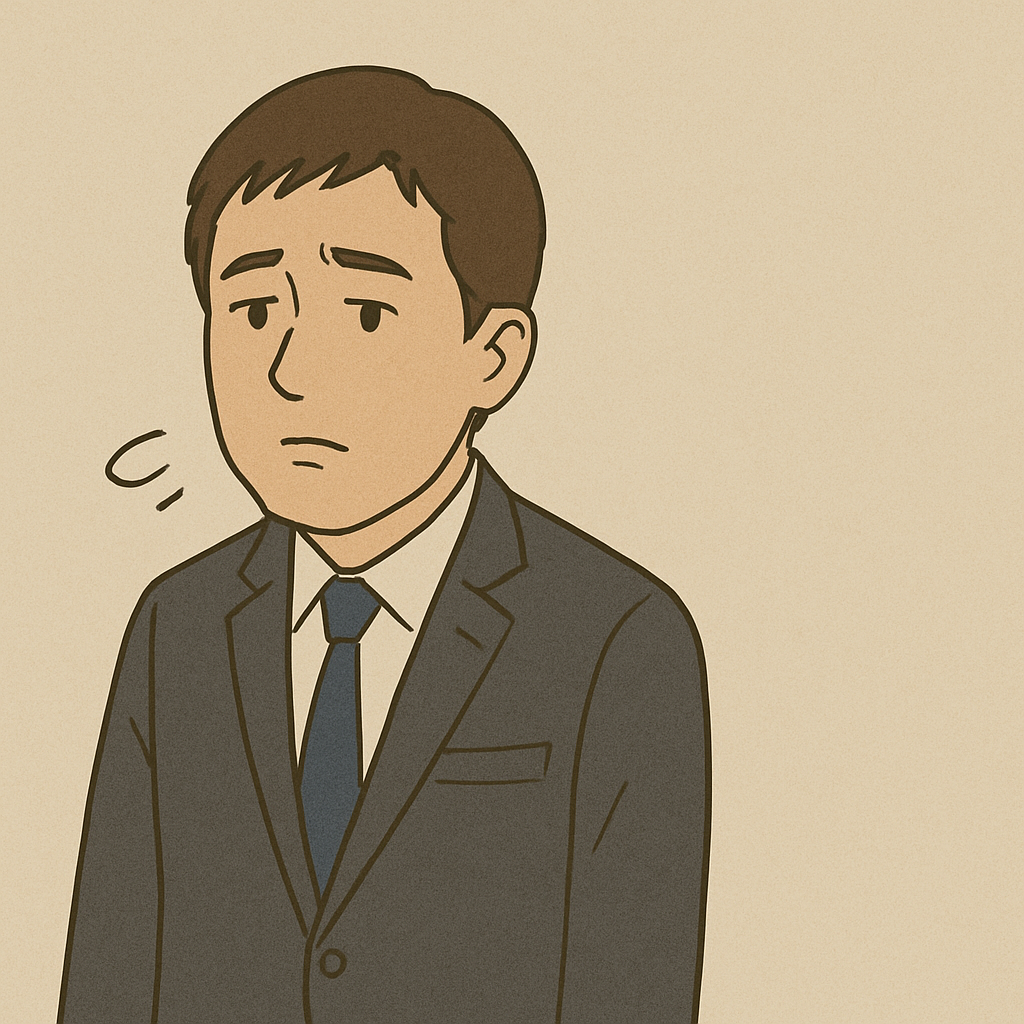登記簿に消えた約束
秋の始まりを告げる風が事務所の窓を揺らしていた。朝の静けさを破るように、入口のチャイムが鳴る。僕はまだ湯気の立つコーヒーを持ったまま立ち上がり、サトウさんが手際よく応対している様子を眺めていた。
訪れたのは年配の男性で、少し戸惑ったような表情で、古い封筒を手にしていた。中には手書きの遺産分割協議書のコピーと、数枚の登記識別情報が挟まれていた。
静かな朝の訪問者
郵便受けに残された封筒
「これ、昨日届いてたんですが、なんだか気味が悪くて」男はそう言って、手紙を差し出した。差出人は不明で、宛名だけが旧字体で書かれていた。宛名と同じ名前が、男の父親だったという。
「封筒の中身がですね、まるで誰かに見られていたような気分になるんですよ」と男は首をすくめた。僕は封筒を受け取り、書類の内容をざっと確認した。明らかに、現状と齟齬がある。
依頼人の違和感
依頼人の話によると、父の遺言はすでに履行され、登記も完了しているはずだった。しかし、その手紙には別の相続案が記されていたのだ。しかも、実現していない仮登記が存在することが示唆されていた。
サトウさんが横から「現地調査と登記簿の写し、すぐに取り寄せましょう」と手際よく対応するのを見て、僕は少し救われた気分になった。やれやれ、、、また変な案件に巻き込まれたらしい。
遺産分割協議の罠
兄弟間での微妙な空気
依頼人には弟がいた。話によると、父の介護の多くを担ったのは弟の方で、当時から相続には不満が残っていたという。だが、協議書には依頼人単独での名義移転が正当とされていた。
「でも弟から、『その土地は俺のだ』と数日前に言われたんです」と依頼人。そこに、この封筒だ。偶然とは思えない。僕の中で、怪しい影が形を取り始めていた。
登記名義と現実のずれ
取り寄せた登記簿を確認してみると、確かに依頼人名義の所有権が記されていた。ただし、その前に仮登記が存在していた。名義は、亡き父と弟の連名。しかも、抹消の記録が見当たらない。
この仮登記は何のためのものか、なぜ残されていたのか。そして、なぜ今になって誰かがそれを掘り起こしたのか。それを解くカギは、過去に交わされた一枚の文書にあった。
調査開始とサトウさんの冷静な指摘
古い登記簿に見つけた異変
「この仮登記、処理の途中で止まってますね」とサトウさんが無感情に言った。「しかも、登記原因が私道の使用許諾になってます。相続とは直接関係ないように見えます」
私道の使用許諾。それは、建物への接道を得るための便宜上の処理だったのかもしれないが、そこに隠された意図があった可能性もある。僕は古いファイルをひっくり返し始めた。
手書きの附属書類の影
一枚だけ、インクのにじんだ書類が出てきた。そこには「相続開始後、本登記に切り替えるものとする」と書かれていた。つまり、仮登記は父と弟の間での“取り決め”だったのだ。
弟は、自分の権利が確実に残るように、父と共謀してこの仮登記を残していた。そして今、その“約束”が現実になろうとしている。だが、それは法的に有効なのか?
謎の仮登記と過去の争い
司法書士の記録から見えた名前
調査を進めるうちに、過去に関与した別の司法書士の名前が浮かび上がった。僕は連絡を取り、その当時の事情を尋ねた。すると、仮登記は「将来の贈与」を意図していたという。
だが、その贈与契約書は見当たらなかった。つまり、それは法的に不完全なまま放置された約束だった。言ってみれば、砂上の楼閣。今さら弟がそれを盾にできるとは思えない。
解消されていない仮登記の意図
「仮登記がある限り、第三者への対抗要件になります」とサトウさんが淡々と告げた。つまり、依頼人は所有権を持ってはいるが、他人から見れば曖昧な権利状況だった。
相続協議と登記のタイムラグ、その隙を突こうとしたのが弟だった。完全にサザエさんで言えば波平が“忘れていた”昔の約束を突然持ち出してきたようなものだ。家族って、面倒だ。
サザエさん的展開と意外な真相
土地を守りたかった父の思い
最終的に、依頼人は父がなぜそんな仮登記を残したのかを理解することになる。「弟に安心させてやりたかったんでしょうね」と彼は静かに言った。だが、法的には無効だった。
土地はそのまま依頼人名義で維持され、弟との争いも表向きは収束した。約束は記憶の中に残り、登記簿には影だけが漂ったままだ。
忘れられた公正証書の効力
事件の最後、サトウさんが一通の公正証書を見つけ出した。内容は、父がすべての財産を長男である依頼人に譲ると記した正式なもので、日付も登記の前だった。
それにより、法的な裏付けは完全に整い、弟の主張は根拠を失った。父の“気持ち”はともかく、法律はあくまで記録と証拠に従う。そこに情は通用しないのだった。
やれやれの一言と解決の余韻
サトウさんの塩対応に救われる
「やれやれ、、、また面倒な話だったな」僕が椅子に沈み込むと、サトウさんは無表情のまま「次は決済の準備が山積みです」と告げた。なんというか、救いのない塩対応である。
だがその冷静さこそが、僕の事務所の命綱なのかもしれない。司法書士という仕事は、書類の山に埋もれながらも、誰かの“過去”にけじめをつけることなのだ。
司法書士という仕事の誇り
事件が終わった後も、僕のデスクには次の案件が積まれていた。古びた土地、消えた名義、謎の書類――日常の中に小さな謎は溢れている。僕はそれを、ひとつずつ解き明かしていく。
少し疲れた身体を伸ばし、僕は小さく笑った。あの仮登記も、きっと誰かの「約束」だったのだろう。そして僕は、それを静かに、法の上で片付ける役目なのだ。