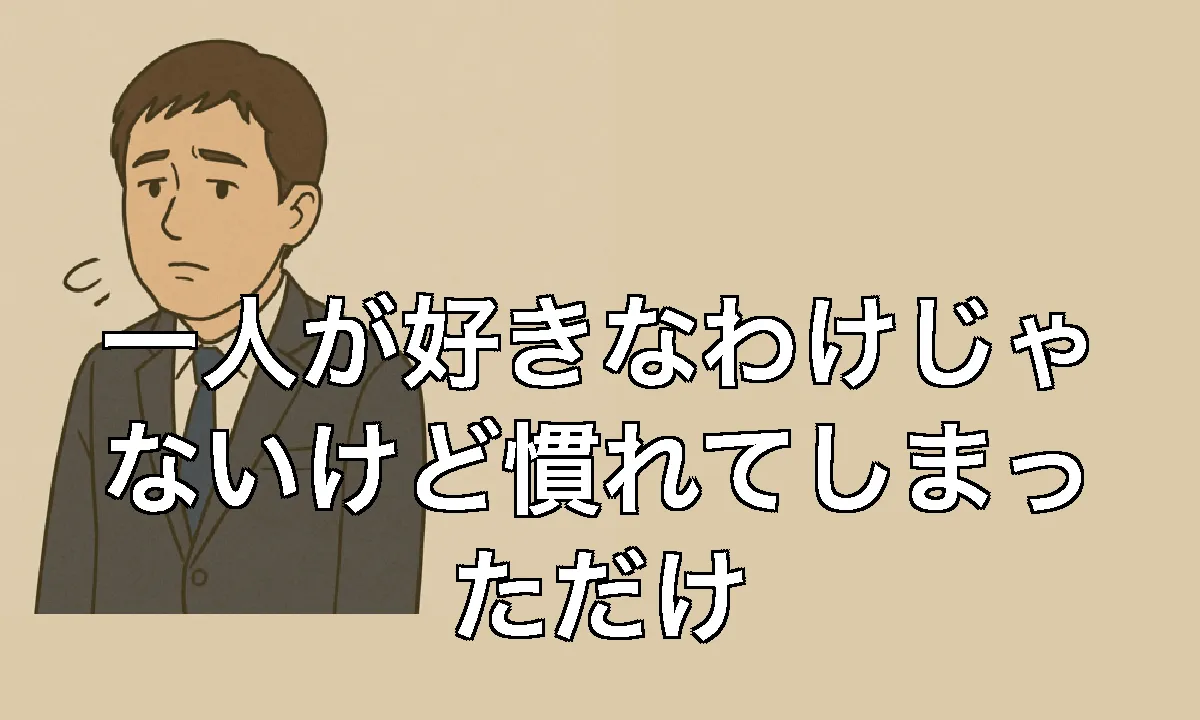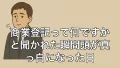静かな事務所に響くキーボードの音だけ
司法書士という仕事は、基本的に「内向き」な業務が多い。朝、事務所の鍵を開け、パソコンを立ち上げ、書類に目を通す。事務員が一人だけいるが、彼女も黙々と作業している。ふと気づくと、事務所内に響いているのはキーボードを叩く音とプリンターの駆動音だけだ。電話が鳴ることもあるが、それすらも最近は少ない。こんな静けさに包まれていると、自分の存在すら薄くなるような感覚になる。まるで、無音の部屋で、自分の思考だけが響いているような不思議な感覚だ。
誰かと笑うことが仕事の救いだったと気づく
昔はもっと賑やかだった。といっても、別に人がたくさんいたわけじゃない。ちょっとした打ち合わせで笑いが起きたり、お客さんとのやり取りの中にユーモアがあったり、そんな些細な「人間味」が日常にあった。今は効率化と孤立化が進んで、雑談の入る余地が少なくなったように感じる。無意識に「無駄」を省いてきた結果、残ったのは静けさと孤独。誰かと笑い合う時間が、実は仕事の中でいちばん救いだったと気づいたのは、だいぶ後になってからだった。
事務員との他愛もない会話に助けられている
今でも、救いがまったくないわけじゃない。事務員とのちょっとした会話が、思いのほか心の支えになっている。たとえば、「今朝寒かったですね」とか、「あのドラマ見ました?」なんて何気ない話が、地味に効く。あの人がいなければ、この事務所の空気はもっと重たくて冷たかっただろう。感謝を伝えるのはちょっと照れくさいが、内心では何度も「ありがとう」と思っている。孤独は誰かがいることでしか和らがないと、こういう瞬間に痛感する。
それでもたまに訪れる無音の時間がしんどい
とはいえ、毎日が快適なわけじゃない。ふと気づくと、昼下がりに二人とも黙々とパソコンに向かっていて、事務所の中に「音」が消える瞬間がある。その時に押し寄せてくるのは、妙な虚無感だ。なんのために働いているのか、誰のために頑張っているのか、そんな問いが不意に頭をよぎる。たかが静けさ、されど静けさ。その重さに、時々押し潰されそうになる日がある。
一人が得意そうに見えると言われるけれど
「先生は一人が好きそうですね」と言われることがある。たしかに、外から見ればそう見えるかもしれない。一人で何でもこなして、昼も外に出ず、事務所にこもって仕事をしている。でも実際は、そうせざるを得なかっただけだ。得意でやっているわけじゃない。選択肢がなかったのだ。慣れただけの話だ。元々は誰かと何かをするのが好きだったはずなのに、いつのまにか「一人が得意な人」になってしまった自分に、少しだけやるせなさを感じている。
元野球部のくせにチーム戦ができない矛盾
高校時代は野球部にいた。チームプレイが当たり前の世界で、ポジションごとに声をかけあい、励まし合いながらプレイしていた。試合に勝っても負けても、必ず誰かがそばにいた。あのころは、孤独なんて想像もできなかった。でも今は違う。チーム戦から遠く離れ、個人戦の世界にいる。矛盾しているように思えるけれど、それが現実だ。一人で判断し、一人で責任を取り、一人で静かに机に向かう。それが司法書士という仕事だ。
声を出す習慣が失われていく恐怖
最近、自分の声に違和感を覚えることがある。誰とも話さない日が続くと、いざ電話が鳴って声を出したときに、妙にかすれているのだ。「あれ、自分ってこんな声だっけ?」と感じる瞬間が怖い。声は感情の出口でもある。それが出なくなっていくということは、内面も静かに蝕まれていくような気がする。だからこそ、意識的に声を出すようにしている。朝の「おはよう」すら、意識して発声している自分がいる。なんだか情けないけれど、それも現実だ。
忙しさにかまけて誰かに甘えることを忘れた
仕事が忙しいと、他人に頼る余裕もなくなる。気がつけば、何でも自分で抱えてしまっている。誰かに「ちょっと聞いてよ」と話すことすら、億劫になってしまった。そうして気づかぬうちに、誰かに甘えることを忘れてしまったのだ。別に強くなったわけではない。むしろ、弱さを見せることができなくなってしまった。これは成長ではなく、退化かもしれない。
人に頼ることが苦手になっていた
司法書士という職業は、何でも一人でこなす力が求められる。だからこそ、「頼らずに済む人」になろうとしてきた。でもその積み重ねが、いつのまにか「頼れない人」になっていたのかもしれない。信頼して任せることは大事だと頭ではわかっている。でも、それを実行に移すのは難しい。自分の中の「責任感」と「不器用さ」が、他人との距離を遠ざけていたのかもしれない。
「大丈夫そう」に見えるだけの自分
よく言われる。「先生って、大丈夫そうですよね」。でも、それはただの表面だ。本当は、大丈夫じゃないこともたくさんある。誰かに弱音を吐けたらどれだけ楽か。でも、仕事柄それを許される雰囲気もなく、結局は「大丈夫な顔」を続けてしまう。演じているうちに、それが素のようになってしまう。そんな自分に気づくたび、ふと虚しさが込み上げてくる。
独身の気楽さと引き換えに失ったもの
独身でいることに、ある種の「自由」はある。誰にも縛られず、好きなように時間を使える。でも、その裏には「共有する相手がいない」という現実がある。今日のこと、感じたこと、ちょっとした愚痴さえ話す相手がいない。自由と引き換えに得たものは、孤独だったかもしれない。最近になって、ようやくその重さに気づいてきた。
仕事終わりの一人飯に漂うわびしさ
仕事終わり、コンビニで買った弁当を片手に、事務所の机で食べる。テレビもつけず、スマホも見ず、ただ静かに食べる。そんな時間が、なんだか切ない。一緒に食べる人がいるだけで、きっとこの味は変わるのだろうな、なんて思ってしまう。誰かと一緒に過ごす「当たり前」が、自分には当たり前じゃなくなっていた。
誰かと帰る夜道が少しだけ恋しい
夜、仕事を終えて一人で歩く帰り道。街灯がぽつぽつと続く道を、ひとりで歩くとき、ふと「隣に誰かいたら」と思うことがある。昔、野球部の帰りに仲間と他愛もない話をしながら歩いた道を思い出す。その頃には戻れないけれど、あの時間の「ぬくもり」が今でも胸に残っている。誰かと歩くというだけで、人生は少しだけ優しくなるのかもしれない。
モテないからこそ優しくなれた気もする
女性にモテたことはない。でも、それが自分の人間性を育ててくれたようにも思う。選ばれなかった分だけ、人に優しくしようと思った。誰かを羨む気持ちが、自分を見つめ直す時間になった。もしかしたら、それは司法書士という仕事にもつながっているのかもしれない。誰かの相談に丁寧に耳を傾けることしか、自分にはできないのだから。
選ばれなかった分だけ誰かを思える
選ばれないという経験は、思ったより人を謙虚にさせる。自分に自信がないからこそ、相手の立場に寄り添えるのかもしれない。だからこそ、依頼者の「どうしようもない話」や「言葉にならない不安」にも耳を傾けられる。司法書士という肩書きの裏で、人としてできることは、それくらいしかない。でも、それでいいのだと思うようになった。
孤独を知っているから共感できる仕事もある
孤独を知っていると、人の痛みに敏感になる。それは司法書士という仕事にとって、決して悪いことではない。たとえば相続や遺言の相談に来る人の中には、言葉にできない不安や悲しみを抱えている人がいる。そんなとき、ただ話を聞くだけで救いになることもある。自分が一人を知っているからこそ、そばにいることができるのだと思う。
相談者の沈黙に寄り添える自分でいたい
言葉が出てこない人に対して、無理に答えを求めない。それは、自分が言葉に詰まったことがあるからこそ、できる姿勢かもしれない。相手が黙っている時間も、ちゃんと意味がある。そう思えるようになったのは、きっと自分も一人の時間を重ねてきたからだ。孤独は、悪いことばかりじゃない。ときには、誰かを理解する力になる。
結局は人の話を聞く仕事だから
司法書士の仕事は、書類を作ることだけじゃない。本質的には「人の話を聞く」ことだと思う。書類の向こう側にいる人の感情や背景を、どれだけ想像できるか。それが、この仕事の深さであり、難しさでもある。自分が一人でいることが多いからこそ、誰かの声に敏感でいられる。それが、今の自分にとっての救いなのかもしれない。