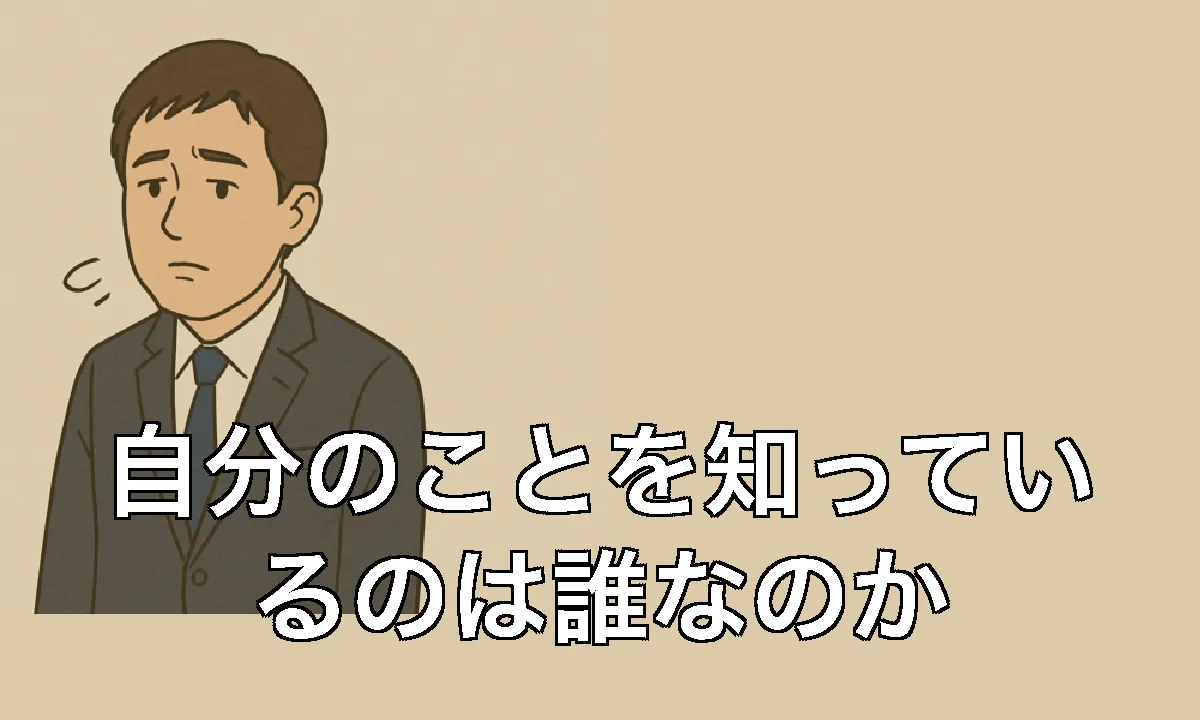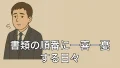毎日誰かと話しているのに独りだと感じる理由
司法書士という仕事柄、日々多くの人と関わっているはずなのに、ふと気づくと、妙に孤独感が襲ってくる。電話もメールも絶え間なく来るし、窓口での対応もある。だけど、それらはすべて「業務」であり、「対人関係」とはどこか違う。自分という人間が、誰かにちゃんと見られている気がしないのだ。たとえば、自分の体調が悪くても、感情が沈んでいても、仕事は回さなきゃいけないし、それに気づいてくれる人もいない。話す相手はいても、心を通わせている感覚がない。それが、たまらなく寂しく感じる瞬間がある。
「先生」と呼ばれても中身は見られていない
「先生」と呼ばれるのはもう慣れた。でも、その言葉が、時には薄っぺらく感じることがある。相手は自分の能力や肩書を見ているだけで、個人としての自分には興味がないのだと感じてしまうことがある。登記の説明をしても、相続の段取りをしても、そこにあるのは役割の遂行であって、「金田さんって、こういう人なんですね」と言われることはまずない。正直、誰でもできることを淡々とやっているだけのように思えて、自分が空っぽな存在になっていくような感覚に陥る。先生という言葉の裏には、本当の自分は隠されたままだ。
業務のやり取りに人間性は必要なのか
依頼者との会話のほとんどは、事実確認と手続きの進行についてだ。お互いに時間がないのもわかっているし、深入りしない方が楽なこともある。でも、その効率ばかりのやりとりの中で、自分が「ただの作業員」になっていくような気がしてならない。たとえば、「この書類、前回と同じ形式で出しておいてください」と言われたとき、相手にとってはそれが安心かもしれないけど、こちらは「誰でもいい」ような存在として扱われているように思えてしまうのだ。業務に人間性はいらないのか、という問いが、頭の中にずっと残っている。
事務所という小さな世界の孤独
事務所を運営していると言えば聞こえはいいが、実際は一人と一人で回している小さな組織だ。事務員さんはよくやってくれている。でも、だからこそ、こちらの弱みや感情を見せづらい。「しっかりしてる」と思われたい気持ちがある一方で、「本当は今日、めちゃくちゃきつい」と言えない空気もある。この密室のような空間で、気を抜くタイミングが見つからない。自分の中の人間味を押し殺しながら、ただ業務を回していく。そんな毎日が、いつしか自分をどんどん「他人行儀」にさせているのを感じる。
事務員さんとの距離感は縮まらない
長年一緒に働いている事務員さんがいる。彼女は真面目で優秀で、本当にありがたい存在だ。でも、だからこそ、仕事以外の話ができない。こちらから踏み込みすぎてもパワハラだし、雑談に逃げるのも気が引ける。結果、必要最低限の会話だけが続くようになる。たとえば、年末年始の挨拶ですら、どこかよそよそしい。お互いに「うまくやる」ことに集中していて、相手を「知ろう」としていないのだと思う。そういう関係性の中で、自分が誰なのか、忘れられていくような気がしてならない。
誰かに弱音を吐けない日々
仕事中に「今日はもうやめたいな」と思うことは、実は月に何回もある。でも、そのたびに、「こんなことで弱音を吐いてはいけない」と自分に言い聞かせてきた。相談相手もいないし、地元の友人に話したところで、「それって甘えじゃない?」と言われてしまう気がする。だから、気持ちを押し殺して、黙々と業務を続ける。気づけば、その我慢が当たり前になってしまっていて、本音を言う場所を失ってしまった。誰にも頼れないことが、こんなにも自分を孤立させるなんて、昔は思ってもみなかった。
沈黙がつらい日もある
何気ない日常の中で、誰とも言葉を交わさずに終わる日がある。そんな日は、夕方の静けさがいつもより重たく感じる。無音の事務所に自分のキーボードの音だけが響いていて、「このまま一生、誰にも知られずに終わるんじゃないか」と思ってしまう。たった一言、誰かが「今日、疲れてそうですね」と声をかけてくれるだけで、救われるような気がする。でも、そんな言葉は滅多にない。だからこそ、自分が感じる孤独は、沈黙とともに深く沈んでいく。
実家にも友達にも話せない話
実家に帰っても、「どうせ仕事忙しいんでしょ」と言われて終わる。地元の友達とも、最近はあまり会わなくなった。仕事の話をしても、専門的すぎて伝わらないし、逆に話さないと「変わったな」と言われる。どちらにしても、素の自分を出せる場所ではなくなってしまった。昔はもっと、何気ない話で笑っていられたのに。今は、自分の生活も心も、すっかり仕事に染まりきってしまって、誰にも「本当の自分」を説明できなくなっている。説明したところで、わかってもらえる気がしないのだ。
昔の仲間には言えない本音
高校の野球部の同期とは、年に一度くらいは集まる。でも、そこで自分の現状を話すことはほとんどない。誰も司法書士の仕事を知らないし、ましてや「孤独」とか「寂しい」なんて言葉を出せる空気じゃない。みんな家庭を持ち、子どもの話やローンの話をしている。自分は相槌を打つだけで、心の中では「おれは何をしてきたんだろう」と思っている。そういう場で本音を出すのは、まるで自分の負けを宣言するような気がして、結局、何も言えずに帰ることになる。
野球部の思い出が今の自分に刺さるとき
あの頃は、仲間と同じ目標に向かって汗を流していた。試合に勝って、みんなで泣いたこともあった。あの「わかり合えていた」時間が、今では遠い過去のように思える。チームで動いていた頃の自分と、今の独りきりで事務所を切り盛りする自分。まるで別人だ。誰かに気持ちを理解してもらえることが、あんなにも力になるなんて、あの頃は当たり前すぎて気づかなかった。いまの自分が一番欲しいのは、たぶん「一緒に悩んでくれる誰か」なのかもしれない。
誰にも知られていないからこそ自由でいたい
自分のことを誰も知らない。だからこそ、誰にも縛られずに仕事ができる。それはある意味での自由でもある。どんな格好で働いていようが、どんな考えで登記を進めようが、誰かに「それってあなたらしくないね」と言われることはない。そういう解放感が、この仕事の魅力でもあると同時に、虚しさでもある。人間は、完全な自由の中では、どこかで不安になる生き物なんだと思う。誰かに見られていること、知られていることが、実は生きる支えにもなっているのだ。
寂しさと引き換えの解放感
誰かに合わせる必要がない生活は、楽でもある。飲み会もないし、誰かと無理に話す必要もない。でも、それは同時に、誰かと喜びや不安を分かち合う機会もないということ。ひとりで自由に生きるということは、ひとりで全部抱えるということでもある。司法書士という職業の特性上、その「ひとり時間」が長くなる。最初は楽だと思っていたけれど、長く続くと、それが「孤独という名の重荷」に変わっていった。解放感は、時に毒になることもあるのだと知った。
理解されないことで守られているもの
誰かに自分のすべてを理解されることは、同時に自分の弱さや未熟さもさらけ出すことになる。それが怖くて、人との距離を保っている部分もある。だから、「知られない」ことで自分を守っているのかもしれない。誰かに意見されることもなく、自分のやり方を貫ける心地よさはある。でも、それって、傷つくのが怖いから逃げているだけじゃないかと、自分でも思う。理解されないことで、安心している自分がいるのもまた事実だ。
それでも誰かに気づいてほしいと願ってしまう
どんなに孤独でも、どんなに自由でも、心の奥底では「誰かに気づいてほしい」と思ってしまう。「大丈夫ですか?」のひとことで救われることもあるのに、そのひとことすら届かない日々に慣れてしまった自分がいる。でも、本当はずっと待っているのかもしれない。「金田さんって、こういう人なんですね」と、ただ一言、誰かに言われるだけでいい。自分のことを知ってくれている人が、ひとりでもいると思えたら、明日はもう少しだけ頑張れる気がするのだ。