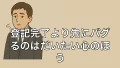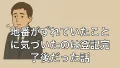気づいたら疲れ果てていた日常
司法書士になって十数年。最初は希望もやりがいも確かにあったはずなのに、気がつけば「ただこなすだけ」の日々になっていた。依頼者の書類を黙々と処理しながら、ふと窓の外を見ると季節が変わっている。心は置き去りのまま、毎日が目の前の「案件」に追われるだけで過ぎていく。地方での開業、事務員ひとりの運営、そうそう誰かと愚痴をこぼす時間もない。やることは山ほどあるのに、心のエネルギーはとうの昔に尽きていた。
朝が来るのが怖い
毎朝、目覚ましが鳴るたびに「今日もまた始まるのか」と天井を見上げる。目覚ましを止めたあと、そのまま布団の中でしばらく動けない日もある。事務所に行けば山のような書類が待っていて、電話やメールに追われ、クレームも少しずつ溜まってくる。寝て起きたらリセットされるどころか、昨日の続きがそのまま襲いかかってくるような感覚。世間で言われる「心の余裕」なんて、もはや都市伝説のようだ。
事務所の電気をつける手が重たい
シャッターを開けて鍵を回し、電気をつける瞬間が、最近は一番しんどい。スイッチを押す手が、まるで鉛のように重たいのだ。「ここからまた始まるのか」という実感がズシリとのしかかってくる。以前は小さな達成感もあった。登記が通れば嬉しかったし、相談者が感謝してくれれば報われた。でも今は、喜びよりも「終わってくれ」という願望が強い。始まるより終わることを求めている。
また今日も一人かと思う開業の朝
朝の開業準備、誰かが待っているわけでもない。事務員さんは遅めの出勤だし、来客の予定もない。事務所の空気が冷たく、機械的にパソコンのスイッチを入れると、自分だけがこの世界に取り残されているような気分になる。仲間がいた頃、大学時代の野球部の部室でみんなと騒いでいた記憶がふと浮かんでくる。でもそれはもう二十年以上も前の話だ。今は、沈黙の部屋で独り、机に向かう毎日が現実だ。
案件処理のはずが心の処理が先
登記手続きや書類確認は確かに仕事の中心だが、本当の意味でしんどいのは心のケアだ。依頼者はただの“案件”ではなく、それぞれにドラマがある。相続のもめごと、離婚の後始末、会社の清算。形式的な業務をこなすだけでは済まない話を聞かされ続けていると、こちらのメンタルもすり減っていく。疲労の質が、肉体よりも精神に偏っているのが司法書士のつらさだ。
依頼者の感情に飲み込まれる
「父の遺産を兄に全部取られて…」と、涙をこらえながら話す依頼者の姿に、思わずこちらまで感情移入してしまうことがある。事務的に聞き流すわけにもいかず、丁寧に受け止める。でもその分、帰宅してからも心が重いままだ。テレビをつけてもぼんやりして内容が入ってこない。無意識のうちに、依頼者の「悲しみ」や「怒り」を背負ってしまうのだ。そして、その荷物は誰にも預けることができない。
登記書類よりも感情の整理が難しい
不動産登記や商業登記の書類は、必要なものを揃えれば完成する。確かに手間はかかるが、形式は決まっているし、締切もある。でも人の感情は違う。誰かに恨みを抱いている人、悲しみにくれている人、焦っている人。そういう感情の波を前にすると、自分自身の感情の整理のほうが先に必要になる。書類よりも、心を整えるほうがずっと難しいと感じることが増えてきた。
先生聞いてくださいが一番のプレッシャー
「先生、ちょっとだけ聞いてください」――この一言が、一番のプレッシャーだ。たいてい“ちょっと”では済まないし、話の内容も重たい。しかも、聞く側は常に冷静でなければならない。言葉の選び方、反応の仕方、すべてに神経を使う。こちらが感情的になってはいけないが、かといって無関心にもなれない。そんな絶妙なバランスを毎回強いられるのが、精神的な消耗を加速させる原因なのだ。
孤独と責任感のはざまで
地方でひとりで事務所を切り盛りしていると、誰かに頼るということがそもそも難しい。すべての判断を自分ひとりでしなければならず、その責任は常にのしかかってくる。誰にも相談できない苦しさが積もっていくと、次第に自分の中で「何が正しいのか」さえわからなくなる。責任感は大事だが、そればかりでは心がもたない。
間違えられない仕事の重み
登記の内容をひとつ間違えれば、大変なことになる。依頼者の資産に関わる問題だけに、プレッシャーは計り知れない。しかも、そのプレッシャーを理解してくれる人は少ない。「書類を出すだけでしょ」と言われたこともある。そんな軽い一言で、心が折れそうになる。細かい確認作業の連続。凡ミスが命取り。常に緊張感を持ち続けることのしんどさは、言葉ではなかなか伝わらない。
誰も褒めない誰にも相談できない
誰かが「頑張ってますね」と言ってくれたら、少しは救われる。でも現実は、トラブルがなければ当たり前、あってもこちらの責任になる。感謝の言葉よりも、文句のほうが多いのが現場だ。友人に話してもピンとこないし、同業者とは愚痴の言い合いになってしまう。そうなると結局、自分の中に抱え込むしかない。どんどん孤立していくのがわかる。
事務員さんに救われる日々
そんな中で、唯一救われるのが事務員さんの存在だ。派手なことはできないけれど、淡々と支えてくれている。その存在のありがたさを、日々痛感している。体力も気力もギリギリの時に、ちょっとした言葉で涙が出そうになることもある。たったひとりでも、誰かが「気にかけてくれている」と思えるだけで、もう少し頑張れる。
お茶でも飲みますかの一言に泣きそうになる
書類に埋もれている昼下がり、「お茶でも飲みますか?」と声をかけられると、不意に心が緩む。まるで疲れた体に染みわたる栄養剤のように、温かい飲み物とその言葉が効いてくる。人間って、気遣い一つで立ち直れるものだと実感する瞬間。事務員さんのさりげない優しさに、何度助けられたかわからない。
でも仕事は二人だけじゃ回らない
感謝はしている。でも現実問題、ふたりだけで回していくには限界がある。急な依頼、トラブル対応、月末処理…。どれもが人手不足を浮き彫りにする。手を増やすにも人件費の問題があるし、求人を出してもなかなか応募が来ない。この業界の地味さときつさが、応募者の足を遠ざけているのだろう。結果、現場の負担は減らない。