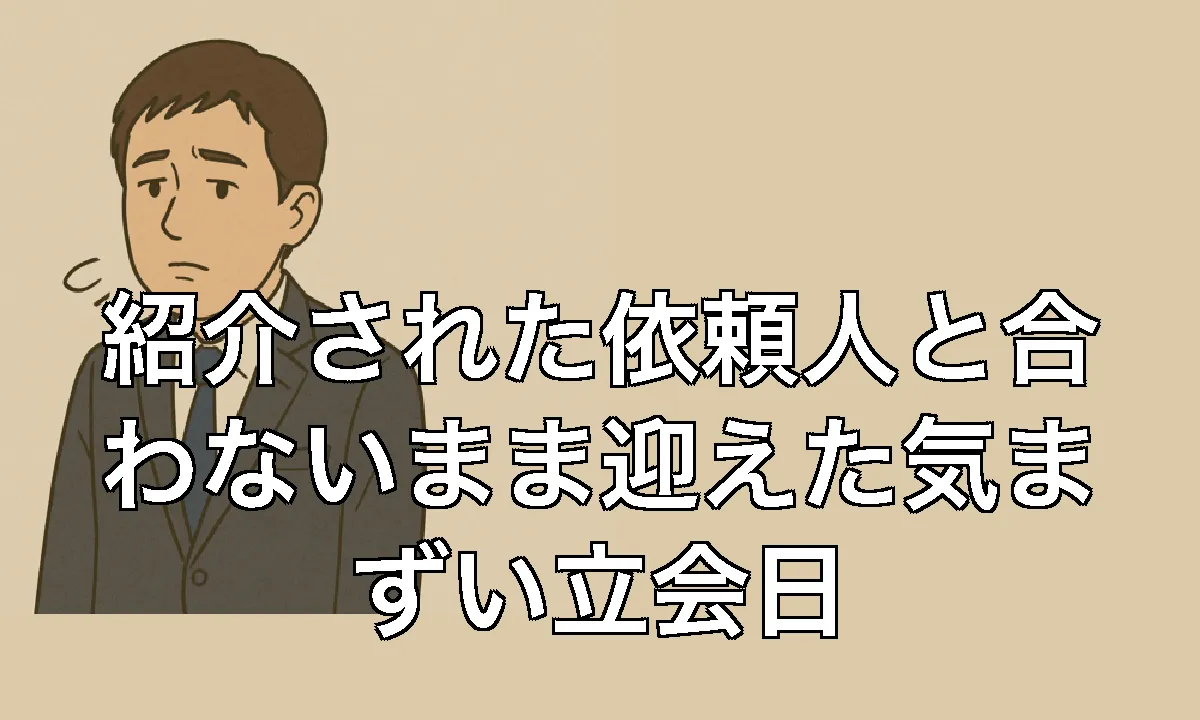立会いの朝に感じた違和感
朝から何となく胸のあたりが重苦しかった。理由はわかっていた。今日の立会い相手は、知り合いの税理士さんから紹介された依頼人。電話のやり取りでもそっけなく、面談でも目を合わせようとしない。「まあ、仕事だしな」と自分に言い聞かせてはみたが、気持ちは晴れなかった。こういう日は決まって、何かが噛み合わない。朝のコーヒーの味も妙に薄く感じた。
事務員がくれた一言がすでに嫌な予感だった
出勤してすぐ、事務員がぼそっと言った。「あの方、ちょっと空気…重いですね」──たったそれだけの一言で、違和感が確信に変わった。彼女は人を見る目が鋭い。こっちは紹介案件だから断れないし、どうにか滞りなく進めたいという一心だった。だけど、こういう“空気”って、努力してもなかなか打ち消せるものじゃない。経験上、無理に明るくしようとすればするほど裏目に出る。
紹介者の顔を立てたい気持ちと現実のギャップ
税理士さんには日頃からお世話になっている。その紹介で来た人だから、できるだけ丁寧に、誠実に対応したいという気持ちは本音だ。けれど、どうしても心のどこかで「この人とは馬が合わないな」と感じてしまうと、言葉選び一つにも気を遣ってしまう。お互いに気を張ったまま会話を続けるのは、まるでキャッチボールで硬球を投げ合っているような緊張感があった。
無理に笑うときの顔が筋肉痛になった
愛想笑いを繰り返しているうちに、顔の筋肉がこわばってきたのが分かった。自分では柔らかい雰囲気を出しているつもりだったが、相手はますます表情を固めていく。たぶん、相手にも「無理してる感」が伝わっていたのだろう。終始、こっちの笑顔は空回りしていた。まるでお通夜のような雰囲気の中で、ただ時が過ぎていくばかりだった。
依頼人の態度に戸惑う
立会いの最中、依頼人の態度は終始ぶっきらぼうで、言葉数も最小限。質問に答えるときも、こちらを見ずに「はい」か「いいえ」だけ。途中から「これは怒ってるのか? それともいつもこういう人なのか?」と疑心暗鬼になってしまった。笑顔を向けても無反応、書類を説明しても反応薄。まるで壁に向かって喋っているような感覚に陥った。
目も合わせず無表情で淡々と
人と人とのやり取りは、目線や表情でも情報を交換している。けれどその日、彼の目は一切こちらを見なかった。無表情、無言、無関心。書類を指さして説明しても「ふーん」と鼻で笑うような態度。正直、ちょっとプライドも傷ついた。こちらは司法書士としての責任を持って対応しているのに、まるで「どうでもいい」と言わんばかりの雰囲気を浴びせられ、途中で集中力も削がれていった。
こちらの説明にも「はあ」「別に」
こちらが「ご不明な点はありませんか?」と丁寧に尋ねても、返ってくるのは「はあ」とか「別に」といった曖昧な返答ばかり。何をどう答えればいいかも分からなくなり、会話がまったくかみ合わない。こうなると一刻も早く終わらせたい一心で、こちらの声もどこか機械的になってしまった。心の中では「もう来るな」と思ってしまっている自分に気づき、余計に落ち込んだ。
話がかみ合わないというより、そもそも会話が成立しない
会話がかみ合わないことには慣れているつもりだったが、今回はレベルが違った。そもそも会話が成立しない。質問を投げても跳ね返ってこない、感情のキャッチボールができない相手だった。説明も一方通行、反応もほとんどゼロ。こちらが話し終えるのをただ待っているような態度。まるで無人島に向かってメガホンで叫んでいるような虚しさがあった。
沈黙が支配する立会現場
立会いの場は通常、適度な緊張感と共に進んでいくものだが、この日はまるで違った。沈黙が重く、場の空気が硬直していた。必要最低限のやり取りだけで、笑いも冗談も生まれない。時間が過ぎるのが遅く感じた。会話も弾まず、時計の針だけがやけに目についた。
気まずい空気に耐えるだけの30分
30分がこんなにも長いとは思わなかった。普通の案件なら、ちょっとした雑談を交えながら進行するところを、今回はほぼ無言。紙のめくれる音とボールペンのカチカチという音だけが響く空間に、息苦しさを感じた。相手の「早く終われ」という無言の圧力が肌に刺さるようだった。
同席した関係者たちの微妙な視線
関係者の一人が、こちらをちらちらと見ていたのも気になった。「ちゃんとやれてるか?」という視線とも、「なんでこんなに気まずいの?」という視線とも取れる。いずれにせよ、いたたまれない気持ちになった。まるで自分が空気を悪くしている張本人のように思えてくる。自己否定の連鎖が始まり、ただ黙って時間が過ぎるのを待つしかなかった。
心の中で「終われ終われ」と念じ続けた時間
「あと何分だ」「もうすぐ終わる」「サインもらえば終わり」──心の中で何度も唱えた。早くこの場から解放されたい、ただそれだけだった。緊張で額にじんわり汗がにじみ、喉もカラカラ。けれど水を飲むタイミングすら掴めなかった。あのときばかりは、司法書士の仕事の中で一番しんどい時間だったかもしれない。