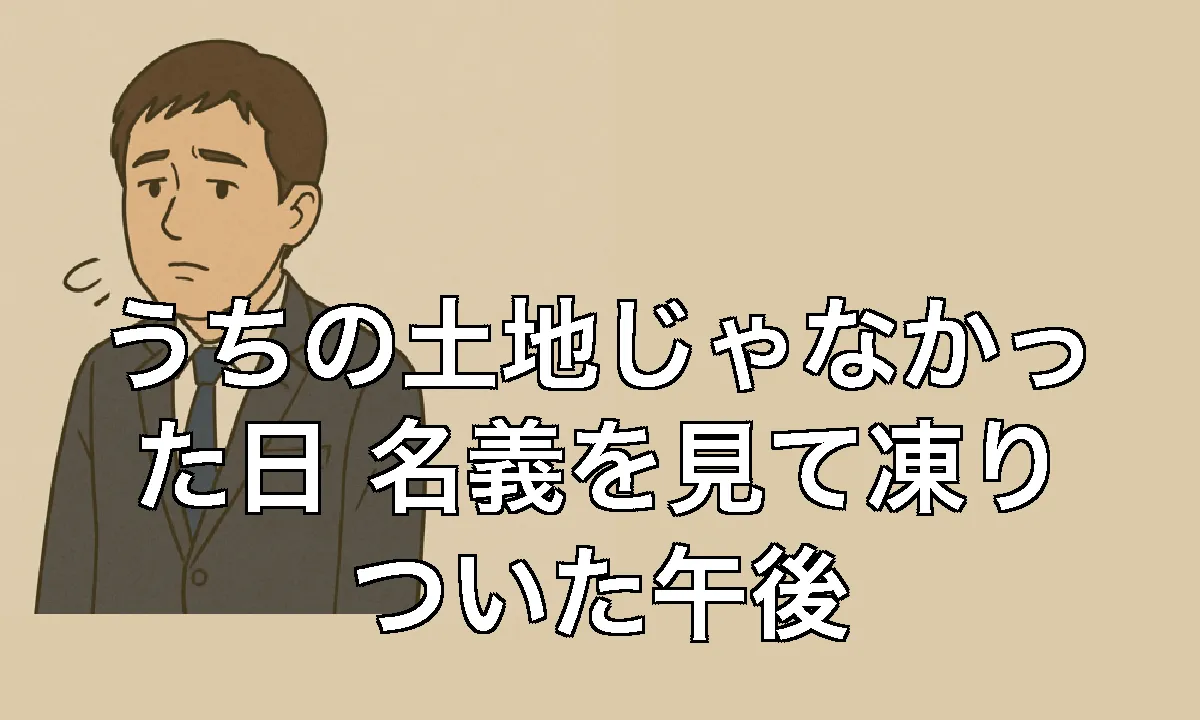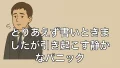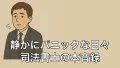ある日突然知った真実 借地だったという事実
司法書士をやっていると、思いもよらぬ事実に直面することがある。ある日の午後、依頼人が持参した資料をもとに登記簿を確認していた私は、ある一点で目を疑った。依頼人が「これは自分の土地」と話していた不動産、実は借地権だったのだ。何度見直しても土地の所有者は別人。冷や汗が背中を流れるような感覚になり、静かにパソコンの前で凍りついた。よくある話、と言ってしまえばそれまでだが、当事者にとっては笑えない。あの日の午後、あの一枚の登記簿が、私と依頼人の両方にとって“信じていたものが揺らぐ瞬間”になった。
「うちの土地です」と言い切っていた依頼人
その依頼人は、地元の商店街で長年店を営んでいた方だった。親の代から引き継ぎ、ずっとその土地と建物を「うちのもの」として使っていたらしい。たしかに周囲から見れば、誰もがその場所をその人のものだと信じて疑わなかった。しかし、登記簿は正直だ。彼の名は建物にしか載っておらず、土地の欄には全く別の地主の名前が記されていた。「借地だったんですか?」と尋ねると、依頼人は数秒固まり、「え…そうだったんですか?」と呟いた。その瞬間、長年の認識が音を立てて崩れるのが、目に見えるようだった。
登記簿を見て違和感 土地の所有者が別人
経験を積んだ司法書士でも、話の流れで見落とすことがある。依頼人があまりにも当然のように「自分の土地」と言えば、書類の確認を後回しにしがちだ。私もそのときは、最初に建物の名義確認に集中していた。だがふとしたタイミングで土地のページをめくったとき、違和感が走った。「あれ、この名前誰?」という直感。間違いない、所有者は別人だ。ここからは慎重に言葉を選びながら、依頼人に事実を伝えなければならない。間違っても「知らなかったんですか?」なんて言えない。
誰も悪くないのに誰かが責められる空気
こういうとき、空気が急に重くなる。依頼人は「自分が悪いのか」と悩み、私も「確認不足だったか」と内心焦る。だけど本当は、誰も悪くないこともある。親から引き継いだ借地で、契約書すら紛失していて、何十年も無事に使えていたから当然「自分の土地」と思い込むのも無理はない。でも、責任の所在を求めたくなるのが人間の性分だ。あの瞬間、無言のまま数十秒が過ぎる中で、私たちの間に流れた沈黙は、正直つらかった。
借地権って何なんだ 本当にややこしい権利関係
借地権という言葉は、一般の人にとって馴染みが薄い。しかも、法的には所有権と大きく違うにもかかわらず、見た目には区別がつかない。そのせいで誤解やトラブルが後を絶たない。司法書士の私ですら、毎回契約内容を確認して「これは地上権か?普通借地か?定期借地か?」と混乱することがある。依頼人からすれば、そんな専門用語の違いは「どっちでもいいから自分のものにしたい」という気持ちが先に立つ。だけど、そこにこそ落とし穴がある。
所有権と借地権の決定的な違いとは
所有権が“絶対的な権利”だとすれば、借地権は“期間付きの使用権”だ。どれだけ長く使っていようが、地主の同意なしに自由にはできない。更新の可否や地代の支払い義務もあるし、売却や建て替えには制限がつく。ところが、土地をずっと使っていると、感覚的に「自分のもの」と思い込むのも無理はない。私も実家が祖父名義だったことを社会人になって初めて知ってショックを受けた経験がある。「じゃあ、あれは誰の土地だったんだ?」と本気で思った。
借地の種類と更新の壁
借地権にはいくつか種類があり、普通借地権と定期借地権が代表的だ。普通借地権は更新を前提としているが、定期借地権は更新ができない。しかも、昭和・平成の法改正をまたいで内容が変わっているため、過去の契約内容を見ないと何とも言えないケースも多い。実際、私の事務所に相談に来た方で「更新できると思っていたのにできない」と言われ、土地を明け渡さざるを得なくなった方もいた。紙一枚の文言が、人生を左右する。司法書士という仕事の重さを痛感した瞬間だった。
「名義変更できますか」の質問が持つ重さ
「この土地、名義変更できますか?」という質問は、見た目には簡単そうだが、実はとても複雑だ。借地であればそもそも土地の名義は他人のもの。変更には地主の承諾が必要で、しかも金銭が絡むこともある。過去に、地主が承諾料を高額に請求してきて、依頼人が泣く泣く諦めた事例もあった。そういったケースでは、司法書士も単なる“手続き屋”では済まされない。気遣い、交渉、場合によっては慰めることまで求められる。誠意だけで乗り越えられることもあるが、現実はなかなか厳しい。
「確認不足でした」で済まされない世界
司法書士の仕事には、「知らなかった」では済まない場面が多い。書類に不備があれば、自分の信用にも関わる。だからこそ、常に慎重にならざるを得ない。でも人間だからミスもある。問題は、そのミスが取り返しのつかないものになる可能性があるということだ。だからこそ、毎回「これでいいのか?」と自問しながら仕事をしている。精神的には正直、かなりしんどい。
ベテラン司法書士でも見落とすことがある
司法書士歴20年以上の大ベテランでも、たまにヒヤリとするミスをする。特に最近の複雑な契約書や新しい制度には、慣れが通用しない。私も「こんなの昔はなかったぞ」と思いながら、日々調べ直している。たとえばオンライン登記申請の仕様変更などは、毎回のように追いかける必要がある。若い頃は「ベテランになれば楽になる」と思っていたが、現実は逆だった。
どこまで説明すべきか 依頼人との線引き
依頼人にどこまで細かく説明するかは、毎回悩むところだ。全部説明しても理解されないこともあるし、逆に黙っていると後から「聞いてない」と言われる。昔、親切心でA4三枚にわたる説明資料を作ったことがあるが、「そんなの読んでない」とバッサリ切られたことがある。それ以来、相手に合わせて調整するようにしているが、正解はない。これがまた疲れる。
説明しても納得されないことも多い
丁寧に説明しても、「なんか納得いかない」と言われることも多い。特に相続や不動産のように金銭が絡む話では、感情が先行しやすい。「兄が納得してないんです」とか「親戚がうるさくて」といった事情を前に、法的な正しさだけでは押し切れない。だからこそ、私はただの専門家ではなく、“寄り添える存在”でありたいと考えている。でも、それができる日もあれば、正直しんどい日もある。
そして今日も一人 机に向かって反省している
ふと夜になると、誰もいない事務所で「今日の対応、あれでよかったんだろうか」と自問する時間がある。正解のない仕事だからこそ、余計に迷いがつきまとう。私のような一人事務所では、誰かに相談することもできず、反省も独り言のようになってしまう。少しでも良い仕事がしたいと思ってはいるのだけど、今日もまた机に向かってため息をついている。
もう誰かに愚痴を聞いてほしい夜もある
たまに、誰かと飲みに行って話をしたくなる。でも同業の友人は少ないし、昔の野球部仲間は家庭を持っていて忙しい。愚痴をこぼせる相手がいないのは、独身司法書士の孤独な現実かもしれない。そんな夜は、結局コンビニ弁当を買って、家で一人、テレビを見ながら寝落ちするだけだ。
独身司法書士のため息と元野球部の意地
45歳、独身、モテない、愚痴っぽい。それでもこの仕事をやっているのは、誰かの役に立てる瞬間があるからだと思う。元野球部のせいか、負けず嫌いなところだけは今も残っている。「もうやめたい」と思う日もあるけれど、結局また次の日には出勤してしまう。そんな自分に少しだけ誇りを持っている。
それでもやめない理由があるからやっている
大変なことばかりだけど、この仕事にはやりがいもある。誰かが「ありがとう」と言ってくれる瞬間、それだけでまた一日分の疲れが癒される。うまくいかない日も、失敗して落ち込む日も、それでもこの仕事を続ける理由がある。今日もまた、小さなことで悩みながら、静かに頑張っている。