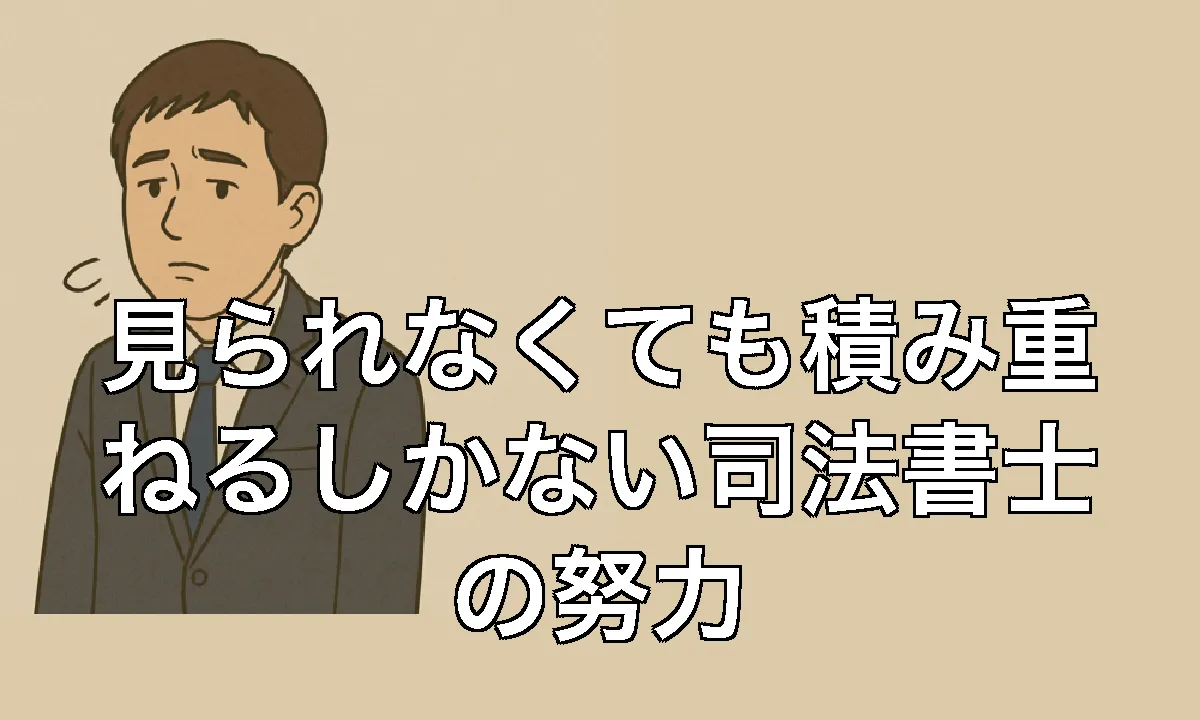見えない努力に意味はあるのかと自問する日々
この仕事をしていると、「この努力には果たして意味があるのか」と、つい考えてしまうことがある。誰かに褒められるわけでもなく、感謝の言葉がもらえるわけでもない。それどころか、何も言われないというのが、うまくやった証だったりする。そんな報われなさに、心がくたびれるのだ。司法書士の仕事は「目立たない」ことが美徳とされる。でもその陰で、どれほどの手間と確認作業を積み上げているかは、なかなか伝わらない。誰にも見られない努力、それでもやるしかない、そんな日々の繰り返しである。
司法書士の仕事は誰に評価されるのか
登記が無事に完了しても、「ありがとう」ではなく「それが当たり前でしょ」という空気が流れる。たしかにそれが仕事だから、当然といえば当然だ。でも、例えば間違いがひとつでもあったら、そのときだけはすぐに指摘される。ミスは目立つ、正確さは目立たない。こんな評価軸の中で働いていると、自分が何を目指して頑張っているのかわからなくなることがある。自己肯定感なんて言葉から遠い場所で、なんとか気持ちをつなぎとめているのが現実だ。
書類が正しくても感謝されるとは限らない
依頼人が求めているのは「結果」であって、その過程ではない。どれだけ複雑な案件でも、完成した書類が正確であれば「ふつうに終わった」と思われる。それがプロというものなのかもしれない。でも時々、ほんの一言でいいから「ありがとうございます」って言われたくなるのだ。実際、昔ある依頼人が「おかげでスムーズにいきました」と言ってくれたときには、不覚にも泣きそうになった。情けないが、それがこの仕事の現実である。
成果よりもトラブルが注目される世界
「なにも起きなかった」ということ自体が最大の成果なのに、それが評価されることは滅多にない。それよりも、ほんの些細なミスがあったときのほうが、強く記憶に残る。以前、法務局から電話がかかってきて、軽微な記載ミスを指摘されたことがあった。依頼人には謝罪し、修正して再提出したが、そのときの「なんでそんなことになるの?」という一言がずっと耳に残っている。そう、うまくいったときは静かで、失敗したときだけ大きな音が鳴る。それがこの世界だ。
間違えられないという無言のプレッシャー
この仕事は「当然のように正しくやること」が前提にされている。だからこそ、少しでも確認を怠れば、即ミスにつながる。そして、そのミスは誰のせいでもなく、すべて自分の責任として跳ね返ってくる。夜中にふと、「あれ、あの書類の添付書類は大丈夫だったか」と不安になり、事務所に戻って確認したこともある。誰にも見られない努力とは、そういう地味な確認作業の積み重ねなのだ。
依頼人には見えない舞台裏の奔走
華やかな仕事だと思われがちな司法書士だが、実際には地味で細かい調整の連続だ。依頼人が目にするのは、あくまで整えられた書類と結果だけ。そこに至るまでの道のりは、まるで裏方の演出のようなものだ。わかってもらえないことに、時には虚しさすら感じる。
連絡がないときほどこちらは動いている
依頼人から「最近どうなっていますか?」と連絡が来るたびに、「いや、こちらはずっと動いているんですけどね」と思ってしまう。進捗の連絡がないのは、問題なく進めているから。だけどそれが逆に「何もしていない」と誤解されることがある。実際には、各種調整や照会、書類の収集など、黙々と動いている。伝わらない動きほど多く、重い。それが少しつらい。
登記完了の裏にある小さな戦いの数々
ひとつの登記を終わらせるまでに、何本の電話をかけ、何枚のFAXを送り、何通のメールを書いているだろう。たとえば物件の筆数が多い案件では、入力作業だけで数時間かかることもある。しかも間違えられない。緊張しながら、黙々とパソコンに向かう時間は、正直言って疲れる。それでも「完了しました」と伝える瞬間には、どこかホッとする自分もいる。それだけ必死だった証拠だと思いたい。
電話一本のために何通もメールを出す
登記原因の確認を取るために、まずは書面で照会、それから確認の連絡、その後に正式な返信を受けてから電話で最終確認。ようやく通話に至るまでに、何度もメールとFAXが往復する。この手間、依頼人には見えていない。そしてそれでいて、電話に出てもらえないこともしばしばある。「なかなかつながりませんね」と言われたときのやるせなさは、なかなか説明しきれない。
地味で手間な業務に命を削っている感覚
決して大げさではなく、本当に命を削っているような感覚になる瞬間がある。ミスが許されない書類作成や申請業務に追われ、昼食を抜いて書類を仕上げた日もある。集中しすぎて、気がついたら日が暮れていたことも一度や二度ではない。そうしてようやく終わった仕事に対して、誰からも一言もない日。自己満足で終わる努力に、どこまで意味があるのか。ふと、そんなことを考えてしまう。
事務員はひとり孤独な現場の現実
都会の事務所とは違い、地方の小さな事務所では事務員も自分も最小限。電話も郵便も自分たちで全部やる。雑務すら手分けしてこなす中で、孤独とプレッシャーに押しつぶされそうになることがある。そんなとき、ふと感じるのが「これって本当に一人で抱える仕事なのか」という疑問だ。
役所と法務局と自分だけの戦い
他の職業と比べても、司法書士は「相手」が少ない。クライアントがいても、一度依頼されたらあとは役所や法務局とのやり取りが中心。つまり、人と会うよりも「手続き」と会っている時間が長い。役所からの指摘、法務局との折衝、全部ひとり。誰とも共有できず、すべてを抱えて動くのは、想像以上に堪える。
相談できる同業者が近くにいない
地方だと、同業者が物理的に近くにいないことも多い。ネットで調べても、似た事例がヒットしない。電話して聞くほどでもない内容は、結局自分で解決するしかない。昔、ある登記で判断に悩んだとき、誰にも聞けずに3時間悩んだことがある。そのとき思ったのは、「仲間がいない」という現実だった。元野球部としては、これは想像以上にしんどいことだった。
孤立感は年々強くなっている
最近では、オンラインでの相談も増えてはきたが、どこか心細さは拭えない。画面越しのやり取りでは、本音を語りにくい。同じ現場で戦っている仲間がそばにいない感覚。それが、年々心に重くのしかかるようになってきている。体力も落ち、集中力も続かなくなってきた今、この孤独感はとても堪える。
支えてくれる事務員の存在のありがたさ
そんな中でも、唯一の救いは事務員さんの存在だ。派手ではないが、的確な対応と穏やかな人柄に、何度救われてきたかわからない。自分がイライラしてしまった日でも、淡々と仕事を進めてくれる。そんな姿を見て、「もう少し頑張ってみようかな」と思える瞬間がある。孤独な現場で支えてくれる存在に、感謝してもしきれない。
元野球部の俺がこの仕事で一番痛感したこと
かつての自分はチームスポーツで生きていた。声を出し合い、支え合い、同じ方向を向いて汗をかく。あの頃の感覚は、この仕事ではほとんど味わえない。完全なる個人戦。誰にも頼れず、声も届かず、淡々とアウトを取り続けるような毎日だ。あのグラウンドでのにぎやかさが、今は少し恋しい。
チームプレイとは無縁の毎日
今の仕事には、「背中を預ける仲間」がいない。誰かがミスをカバーしてくれることもないし、自分の仕事を代わってくれる人もいない。全部自分、すべて自分。その責任の重さが、精神的にどんどん堪えてくる。昔のように、ベンチで笑いながら励まし合うなんてことは、もう二度とないのだろうかと思うと、少し切ない。
声をかけてくれる仲間がいないということ
ミスをして落ち込んでも、誰かが「ドンマイ」と声をかけてくれるわけではない。ひとり、心の中で処理するだけだ。この孤独感は、思った以上にじわじわと精神を蝕んでいく。特に繁忙期になると、ふと涙が出そうになることすらある。人はやっぱり、誰かに「おつかれ」と言われたい生き物なんだと思う。
一球入魂よりも百本ノックのような日常
司法書士の仕事は、どちらかというと一発勝負ではない。地味で延々と続く作業の連続。まさに百本ノックだ。集中力が切れても、誰も代わってくれない。でも、だからこそ、一つ一つを丁寧に処理する姿勢が求められる。昔のように声を張ることはないが、心の中で「もう一球」と言い聞かせながら、今日もパソコンに向かっている。
根性論ではどうにもならない疲労の蓄積
「気合いでなんとかなる」なんて言っていられたのは、若い頃だけだ。今は、目も疲れるし、集中力も落ちる。根性だけでは乗り越えられない疲労が、確実に積み重なっている。それでも前に進まないといけないのがこの仕事だ。誰にも見られなくても、今日もまた、積み重ねるしかない。