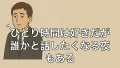職印が主役で私はただの脇役
司法書士より目立つ職印という存在
朝。いつものように冷えた事務所の空気を一息吸い込む。机の上に陣取るのは、私ではない。朱肉の隣に居座る、漆黒の円筒。
そう、我が事務所の主役——職印だ。
「シンドウ先生、今日の書類、全部で22件です」
奥のデスクから、サトウさんの声が届く。さながらサザエさんのオープニングよろしく、書類という名の波が押し寄せる。
波平が毛をむしる理由が、今ならわかる。
机の上の主役は誰なのか
机の上に並ぶ書類の列。中央に鎮座する職印。それはまるで、江戸時代の将軍のような風格だ。私はその脇に控える与力か、はたまた茶坊主か。
「それ、ハンコ押さないと何も進まないんですよね」
サトウさんの言葉が、ささやかな皮肉に聞こえる。いや、事実だ。書類の内容をいくら精査しようが、最終的に押す「印影」がなければ、世の中は動かない。
依頼人の視線はまず職印へ
「この印鑑、先生のですか?すごく立派ですね」
依頼人は、書類よりも先に私のハンコを見た。
どうやら私は、話しかけやすい司法書士ではなく、「立派な職印の持ち主」として存在しているらしい。
やれやれ、、、
押すだけで決まってしまう恐怖
確認したはずなのに震える指
「えーと、ここですね。被相続人の氏名、住所、生年月日……」
一つひとつ確認する。だが、指が印面に触れる瞬間、わずかに震える。
私の指先ひとつで、すべてが法的に「確定」してしまうのだ。
その責任の重さは、紙よりもずっと重たい。
誤記と訂正のはざまで
「先生、この“東京都品川区”の字が“品川”じゃなく“品原”になってます」
サトウさんが冷静に指摘する。
ひと呼吸置いて訂正印。ハンコひとつで訂正できる?
いや、その裏にどれだけの神経戦があるか。書類の海で溺れる者にしか分からない。
「押した後」ではもう遅い現実
司法書士界の「探偵学園Q」だとしたら、私の役割は間違いなく“地味担当”。一度押してしまった印影は、時間を巻き戻せない。
職印は万能だが、間違いには冷酷なのだ。
サトウさんの冷静なひと言に救われる
「その印影、ちょっとズレてます」
「えっ、また?」
サトウさんはルーペでも使ってるのかと思うほど、ズレに敏感だ。
私は再度朱肉をつけ、丁寧に……
「ポンッ」
沈黙。二人して印影をじっと見つめる。
「今回はOKです」
そのひと言が、なぜかホッとする。
ハンコ押し職人のような眼力
「先生って、ハンコ押すときちょっと首傾げますよね」
「そう?」
「なんか、猫背のくせに武士みたいです」
それ、褒めてるのか?
黙って修正するその背中
彼女は黙って打ち直しの申請書を作成していた。気づけば、私よりも書類に強くなっているかもしれない。
そして私は、ただ職印を押すだけの存在。
やれやれ、、、本当に、そう思う。
ハンコと責任の重さは比例するのか
名前ではなく印影で判断される職業
司法書士という肩書きよりも、「あのハンコの人」で覚えられている。
それが嬉しい日もあれば、虚しい日もある。
責任は軽くならないのに
たとえ電子署名に変わっても、この職印の重みは変わらない気がする。
むしろ、印影があるからこそ誤魔化しが効かない。
そう思うのは、昭和の野球部出身だからかもしれない。
ハンコ一つで通る世界の不条理
「内容は誰が確認したんですか?」
「先生が押印してるので、間違いないと思います」
いや、それサトウさんが全部見てるから。
私はただの“押印ボタン”だ。
誰も見ていない私の苦悩と愚痴
やれやれと言いたくなる瞬間
今日も22件。黙って印を押す私に、誰かが言う。
「先生、印影がすごく立派ですね」
……顔じゃなくて?性格じゃなくて?
やれやれ、、、
もはや私のアイデンティティは、朱肉に染まっている。
独身司法書士の独り言
印鑑の存在感に嫉妬する男の話なんて、誰が読むのだろう。
だが、今日も私は押す。静かに、確実に、そして愚痴をこぼしながら。