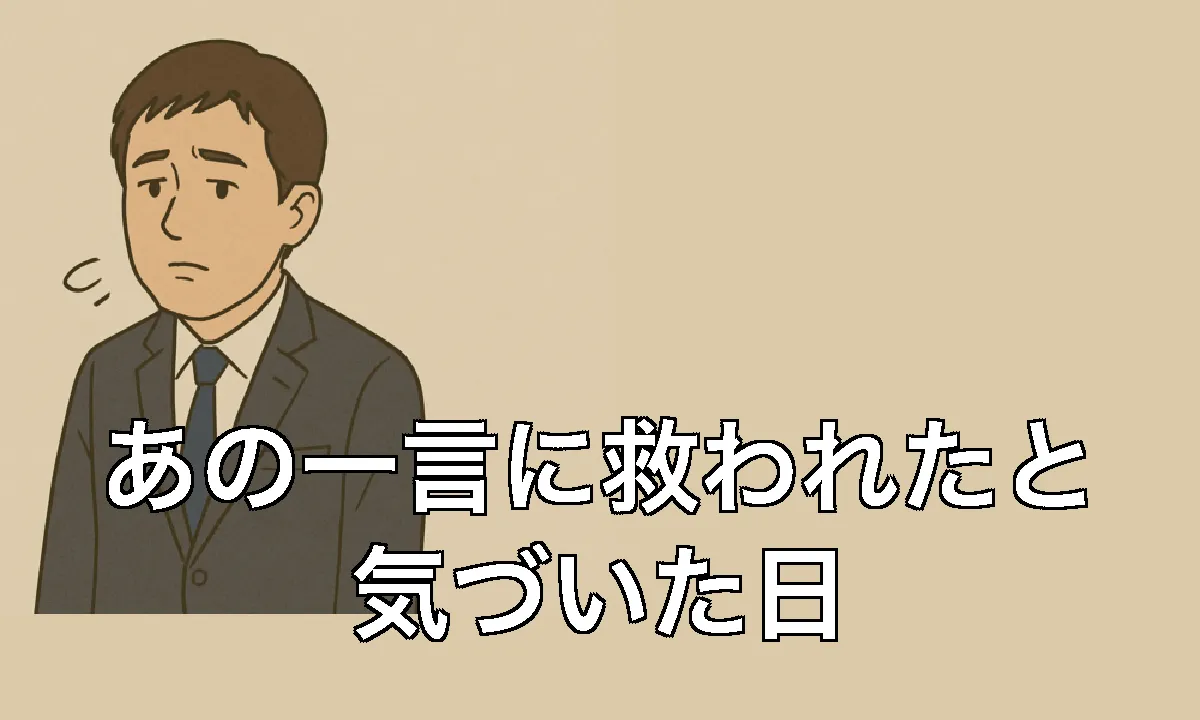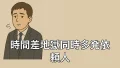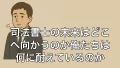朝から気が重い日常に差し込んだ光
司法書士として地方で事務所を営んでいると、忙しさと孤独の両方が押し寄せてくる日がある。朝、目覚めた瞬間から「今日もミスが許されない」という緊張感がのしかかり、布団から出るのが億劫になる。誰にも弱音を吐けない日々。そんな朝に限って、机の上には依頼書類の山。前向きに仕事を始めたいと思いながらも、心は重く沈んでいた。けれど、そんなある日、小さな言葉が僕の中に灯をともした。
やる気が出ない朝に限って山積みの書類
冬の朝は特に苦手だ。気温と同じく気持ちも冷えきっていて、ストーブの前でボーっとしてしまう。目の前にあるファイルの束を見ると、クライアントの手続き、登記の準備、書類の確認、あれこれ考えるだけでげんなりしてしまう。以前は「段取りさえしっかりしていれば」と前向きだったが、年を重ねると疲れも蓄積するし、何より“気力”の立ち上がりが遅い。
一人事務所の現実と向き合う疲弊
僕の事務所には事務員が一人いるが、彼女もまた手一杯だ。結局、登記の判断や対外的なやり取り、補正の対応など、最終的な責任はすべて僕にのしかかってくる。思わず「自分の存在って、ただの“処理マシーン”か?」なんて思ってしまう日もある。人と話すのは好きだが、相談じゃなくて苦情ばかりが耳に入ると、どんどん心がすり減っていく。
時計ばかり見ている自分に嫌気が差す
午前10時。もう3回も時計を見た。午前11時。まだ1時間しか経っていない。そんな日がある。集中力が保てず、ふとしたことでため息が出る。無理やり机に向かっても、目は書類を追っていても頭に入ってこない。ああ、こんな状態でミスでもしたら…。負のスパイラルに入っていくのがわかっていても止められない。そんな自分にまた落ち込む。
思わず口をついた「もう限界かも」
その日も、登記簿の添付書類に関するトラブルで朝から電話が鳴り続けていた。役所からは補正の指示、クライアントからは催促。電話を切った瞬間、僕の口から出たのは、「…もう限界かもなぁ」という言葉だった。事務所の奥にいた事務員が顔を上げたが、僕は苦笑いしてごまかした。誰かに本音を言うことも少なくなった。でもその日は、出てしまった。
誰にも言えない本音を吐き出した瞬間
普段は意地でも弱音を吐かない。元野球部だし、体育会系の名残で「辛いなんて言うな」が染みついている。でもその日は本当に限界で、言わずにはいられなかった。口にしてしまったあと、なんとも言えない情けなさがこみあげてきて、内心「聞かれたくなかったな」と思っていた。けれど、その数分後に返ってきた言葉が、思いがけず心を揺さぶった。
事務員さんの何気ない返事が胸に刺さる
「先生も人間なんですから、限界って感じても当然ですよ」──彼女がぽつりと言ったその一言に、不意に目頭が熱くなった。慰めようという意図はなかったのかもしれない。それでも、責任やプレッシャーで押しつぶされそうだった心に、スッと染み込んできた。そうか、自分を許してもいいんだと、初めて思えた瞬間だった。
たった一言が支えになることを実感した瞬間
日々、目の前の業務をこなすだけで精一杯。でも、人間は誰しも孤独な戦いの中で、誰かの「たった一言」に救われることがある。その日の出来事は、僕にとっての転機だったかもしれない。心を固くしていた部分が少し緩んだ。司法書士という仕事の中で、優しさを受け取る側になることの大切さを、ようやく学べたのかもしれない。
「先生も人間なんですから」で肩の力が抜けた
ふだん「先生」と呼ばれ続けていると、「失敗してはいけない」「常に正しくあれ」といったプレッシャーが当たり前になってしまう。だけど、それはしんどい。誰だって間違えるし、疲れるし、落ち込むこともある。その当たり前を認めてもらえた気がして、スッと肩の力が抜けた。まるで、息ができるようになったような感覚だった。
責任感が強すぎることの落とし穴
司法書士という仕事は、法的なミスがダイレクトに依頼者の不利益につながる。そのため、「自分が最後の砦」という思いで取り組む人が多い。僕もその一人だ。だが、その意識が強すぎると、自分を追い詰めることにもなる。責任感は大切だけれど、それが自分の首を締めていないか、時々振り返る必要がある。
完璧じゃなくてもいいという許し
「間違えてはいけない」と思い続けるあまり、完璧主義に陥っていた。けれど、あの事務員の一言は、そんな僕に「それでもいいんだよ」と言ってくれているようだった。実際には、少しくらい失敗しても、誠意を持って対応すれば大きな問題にならないことの方が多い。むしろ、柔らかさや人間味が信頼につながることもある。
共感が人を立ち直らせるという現実
誰かに寄り添ってもらうことで、自分が立ち直れる瞬間がある。それは、何か特別なアドバイスではなく、「そうですよね」「つらいですね」といった共感の言葉だったりする。僕もそれを忘れていた。司法書士として常に“与える側”でいる必要はない。時には“もらう側”になることも、仕事を続けていく上では必要だ。
言葉以上に伝わる「気持ちの寄り添い」
事務員のその一言に、実はこれまでの感謝やねぎらいが込められていたのだと思う。日々の業務でぶっきらぼうに指示してしまっていたけれど、ちゃんと見てくれていたのかもしれない。人は、ほんの少し気持ちが通じただけで、もう一度前を向ける。そんなあたたかさを、改めて知ることになった。
元野球部としての“声かけ”の大切さを思い出す
野球部時代、仲間がエラーしたときにかけた「ドンマイ」という一言が、その人の顔を変えることがあった。今、自分が言われてみて初めて、それがどれだけ大切なことか身に染みてわかった。司法書士という堅い世界にいると忘れがちだけれど、人間関係の基本は、思いやりのある言葉なのだ。
司法書士という仕事の重みと向き合う
毎日多くの書類とにらめっこし、正確さを求められ続ける日々。責任は大きいが、孤独も深い。そんな中で、人の言葉に救われることがある。司法書士として生きることの重さと、同時に人間らしさを持ち続けることの意味を、ようやく実感できたような気がする。
毎日が「失敗できない」の連続
僕たち司法書士は、間違えたら「ごめんなさい」では済まない世界にいる。登記情報の一文字の間違いが、大きなトラブルにつながることもある。だからこそ、常に緊張感を持って仕事をしている。でも、その緊張の積み重ねは、確実に心をすり減らす。緊張を抜く時間や、支えになる言葉がなければ続けられない。
知られざるプレッシャーと孤独
外から見れば「先生」と呼ばれ、立派な仕事に見えるかもしれない。けれど実際は、責任と孤独に押しつぶされそうな日々。誰かに愚痴をこぼす余裕もない。そんな中で、ちょっとした一言に救われることもある。僕のように、表では強がっている司法書士さんたちにこそ、知ってほしい。
それでも続ける理由は何か
苦しいのに、それでも続けている。それはたぶん、自分なりに「人の役に立っている」という実感があるからだと思う。そして時には、自分が人に助けられることもある。誰かの「ありがとう」や「大丈夫」という言葉が、次の日の一歩を支えてくれる。そんな日々を、もう少し続けてみようと思う。
だからこそ言葉の力が沁みる
司法書士として働く中で、「言葉の重み」は何度も実感してきた。契約書の一言、説明の一文、そして日常の何気ない言葉。どれもが人の心を動かす。今回の経験を通じて、僕は「発する側」としてだけでなく、「受け取る側」としての感性も大切にしようと思った。
役所の冷たい対応に心折れかけても
補正を受けて役所へ出向いたときの、あの冷たい対応。誤字を指摘された瞬間、「はい、やり直しです」の一言で済まされると、心がくじけそうになる。それでも、戻ってきた事務所での「お疲れ様です」の一言が救いになる。人の優しさと冷たさの落差を感じながら、それでも前に進んでいくのが司法書士だ。
クライアントの「ありがとう」が救いになる
最後にやっぱり心に残るのは、依頼者の「助かりました」「本当にありがとうございます」という言葉だ。どんなに疲れていても、この一言があるだけで、「また頑張ろう」と思える。言葉の力を、僕たちはもっと信じていい。そして、自分も誰かにそういう言葉をかけられる存在でありたい。