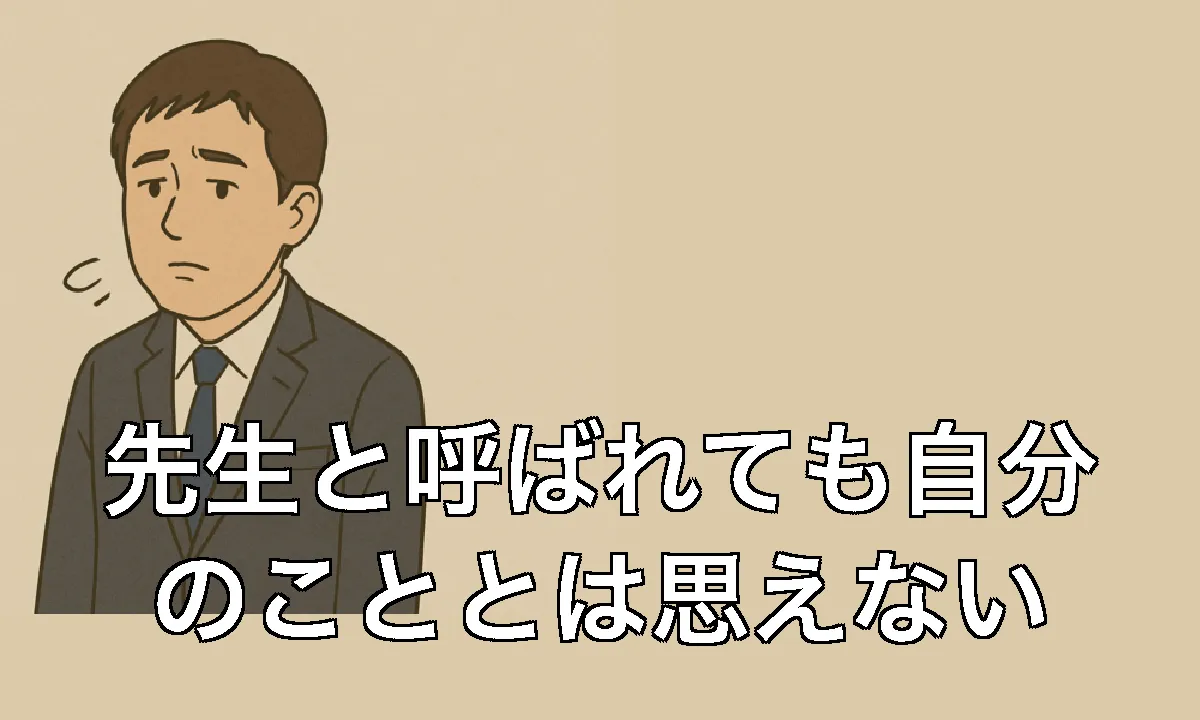肩書きだけが立派になっていく気がする
司法書士という肩書きがついてから、もう十数年になる。依頼者に「先生」と呼ばれることにも、さすがに慣れてきたはずなのに、どこかその呼び方が自分のことを指しているとは思えない感覚がずっと残っている。特別な存在になったわけでもないし、たいした人格者でもない。ただ、国家試験に通って登録したというだけで、自分の中身は学生時代とそう変わっていないような気がしてしまうのだ。だからこそ、日々の業務の中で肩書きだけがどんどん先を歩いていってしまって、自分自身が取り残されているような感覚を覚えることがある。
「先生」と呼ばれるたびに戸惑う
例えばコンビニで書類のコピーをしていて、ふと隣の人が「先生、これお願いできますか?」なんて声をかけてきたとき。反射的に「自分じゃないですよね?」と周囲を見渡してしまう。名札でもつけて歩いているわけではないのに、事務所の中でも同じような感覚に陥ることがある。依頼者から「先生」と呼ばれても、心の中で「そんな立派な人間じゃないのに」と毎回つぶやいてしまう自分がいる。その言葉が持つ重さと、自分の等身大の姿が一致しないのだ。
昔の自分と今のギャップに苦笑い
元々、野球部で汗まみれになってグラウンドを走っていた高校時代、そして夜な夜な司法書士試験のテキストを読んでいた浪人時代。そんな泥くさい過去を持つ自分が、今は「先生」と呼ばれている現実がどこか笑える。あの頃は、とにかく一人前になることだけを目指していた。でも、いざその「一人前」になってみると、どこか「これで良かったのか」という疑問も出てくる。呼び方や肩書きではなく、もっと中身で信頼される人間でありたいという気持ちがあるからこそ、余計に違和感が拭えないのかもしれない。
立場に追いつかない自覚と焦り
「先生」と呼ばれるたびに、自分の足りなさが浮き彫りになる。登記の内容をすべて完璧に把握できているわけでもなく、相続や遺言の相談では「こうすれば正解」と簡単に割り切れないケースも多い。そんなとき、依頼者の期待に応えられていない自分が情けなくなる。立場だけが先を歩いていて、自分の実力や精神的な成熟が追いついていない。40代半ばになっても、まだまだ不安だらけだ。だからこそ、「先生」と呼ばれることに戸惑い、重荷を感じてしまうのだろう。
人の役に立ちたい気持ちはある
「先生」と呼ばれるからには、それなりの責任が伴うのは分かっている。依頼者の人生に関わる仕事をしているのだから、真剣に向き合わなければならない。その気持ちは常にあるし、決して手を抜いたことはない。それでも、自分に自信が持てないときがあるのだ。ミスを恐れて慎重になりすぎてしまったり、言葉選びに悩んだり、依頼者の期待に応えられているのか不安になる瞬間は少なくない。
それでも自信が持てない日がある
ある日、遺産分割の調整で感情的になった依頼者に「先生なのに、そんなこともわからないんですか」と言われたことがある。その場では冷静に対応したが、心の奥ではグサリと刺さった。知識が足りなかったわけではなく、説明の仕方やタイミングが悪かった。それでも「先生」という言葉を盾にされたとき、自分がいかに未熟であるかを突きつけられたように感じた。その日はずっと落ち込んでしまい、事務所に帰っても机に座ってボーッとしていたのを覚えている。
ちょっとした言葉が心に刺さることも
依頼者の一言は、ときに剣のように鋭い。たとえば「先生は忙しそうだから、ちゃんと見てくれてないんじゃないかと思ってました」なんて言われると、こちらがどれだけ必死でも、伝わっていないのかとがっかりする。言い方に悪意があったわけじゃないのは分かっている。でも、「先生」という言葉が前提にあるからこそ、「それくらいできて当たり前」だと思われてしまう。その期待に応えるために、常に神経を張り詰めているような気がして、心がすり減る。
「先生だから分かるでしょ」はプレッシャー
相談の場面でよくあるのが、「先生なら、こういうときどうするか教えてください」という投げかけだ。こちらも真摯に考えて答えるけれど、まるで人生相談のように広範な問いを投げられると戸惑ってしまう。法律の話だけでなく、「人としての答え」まで求められているような気がして、気が抜けない。自分の答えがその人の人生を左右するかもしれない。そんな責任感が、時にプレッシャーとなってのしかかってくる。
事務所の空気は今日も静かすぎる
田舎の司法書士事務所。スタッフは事務員の女性が一人だけ。電話が鳴るたびにピリッと緊張し、沈黙の時間がやけに長く感じられる。静かすぎて、たまにコピー機の音すら耳障りに感じるほどだ。この空気に慣れたとはいえ、どこかで孤独と常に向き合っている感覚がある。相談の電話が終わったあとに、ぽつんとため息をつくのが日課のようになっている。
事務員さんと二人きりの世界
事務所にいるのは、長年働いてくれている事務員さんと自分だけ。淡々と仕事をこなす彼女に支えられていることは、間違いない。だけど、必要以上に話すこともない関係は、ちょっと味気ない。昼休みにラジオの音だけが流れる空間で、一人でカップラーメンをすする自分に、ふと寂しさを感じることがある。「先生」と呼ばれても、誰かと心を通わせている実感がなければ、その言葉も空虚に響いてしまう。
気まずさとありがたさが同居している
ときどき、こちらの機嫌が悪いと感じたのか、事務員さんが気を遣って余計に静かになることがある。そういうときほど「申し訳ないな」と思ってしまう。でも、自分の心の余裕がないと、感謝の言葉すらうまく出てこない。彼女がいることでどれだけ助けられているか、本当は伝えたいのに、それを口にするのがなぜか苦手だ。感謝と気まずさがせめぎ合う中で、今日もまた無言の時間が流れていく。
仕事が忙しくても心はどこか満たされない
登記の締切、相続の相談、法務局への提出。やるべきことは山ほどある。スケジュールは常に埋まっていて、暇だと感じる日はまずない。それでも、心の奥底ではどこか「これでいいのか?」という虚しさがつきまとう。がむしゃらに働いてきたが、気づけば独り身のまま、仕事だけに追われている。そんな生活が、ふとした瞬間に重くのしかかってくる。
案件をさばくだけの毎日に意味を探す
日々の業務をこなすこと自体が目的になってしまって、誰かのためにという実感が希薄になっているような気がする。もっとじっくり話を聞いたり、相手の背景に寄り添ったりしたいけれど、現実には時間に追われてしまう。結果として、「ただの作業員」のような感覚に陥ることもある。それでも、「先生」として信頼してくれる人がいる限り、もう少しだけ踏ん張ってみようかと思える。
「やりがい」はどこへ行った
昔は、誰かの問題を解決できたときに「この仕事やっててよかった」と感じることがもっとあった。今もゼロではないが、心からの達成感や喜びは少なくなった。もしかすると、自分の感情が摩耗しているのかもしれない。案件数は増えても、心が動く回数は減っている。そんな自分に気づいたとき、情けなさと悲しさが同時に込み上げてきた。
独身生活の空虚さがじわじわと
誰にも文句を言われない自由な生活。そのはずが、家に帰って誰とも話さず、テレビの音だけが響く夜が続くと、虚しさが積もってくる。友人も少なくなり、恋愛も遠い話。気づけば仕事だけが自分を支えている。だからこそ、「先生」と呼ばれることに少しだけすがっている自分もいるのかもしれない。
それでもこの道を選んだ理由
決して順風満帆ではないし、いまだに「自分が先生なんて」と思っている。それでも、自分で選んだ道であることは間違いない。誰かの人生の節目に関わることができる仕事。泥くさくても、失敗しても、やっぱりこの仕事を続けたい。そう思える瞬間が、まだある。だから、明日もまた、呼ばれて戸惑いながら「はい」と返事をするのだ。
元野球部らしく泥臭くても前を向く
部活での泥だらけのユニフォーム、ノックで手を痛めた日々。司法書士の仕事とはまるで違うようで、どこかで繋がっているような気がする。地道にコツコツ積み重ねていく姿勢、試合に勝てなくても諦めずに食らいつく気持ち。それが今の仕事の中にも息づいている。華やかじゃなくても、自分なりに戦っている。そう思えるから、まだ踏ん張れる。
過去の自分が今の自分を支えている
苦しかった受験時代、失敗を繰り返した修習時代、そして独立してからの不安だらけの日々。振り返れば、自分にはいつも不器用な過去がついて回っている。でも、そのすべてが今の自分を形作っている。先生と呼ばれても実感はない。でも、それでいいのかもしれない。不安や違和感を抱えながら、それでも前を向く。そんな司法書士がいてもいいじゃないか。