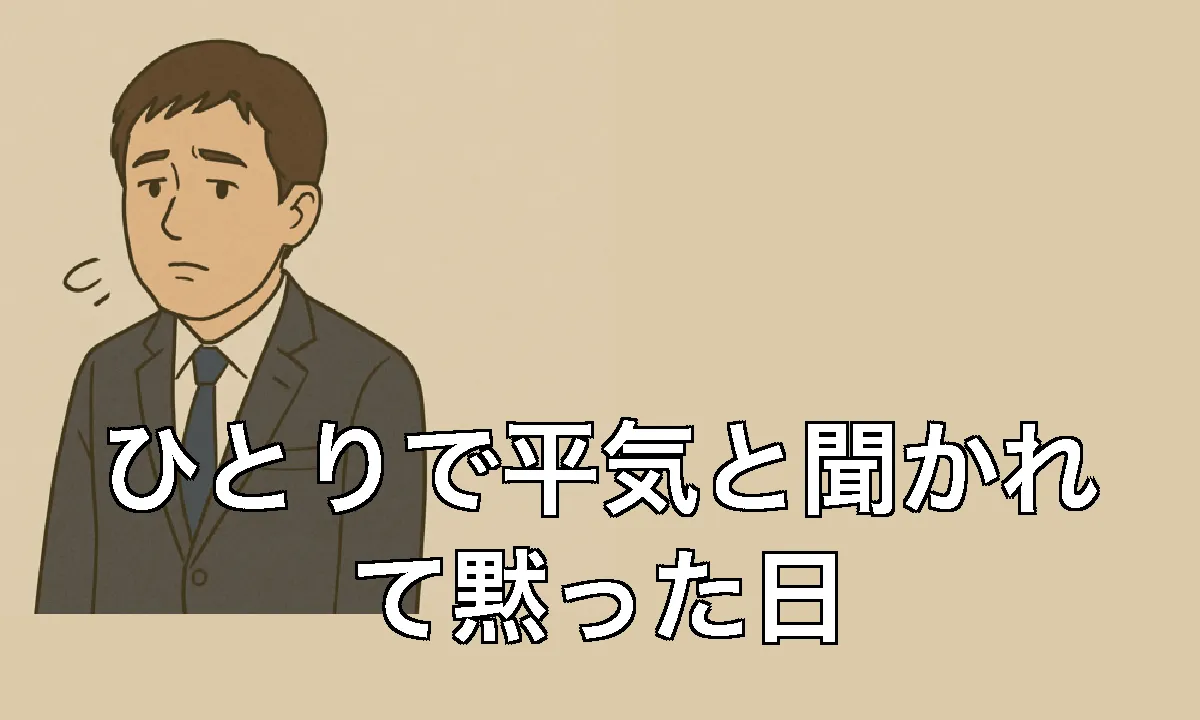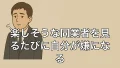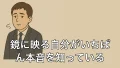平気のふりが板についた頃に
「ひとりで平気でしょ」と言われることが増えてきたのは、たぶんここ数年の話だ。自分でもそう思われるように、無意識のうちに振る舞ってきたのかもしれない。司法書士という職業柄、黙々と書類を整え、ひとつひとつ処理していく日常には孤独がつきものだ。誰かに相談するより、ひとりで決断した方が早いし、間違いもない。そう思ってきた。気づけば、「一人で大丈夫な人」として周囲に認識され、そういう自分を演じることが普通になっていた。でも、それが“板につく”ということの意味を、あの日、思い知らされるとは思っていなかった。
なんでも一人でやるのが当たり前になっていた
朝の掃除から郵便の投函、銀行とのやりとり、相続人との調整、役所との折衝。たいていのことは自分でできるし、そうしてきた。誰かに任せるほうがストレスだと思っていた。事務員の彼女には必要最低限しか頼まないし、こちらも忙しそうな彼女の様子を見てつい遠慮してしまう。気づけば「一人でやったほうが早い」が口ぐせになり、それが生き方そのものに染みこんでいた。けれど本当にそれが“平気”だったのかどうかは、きっと誰にも聞かれなければ、ずっと考えもしなかっただろう。
誰にも頼らないことが強さだと思っていた
昔からそうだった。高校時代の野球部でも、怪我してるのに黙って練習を続けてた。人に弱みを見せるのが何より苦手で、口数も少なかったから、周囲からは「無口で我慢強い奴」って思われていた。司法書士になってからも、黙ってこなすスタイルは変わらない。誰にも頼らないことが“責任感”であり、“大人の男”の証明みたいに思っていた。でも、頼れない自分は、本当に強いのか?あのときの自分を見て、そう問い直したくなった。
でも実際は、頼れないだけだったかもしれない
本当はただ、頼み方がわからないだけだったのかもしれない。誰かに声をかけるとき、どう言えばいいのか、どう思われるか、それを考えてしまって動けない。強がっているというより、不器用で、情けないだけ。でもそれを誤魔化すために「一人が楽」と言ってみせる。そんな自分に、気づいてしまったとき、胸の奥がじんわりと重たくなった。頼れないというのは、強さではなく、ある種の“欠落”だったんじゃないかと思う。
その一言が、胸にひっかかった
「先生って、ひとりで平気なタイプですよね?」──たまたま依頼人との面談中、ぽろっと出たその言葉に、反応が遅れた。いや、正確には言葉が出なかった。笑って返すのが普通なのに、のどの奥がつかえたようになって、何も出てこなかった。たった一言がこんなに刺さるとは思わなかったし、自分がそんなに“ひとり”にこだわっていたとも気づかなかった。平気って、なんだ?それは強がりの言い換えじゃないか?そう思ってしまった瞬間、黙るしかなかった。
「ひとりで平気?」という何気ない問い
その問いかけは、決して責めでもなければ、深い意味のあるものでもなかったのだろう。ただの雑談の一部。だけど、自分の中でだけ大きく波紋を広げた。「平気」という言葉には、何かを我慢しているようなニュアンスがある。それを問いかけられて、自分でもその“我慢”に気づいてしまったから、言葉が出てこなかったのだろう。たまに誰かに「大丈夫?」と聞かれると、かえって苦しくなるときがある。それと似たような感覚だった。
咄嗟に笑えなかったのはなぜか
ふつうなら「ええ、全然平気ですよ」と笑って返せばよかった。それが大人の対応ってもんだ。でも、あの瞬間はそれができなかった。なんとなく、自分の内側を見透かされたような気がして、無理に笑うのがバカらしくなった。ずっと平気そうに振る舞ってきたけど、本当は、たまに誰かとラーメンでも食べに行きたかったし、無意味な話をする時間も欲しかった。そんな気持ちを、押し込めてきたのかもしれない。
言葉にできない感情があると知った瞬間
「言葉が出なかった」という経験は、司法書士という職業をしているとなかなかない。いつも冷静に説明して、法律的に整理して、書類に落とし込んでいく。それが仕事だ。でも、このときだけは、理屈じゃなかった。ただただ、心が詰まってしまった。情けないような、でもどこかホッとしたような、そんな複雑な感情だった。言葉にできない気持ちが、たしかにある。そのことを、初めてはっきりと知った気がする。
事務所での孤独という現実
小さな事務所。事務員一人、所長一人。声をかけることも、かけられることも、最低限にとどまる日が多い。黙々と、それぞれの業務をこなすだけ。相談ごとがあっても、「忙しそうだからまた今度にしよう」と思って口を閉ざす。その繰り返しが積もって、気づけば“誰とも話していない日”ができてしまう。寂しいというより、“空洞”がある。これが孤独か、と実感する瞬間が増えてきた。
相談相手がいないというしんどさ
経営のこと、売上のこと、依頼人対応のこと。何かひとつでも迷いがあるとき、誰かに「これってどう思う?」と聞ける環境があれば、どれだけ救われるだろうと思う。でも、それがない。一人で判断し、結果に責任を持つ。それが開業司法書士の宿命かもしれないが、たまに、その重さに押しつぶされそうになる。愚痴を吐き出す相手がいるだけでも違うのに、と思ってしまう。
事務員はいるけれど「業務外の話」は難しい
事務員さんは優秀だし助かっている。でも、こちらの立場として「ちょっとした悩みを話す」には気を使う。自分の弱さを見せることで、相手の不安を煽りたくないし、パワーバランスもある。だから結局、自分の感情は自分の中で処理するしかなくなる。そうやって少しずつ孤独が蓄積していく。会話はあっても、共有はされない。それが小規模事務所の現実だ。
元野球部だった自分と、今の自分
昔は、もっと人と一緒に声を出して、体を動かしていた。高校の野球部では、声出しだけでも練習の一環だったし、励まし合って試合を乗り切る感覚があった。勝っても負けても、誰かと分け合う時間があった。でも今は、嬉しいことも苦しいことも、すべてひとりで受け止める。あの頃の“チーム”という感覚が、今は遠い昔の幻のように思える。
あなた: html形式にしてコピペできる形で出力してください ダウンロードファイルにはしないでください。!DOCTYPE htmlからスタートしてhtmlを閉じるところまで書いてください。最後まで出力してください。
平気のふりが板についた頃に
「ひとりで平気でしょ」と言われることが増えてきたのは、たぶんここ数年の話だ。自分でもそう思われるように、無意識のうちに振る舞ってきたのかもしれない。司法書士という職業柄、黙々と書類を整え、ひとつひとつ処理していく日常には孤独がつきものだ。誰かに相談するより、ひとりで決断した方が早いし、間違いもない。そう思ってきた。気づけば、「一人で大丈夫な人」として周囲に認識され、そういう自分を演じることが普通になっていた。でも、それが“板につく”ということの意味を、あの日、思い知らされるとは思っていなかった。
なんでも一人でやるのが当たり前になっていた
朝の掃除から郵便の投函、銀行とのやりとり、相続人との調整、役所との折衝。たいていのことは自分でできるし、そうしてきた。誰かに任せるほうがストレスだと思っていた。事務員の彼女には必要最低限しか頼まないし、こちらも忙しそうな彼女の様子を見てつい遠慮してしまう。気づけば「一人でやったほうが早い」が口ぐせになり、それが生き方そのものに染みこんでいた。けれど本当にそれが“平気”だったのかどうかは、きっと誰にも聞かれなければ、ずっと考えもしなかっただろう。
誰にも頼らないことが強さだと思っていた
昔からそうだった。高校時代の野球部でも、怪我してるのに黙って練習を続けてた。人に弱みを見せるのが何より苦手で、口数も少なかったから、周囲からは「無口で我慢強い奴」って思われていた。司法書士になってからも、黙ってこなすスタイルは変わらない。誰にも頼らないことが“責任感”であり、“大人の男”の証明みたいに思っていた。でも、頼れない自分は、本当に強いのか?あのときの自分を見て、そう問い直したくなった。
でも実際は、頼れないだけだったかもしれない
本当はただ、頼み方がわからないだけだったのかもしれない。誰かに声をかけるとき、どう言えばいいのか、どう思われるか、それを考えてしまって動けない。強がっているというより、不器用で、情けないだけ。でもそれを誤魔化すために「一人が楽」と言ってみせる。そんな自分に、気づいてしまったとき、胸の奥がじんわりと重たくなった。頼れないというのは、強さではなく、ある種の“欠落”だったんじゃないかと思う。
その一言が、胸にひっかかった
「先生って、ひとりで平気なタイプですよね?」──たまたま依頼人との面談中、ぽろっと出たその言葉に、反応が遅れた。いや、正確には言葉が出なかった。笑って返すのが普通なのに、のどの奥がつかえたようになって、何も出てこなかった。たった一言がこんなに刺さるとは思わなかったし、自分がそんなに“ひとり”にこだわっていたとも気づかなかった。平気って、なんだ?それは強がりの言い換えじゃないか?そう思ってしまった瞬間、黙るしかなかった。
「ひとりで平気?」という何気ない問い
その問いかけは、決して責めでもなければ、深い意味のあるものでもなかったのだろう。ただの雑談の一部。だけど、自分の中でだけ大きく波紋を広げた。「平気」という言葉には、何かを我慢しているようなニュアンスがある。それを問いかけられて、自分でもその“我慢”に気づいてしまったから、言葉が出てこなかったのだろう。たまに誰かに「大丈夫?」と聞かれると、かえって苦しくなるときがある。それと似たような感覚だった。
咄嗟に笑えなかったのはなぜか
ふつうなら「ええ、全然平気ですよ」と笑って返せばよかった。それが大人の対応ってもんだ。でも、あの瞬間はそれができなかった。なんとなく、自分の内側を見透かされたような気がして、無理に笑うのがバカらしくなった。ずっと平気そうに振る舞ってきたけど、本当は、たまに誰かとラーメンでも食べに行きたかったし、無意味な話をする時間も欲しかった。そんな気持ちを、押し込めてきたのかもしれない。
言葉にできない感情があると知った瞬間
「言葉が出なかった」という経験は、司法書士という職業をしているとなかなかない。いつも冷静に説明して、法律的に整理して、書類に落とし込んでいく。それが仕事だ。でも、このときだけは、理屈じゃなかった。ただただ、心が詰まってしまった。情けないような、でもどこかホッとしたような、そんな複雑な感情だった。言葉にできない気持ちが、たしかにある。そのことを、初めてはっきりと知った気がする。
事務所での孤独という現実
小さな事務所。事務員一人、所長一人。声をかけることも、かけられることも、最低限にとどまる日が多い。黙々と、それぞれの業務をこなすだけ。相談ごとがあっても、「忙しそうだからまた今度にしよう」と思って口を閉ざす。その繰り返しが積もって、気づけば“誰とも話していない日”ができてしまう。寂しいというより、“空洞”がある。これが孤独か、と実感する瞬間が増えてきた。
相談相手がいないというしんどさ
経営のこと、売上のこと、依頼人対応のこと。何かひとつでも迷いがあるとき、誰かに「これってどう思う?」と聞ける環境があれば、どれだけ救われるだろうと思う。でも、それがない。一人で判断し、結果に責任を持つ。それが開業司法書士の宿命かもしれないが、たまに、その重さに押しつぶされそうになる。愚痴を吐き出す相手がいるだけでも違うのに、と思ってしまう。
事務員はいるけれど「業務外の話」は難しい
事務員さんは優秀だし助かっている。でも、こちらの立場として「ちょっとした悩みを話す」には気を使う。自分の弱さを見せることで、相手の不安を煽りたくないし、パワーバランスもある。だから結局、自分の感情は自分の中で処理するしかなくなる。そうやって少しずつ孤独が蓄積していく。会話はあっても、共有はされない。それが小規模事務所の現実だ。
元野球部だった自分と、今の自分
昔は、もっと人と一緒に声を出して、体を動かしていた。高校の野球部では、声出しだけでも練習の一環だったし、励まし合って試合を乗り切る感覚があった。勝っても負けても、誰かと分け合う時間があった。でも今は、嬉しいことも苦しいことも、すべてひとりで受け止める。あの頃の“チーム”という感覚が、今は遠い昔の幻のように思える。