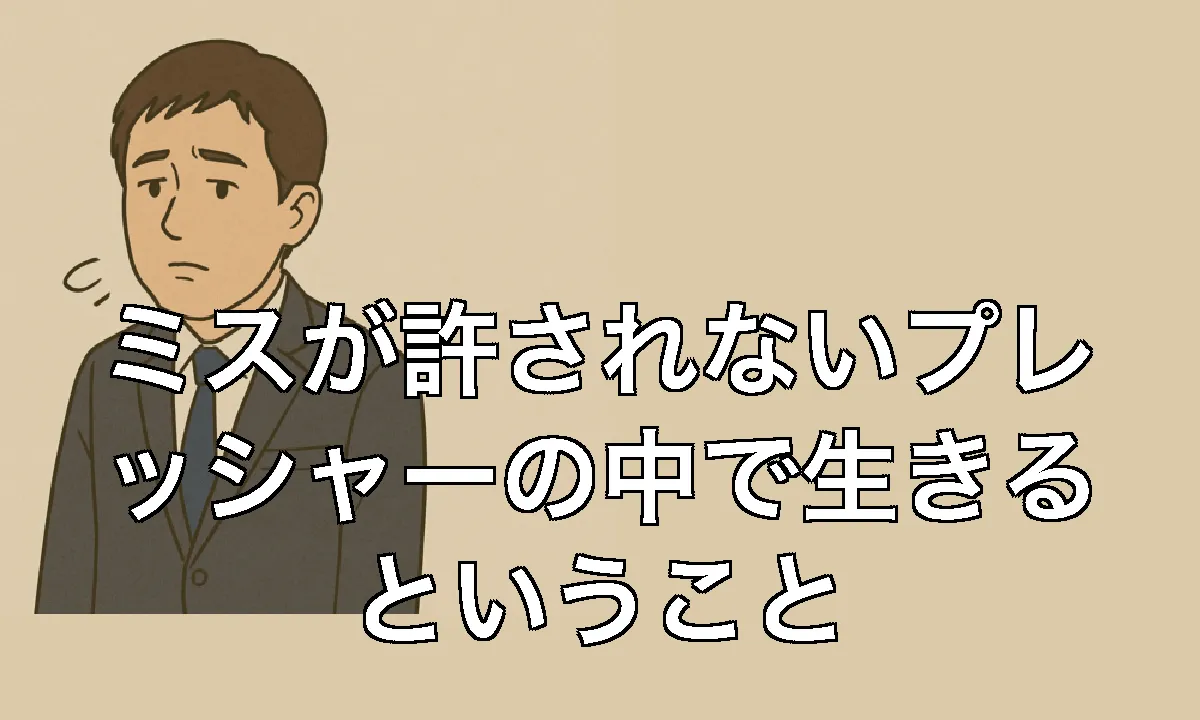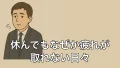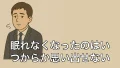完璧でなければならないという呪い
司法書士として生きていると、常に「ミスは許されない」という空気がまとわりついている。ちょっとした確認漏れが命取りになる。私たちの仕事は、登記や遺言など人生を左右する書類を扱う以上、信用を失えば次はない。ミスをした瞬間に「この人に頼んだのが間違いだった」と思われたら、それで終わりだ。頭ではわかっているのだが、実際にそのプレッシャーの中で毎日を生きるのは想像以上にしんどい。だから朝の目覚めからすでに心が張り詰めている。
朝から始まる緊張感との戦い
朝の始業前、パソコンを開くその瞬間から神経は尖っている。メール一通、FAX一枚、書類の束。どれも「落とし穴かもしれない」と疑いながら確認するのが癖になった。実際、以前に登記申請書に添付する住民票の日付が1日違っていたことで、補正の連絡が来たことがあった。それだけならまだいい。しかし、依頼人には「手間をかけてすみませんでした」と頭を下げ、相手の不安に対応しなければならない。朝の一通のメールで、1日が台無しになることもある。
メール一通にも神経を使う
メールの送信ボタンを押す前、10回は読み直す。敬語の使い方、相手の名前の表記、誤字脱字、日付や金額の記載…。昔、ある依頼者に「この文面、なんだか高圧的ですね」と言われたことがトラウマになっている。それからというもの、文面の一語一句に異常なほど気を遣うようになった。これが地味に神経を削る。事務員が作成したメールの下書きですら、「これは本当にこれでいいのか」と疑ってしまう。完璧を求めるあまり、全てを自分で抱え込んでしまう。
電話対応ひとつで信頼が揺らぐ
電話対応もまた、地雷の宝庫だ。相手が求める答えを即座に返せなければ、不信感を持たれる。少しでも「えーっと…」と間が空けば、「この人に任せて大丈夫なのか」と思われる可能性がある。以前、土地家屋調査士からの問い合わせに曖昧な返答をしてしまい、あとで訂正の電話を入れたことがある。それ以来、その調査士からの依頼は来なくなった。言葉ひとつで信用が崩れる現場では、気を抜ける瞬間が本当にない。
「失敗したら終わり」の刷り込み
気づけば、「失敗=即終了」という思考が染みついている。学生時代、野球部のキャプテンだったときもエラーをして落ち込んだ経験はあったが、あの頃は仲間がいたし、次の試合があった。だが今は違う。ひとりで事務所を構え、すべての責任を背負っている以上、取り返しのつかない失敗が現実にある。それが怖いのだ。失敗を許されない世界にいること自体が、精神をすり減らしていく。
実体験からくる恐怖の記憶
数年前、相続登記の案件で住所の字番を誤って申請してしまった。法務局からの補正通知に冷や汗が止まらなかった。依頼者には頭を下げ、再申請の書類をすぐに作成。幸いにも大きなトラブルには発展しなかったが、依頼者の一言が今も忘れられない。「こんなことで大丈夫なんですか?」。たった一言で、自信が粉々になった。あれ以来、申請前のチェックには2時間以上かけることもある。
他人の失敗を見るたびに自分が怖くなる
知り合いの司法書士が登記ミスで損害賠償を請求されたという話を聞いたとき、自分のことのように震えた。自分にも同じことが起きるのではないか。毎日が、何かの爆弾処理のような感覚だ。周囲の失敗談は、決して「他人事」として聞けない。むしろ「次は自分かもしれない」という恐怖を植え付けてくる。そうしてどんどん、自分を守るための鎧が厚くなり、柔軟な思考や心の余裕が削られていく。
プレッシャーの正体とその根
プレッシャーがなぜこんなにも重く感じるのか。それは、司法書士という仕事の性質そのものに原因がある。人の人生や財産に直結する業務を扱う以上、求められるのは「正確さ」と「信頼性」。さらに地方という閉鎖的な環境も、その重圧を倍加させる。「間違えたら終わり」「噂は一瞬で広がる」…それが日常だ。
司法書士という職業の性質
「書類を通じて人の人生を動かす」――それが司法書士の仕事だ。ちょっとしたミスで不動産取引が遅れれば、何百万円もの損害が出ることもある。責任が重いのは当然だ。さらにややこしいのが、「プロなんだから当然でしょ」という空気だ。ミスをしないことが前提で、それを褒められることもない。普通を保つことに必死なのに、それが「当たり前」で済まされる世界は、心がすり減る。
法的ミスが人生を狂わせる
相続放棄の期限を誤って処理すれば、相続人が多額の借金を背負うことになりかねない。遺言執行での手違いで、兄弟同士が争うこともある。そんな「一手で人生が狂う」場面が日常的にあるのが、私たちの仕事なのだ。だから、夜寝る前にも「今日の処理、間違ってなかったか」と思い返してしまう。そして、不安が消えないまま朝が来る。
信用こそがすべてという現実
司法書士にとって、資格よりも実は「信用」が命綱だ。資格を持っているだけでは食えない。地元の人たちから「あの人なら安心」と思ってもらえて、ようやく仕事が回る。その信用を壊すのは一瞬。だからこそ、どれだけ小さなミスにも過敏にならざるを得ない。事務所の看板は背中に貼り付いていて、どこへ行っても見られている気がする。
田舎ならではの「噂」リスク
地方の町では、「あの人、最近こんなことがあったらしいよ」という話が、翌日には広まっている。私も過去に、少しトラブルになった相続案件で「〇〇さんのところで問題が起きたらしい」と近所のスーパーで噂されていたことがある。誰が言ったのかわからない。ただ、それだけで信用にヒビが入るのだ。見えない目が常にあるようで息苦しくなる。
一度のミスで地域全体に広がる
東京なら、たとえ一度ミスしても次の依頼が入るだろう。でもここではそうはいかない。紹介が途絶える。電話が鳴らなくなる。それが現実だ。10年かけて築いた信頼も、1件のミスで壊れる。誰も「気にしないよ」なんて言ってくれない。だからこそ、神経をすり減らしてでもミスを避けようとする。自分の人生と生活がかかっているのだから。
取り戻せない名誉というもの
一度失った信用は、なかなか戻ってこない。どれだけ誠実に対応しても「また何かあるかも」と思われる。その視線が怖い。その空気が重い。だから私は、どんな小さなことでも慎重に、慎重に進める。でも、気を張りすぎて疲れ果ててしまうこともある。「今日は何もなかった」だけで、安心してビールが美味しく感じる日もある。