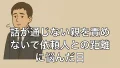玄関のドアを開けても変わらない空気
仕事を終えて家のドアを開けた瞬間、「ただいま」とつぶやく癖は未だに抜けない。けれど、それに返ってくる声はない。真っ暗な部屋。誰かの気配もない。スーツのままソファに沈み込み、天井を見上げる。誰かが迎えてくれるわけでもないし、夕飯の匂いが漂うわけでもない。気づけばこの生活にも慣れてしまったようで、感情を揺さぶられることも少なくなってきた。それがまた、少しだけ悲しい。
ただいまに返事がない暮らし
以前、結婚している友人に「家に帰ったら誰かが待ってるってどんな感じ?」と聞いたことがある。彼は笑いながら「うるさいけど、やっぱり安心するよ」と言っていた。正直、少し羨ましかった。自分の帰宅が誰かの心を動かすって、それだけで救われる気がする。けれどこちらは、今日も変わらず、誰もいない部屋に「ただいま」を投げて、そのまま消えていく。
テレビの音が唯一の生活音
無音の空間に耐えられず、帰宅してすぐテレビをつける癖がある。見ていなくても、誰かが喋っている音がしているだけで心が落ち着く。ニュース、バラエティ、何でもいい。音がしていれば、自分がこの空間でひとりきりじゃないと錯覚できる。バカみたいだけど、そんなもんだ。
今日あったことを話す相手がいない
「今日こんな依頼があってさ」なんて話せる相手がいたら、どれだけ楽になるだろう。ミスをした時の悔しさも、無事終わった時の安堵も、全部自分の中に留めるしかない。元野球部だった頃は、仲間と反省会だの武勇伝だので夜を明かしたもんだ。今はそのエネルギーを吐き出す場所が見つからない。
昔は誰かが待っていた気がする
実家にいた頃は、帰ると母親が「おかえり」と言ってくれていた。それが当たり前だった。今思えば、あれは貴重だったんだなと痛感する。母の作った夕飯の匂い、テレビの音、兄弟の喧嘩。うるさいけど、確かにあそこには温度があった。
家族の存在とその記憶
今はもう、実家も遠く、親も年老いている。年に一度会うか会わないか。そのたびに「元気でやってるの?」と心配されるが、元気と答えるしかない。家族にすら、寂しさを悟られたくない。そういう変な意地が、余計に孤独を深くしていく。
独立と孤独は似て非なるもの
司法書士として独立したとき、「一人で食っていく」という強い気持ちがあった。けれど、一人でやっていくということは、すべての責任を背負い、すべての重さを受け止めることだった。自由と孤独は背中合わせだと今さらながら思う。
事務所では誰かがいても「ただの職場」
事務員の女性がひとりいるけれど、仕事の話以上のことは話さないようにしている。話してはいけない、というより、話せないのだ。こちらが少し気を抜けば、妙な距離感になってしまいそうで怖い。だから常に「先生」として、平静を装っている。結果、事務所でもどこか孤独を感じてしまう。
事務員との距離感と気遣い
彼女はとても真面目で、仕事も丁寧だ。けれどその分、ミスに対しても敏感で、自分が怒ることで彼女を傷つけるんじゃないかと心配してしまう。だからつい、怒ることも言うべきことも飲み込んでしまう。その優しさが自分の首を絞めている。
愚痴すら言いにくい相手
例えば今日、依頼者が無理難題をふっかけてきたとしても、彼女の前ではそれを言えない。「感じ悪い人だなぁ」くらいは言えるけど、本音は見せられない。見せたところで、彼女はうまくリアクションできないだろうし、それを見てまた自分が傷つく。だったら最初から言わない。そんな関係だ。
怒れない性格が疲れを増幅させる
本当はもっと、厳しくしてもいいのかもしれない。でも、怒った後の空気が苦手だ。野球部時代の上下関係の厳しさが、今になってトラウマみたいに残っているのかもしれない。だから余計に、黙って自分の中で処理する癖が抜けない。
帰宅後の夜に襲ってくる虚無
一日の業務を終え、家に帰ってきた瞬間、ほっとするどころか、むしろ寂しさに襲われる。特に何かあったわけじゃないのに、虚しさだけがジワジワと広がる。やることがないわけでもない。けれど、誰かと共有できる出来事がないという事実が、心を空にしていく。
食事は義務でしかない
夕飯は大体コンビニで買ってくる。仕事帰りのスーパーは疲れるし、自炊する気力もない。食べたいものも特にない。ただ空腹だから食べる。生きるための作業。味なんて正直、どうでもいい。唯一、ビールだけが味覚としての楽しみかもしれない。
コンビニ弁当とビールの定番化
最初は手抜きのつもりだった。でも、今やそれがスタンダードになってしまった。冷蔵庫には缶ビールと漬物。温めた弁当を机に置いて、一人で黙々と食べる。テレビを流しながら、誰とも話さずに箸を動かすだけの時間。それでも、誰かと一緒に食べるより気楽だと思ってしまう自分がいる。
自炊へのやる気は3日で消えた
一時期、健康を意識して自炊を始めたことがある。けれど、仕事終わりの疲れた頭で献立を考え、材料を買い、作り、片づける。それがどれほど大変なことかを思い知らされた。3日で冷蔵庫の中身が腐り始め、俺のやる気も同時に腐った。
それでも続けている理由
こんな生活をしていても、司法書士の仕事は嫌いじゃない。いや、正直に言えば「嫌いになれない」が正しい。時に辛く、報われないこともあるけれど、ふとした瞬間に「ああ、やっててよかった」と思えることがある。その瞬間が、次の日を生きる力になる。
誰かの役に立っているという実感
相続登記が完了したときに「助かりました」と深々と頭を下げられると、心の奥がじんわりと温かくなる。そのために働いてるんだな、と感じる。大げさだけど、誰かの人生の一部に関われるのはこの仕事の特権だと思う。
感謝の言葉が唯一の救い
「ありがとう」って言われると、それだけで一日分の疲れが少し軽くなる。報酬以上に、その言葉が自分の支えになっている。だからこそ、どれだけ孤独でもやめられない。誰にも「おかえり」と言われなくても、「ありがとう」さえあれば、もう少しだけ頑張れる気がする。
自己肯定感をつなぎとめる依頼者の笑顔
普段は無表情で事務的な依頼者が、最後に笑って「助かりました」と言ってくれると、こちらもつられて笑ってしまう。その一瞬の表情に、全てが報われる気がする。何のために働いているのか、自分でもわからなくなるときがあるけれど、たぶん、その笑顔を見るためなんだろう。
司法書士という仕事がくれる誇り
人に胸を張って「司法書士です」と言えるのは、ありがたいことだと思う。世の中に必要とされている仕事。地味だけど、確かに社会を支えている仕事。その誇りが、誰もいない部屋に帰る寂しさを、少しだけ軽くしてくれる。
数字に表れない達成感
この仕事は、数字では評価されにくい。でも、自分の中での「やりきった感」は確かにある。書類一つを丁寧に仕上げたときの満足感。それを誰にも伝えられないのがもどかしいけれど、自分だけが知っていればいいとも思っている。
「辞めたい」と「でも続けたい」の間
何度も「もう無理だ」と思った。でも、「もう一人でも自分を必要としてくれるなら」と思い直す。きっとこれからも、この矛盾した気持ちを抱えながら続けていくんだろう。誰も迎えてくれない家に帰っても、「今日も誰かのために働いた」と思えるなら、それだけで十分だ。