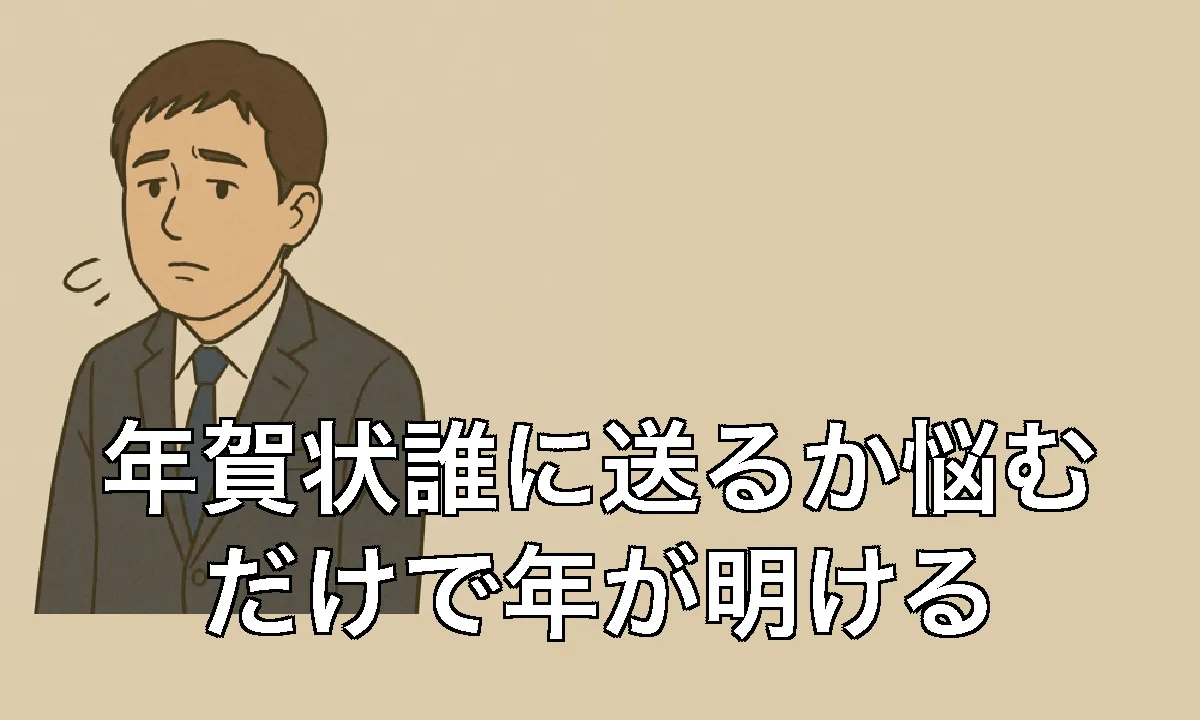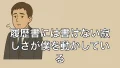年賀状の宛先が思い浮かばない年末の夜
毎年12月に入ると、書類の山に埋もれながらふと「あ、年賀状そろそろだな」と思い出す。昔は住所録を見ながら、思い出のある人に一言添えていたけれど、今では誰に送るべきかで手が止まる。なにより、宛先を見返すたびに「この人まだ住所同じだっけ?」「最近会ってないな…」と余計なことばかり浮かんでしまう。結局そのまま年越しまで持ち越してしまうのがここ数年の恒例行事になってしまった。
昔はたくさん書いていたという記憶だけが残る
若いころは、事務所を開業したばかりということもあって、それこそ毎年100枚近く書いていた。業者のテンプレートを使いつつ、ひとこと添えることには意味があると思っていた。でも、それから20年近く経って、自分から関係を築いていたはずの人たちが、自然と離れていっていることに気づく。実際、連絡を取っていない人に年賀状だけ送るのも、どこか空々しく感じてしまうのだ。
出す人が減っていくのは自然なことなのか
一度関係が途切れると、戻すのが難しい。年賀状はその関係の名残のようなもので、「去年出したし今年も出さなきゃ」と惰性で出していた相手も、ふとしたきっかけでやめてしまうと、それっきりになる。最初は後ろめたさがあるけど、それも時が経つと薄れていく。だからこそ、毎年書いていた人が減っていくのも、「そういうもんか」と自分に言い聞かせてしまう。
続ける意味を考えたら手が止まった
正直に言えば、今年こそはやめようかとも思った。でも、それってただ面倒だから?いや違う、誰かとの繋がりが本当に希薄になっていることを突きつけられるのが怖いのだ。毎年年賀状を書いていたあの人、この人に、もう出す理由が見つからない。続けることが義務になり、心が込められないものになってしまったら、それはもう意味を持たない気がする。
「誰に出すべきか」で悩むだけで疲れる
名簿を前にして、「この人にだけ出さないのは感じ悪いかな」とか「いや、去年向こうから来てなかったし…」と自問自答が始まる。こうなると、年賀状を書くという行為が純粋な感謝の表現ではなく、「誰を外すか」という消去法の選別作業になってしまう。そんな自分にも嫌気が差してきて、気づけば封筒も筆ペンも取り出さずじまいになる。
関係が薄れた相手に気を遣いすぎてしまう
「3年くらい前に仕事を一緒にしただけの人」「開業当初に世話になっただけの人」──そんな微妙な距離感の相手が一番厄介だ。出さなければ礼を欠くように思えるし、出せば出したで「今さら?」と思われるかもしれない。自意識過剰とわかっていても、年賀状には妙な「気を遣いすぎる空気」がある。関係をつなぐはずのツールが、逆に壁になっている。
出さないことで失礼になるのが怖い
年賀状を出さない年に限って、相手から届いたりする。そうなると「しまった」と思うし、気まずさがしばらく尾を引く。とっさに返事を書くか、翌年また送るか…どちらにしても、遅れを取り戻すのは難しい。しかもこちらは一方的に「やめる」判断をしたわけで、そう考えると、自分勝手なようにも思えてくる。そうしてまた宛名リストを見て、悩みが再発する。
書かない理由を正当化して年越しする
もう何年も「今年こそちゃんと出そう」と思って12月を迎え、結局31日に「まぁいっか」と諦める。そのたびに、「年賀状文化ももう時代遅れだし」「どうせ誰も気にしてない」などと自分に言い訳する。だけど、そういう理由を並べながら、内心ではちょっとだけ罪悪感を覚えているのが本音だ。
どうせ相手も忘れていると思い込みたい
出さなかった相手がこちらをどう思っているかなんて、確かめようがない。だから「たぶん向こうももう出してないよな」と、都合よく解釈して自分を納得させている。でも、そんな風にして人付き合いがフェードアウトしていくことに、どこかで寂しさを感じている。気にしないふりをしているだけで、気にしているのだ。
「出さなかったらどう思われるか」の無限ループ
一人一人について「この人は気にするだろうか」「いや、こっちは多分大丈夫」と頭の中で裁判のように判断を下していく。そんな作業を年末の忙しい合間にしている自分に、なんとも言えない虚しさを感じる。思い切って全員に出すか、全員に出さないか、その方がラクなのに、結局どっちつかずになってしまうのが毎年のパターンだ。
結局SNSの年始投稿で済ませてしまう
そんな中、最終的には「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」とだけSNSに書いておしまいになる。「これで十分でしょ」と自分に言い聞かせるが、毎年元旦の夜になると、ふと「このままでいいのかな」と感じる瞬間がある。手書きの一言が持つ温かさには、SNSの一文では届かない何かがある。
自分が年賀状をもらう立場になったときの戸惑い
出していないのに届く年賀状は、ありがたい反面、プレッシャーでもある。「うわ、今年もこの人から来た…」と嬉しさよりも焦りが先に立つ。それだけでなく、「自分はもうこの人のリストから外されてるだろうな」と思いながら待ってしまう自分にも、ちょっと情けなさを感じる。
気まずさとありがたさが同時に押し寄せる
もらえば嬉しい。でも、返していないという事実が、その喜びに陰を落とす。毎年同じ人から届く年賀状に対して、自分は何もしていない。相手の律儀さに頭が下がると同時に、自分のずぼらさにちょっと落ち込む。感謝と後悔と気まずさが、元旦から入り混じる。
書き忘れた相手から届く年賀状の破壊力
去年までは送っていたのに、うっかりリストから外してしまった人から届いた年賀状ほど気まずいものはない。「あぁ、やってしまった…」と心の中で土下座するしかない。すぐ返しても遅いし、返さなければ無礼が残る。何を書いても言い訳がましくなるから、筆が進まず、そのまま箱に入れて忘れたふりをする。
後出しで返す勇気も出ないまま保管箱行き
年明けに「返そうかな」と思って一度ははがきを手に取る。でも、「今さら?」と思われそうで書けない。そのまま2月、3月と月日は流れ、結局未返信の年賀状は保管箱の底に眠ることになる。返事を出さなかった罪悪感だけが、自分の中に積み上がっていく。
年賀状文化と人付き合いの距離感
年賀状という存在が、昔よりずっと重く感じるようになったのは、たぶん自分自身の人間関係の変化とリンクしている。つながりを確認する手段だったものが、今では関係性の薄さを浮き彫りにする鏡のようになってしまった。
手紙を書く行為に込める気持ちが昔とは違う
昔は、書くことに意味があった。紙を選び、ペンを取り、一言に思いを込める時間に価値があった。今は、効率が求められる時代。年賀状でなくてもつながれる手段がある。だからこそ、年賀状が持つ「時間をかけた証」の重さに、気持ちが追いつかないのかもしれない。
無理に続けるものでもないと頭ではわかっている
「もう出さなくていいや」と思う自分と、「やっぱり出した方がいいかな」と思う自分が毎年頭の中で争う。でもそれも、年賀状にこだわる時代が終わりつつあることへの寂しさなのかもしれない。合理的な判断をしても、心が納得しない。
でもやめたときに自分の孤独が見える気がする
年賀状を出さないと、ポストに何も届かない。誰からも来ない正月の朝は、思った以上に静かで寂しい。年賀状は、自分が誰かとつながっている証のようなものだった。やめることは、つながりがないことを自分で受け入れること。それが、年賀状を出すかどうか以上に、重たい選択なのかもしれない。