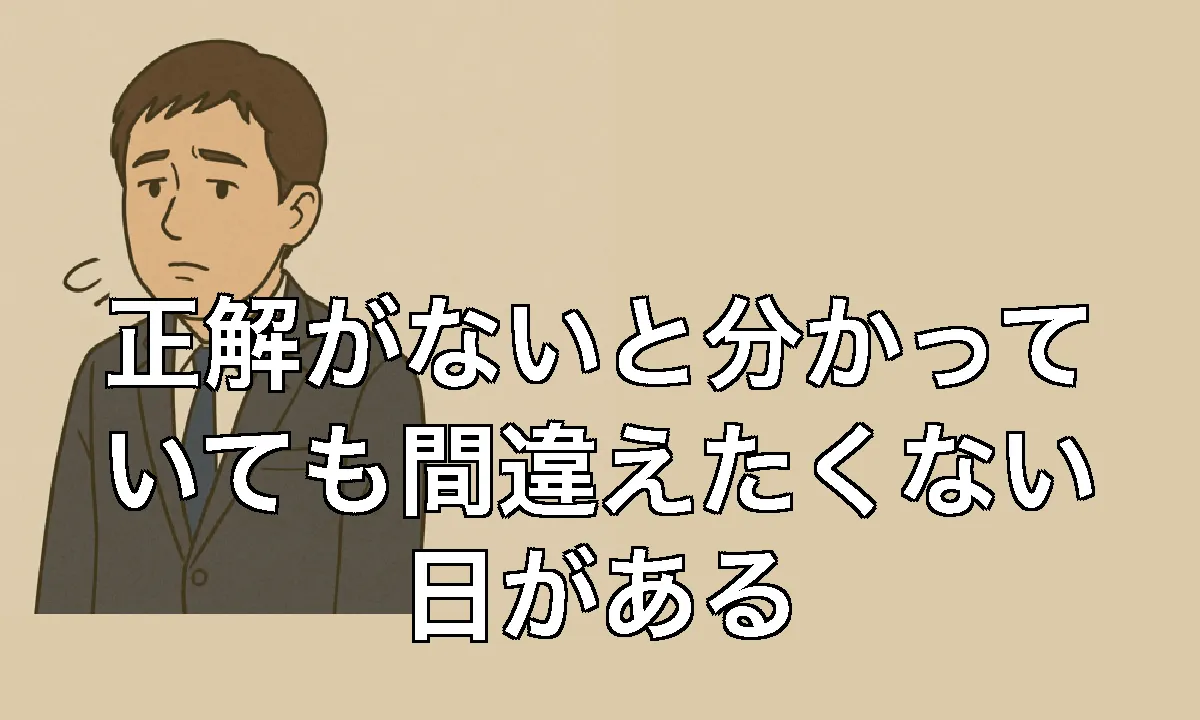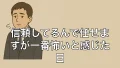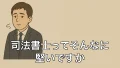正解を求めすぎて疲れてしまう日常
司法書士の仕事は、正解があってないような場面が多々あります。法律や手続きの正確さが求められる一方で、現実の現場では常にグレーゾーンがつきまといます。誰かにとっての「最善」が、別の誰かには「不満」となる。そんな相反する要素に挟まれながら、日々の判断を積み重ねていくうちに、正解を求めること自体が苦しくなってくる瞬間があります。
判断を求められる重圧に押しつぶされそうになる
たとえば、相続登記の相談で、遺産分割協議の内容があいまいなとき。依頼者は「先生が大丈夫って言ってくれたら安心なんですけど」と言う。いや、それが一番怖いんですよ。判断を任されるたび、間違えたらどうしようという思いがよぎる。自分の経験や勘に頼るしかない場面で、自信を持てることの方が稀です。
相談されることが増えるほど怖くなる
昔は、相談されること自体が嬉しかった。頼られている実感があったから。でも今は違う。増えれば増えるほど、失敗する可能性も増える。ある日、登記の内容に対して「こうじゃなかったのか」と言われたことがありました。それ以来、頼られるほどに責任の重さがのしかかるようになりました。うっかりでも許されない立場って、案外しんどい。
一度の判断ミスが信頼を壊すと知っているから
信頼は一瞬で壊れます。10年積み上げても、1回の誤りで台無し。私は一度だけ、軽微とはいえ登記漏れを出したことがあります。そのときの「がっかりした顔」は今でも忘れられません。補正をしても謝っても、相手の心は戻らないこともある。だからこそ、正解がないと分かっていても、間違えたくないのです。
それでも誰も正解を教えてくれない現実
困ったとき、法務局に聞いても曖昧な答えしか返ってこないことがあります。「解釈による」「登記官の判断次第」…それじゃ判断材料にならない。結局、自分で考えるしかない。でもその“考える”が正解かは誰にもわからない。ひとつの登記が、こんなに孤独で、苦しいものになるなんて、若いころは思いもしませんでした。
自分の中の基準すら信じられなくなるとき
長くこの仕事をしていると、「これまでこうやってきた」が通用しない瞬間が訪れます。新しい法改正や、判例、担当官の交代で、一気に“当たり前”が変わる。自分の中にある判断基準が、ぐらりと揺れるような感覚に陥ることもあるのです。
常識も法令も通じない現場のリアル
「条文ではこう書いてあるのに、現場では通らない」なんてことが、司法書士の世界では珍しくありません。ある建物表題変更の案件で、法的には不要な添付書類を「一応出してください」と言われたことがあります。「一応」って何?と思いつつ、結局出しました。ルール通りでは通らない、そんな理不尽が日常です。
過去の成功体験が通用しない瞬間
「前もこれで通ったのに、なぜ今回はダメなんだ?」というケース、ありませんか?私は一度、同じ市内の似たような案件で、登記官から真逆の指摘をされたことがありました。「今回は状況が違いますから」とのこと。でも何が違うのか明確には教えてくれない。そんなとき、過去の経験が足かせになることもあります。
判断の後に残るのは自責と疑念だけ
判断を下したあとの静けさが、時に一番こたえます。誰にも相談できず、自分の判断を信じるしかない。そして後になって「あのとき、別の選択肢もあったのでは」と自問が始まる。完了してホッとしたはずなのに、ふと夜中に目が覚めてしまう。そんな夜、いったい何度過ごしたかわかりません。
正解がない仕事に向き合い続けるということ
それでも、この仕事を辞めなかったのは、たぶん「誰かのため」になっているという実感が、どこかにあるからです。正解がないからこそ、やりがいもまたある。苦しいときほど、それを忘れずにいたいのです。
誰にも褒められず誰にも理解されない役回り
司法書士の仕事って、華やかさがないんです。成果も見えにくいし、依頼者も「無事に終わって当然」くらいに思っている。でも実は、その「無事に終わった」裏には、何重にもわたる確認と配慮が詰まっている。誰にも気づかれない地味な努力が積み重なっている。それがちょっと寂しく感じる瞬間も、正直あります。
感謝よりも文句が先に返ってくる現実
「思ったより時間がかかるんですね」とか、「これだけで費用がかかるんですか?」とか。感謝よりもまず疑問や不満が出てくることが多い。でも、誰かがやらなきゃ進まないのがこの仕事。文句を聞きながらも、淡々と手続きを進める日々。時々、自分は便利屋なのかなと思ってしまうこともあります。
これでよかったんでしょうかと聞かれたら終わり
「先生、これでよかったんでしょうか」──この言葉を聞くたび、心が揺れます。「大丈夫ですよ」としか言えないけど、本当にそうかは、正直わからないこともある。自信のなさを隠して笑って答えるしかない自分に、ふと情けなさを感じてしまうこともあるのです。
成果よりも何も起こらなかったを目指す矛盾
「成果」とは言いにくい世界です。トラブルが起きなかったことが成果。でも、それは誰にも見えない。何も起こらなかったから評価されない。そんな矛盾の中で、「問題が起きなかったこと」に誇りを持てるかどうか。それがこの仕事を続けるうえでの、自分との静かな闘いです。
結局自分で自分を納得させるしかない
最終的に、評価してくれるのは誰でもない。自分自身なんですよね。寝る前に「今日も無事に終わったな」と思えるかどうか。それだけが、私の中での小さな救いです。誰にも見えない孤独な努力に、ささやかでも意味があると信じたいのです。
他人の評価よりも自己基準を育てる努力
人の目ばかり気にしていたら、やっていけません。自分なりの判断基準を持ち、それを信じる努力を続ける。それができるようになって、ようやく少し気持ちが楽になってきました。「先生の判断なら間違いない」と言ってもらえることも、たまにあります。それが今の私の支えです。
判断のあとで眠れない夜に何を考えるか
あれでよかったのか、他に道はなかったか。そんなことばかり考えて眠れない夜、つい天井を見つめながら「誰か正解を教えてくれ」と心の中で叫んでしまうことがあります。でも答えはどこにもない。だからまた次の日も、自分なりの正解を探して机に向かうしかないのです。
それでも誰かのためと思えるかどうか
仕事をしていて一番救われるのは、依頼者がふと見せる笑顔です。何も言わなくても、「助かりましたよ」と目で伝えてくれるような瞬間。それがあるから、また頑張ろうと思える。正解はないかもしれないけれど、「あなたに頼んでよかった」と思ってもらえるなら、それが私の中の“正解”なんだと、そう信じたいです。