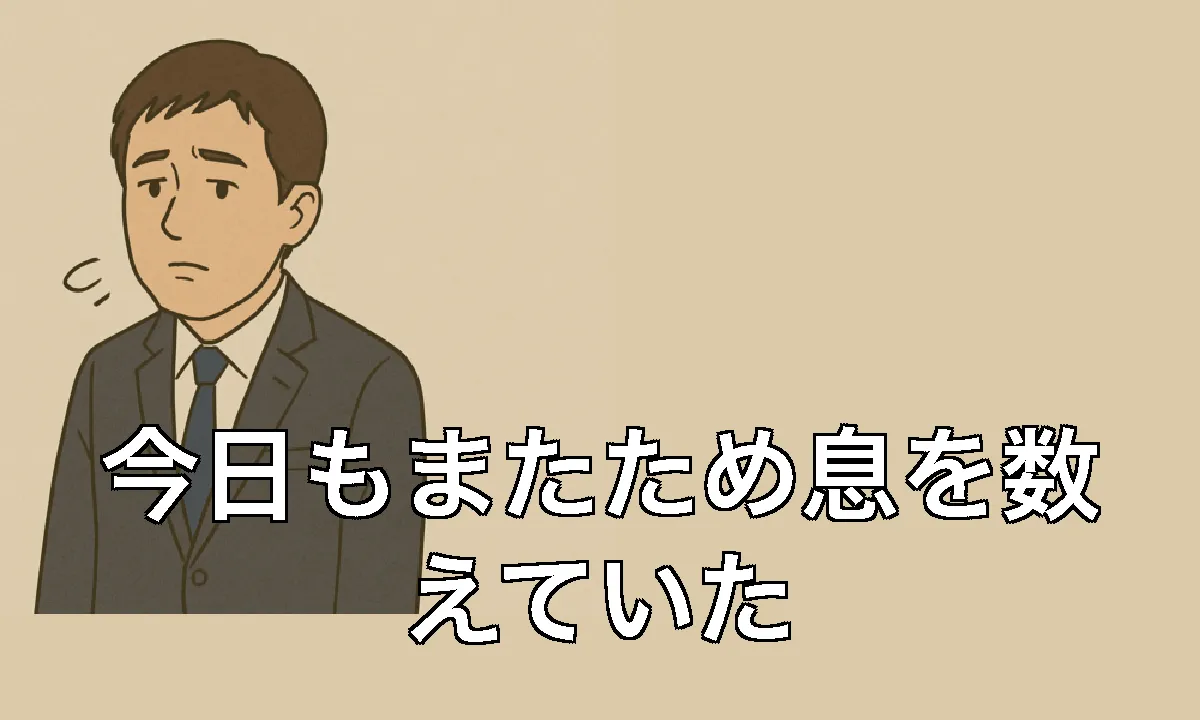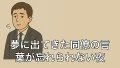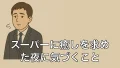気づけば深いため息ばかりついていた日々
朝、机に向かう。パソコンを立ち上げて、メールを開く。その瞬間、無意識のうちに「はあ」と息が漏れていた。最初はただの疲れだと思っていた。でも、ふとした瞬間、日に何度もため息をついていることに気づいたとき、少し怖くなった。ため息というのは、感情が表に出るもっとも簡単なサインかもしれない。何かがうまくいかない、何かが重たい。そんな時、言葉にできない分、体が代わりに訴えてくるような気がした。
ため息が出るのは甘えなのか
学生時代、野球部では「気合いが足りないからため息が出るんだ」と先輩に言われた記憶がある。それ以来、ため息はネガティブなもの、弱さの象徴として刷り込まれていた。だから社会人になっても、つい「こんなことでため息なんかついてちゃダメだ」と自分を責める癖が抜けない。でも本当にそうだろうか? 心が張り詰めているとき、ふと漏れ出すため息。それは体が限界に近づいているサインかもしれない。
「弱音を吐かない」は美徳じゃない
司法書士という仕事柄、相談者の前ではいつも冷静でなければならない。感情的になるわけにはいかない。だけど、そんな「役割」にばかり自分を合わせていたら、肝心の自分の気持ちが置き去りになる。弱音を吐くことが悪いことではないと頭ではわかっていても、なかなかそれができない。「プロである以上、常に強くあれ」と自分に言い聞かせてきた。でも、気づけばその強がりが自分の首を締めていた。
自分で自分を追い込んでいたかもしれない
誰にも頼らず、なんでも自分で抱え込む癖がある。気づけば「自分がやらなきゃ」と思い込んで、仕事も感情も全部一人で処理しようとしていた。ため息が増えたのは、単に忙しさのせいじゃない。無意識のうちに自分に課していた期待やプレッシャー。それが積もりに積もって、ため息という形で漏れ出していたのかもしれない。もっと自分に優しくしても良かったのだ。
職場にこもる重たい空気の正体
事務所の空気が重たいと感じる日がある。それは誰かが機嫌が悪いというより、全体に静かすぎるからだ。静かに事務員が書類を処理し、私は黙々と登記の入力を進める。その沈黙の中で、自分のため息だけが妙に響くことがある。周囲に気を遣って音を立てないようにしても、内側から出る空気は抑えきれない。そういう日は、仕事が進んでいてもどこか気持ちが停滞している。
事務員の前では明るく振る舞う癖
うちの事務員はまじめでよく働いてくれる。そんな彼女の前で、私が不機嫌な顔をするわけにはいかない。無意識に「明るい上司」を演じている自分がいる。でも、そんな演技も毎日となると疲れる。もちろん職場の雰囲気を悪くしたくないという気持ちもあるが、それ以上に、自分自身が本音を出せる場所をなくしているのかもしれない。ため息が漏れるのは、仮面を外したいという心の声だ。
「いい上司」でいようとして疲れていた
「先生はいつも元気ですね」と言われたとき、思わず苦笑いした。実際は、机の下で足を組んで、ぐったりしているのに。「いい上司」でいることと、自分の気持ちを守ること。両立できていないことに気づいた。ため息は、それに気づくきっかけだったのかもしれない。もっと自分のコンディションに正直になって、無理をしないことも、事務所全体のためになるのではないかと思う。
そもそも何がそんなにしんどいのか
「なんでこんなに疲れてるんだろう」と自分でも不思議になる時がある。特に忙しいわけじゃない日でも、息が重たい。ふと思い返すと、疲れの正体は仕事量ではなく、気の張り詰めた状態がずっと続いていることかもしれない。周囲には「順調そうだね」と言われるけど、心の中はぐちゃぐちゃ。そんなギャップに、自分でもついていけなくなっていた。
依頼が多いのはありがたい だけど
事務所を経営している以上、依頼が多いのはありがたいことだ。それは間違いない。でも、それに比例して「責任」も「判断」も増えてくる。ひとつの登記でさえ、細かいチェックを怠ると大ごとになる。特に相続関係の案件では、遺族の思いも絡んでくるから、精神的にも気を張り詰めて対応しなければならない。ありがたさと同時に、じわじわと心が摩耗していく。
やるべきことは増えるのに報われた気がしない
ひとつ片付けば、またひとつ新しい案件が入ってくる。悪い流れではないが、達成感を味わう暇がないのが現実だ。毎日書類に追われ、気づけば夜。報酬が入るのは嬉しい。でも心はどこか空っぽだった。ため息が出るのは、その空虚さに気づいている証拠かもしれない。「頑張ってるのに報われてない気がする」という感情が、ため息になっていた。
書類と独り言だけが増えていく日常
最近、やたらと独り言が増えた。「あれ、どこやったっけ」「これは…先に出さないとな」そんな言葉が、事務所の静寂の中に響く。誰かに聞いてもらいたいというより、自分の気持ちを確認するための言葉。書類が積み上がるたび、言葉もため息も増えていく。そんな日々に、ふと「このままでいいのか」と立ち止まってしまうのだ。
心を落ち着けるための小さな習慣
ため息をつく自分を責めるのではなく、まず受け入れること。それが今の自分のスタート地点だった。疲れてる自分を許すこと、がんばりすぎないこと、無理に笑わないこと。それだけでも、少しずつ気持ちは変わってきた。毎日は変えられなくても、呼吸の仕方ひとつで気持ちは軽くなる。それに気づいたのは、皮肉にも「ため息」のおかげだった。
ため息が出そうなときに試すこと
無理に「頑張ろう」と思わず、まずは窓を開けて外の空気を吸う。スマホを置いて、5分だけ目を閉じる。近くのコンビニまで歩いてコーヒーを買う。それだけでも、心が少しリセットされる。ため息が出るのは悪いことじゃない。でも、それに気づいたら「少し自分に休憩を」とサインを出すことにしている。自分を責めるより、自分を休ませる選択を大切にしたい。
「誰かと比べない」ことの難しさ
SNSを見ては「同業者はもっと立派にやってる」と落ち込むこともある。でも、比べたところで、自分の疲れが癒えるわけじゃない。自分のペース、自分のやり方。それを信じることのほうがずっと大切だった。ため息をついたとき、「それでもいい」と思えるようになってから、少しだけ気持ちが楽になった。他人の物差しではなく、自分の心の声に耳を傾けるようになった。
元野球部が教えてくれたリセットの方法
高校時代の野球部で、試合前に必ず深呼吸をしていた。大きく吸って、大きく吐く。今思えば、あれも「いいため息」だったのかもしれない。緊張をほぐす、心を落ち着ける、そんな儀式のような呼吸。今も、気持ちが落ち込んだときはグラウンドの風を思い出して、あの深呼吸をするようにしている。ため息も使い方次第で、リスタートの合図になる。