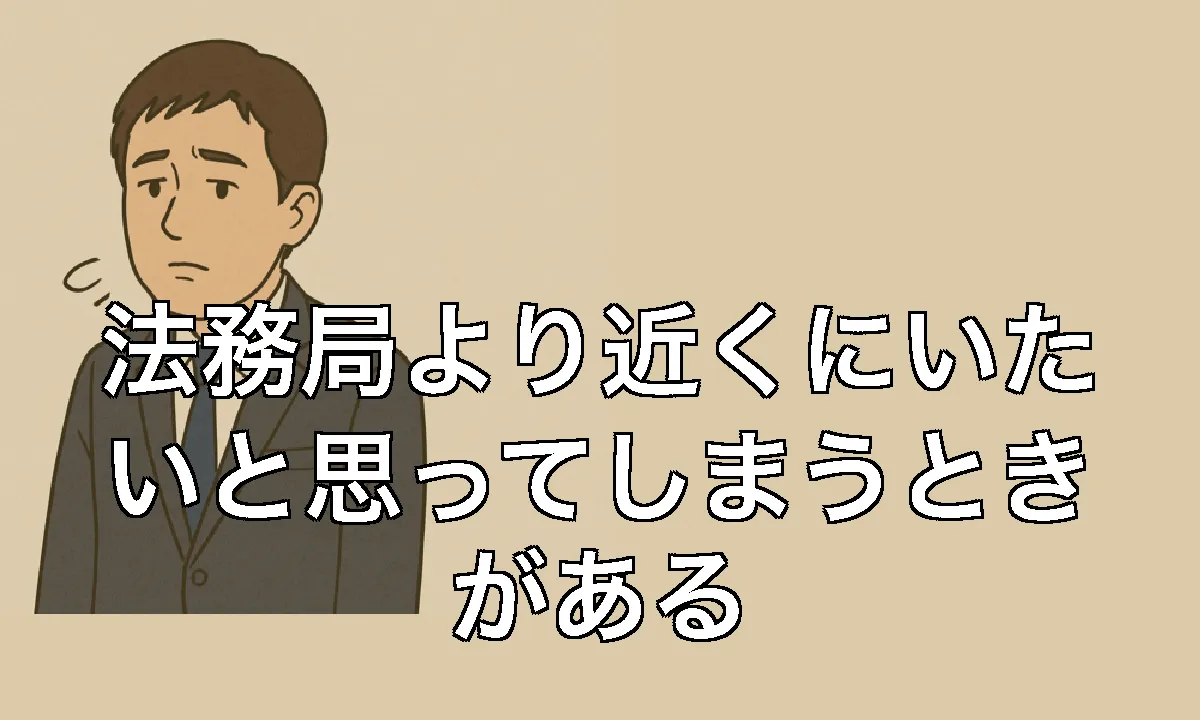法務局より近くにいたいと思ってしまうときがある
書類の山に埋もれて見失うもの
朝から晩まで書類と向き合っていると、ふと「自分は何をしているんだろう」と思うことがあります。登記識別情報の交付申請、不動産の売買、相続関係説明図……どれも大切な業務です。でも、毎日処理していると、目の前の人の顔や気持ちがどんどん霞んでいくような感覚になることがあるんです。自分の仕事が機械的になっていくことへの違和感。その違和感が、時々胸を締めつけます。
処理の正確さばかりが評価される毎日
この仕事、間違いが許されないのは当然です。だからこそ一つひとつの確認作業に神経を尖らせます。でも、誰も「よくやってるね」とは言ってくれません。ミスがなければ当たり前、あれば責任。評価の基準が「失敗しないこと」だけだと、心が乾いていきます。努力は透明で、存在が空気のようになっていく。そんな日々の中で、自分の存在価値が見えなくなる瞬間もあるんです。
褒められるよりも「間違えないこと」が当然の空気
「先生、間違ってませんよね?」って確認されることはあっても、「助かりました」と言われることは少ないです。事務所の外でも中でも、司法書士って、基本的に「間違わないことが前提」で扱われます。人として見てもらえるより前に、制度の歯車の一部になってしまっているような気分になります。たまには人間扱いしてほしい、そんなことを思うこともあります。
完璧を求められるけれど誰も寄り添ってはくれない
法務局に書類を提出したとき、ちょっとした不備を指摘されることがあります。そのたびに胃がキュッと締まります。もちろんこちらの責任。でも、その指摘の仕方がどうしても「人」として接してくれていない気がしてしまう。機械的な対応に心がすり減る一方で、こちらは「人」として関わろうとしている。その落差に、ぽつんと独りぼっちになったような気持ちになります。
法務局との関係は必要だけど冷たい
法務局とは、司法書士にとって切っても切れない関係です。登記が成立するのも、補正が必要な案件が処理されるのも、すべては法務局あってのこと。ただ、やっぱり「壁」は感じます。必要以上に話すこともなく、丁寧だけれど事務的なやりとり。その関係性に、ふと虚しさを覚えることもあります。もっと近くに寄れたら、もっと人間らしくなれるのに、と思ってしまうのです。
制度と向き合う中で感じる「人との距離」
制度は公平であるべきだし、誰に対しても同じ対応をする必要があります。それは理解しています。けれど、相手が困っていることを察しても、制度の枠に縛られて対応できない——そんな場面が多々あると、「人として何ができるのか」を自問せずにはいられません。書類の世界は正しい。でも、心の温度がないと、ただの記号処理のように感じてしまうんです。
受付の向こうにある無言の圧
窓口に書類を提出する際、黙って印鑑を押されるだけの日もあります。言葉は丁寧でも、表情は無機質。その空気感が、たまに自分の存在を否定されているように感じることがあります。「そんなつもりはない」ってわかっていても、孤独に戦っている身には少し堪えるんです。ほんの一言、「お疲れさまです」とか言ってもらえたら、それだけで救われる気がするのに。
質問することすら気を使ってしまう毎日
法務局に電話をかけるときも、すごく緊張します。「こんなこと聞いたら嫌がられるかな」って毎回心配してしまう。でも、業務上どうしても確認しないといけないこともある。それなのに、「またこの人か」と思われるんじゃないか、と気を張る。そんな小さなストレスが積もって、気づけば週末にドッと疲れが来るんです。これも「司法書士あるある」なんでしょうかね。
もう少しだけ温度のある関係を
自分がこの仕事を選んだのは、制度を扱いたかったからではなく、困っている人の力になりたかったからです。法律の専門家としてではなく、生活に寄り添える存在としてありたい。けれど現実は、制度の枠をはみ出すことが許されない。だからこそ、その「はざま」でできることを探し続けています。書類の裏にある人生のドラマ、それに耳を傾けることが、せめてもの温度です。
「困ってる人」に寄り添いたい気持ちはある
あるとき、相続の相談に来た高齢の女性がいました。手続きの話を始める前に、彼女は「息子が亡くなった時の話、聞いてくれる?」と静かに言いました。法律の話じゃない。でも、そういう話にこそ意味があると思うんです。全部聞いてあげたら、「司法書士さんって、もっと冷たい人かと思ってた」って笑ってくれた。こういう一言のために、頑張れる気がするんです。
目の前の人が「安心した表情」になる瞬間が嬉しい
お金や財産の話は、誰にとってもセンシティブなものです。だからこそ、安心して話せる空気を作ることが一番大事だと思っています。「大丈夫ですよ」「心配いりません」そう言ってあげるだけで、表情がふっと和らぐ瞬間がある。あれが、自分にとってのご褒美です。法務局の向こう側にはない、人との距離感。それがこの仕事の一番のやりがいかもしれません。
登記のことより、暮らしの悩みを語られることも
気がつけば「お隣さんと揉めててね」とか、「息子が帰ってこない」とか、法律とは関係ない話をされることも増えました。最初は戸惑っていたけれど、今はそういう話が一番心に残ります。専門家としてではなく、ただの「話を聞いてくれる人」としてそこにいること。それって、法務局にはできないことなんです。だからこそ、自分の存在意義を感じられるんですよね。