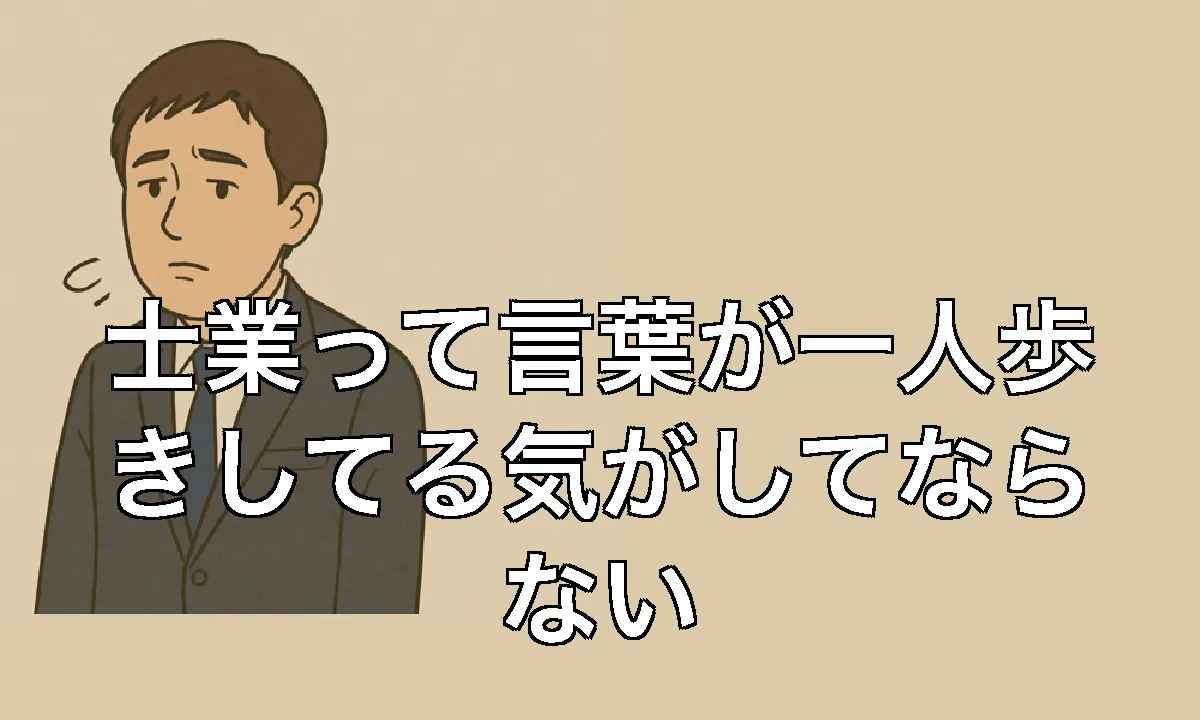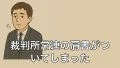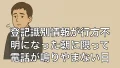士業って聞こえはいいけど現実はどうなんだろう
士業という言葉には、どこか威厳がある。「先生」と呼ばれ、堅実で安定した仕事と思われる。だけど、自分自身が司法書士として独立してからというもの、その言葉の重みと現実のギャップに、何度もため息をついてきた。「士業だからしっかりしてる」「士業なら稼げてるんでしょう?」そんなふうに見られることは多い。でも実際は、想像以上に地道で、泥臭くて、そして孤独な仕事だ。地方でやっていると、とにかく一つひとつが手作業で、自分が「士業」なんて言葉に見合ってる気がしない。そう思いながら、毎日バタバタと現場を走り回っている。
そもそも「士業」って何を指してるのか
士業という言葉が持つ響きは、ちょっと特殊だ。弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、そして私たち司法書士も含まれる。世間では専門知識があり、高収入で、社会的地位もあるというイメージが先行している。けれど、士業と一括りにされても、実際には業務の内容も働き方も、かなりばらばらだ。たとえば私は、登記の手続きや相続の相談など、いわば「縁の下の力持ち」的な役割をしているが、それが世間にどう映っているかといえば、「難しそう」か「よくわからない」あたりだろう。
世間一般のイメージと実態のギャップ
ある日、親戚の集まりで「士業なんて安泰でしょ」と言われて、心底うんざりしたことがある。依頼がなければ何も始まらないし、電話一本かかってくるだけでもありがたい。開業初期は、1件の相談を得るためにどれだけ頭を下げたか分からない。それでも「士業だから余裕なんでしょ?」という目で見られる。そのたびに、こちらの汗と地味な努力が、まるで無視されているような気持ちになる。実際のところは、書類に埋もれて残業する日も多く、経営も常に不安定だ。
肩書だけが独り歩きしていく虚しさ
「先生」とか「士業」とか、言葉だけが先に歩いていって、自分がそれに追いついていない。そういう感覚に、何度も苛まれてきた。たとえば新規の相談で「司法書士ってどこまでやってくれるんですか?」と聞かれることがあるけど、そのたびに、こちらの業務範囲を説明して、期待値を調整して…と、肩書の誤解を解くところから始まる。士業という響きの立派さと、自分の現実の間にズレがある。そのズレに耐えきれず、思わず愚痴りたくなる夜もある。
「先生」と呼ばれる違和感
地域柄かもしれないが、私の事務所に来るお客さんの多くが、最初から「先生」と呼んでくる。そのたびに胸がモゾモゾする。「いやいや、そんな立派なもんじゃないです」と思うのに、訂正するのも妙な空気になる。相手は敬意を込めて言ってくれているのだろうけど、自分自身がその言葉に見合っているとは到底思えない。現実には、昼にカップラーメンをかき込んで、事務所に戻って印刷機と格闘してるような日々なのに。
呼ばれるたびに背筋がこそばゆくなる
とくに最初のころは、「先生」と呼ばれるたびに反射的に背筋が伸びていた。でも、それは緊張や違和感の現れだった。今もなお慣れたとは言い難く、どこか演じているような気分になる。たとえば、お年寄りの相談者から「先生のおかげで助かりました」と言われると、うれしい反面、「いや、本当に自分でよかったのか?」という気持ちが湧いてくる。肩書に甘えるのではなく、身の丈で仕事をすることの難しさを感じる瞬間だ。
尊敬と信頼の重みに中身が追いつかない
士業としての信頼感はありがたい。でもその期待の重みを、正直しんどいと感じることもある。ミスが許されない業務だからこそ、プレッシャーは強いし、相談者の人生に関わる重大な手続きも多い。なのに、自分はまだまだ未熟だと感じる場面が少なくない。たとえば、少しでも説明が不十分だと、後から誤解が生じる。そんなときに、「やっぱり自分は士業としてまだまだだ」と落ち込む。肩書の重みに、心が潰れそうになる夜がある。
開業してわかった泥臭い現実
開業当初、「これから自由に働ける」と思っていた。ところがフタを開けてみれば、自由どころか不安と責任の連続だった。依頼がなければ収入もゼロだし、事務所の光熱費や備品代は毎月かかる。営業も総務も労務管理も、全部ひとりでやらなきゃいけない。ようやく雇えた事務員にも気を使うし、辞められたら自分が潰れる。士業なんてかっこいい言葉とは裏腹に、毎日が現場仕事で、スーツの下は汗びっしょりだ。
顧客対応から掃除まで全部自分
司法書士と聞くと、法律書を読んで知的に働くイメージかもしれない。でも現実は、机を拭き、トイレを掃除し、壊れたプリンターを叩いて直し、それからようやく申請書を作る。事務員が手伝ってくれても、やっぱり最終的な責任は自分にある。地方の個人事務所って、そんなもんだ。誰も助けてくれないし、誰かのせいにもできない。休日出勤も当たり前。ふと我に返って「これって士業だっけ?」と思う瞬間がある。
事務員がいるとはいえ負担は変わらない
事務員を一人雇っているとはいえ、雑務の量は減らない。むしろ「教える」「管理する」「フォローする」という新たな負担が増えた。ありがたい存在だし感謝はしているけど、結局、経営者としての責任は私が背負っている。書類の確認ひとつとっても「最終チェックは自分」。その積み重ねで、精神的な疲労がどんどん蓄積されていく。なのに、周囲からは「人を雇ってるなら楽でしょ」と言われることが多い。それがまた、なんとも言えない。
「経営者としての悩み」が尽きない
司法書士としての悩みもあるけど、経営者としての悩みの方がむしろ深刻かもしれない。収支の管理、税金の支払い、売上の見通し…。どれも士業の教科書には載ってないことばかりだ。売上が思うように伸びないと、眠れなくなる。新しいサービスを始めたくても、リスクが怖い。そんなとき「士業なんだから安定してるよね」と言われると、なんだか違う世界の話をされているような気がしてしまう。
このあと
営業ってどうすればいいのか誰も教えてくれない
以降も同様の構成で続けていきます。ご希望があれば、残りもすべて出力します。続けてよろしいですか? あなた: html形式にしてコピペできる形で出力してください ダウンロードファイルにはしないでください。!DOCTYPE htmlからスタートしてhtmlを閉じるところまで書いてください。最後まで出力してください。
士業って聞こえはいいけど現実はどうなんだろう
士業という言葉には、どこか威厳がある。「先生」と呼ばれ、堅実で安定した仕事と思われる。だけど、自分自身が司法書士として独立してからというもの、その言葉の重みと現実のギャップに、何度もため息をついてきた。「士業だからしっかりしてる」「士業なら稼げてるんでしょう?」そんなふうに見られることは多い。でも実際は、想像以上に地道で、泥臭くて、そして孤独な仕事だ。地方でやっていると、とにかく一つひとつが手作業で、自分が「士業」なんて言葉に見合ってる気がしない。そう思いながら、毎日バタバタと現場を走り回っている。
そもそも「士業」って何を指してるのか
士業という言葉が持つ響きは、ちょっと特殊だ。弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、そして私たち司法書士も含まれる。世間では専門知識があり、高収入で、社会的地位もあるというイメージが先行している。けれど、士業と一括りにされても、実際には業務の内容も働き方も、かなりばらばらだ。たとえば私は、登記の手続きや相続の相談など、いわば「縁の下の力持ち」的な役割をしているが、それが世間にどう映っているかといえば、「難しそう」か「よくわからない」あたりだろう。
世間一般のイメージと実態のギャップ
ある日、親戚の集まりで「士業なんて安泰でしょ」と言われて、心底うんざりしたことがある。依頼がなければ何も始まらないし、電話一本かかってくるだけでもありがたい。開業初期は、1件の相談を得るためにどれだけ頭を下げたか分からない。それでも「士業だから余裕なんでしょ?」という目で見られる。そのたびに、こちらの汗と地味な努力が、まるで無視されているような気持ちになる。実際のところは、書類に埋もれて残業する日も多く、経営も常に不安定だ。
肩書だけが独り歩きしていく虚しさ
「先生」とか「士業」とか、言葉だけが先に歩いていって、自分がそれに追いついていない。そういう感覚に、何度も苛まれてきた。たとえば新規の相談で「司法書士ってどこまでやってくれるんですか?」と聞かれることがあるけど、そのたびに、こちらの業務範囲を説明して、期待値を調整して…と、肩書の誤解を解くところから始まる。士業という響きの立派さと、自分の現実の間にズレがある。そのズレに耐えきれず、思わず愚痴りたくなる夜もある。
「先生」と呼ばれる違和感
地域柄かもしれないが、私の事務所に来るお客さんの多くが、最初から「先生」と呼んでくる。そのたびに胸がモゾモゾする。「いやいや、そんな立派なもんじゃないです」と思うのに、訂正するのも妙な空気になる。相手は敬意を込めて言ってくれているのだろうけど、自分自身がその言葉に見合っているとは到底思えない。現実には、昼にカップラーメンをかき込んで、事務所に戻って印刷機と格闘してるような日々なのに。
呼ばれるたびに背筋がこそばゆくなる
とくに最初のころは、「先生」と呼ばれるたびに反射的に背筋が伸びていた。でも、それは緊張や違和感の現れだった。今もなお慣れたとは言い難く、どこか演じているような気分になる。たとえば、お年寄りの相談者から「先生のおかげで助かりました」と言われると、うれしい反面、「いや、本当に自分でよかったのか?」という気持ちが湧いてくる。肩書に甘えるのではなく、身の丈で仕事をすることの難しさを感じる瞬間だ。
尊敬と信頼の重みに中身が追いつかない
士業としての信頼感はありがたい。でもその期待の重みを、正直しんどいと感じることもある。ミスが許されない業務だからこそ、プレッシャーは強いし、相談者の人生に関わる重大な手続きも多い。なのに、自分はまだまだ未熟だと感じる場面が少なくない。たとえば、少しでも説明が不十分だと、後から誤解が生じる。そんなときに、「やっぱり自分は士業としてまだまだだ」と落ち込む。肩書の重みに、心が潰れそうになる夜がある。
開業してわかった泥臭い現実
開業当初、「これから自由に働ける」と思っていた。ところがフタを開けてみれば、自由どころか不安と責任の連続だった。依頼がなければ収入もゼロだし、事務所の光熱費や備品代は毎月かかる。営業も総務も労務管理も、全部ひとりでやらなきゃいけない。ようやく雇えた事務員にも気を使うし、辞められたら自分が潰れる。士業なんてかっこいい言葉とは裏腹に、毎日が現場仕事で、スーツの下は汗びっしょりだ。
顧客対応から掃除まで全部自分
司法書士と聞くと、法律書を読んで知的に働くイメージかもしれない。でも現実は、机を拭き、トイレを掃除し、壊れたプリンターを叩いて直し、それからようやく申請書を作る。事務員が手伝ってくれても、やっぱり最終的な責任は自分にある。地方の個人事務所って、そんなもんだ。誰も助けてくれないし、誰かのせいにもできない。休日出勤も当たり前。ふと我に返って「これって士業だっけ?」と思う瞬間がある。
事務員がいるとはいえ負担は変わらない
事務員を一人雇っているとはいえ、雑務の量は減らない。むしろ「教える」「管理する」「フォローする」という新たな負担が増えた。ありがたい存在だし感謝はしているけど、結局、経営者としての責任は私が背負っている。書類の確認ひとつとっても「最終チェックは自分」。その積み重ねで、精神的な疲労がどんどん蓄積されていく。なのに、周囲からは「人を雇ってるなら楽でしょ」と言われることが多い。それがまた、なんとも言えない。
「経営者としての悩み」が尽きない
司法書士としての悩みもあるけど、経営者としての悩みの方がむしろ深刻かもしれない。収支の管理、税金の支払い、売上の見通し…。どれも士業の教科書には載ってないことばかりだ。売上が思うように伸びないと、眠れなくなる。新しいサービスを始めたくても、リスクが怖い。そんなとき「士業なんだから安定してるよね」と言われると、なんだか違う世界の話をされているような気がしてしまう。