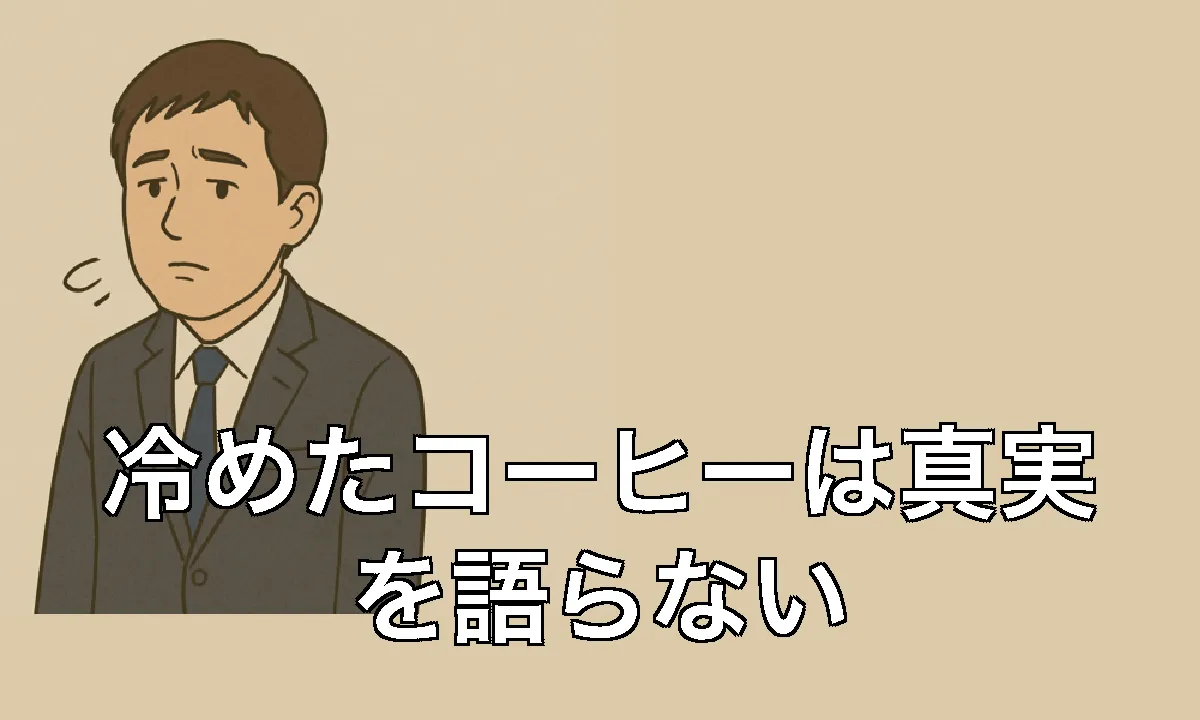朝の珈琲と訪問者
午前九時を少し過ぎた頃、事務所のドアがかすかに軋んだ音を立てて開いた。来客の気配に、僕は慌てて書類を机の下に滑り込ませる。カップのコーヒーからは、まだかすかに湯気が上がっていた。
現れたのは、白髪混じりのスーツ姿の男だった。深く刻まれた眉間のシワが、何か重大なことを背負っていることを物語っている。彼は静かに頭を下げると、席に腰を下ろした。
予定になかった依頼人
「先生、突然でが、亡くなった妻の遺言について相談があります」そう言って彼は一通の封筒を差し出した。表には見慣れた手書き文字。だが、どこか不自然だ。僕は視線をサトウさんに送ると、彼女は無言で頷いた。
「やれやれ、、、またひと波乱ありそうだな」と心の中で呟きつつ、僕は封筒の封を慎重に開けた。
冷めかけたカップの中で
コーヒーに手を伸ばすが、もうすっかり冷えていた。まるで今から語られる話が、冷たく張り詰めたものになることを暗示しているようだった。遺言書の文面を読む僕の指先に、かすかな震えが走る。
「死後、全財産を夫に相続させる」と書かれていた。形式は整っているようだが、内容に引っかかる。なぜならこの女性は、かつて別れた夫に資産を渡さぬよう、僕のもとを訪れていたからだ。
遺言書に滲む違和感
違和感はひとつではなかった。日付が直近すぎること、筆跡が微妙に揺らいでいること、そして何より、その文面にあった「私の愛する夫へ」という書き出しが、どうにも引っかかる。
かつて彼女が使っていたフレーズとは違っていた。彼女は夫のことを一度も「愛する」とは言わなかった。むしろ「金にがめついだけの人」と言っていたのを僕は記憶している。
文面のクセと法的矛盾
「この“へ”の書き方、変ですね」横からサトウさんが、するどい指摘を飛ばす。彼女は遺言書をコピー機にかけながら、原本と手元のスキャンを照らし合わせている。書き出しの文字が、妙に筆圧が弱い。
「たぶんこれ、なぞって書いてます。元の文章にトレーシングペーパーか何かを乗せて」彼女の声に、依頼人の男の顔がわずかにこわばった。僕の中の警鐘が大きく鳴り響く。
誰が手を加えたのか
「この遺言、どこで保管されていたんですか?」僕の問いに、男は目を伏せた。「妻の仏壇の引き出しの中です。鍵はかかっていませんでした」その答えは、むしろ決定打だった。あの彼女が、無防備に遺言を放っておくとは思えない。
サトウさんはすでにスマホで筆跡鑑定の知人に連絡を取っていた。まるで、ルパン三世の次元大介ばりの早撃ちだ。…ただし、銃ではなく法的根拠という弾丸で、だ。
サトウさんの静かな疑問
「奥さんは病院で亡くなったんですよね?だったら、こんな筆跡、病床じゃ書けないですよ」サトウさんがつぶやくように言った言葉が、事務所に重くのしかかる。冷たい事実が、ゆっくりと浮かび上がってくる。
遺言書の作成日、彼女はすでに入院していた。そしてその時期、家に帰る体力などなかったという証言も残っている。つまり、この文書は——。
筆跡鑑定より鋭い観察眼
「この“し”の形もおかしい。病気で手が震えていたはずなのに、むしろ丁寧になってる」机に広げたサンプル文書を並べながら、サトウさんが口にした。鑑定がなくても、矛盾は明らかだった。
僕は昔読んだ名探偵コナンのエピソードを思い出した。被害者のメモに残された「止めた」という字のクセ。あれと同じように、ほんのわずかな文字の乱れが、真相を照らすこともあるのだ。
糖分ゼロの言葉に刺さる真理
「で、どうするんですか?告発します?それとも見逃します?」彼女の言葉は相変わらず冷たい。だけど、その裏にある優しさを僕はもう知っている。言外に「先生がどうするか、見てますよ」と言っているのだ。
僕は椅子にもたれ、冷めたコーヒーをひと口飲んだ。苦い。けれど、その苦味はどこか覚悟を与えてくれる味だった。
彼の嘘と亡き妻の声
「この文書は無効と判断します。あなたには悪いが、正式な手続きは踏んでいない」僕は静かに告げた。男の顔から血の気が引いていくのが分かった。彼の瞳には、ほんの一瞬、罪悪感と安堵が混じったような色が見えた。
もしかすると、彼は遺産が欲しかったのではない。彼女の“愛”が、少しでも残っていることを確認したかっただけなのかもしれない。
語られなかった入院中の面会
「実は、亡くなる数日前に会いました。その時、彼女は何かを言おうとして……泣いていました」男は涙ぐみながら語り出した。その告白が本物かどうか、僕には分からない。だが、その涙だけは、演技には見えなかった。
コナンなら「真実はいつもひとつ」と言うだろう。でも僕たち司法書士にできるのは、法に従い、整合性を照らすことだけだ。
病室で交わされた最後の一言
「あなたに財産を残すつもりはない。でも、私を許して」それが彼女の最後の言葉だったという。ならば、この遺言のねつ造は、彼なりの懺悔だったのかもしれない。
それでも、僕らは事実を歪めてはいけない。苦いコーヒーのような人生の中でも、真実は真実として残さなければならない。
やれやれ、、、コーヒーがぬるい
事件がひと段落し、僕は改めてコーヒーを口にした。もう冷め切っていたが、今度はそれが不思議と心地よい味に思えた。きっと、少しだけ肩の荷が下りたからだろう。
「先生、次は午後の抵当権抹消ありますけど、寝ないでくださいね」サトウさんの塩対応が戻ってきた。なんだかんだで、僕たちの日常もまた、コーヒーのように苦くてあたたかい。
紙の上に残った指紋の主
提出された遺言書からは、彼の指紋しか出なかった。鑑定結果が決定打となったのだ。彼は罪に問われることはなかったが、二度と遺産の話を口にすることもなかった。
静かに去っていったその背中は、どこか吹っ切れたようでもあり、深く後悔しているようでもあった。
思い出されるあの一杯の味
昔、妻を亡くしたばかりの依頼人が、泣きながら飲んでいた缶コーヒーの味を思い出した。人生で最も苦いコーヒーは、いつも誰かを失ったときに味わうものなのかもしれない。
やれやれ、、、僕はまた一つ、依頼人の人生の端っこに触れてしまった。そう思いながら、新しいコーヒーを淹れ直した。
冷めた真実と再加熱できない愛
どんなに後悔しても、過去の言葉や行動は再加熱できない。真実とはそういうものだ。冷めたままでも、それを受け入れる強さが、きっと誰にとっても必要なのだろう。
僕は今日も書類にハンコを押し、コーヒーをすする。そして思うのだ。「さて、次の事件はどこから来るのだろう」と。