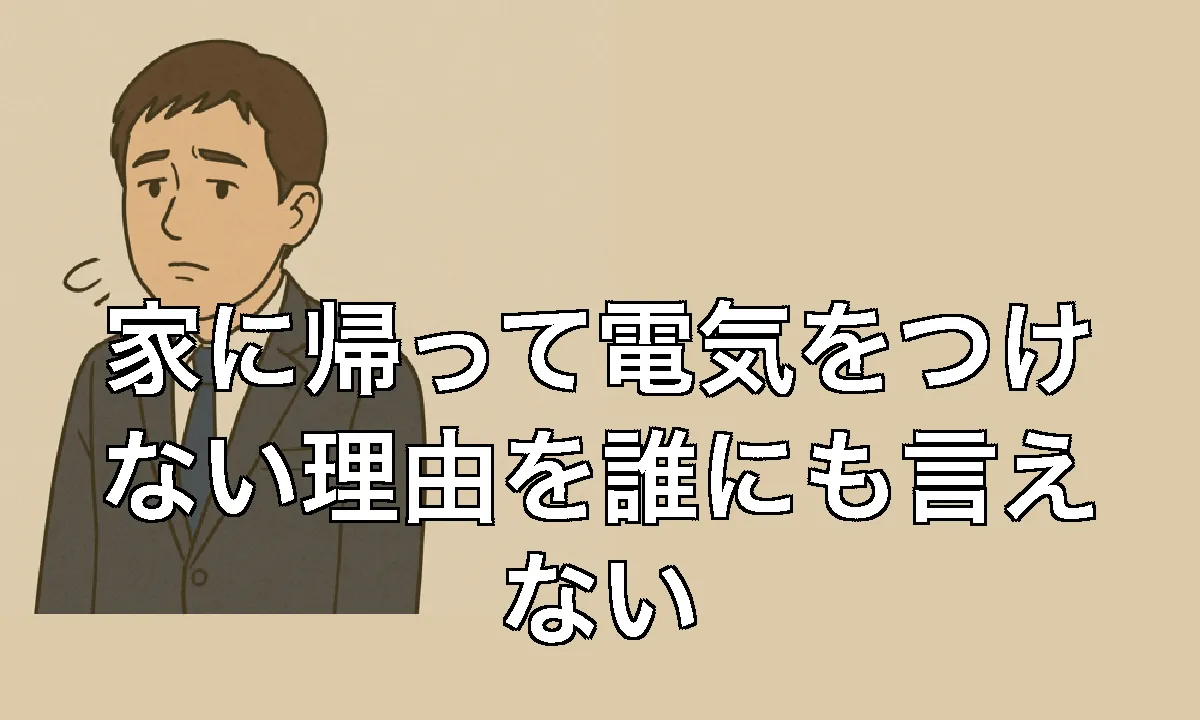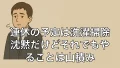電気をつけない帰宅が当たり前になった
仕事を終えて家に帰ると、まず玄関の鍵を開けて、そのまま暗闇の中を歩く。靴を脱ぎ、カバンを置き、スーツのジャケットを脱いでも、照明のスイッチには手が伸びない。そんな夜が増えている。昔はテレビをつけて、明るい部屋で食事をしていたはずなのに、今では明かりをつけることすら面倒になった。特に何かをするわけでもなく、暗い部屋でそのまま床に座り込み、ただ息を吐く。理由なんて聞かれても、うまく説明できない。けれど、電気をつけたくない。それだけははっきりしている。
いつからか部屋の明かりが煩わしくなった
部屋の明かりが、まぶしいと感じるようになったのはいつからだろう。明るさが、自分の疲れや空虚さを強調するようで嫌になったのかもしれない。仕事でクタクタになって帰ってきたとき、蛍光灯の白々しさが、どうにも受けつけられなかった。まるで「おかえり」と言う代わりに、「今日も何も変わらなかったね」と冷たく照らしてくるような気がした。テレビの音も煩わしく、BGMすらつけずにただただ暗闇に包まれる時間。そんな日が続くうちに、自然と「明かりをつけない」という選択が習慣になっていた。
事務所の蛍光灯の光で一日分のまぶしさは十分
事務所では朝から晩まで書類とパソコンに向き合い、蛍光灯の真下で目を酷使する生活だ。あの冷たい光は、作業には必要かもしれないが、心にはなんの癒しもくれない。電話の応対、役所とのやりとり、登記申請のミスチェック。神経を張り詰めたまま、気づけば外は真っ暗。ようやく業務が終わって帰ってきたとき、もうこれ以上、光はいらないという気持ちになる。まぶしさは、十分に足りている。いや、むしろ過剰なくらいだ。
机の上の書類とPCの画面で目も心も疲れ果てる
パソコンの画面と向き合う時間が長くなると、目の奥がズーンと重くなる。とくに細かい不動産の相続登記や会社設立の手続き書類を扱っていると、神経がすり減っていくのが分かる。間違いが許されない仕事ゆえに、確認に次ぐ確認。目で見て、心で疑って、また確認。そんな繰り返しに疲れ果てて、家に帰るころには「もうなにも見たくない」と思ってしまう。明かりをつけないのは、もしかすると目を閉じたままでもいたいという、無意識の拒絶反応かもしれない。
ただの疲れでは片づけられない気持ちの正体
単なる「疲れ」なら、シャワーを浴びて、少し寝れば回復するはずだ。でも、最近のこれは違う。肉体よりも、心が重たい。そう感じる日が増えた。やるべきことは山ほどあるのに、気持ちがどうにも動かない。明かりをつけて、洗濯して、食事をして、片づけて…その「普通の生活」の一つひとつが、まるで山を登るように感じられる。やらなきゃいけないと分かっていても、体がついてこない。そしてまた、電気もつけずにじっと座る夜が始まる。
やることは終わらないのに感情は空っぽ
仕事をしていても、どこか「無」の状態に近い。朝はメールチェック、昼は顧客対応、夕方は申請書類の作成、そして夜は疲れきってデスクに突っ伏す。頭では「これもやらなきゃ」「明日までに出さなきゃ」と分かっているのに、心がまるで反応してくれない。感情の電源が切れたみたいな状態だ。こういうとき、誰かに「がんばって」と言われても、逆に空しさが広がる。電気をつけない部屋でじっとしていると、自分の感情が空っぽであることをようやく認められる。
ひとり事務所経営の重みがじわじわくる夜
司法書士として独立してもう十年以上経つが、結局ずっと一人きりで走り続けてきた。事務員はいるけれど、経営の判断や責任はすべて自分に降りかかってくる。誰にも相談できず、誰にも甘えられない。ミスすれば信用が落ちるし、手を抜けばお客さんが離れる。そんな張り詰めた緊張感のなか、なんとか今日も乗り切ったと思ったとき、家に帰って明かりをつける気力もなくなっている。電気すら重たい。そんな夜が、自分の生活には何度も訪れる。
誰にも頼れないのは自由と引き換えの孤独
自由にやりたくて開業した。誰にも指示されず、好きなように仕事ができる。でも、その裏側には「誰にも頼れない」孤独が潜んでいる。事務所の光が消えた後、相談する相手も、悩みを吐き出す場所もない。SNSで誰かの成功報告を見れば、余計に虚しさが押し寄せてくる。自分の部屋くらい、せめて無音で、無光であってほしいと願ってしまうのは、その孤独をごまかすためなのかもしれない。
明かりをつけない時間がくれるもの
けれど、電気をつけない夜にも、少しだけ救われる感覚がある。明かりがないからこそ見えてくる自分の内側。何も隠せない暗闇の中で、自分の弱さや本音にようやく触れられる。ごまかすためのテレビも、気を紛らわせるスマホも開かず、ただ静かに息をする時間。目を閉じれば、外の虫の声や、冷蔵庫の低いモーター音すら、やけに愛おしく感じる。誰かと分かち合える日が来たら、この感覚も話せるのだろうか。
照明がないからこそ聞こえる心の音
暗い部屋に身を置いていると、心の奥に沈んでいた声がふっと浮かんでくる。「本当はどうしたいのか」「今、何に疲れているのか」。明かりのある場所では気づけなかったことが、暗がりでは不思議とクリアになる。誰かに話すわけでもなく、自分との会話が始まる。泣きたくなるようなときもあるけれど、それすらもどこか心が動いている証拠のようで、少しだけ安心する。光がないからこそ、心の微細な揺れを感じられるのかもしれない。
暗闇に沈んだ部屋と自分だけの会話
明かりを消した部屋に寝転びながら、天井も見えない暗闇の中、自分自身に問いかける。「今日、ちゃんとやれたか?」「このままでいいのか?」。答えなんて出ない。けれど、問いかけること自体が、なんとなく大事なことのような気がする。電気がついていたら、きっとテレビをつけてごまかしていた。スマホをいじって現実逃避していた。そうじゃない、真っ暗な部屋で、自分とだけ向き合う時間。それが、今の自分には必要な気がしている。
たった一人の帰宅に意味を持たせたい
誰もいない部屋に帰るたび、「今日もまた独りか」と思う。だけど、ただの孤独で終わらせたくはない。せめて、その孤独に意味を持たせたい。誰かと住んでいたら、電気をつけるのが当たり前になっていたかもしれない。でも今の自分は、ひとりだからこそ味わえる「静けさ」を知った。明かりのない帰宅が、少しずつ自分をリセットしてくれているような気がする。そう思えるようになったことだけが、今の救いかもしれない。
明かりをつけるその一歩がまだ遠い
いつかまた、「ただいま」と言って明るい部屋に入れる日が来るのだろうか。誰かと暮らす未来を想像することもあるけれど、それはまだずっと遠い夢のようなものだ。仕事は忙しく、人間関係も広がらないまま、年だけを重ねている。だから今日も、スイッチには触れずにソファに腰を下ろす。それでも、まったく真っ暗じゃない。窓の外から漏れる街灯の光、隣家の生活音、それらがほんの少しだけ、孤独を照らしてくれる。
それでも今日も仕事は誰かのために
電気をつけない夜が続く中でも、仕事だけは止められない。誰かの相続、誰かの登記、誰かの不安を少しでも軽くするために、明日もまた事務所の電気はつけるだろう。家の電気はつけなくても、人の人生の「明かり」に関わる仕事をしている。その事実が、唯一自分を保ってくれる理由だ。だから、今日も誰かの役に立つために働く。そのための孤独であり、そのための暗闇なのだと思うことにしている。