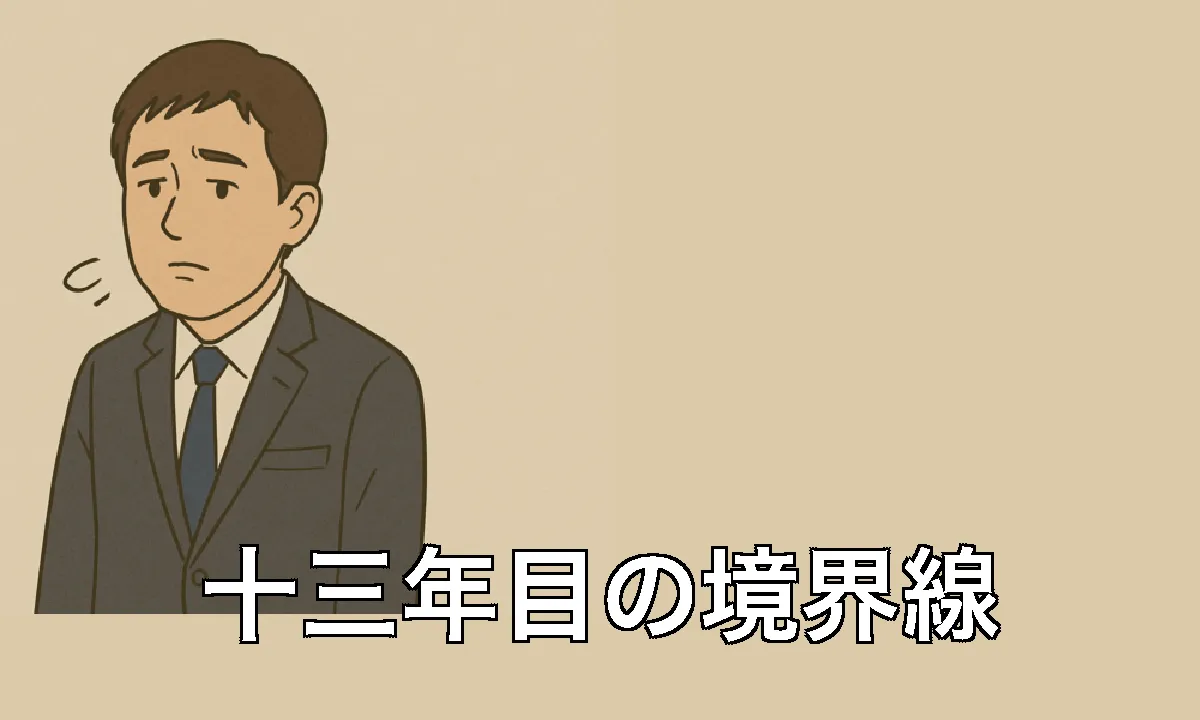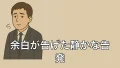境界杭が消えた朝
その朝、町内の端にある農道に一本の杭が足りないと騒ぎが起きた。境界を示す赤いプラスチック杭が、誰の目にも明らかに抜かれていたのだ。農業法人と個人所有の地目の境界だと聞けば、それは些細では済まされない。
連絡を受けた私は、眠い目をこすりながら現場に向かった。秋風が肌寒く、境界杭のあったと思われる地面にはまだ新しい土の乱れが残っていた。
静かな町に走るささやき
こういう話題はすぐに町中に広まる。中でも噂好きの理事長が「ついに境界争いが始まったか」と言いふらしていた。サザエさんの波平が隣の家と塀の位置で喧嘩する回を思い出す。あの回は結局、境界は二人の心の中にある、なんて締めくくりだったが、現実はそう甘くない。
農地の所有権を巡る争いは、笑い話にはならない。特に、そこに十三年という年月が絡んでいるとしたら。
年季の入った農家の顔
地主の中村氏は八十に近いが、目は鋭く、口調は若い頃のままだという。彼は言った。「あの土地はうちのもんだ。十三年、草刈りもしてきた。文句あるなら証拠を持ってこい」
私は一瞬戸惑った。たしかに占有を続けていたなら、取得時効という可能性はある。しかしその場合、善意無過失であったことを証明する必要がある。
相談室に差し込む秋の光
事務所に戻ると、サトウさんがコーヒーを片手に待っていた。机の上には地積測量図と公図が広げられている。さすがだ。私が現地で震えている間に、すでに下調べが始まっていた。
彼女は言った。「シンドウさん、境界確認書があるにはあるんですけど、なんだかおかしいんですよ」
サトウさんの冷静な眼差し
彼女の指が示したのは平成二十四年に交わされた境界確認書だった。一見、問題はなさそうに見えるが、隣地の署名が妙に雑で、印影が二重になっていた。「誰か、あとで押し直してません?」
私は眉をひそめた。なるほど、押印は確かに不自然だ。そして、この時期は中村氏が農地を借りていた頃とも一致する。
三筆の土地と一つの謎
土地は三筆に分かれているが、実際には一続きに使われていた。中央の筆が問題の土地だった。登記上は隣人の所有だが、使用実態は中村氏の方が強い。
境界確認書が偽造されている可能性が浮上する。つまり、杭を抜いた者は真実を知っていた上で、時間を巻き戻すような工作を試みたのではないか。
境界確認書のゆがみ
私たちは市の農業委員会へ足を運んだ。過去の使用履歴、農地法の許可申請、地元の証言。それらを突き合わせると、境界確認書が後日作成された可能性が濃厚になった。
それはつまり、取得時効を成立させるための「根回し」だったのかもしれない。
書類の隅に潜む矛盾
境界確認書の日付は平成二十四年。しかし、そこに添付された写真の撮影データには平成二十五年の日付が刻まれていた。つまり、書類の体裁を整えるために後から証拠を足したのだ。
やれやれ、、、。またこのパターンか。サトウさんが静かに、しかし呆れた声でつぶやいた。
あの時押した印鑑の正体
私は市役所の印鑑証明簿を照合し、確認書の署名者が実際には亡くなっていたことを突き止めた。日付上は、生きていたことになっているが、死亡届はその数日前に出されている。
つまり、その印鑑は家族が勝手に使った、もしくは誰かが代筆した。そこに中村氏の指示があったかどうかは定かではない。
十三年という数字
法律上、民法162条では占有が20年、あるいは10年(善意無過失)で取得時効が成立するとされる。だが中村氏の占有は13年。微妙なラインだ。
これに書類偽造の疑いが重なると、時効の成立はおろか、逆に損害賠償を請求されかねない。
登記簿では語れない事実
登記簿には所有権しか載らない。だが実際には、使用の実態、境界の取り決め、土地への思いまでが渦巻いている。それを法的に整理するのが、私の役目だ。
とはいえ、こんな面倒ごとをなぜ毎回引き受けるのか、自分でもわからない。
やれやれ、、、結局こうなる
カフェインの効き目も切れた午後、私はうっかりコーヒーをこぼして書類を濡らしてしまった。サトウさんは無言でハンカチを差し出してくる。やれやれ、、、本当に助かる。
だが事件は、ここから一気に解決に向かったのだった。
杭を抜いた者の目的
翌日、現場近くの防犯カメラ映像を確認した。杭を抜いたのは、なんと中村氏の孫だった。彼は言った。「じいちゃんがあそこは自分のものだって…証明しろって…」
つまり、法的には無理があるとわかっていたが、心理的な所有感を信じていたのだ。
裏山で見つけた古い赤杭
撤去された杭は裏山の竹藪に隠されていた。それも二本。一本は古く、一本は新しい。つまり、誰かが既存の境界を動かそうとした形跡がある。
それは一種のアリバイ工作。だがそれが仇となった。
隣人の語らぬ過去
隣人である旧地主は語らなかったが、実際には数年前に中村氏に無償で貸していたことがあった。契約書はない。しかし、当時の地元新聞に「農地協力」として名が出ていた。
これが決定的な証拠となった。
取得時効と善意のトリック
中村氏は、当初から土地が他人名義であることを知っていた。そのため「善意無過失」には該当せず、取得時効は成立しない。
逆に、偽造の疑いと損害の訴えで立場が不利になっていく。
占有とは何かという闘い
「使っていた=自分のもの」という思い込みは、登記の壁を越えるには弱い。事実と法のギャップを埋めるには、誠実さと証拠がいる。
今回、それが欠けていた。
「知らなかった」が武器になるとき
もし中村氏が本当に知らなかったなら、あるいは結果は変わっていたかもしれない。しかし彼は、所有権を「知った上で」行動していた。
それは武器ではなく、重荷だった。
最後の現地調査
争いの終わりは、静かだった。私は境界立会いに同行し、関係者たちと無言で杭の位置を確認した。そこには、十三年分の埃がたまっていた。
風が吹き、落ち葉が一枚、杭に絡まった。
立会いの沈黙と視線
誰も何も言わなかった。ただ、お互いの視線が杭の上で交差していた。そのときだけは、法も感情も、存在を消していた。
静かな合意。それが一番の和解だった。
杭の記憶とカラスの鳴き声
上空を横切ったカラスが一声鳴いた。まるで、幕が下りたことを告げるように。
「この杭は、十三年分の記録だ」私はつぶやいた。
真実は証明書の外にある
事件は終わった。しかし、そこにはどこにも記録されない真実があった。誰かが譲り、誰かが諦め、誰かが杭を抜いた。
それでも、土地は動かない。人の心だけが揺れていた。
一通の古い手紙
中村氏の仏壇の引き出しから、古い手紙が見つかった。亡き隣人からの礼状だった。「農地を使ってくれてありがとう。いずれお返しできるといいね」
私はそっと目を伏せた。時効取得では語れない、あたたかなやりとりだった。
風の中でほどけた嘘
証拠はないが、確信がある。中村氏は、自分の正義を信じていただけなのだ。そして、その正義が法に敗れただけだった。
風が吹き、全てを洗い流していった。
そして誰も杭を打たない
和解が成立したことで、新たな杭は打たれなかった。皆が、そこに杭があると信じることで終わりにしたのだ。
目に見えない線。だがそれこそが本物の境界かもしれない。
争いの余白に残る影
私は報告書を書きながら、ふと思った。争いは終わったのか、それとも始まりもしなかったのか。
影は、静かに事務所に戻ってきた。
一筆書きの和解文
サトウさんが差し出した和解文には、まるで詩のような簡潔さがあった。「双方、今後の境界については争わないものとする」
それがこの町の、やさしい決着だった。
午後のコーヒーと報告書
書類の山と静寂の中、私は椅子にもたれた。事務所の壁掛け時計が午後三時を告げる。
少し冷めたコーヒーを啜ると、カップの底に苦味が残っていた。
サトウさんの冷たい一言
「次は境界じゃなくて、心の距離でも測ります?」とサトウさんが呟いた。私は苦笑いした。たしかに、心の杭を打つ方が、よほど難しいかもしれない。
「やれやれ、、、こっちはまだ十三年どころか、ゼロ歩目ですけどね」
また一つ増えた裏話
報告書の最後に、小さな付箋を貼っておいた。「今回の件、誰にも話すなよ」と。だが私は知っている。サトウさんは、こういう話を酒の席でよく使うのだ。
司法書士の仕事は、法の裏で物語を紡ぐことなのかもしれない。