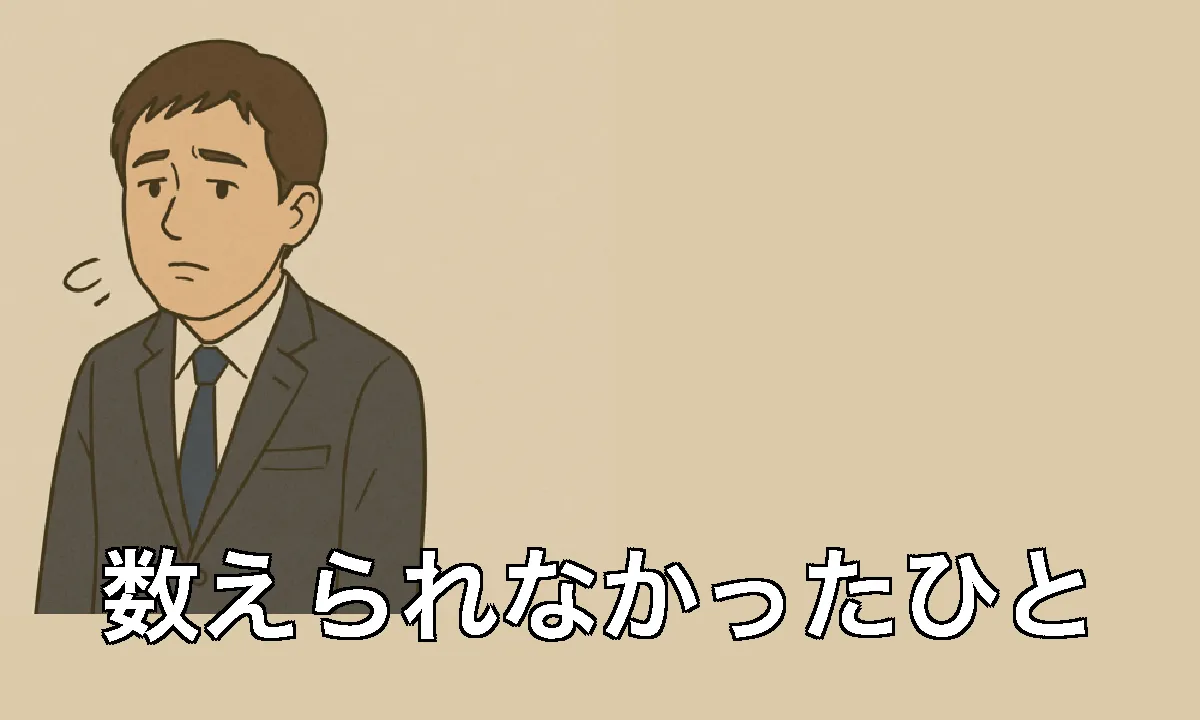登記簿に現れない名前
その案件は、市役所からの一本の電話で始まった。
「旧町域の空き家登記、相続人不明につき相談したい」
役所の言葉はいつも曖昧で、ぼんやりと霧がかかっている。だが今回ばかりは、その霧の奥に何か不穏なものが見えた気がした。
通知の届かなかった相続人
名義人は十年前に亡くなっている。だが、相続人の登記が一切行われていない。
通知を出しても返ってくるだけで、連絡先は不明。唯一の手がかりは「長男がいたらしい」という近所の噂だけだった。
いわゆる不在者相続案件。いや、それでも通常ならば戸籍の追跡でなんとかなる。
町外れの空き家と一枚の名簿
調査のため、僕は町外れの空き家へ向かった。
サトウさんは「お一人でどうぞ」と、そっけない塩対応で鍵だけを寄越した。
玄関の隅に、古びた町内会の名簿が落ちていた。最後の行だけ、名前が書かれていないのが妙に気になった。
サトウさんの無言の視線
戻ってきた僕を、サトウさんは無言で睨んでいた。
「何も手がかりがなかった」と僕が言うと、彼女は名簿を覗き込んでぽつりと言った。
「この空欄、計算が合わないんですよ。世帯数と世帯主数が、ひとつずれてる」
まるで名探偵コナンが言う「真実はいつもひとつ」とでも言い出しそうな切れ味だった。
九人と一軒分の謎
確かに、名簿には十軒分の住所があるのに、記載されている名前は九人分だった。
ひとつだけ、番地の下に「記録なし」の文字。
その住所が、件の空き家だった。数字の不一致。それは司法書士としてもっとも嫌な違和感だった。
それは登記か統計か
この案件は相続登記だ。だが、名簿や世帯数といった「統計」的資料も重要な鍵になっている。
登記簿上は存在していない人間が、現実にはそこに暮らしていた可能性。
住民票すら存在しない者が家を相続していたとしたら……それはまさに、「数えられなかったひと」だ。
不在という名の存在
サザエさんの家族なら、とっくに波平が「こらカツオ」と一喝して片がついている。
だが現実はそう甘くない。誰かが意図的に一人の存在を消したのか、あるいはその人が消えたのか。
不在とは、物理的なことではない。記録から名前が消えることで、人は社会的に「いないこと」にされる。
役所の数字が合わない理由
市役所に戻り、過去の統計資料を引っ張り出す。
五年前の資料には「世帯数10、人口33」とある。しかし、二年後には「人口32」に変わっていた。
死亡届は出されていない。転出記録もない。それでも数字が減っていた。
実在するのにいないと言われた男
調査の末、かつてその空き家には“兄”がいたことがわかった。
だが、戸籍には彼の存在はない。出生届を出さず育てられた影のような存在だった。
兄は数年前に病死し、その遺体は弟によって火葬されたが、すべてが非公式だった。
番号の飛び方が示すもの
登記簿を見返すと、申請番号の連番に不自然な飛びがあった。
ひとつだけ欠番となっている番号が、ちょうどその家に対応していたことが判明した。
記録が消されたか、そもそも提出されなかったか。どちらにせよ、人為的な「空白」だった。
やれやれと僕は頭をかいた
やれやれ、、、何をやってるんだろうな、俺は。
司法書士というのは、もっとこう、地味に書類を黙々と片付ける職業だったはずだ。
それがいつの間にか、行方不明者の人生を掘り返すような真似をしている。
空欄にペンを走らせたのは誰か
記録に穴が空くとき、それはミスではない。誰かがそう「した」のだ。
名簿に空欄を作り、住民票を出さず、出生届を出さず、それでも一緒に暮らした兄。
その弟は、兄が死んだあとも黙っていた。だが今、数字の不一致がその存在を告げている。
最後の証明は司法書士に託された
証明はできる。非公式な火葬記録、名簿の空欄、消えた申請番号。
すべてが合わさり、そこに一人の人間がいたことを指し示している。
僕は「不在者相続人の存在を認定する」ための法定相続情報一覧図に、彼の名前を記入した。
数字の外に取り残された真実
人は、数字では測れない。だが数字の裏に、人の営みがある。
今回のように、数の違和感が、消された人生を照らすこともある。
サトウさんがぽつりと呟いた。「この仕事、結局は人間を見てるんですね」
静かな引っ越しと静かな結末
空き家は、市の事業で取り壊されることになった。
兄の名は、ようやく一枚の紙に記された。誰にも知られず、誰にも褒められず。
けれど、それでよかったのだろう。少なくとも彼は、もう「数えられた」のだから。