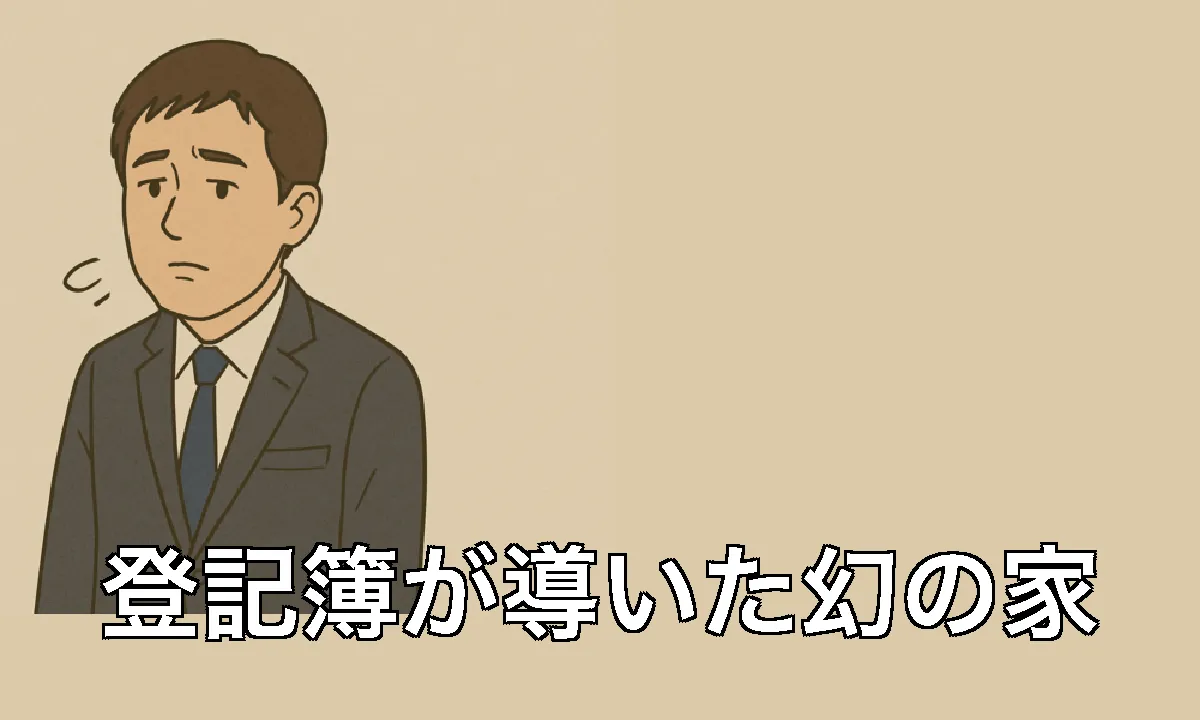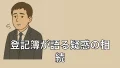依頼人は突然に
朝のコーヒーを一口飲もうとした矢先、玄関のチャイムが鳴った。時計はまだ九時を回ったばかり。飛び込みの相談にしては早すぎる。
扉を開けると、緊張した面持ちの中年女性が立っていた。手に握られていたのは、黄ばんだ登記簿の写しだった。
「この家、どこにもないんです」と彼女は言った。まるで幽霊屋敷の話でもするように。
朝一番の来客
「家が…ない、とは?」と聞き返すと、女性はうなずいた。古い登記簿に記載された住所に行っても、現地には空き地しかなかったという。
登記上はまだ建物が存在し、所有者も亡くなった祖父になっている。それなのに、実際には何もない。
どうやら話は、ただの未登記問題ではなさそうだ。
失われた記録の謎
登記簿の写しを見ながら、私は一つ気になる点を見つけた。昭和49年の保存登記のあと、なぜかそれ以降の動きが一切ない。
固定資産税の課税記録とも一致しない。つまり、法務局も市役所も、その家の存在を忘れているのだ。
「幽霊屋敷」ではなく「幻の家」か。これは少し面白くなってきた。
古びた登記簿
私は法務局に足を運び、原本の閉鎖登記簿を確認した。そこにあったのは、やはり同じ住所と、同じ筆界。
しかし、唯一の違いは「仮登記」の痕跡だった。昭和50年代初頭、なにかが確かに起こっていた。
それが抹消された理由も、記録の中にはなかった。
法務局で見つけた違和感
普通なら登記原因の書類があるはずの欄に、線が引かれていた。白紙のまま、無かったことにされている。
「これは一種の隠蔽かもしれません」と私がつぶやくと、隣でサトウさんがため息をついた。
「先生、陰謀論に行く前に、資料整理してください」塩対応だった。
所有権移転の空白
登記の移転があったはずの時期に、何も記載がない。つまり誰かが手続を途中で止めた、または意図的に遅らせたということになる。
だとすれば、その動機は何か。考えられるのは、相続を巡る争いか、あるいは税逃れのための偽装登記だ。
サザエさんで言えば、波平さんの隠し子が家を狙ってきた感じだろう。いや、そんな話は昼ドラすぎるか。
塩対応の推理
私が案件の複雑さに唸っていると、サトウさんが静かに地図を差し出した。「この地番、実は隣町とまたがってます」
彼女の調査によると、昭和の区画整理の際、住所表示と登記地番が一致しなくなったとのことだった。
つまり、「幻の家」は本当にそこに存在していたが、地図上では消されていたというわけだ。
サトウさんの冷静な指摘
「これ、単なる登記ミスじゃないですか?」サトウさんの言葉は淡々としていたが、その指摘は核心を突いていた。
人為的なミスが、数十年の空白を生んだというわけか。まるでコナンのように論理的で、私は少し悔しかった。
「やれやれ、、、助手にしておくにはもったいないな」と、思わずつぶやいた。
昭和の地図が語る真実
古地図を照らし合わせると、登記簿上の「幻の家」は現在の駐車場の真下にあたることが判明した。
土地の所有者は、依頼人の祖父のままだ。つまり誰かが無断でその土地を使っていた可能性が高い。
どうやら、事件の本質は「家の謎」ではなく「土地の不正利用」に移りつつあるようだった。
幻の土地と実在の人物
私は登記簿の旧所有者からの相続人調査を進めた。やがて、関東に住む一人の男性が浮かび上がった。
彼は依頼人の叔父にあたり、現在その土地を管理している駐車場業者の代表でもあった。
これが偶然であるはずがない。
見えない所有者の正体
実はその叔父、祖父の死後、勝手に管理を名乗り、土地の使用料を受け取っていた。だが登記上の名義は変えず、相続登記も放置。
つまり彼は、相続人を出し抜き「幽霊土地」を現金化していたのだ。まるで現代の怪盗ルパンである。
「怪盗土地男…とか名乗ってたら漫画になるのに」と私は苦笑した。
登記と実在のズレ
この事件が教えてくれたのは、「登記がすべてではない」ということだ。だが同時に、「登記がなければ何も守れない」現実でもある。
依頼人は涙ぐみながら、「祖父の土地が戻ってくるなら、それだけで充分です」と言った。
法の隙間で人の善意が食い物にされることは、決して珍しくないのだ。
意外な訪問者
数日後、事務所に現れたのは、あの叔父本人だった。彼は何も言わず、古びた謄本と判子を机に置いた。
「もう、疲れたよ」とつぶやきながら去っていった背中は、妙に小さく見えた。
正義とは、時に重い。
町の古老が語る記憶
その日、私は町の古老に話を聞いた。あの家は、戦後すぐに建てられ、地域の人の集まる場所だったらしい。
祖父は人望があり、町内のまとめ役でもあった。幻の家が、記憶の中では確かに存在していた証だ。
「昔は良かった」という言葉に、私は何も返せなかった。
隠された相続の影
叔父が書いた上申書には、こう記されていた。「父の死後、遺言もなく、何が正しいか分からなかった」
結局、人は「分からないこと」に蓋をしながら生きている。そして蓋を開けると、こんな風に埃が舞う。
司法書士の仕事は、その埃を丁寧に払うことなのだろう。
登記簿の罠
今回は「登記簿通り」だったことが、かえって混乱を招いた。法的な正しさと、現実との乖離が大きすぎた。
登記は嘘をつかない。ただ、更新されなければ「真実を黙る」だけなのだ。
まるで、口を閉じた証人のように。
二重登記という落とし穴
途中で見かけた仮登記は、実は叔父が行った「保全措置」だった。表向きは正当、でも中身は不完全。
結果的にそれが、他の相続人を混乱させ、長年の空白を生んだ。
あらゆる登記の影には、人間の事情がある。
そこにあったはずの家
今はもうない、幻の家。だが祖父の想いと共に、その土地は家族に戻った。
私は、依頼人に報告書を手渡しながら思った。「これが仕事だ」
それでも、サトウさんに「先生、書類まだです」と叱られるのは変わらない。
夜の決断
その夜、私は一人で駐車場跡を訪れた。月明かりの下、地面にはかすかな土台の跡が残っていた。
「ここに、誰かの人生があったのだ」と実感した。
風が吹き、秋の気配が静かに忍び寄っていた。
手がかりは一枚の古写真
依頼人が持ってきた古いアルバムには、家の前で笑う家族の写真があった。
それが「家があった証拠」として、心の中に深く残った。
記録とは、必ずしも紙の上にあるとは限らない。
謄本の裏側に潜むもの
最後に確認した閉鎖登記簿の裏に、鉛筆で走り書きされた住所変更のメモがあった。
それはきっと、祖父が生前に書いたものだろう。正式な申請に至ることはなかったが、彼の想いはそこに残っていた。
書類の隙間に、人の人生がにじんでいる。
法廷ではなく現場へ
今回の件は、裁判にも調停にもならなかった。すべて現場で、地道な調査と調整で解決した。
それこそが、司法書士の腕の見せどころなのかもしれない。
どんなに地味でも、誰かの人生を取り戻す仕事には違いない。
現地調査という名の冒険
泥だらけになって測量テープを巻き直す私を見て、サトウさんが苦笑いした。
「先生、もう少しスマートにできません?」その一言に、私は苦笑いを返した。
やれやれ、、、これが現場主義というやつだ。
サトウさんの一手
結局、最後の決定打になったのは、サトウさんが見つけた納税通知書だった。
それが証拠となり、すべてのピースが揃った。
私は心の中で、助手にして名探偵と敬礼した。
終わらない書類仕事
事件が終わっても、事務所の机には書類の山。決してミステリーは終わらない。
次の依頼人が来るまでに、少しは片付けておきたい。……たぶん無理だけど。
それでも今日も、この仕事をやっていて良かったと思うのだった。
日常に戻る司法書士
「先生、昼はカップ麺でいいですね?」いつもの塩対応が、なぜか少しだけ優しく感じた。
「ああ、それでいいよ」私は書類をめくりながら答えた。
静かな午後が、また始まろうとしていた。
サトウさんのため息
「…ところで、この書類のファイル名が’最終版’ってついてるのに三つありますけど」
「やれやれ、、、それはたぶん、過去の俺の残骸だな」
事務所には、今日も平和なようで、ちょっとした戦いが続いている。