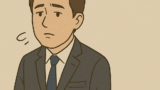依頼人は無口な男
午前十時の事務所
事務所のドアが開いたのは、ちょうどコーヒーに口をつけた瞬間だった。無精髭の男が無言で立っていた。無言のまま、机の前の椅子に腰を下ろす。
「相続の相談を」と、ようやく絞り出すように言ったその声には、どこか怯えたような響きがあった。資料を取り出す手もわずかに震えている。
私はファイルを開きながら、ふと、昔テレビで見た『サザエさん』のノリスケのような優柔不断な人物像を思い出していた。
登記簿に刻まれた名前
提出された登記簿の写しには、確かに依頼人の名前が記されていた。ただし、それは共有者として。そしてもう一人、聞き慣れない名前が並んでいる。
「兄です。でも、二十年以上会ってません」と彼は答えた。その言葉には、説明を拒む意思が込められていた。
私は何も言わずに、静かに登記情報を読み込んだ。土地は父親名義だったが、数年前の遺産分割で兄弟二人の共有名義となっていた。
不可解な相続放棄
兄弟なのに連絡を取らない理由
なぜ相続放棄の話が今になって出てきたのか。遺産分割協議が既に完了していたはずなのに。依頼人の口は重い。
「兄が放棄するとは思えない。でも、もし放棄するなら、それを証明する書類が欲しい」と、つぶやくように言った。
司法書士としての私の仕事は、事実を確認することだ。感情の奥にあるものには踏み込まない主義だ。
法定相続人の欠落
改めて家系図を確認すると、不思議な点があった。兄の存在は登記には反映されているのに、住民票上では十年以上前から所在不明となっていた。
「失踪宣告とかは?」と訊ねると、依頼人は首を横に振る。「家族の誰も手続きしてません」とだけ答えた。
どこかに兄は生きているのか、それとも……その空白が、逆に濃い影を落としていた。
サトウさんの冷たい推理
メモの筆跡が語るもの
「これ、同一人物じゃないですね」サトウさんは、依頼人が持参したメモの文字を一瞥して、淡々と言った。
「本当に兄の字かどうか、確認されました?」という追及に、依頼人は目を逸らした。まるで子供が怒られた時のように。
「やれやれ、、、」思わずため息が漏れた。司法書士という仕事は、時に親でも教師でもない役割まで担わされる。
登記済証の端にある異変
一見、問題なさそうな登記済証だったが、サトウさんの指摘で私は気づいた。裏面に貼られた印紙が、微妙に歪んでいる。
よく見ると、そこには本来存在しないはずの署名がかすかに透けていた。「これ、誰かが上から貼り直してます」とサトウさん。
登記という紙の世界の中に、もう一つの物語が隠されていた。それは、兄が書いたものではなかった。
消えた相続人の謎
過去の住民票をたどって
私は市役所に照会をかけ、兄の過去の住民票履歴を洗った。そこにあったのは、十年前に都内のアパートでの転出記録だった。
「転出先不明」それだけが記されていたが、隣の欄にある電話番号がわずかな手がかりとなった。
私は旧式の公衆電話から、番号を押した。出たのは、高齢の女性だった。「あの子なら、去年亡くなったよ」と、静かに告げられた。
家族写真の中の見知らぬ顔
依頼人が持参した古い家族写真には、三人の子どもが写っていた。だが戸籍上は二人きょうだいのはず。
「これは……?」と問うと、「……いとこです。昔は一緒に住んでたんです」と苦しげに答えた。
本当にそうだろうか。私には、まるで見えない線が彼の心の奥に引かれているように感じられた。
空き家に残された手紙
封筒に残るインクと意図
私は兄が最後に住んでいたというアパートを訪れた。今は空き家で、郵便受けも剥がれ落ちていた。
部屋の片隅に落ちていた封筒には、インクがにじんだ手紙が入っていた。差出人は依頼人。受取人は兄。
内容は短い。「会って話したい」それだけだった。だが返事は、二度と届かなかったようだ。
母の遺志をめぐる嘘
手紙の最後には、こう書かれていた。「母さんの遺言は、兄さんに全部を託すって言ってた」
しかし、実際の遺言書には「兄弟平等に」と明記されていた。依頼人は、そのことを知らなかったのか、それとも……
登記簿には「共有」と記されていたが、心の中ではずっと「奪われた」と思っていたのかもしれない。
やれやれ俺の出番か
元野球部の嗅覚が動く
過去の話と現在の情報を繋ぎ合わせると、一つの構図が浮かび上がる。名義は共有、兄は既に他界、しかし遺言書は存在する。
私の役目は、遺産分割協議の正当性を法的に確認すること。感情の綾はさておき、証拠と手続きが全てだ。
「これ、当時の協議書に兄の署名がないですよね」私は淡々と指摘した。「つまり、未分割状態のままです」
真実は紙の裏に
協議書の裏には、折り目の間にうっすらと鉛筆の跡が残っていた。誰かが書いたが、写し損ねた跡。
筆跡鑑定を依頼したところ、それは兄のものではなかった。サトウさんがぼそっと言った。「つまり、誰かが書いたフリをしたんですね」
その誰かは、目の前に座っていた依頼人だった。だが私は何も言わない。ただ静かに、法的な再手続きを促した。
全ては登記簿の中に
嘘を暴く唯一の証拠
登記簿は嘘をつかない。たとえ人が口を閉ざしても、紙は記憶している。時系列、所有関係、そして過去の手続き。
私は訂正申請とともに、改めて兄の死亡届を提出した。全てを整理することでしか、依頼人は前に進めない。
「全部、書き直しですね」と、依頼人はつぶやいた。それは登記簿の話か、それとも人生の話か。
静かな兄弟の再会
兄の名前が消え、新たな登記簿が作られた日。私は小さな花束を持って、墓前に立った依頼人を遠くから見守った。
風が吹き、花が揺れた。サザエさんのエンディングのように、静かで、少しだけ寂しい余韻が残った。
これが司法書士という仕事の、ある一つの形だ。
サトウさんの一言で幕引き
「だから言ったでしょ」
事務所に戻ると、サトウさんが資料を片付けながら言った。「最初から偽筆っぽかったんですよね」
「うん、俺もそう思ってた……ことにしとこう」私は曖昧に笑って、コーヒーを口に運んだ。
「やれやれ、、、疲れたな」私は椅子に深くもたれかかった。事件が解決しても、机の上の書類は減らないのだった。
依頼人が最後に見せた笑顔
数日後、依頼人から小さな包みが届いた。中には地元の焼き菓子と、短い手紙が入っていた。
「ありがとうございました。ようやく兄に会えた気がします」そこには、あの日にはなかった柔らかい字が並んでいた。
私は黙って、手紙を引き出しにしまった。今日もまた、登記簿の中に誰かの人生が眠っている。