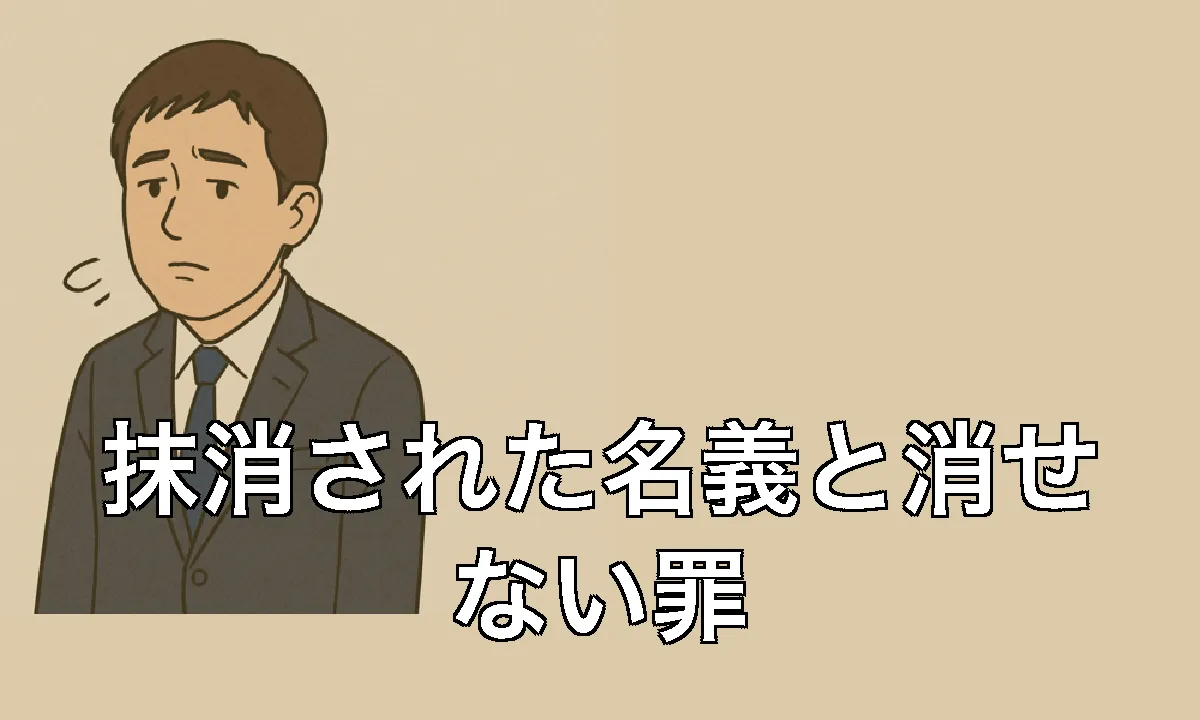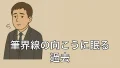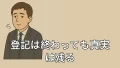午前九時の依頼人
朝一番の事務所に、妙に緊張した様子の中年女性が訪ねてきた。顔色は悪く、手には古びたファイルを握っている。依頼内容は「抹消登記」だった。
不動産の名義を父親の死後に整理したいという話だが、なぜかその言い回しが曖昧だった。いつものようにサトウさんが冷ややかに応対し、私は書類を眺めながら首を傾げた。
「お父様が亡くなられて、何年経ってますか?」と尋ねると、依頼人は答えに詰まった。どうやら、話の裏に何かあるようだ。
サトウさんの冷たい視線
「シンドウさん、これ、なんか変じゃないですか?」とサトウさん。目つきが完全にコナンくんだった。私は言われて初めて、委任状の日付が平成十二年であることに気づいた。
依頼人の父親は、平成十年に亡くなっていたはずだ。つまりこの委任状は、死者の筆跡だということになる。やれやれ、、、朝からこれか。
私は肩を落としながら、ひとまず法務局の登記簿謄本を取り寄せることにした。
過去から届いた委任状
送られてきた登記簿には、確かに依頼人の父親の名義が残っていた。しかし、その後に所有権を移転した記録は見当たらない。
「これ、途中で止まってますね」とサトウさん。謄本に記載されていたのは、中途半端に提出された所有権移転登記の申請だけだった。
つまり、当時の司法書士が登記を完了させていない、あるいは何らかの理由で止めたということか。
二十年前の贈与契約
依頼人によれば、父親が亡くなる直前に土地を譲るという約束をしていたという。しかし書面もなく、記憶も曖昧。これでは登記理由としては不十分だ。
「でも、父が渡したって言ってたんです!」と依頼人は強く主張したが、贈与契約における登記原因証明情報が一切見当たらない。
一方で、その土地はずっと依頼人が管理していたという。真実は果たして、書面の中にあるのか、それとも記憶の中か。
名義抹消の落とし穴
法務局に相談に行ったが、やはり記録の不整合については問題視された。「名義抹消」とは簡単に言っても、それは権利の消滅ではなく、手続き上の整合性が必要なのだ。
しかも提出された印鑑証明書の日付が、父親の死亡日より新しいというオカルト現象まで発生していた。もうこれは、どこかの探偵漫画のネタだ。
「死人が印鑑登録できるなら、うちのばあちゃんも土地持ちだったかもなあ」なんて、ぼやきたくもなる。
印鑑証明の謎
再確認してみると、印鑑証明の発行元は遠方の市役所だった。本人確認が甘かった時代に、偽造されて発行された可能性もある。
「これ、当時の登記官が見逃したのか、それとも気づいてあえて放置したのか」——サトウさんが鋭く指摘する。
その可能性を探るため、当時の登記に関わった法務局職員を訪ねることにした。
登記官との密談
もう定年退職していたその登記官は、私の名刺を見て苦笑いを浮かべた。「まだあの件、出てきたのか」とポツリ。
聞けば、申請時に疑義があり、職権で補正を求めたが、それ以降何の応答もなく、登記を止めたままだったという。
しかし裏では、家族内で名義を勝手に変更する動きがあったようで、確信犯だった可能性が高い。
抹消された記録の記憶
登記官は記録を残していなかったが、当時の相談メモが自宅に残っていた。そこには「娘が勝手に抹消を望む」と手書きのメモがあった。
やれやれ、、、記録に残らぬ記憶が、こうして事件を語るとは。紙一枚で変わる人生、それを知っているからこそ司法書士は慎重であるべきなのだ。
私は静かに頭を下げて、事務所へ戻った。
真実を知る唯一の人物
依頼人の妹が実は真実を知っていた。彼女は現在、父の面倒を最期まで看取った人物でもあり、相続に関する感情が強かったようだ。
「姉が全部持っていこうとしたのよ」妹は淡々と言った。確執は深く、二人は法的整理を一切していなかった。
サトウさんがその話を聞きながら、うっすらと笑った。「人って、相続の時に本性が出ますよね」
家族が隠していた秘密
父親が亡くなる直前に手紙を遺していたことが判明した。それには、土地のことも、娘たちの将来についても記されていた。
しかしその手紙は、妹の手によって隠されていたのだ。自分の立場が不利になると感じたからだろう。
真実を語らぬまま、抹消登記だけを依頼された理由がここにあった。
閉じられた家に残る証拠
空き家となった旧宅に、登記識別情報通知が残っていた。古い封筒に入ったそれは、決して誰のものでもないように放置されていた。
証拠が残っていたことにより、抹消登記の正当性がさらに疑われる形となった。私の役目は、それを判断することではない。
ただ、事実と手続きの整合性を担保すること。それが司法書士としての仕事だ。
古びた登記識別情報通知
破れかけた紙片に、かすかに印字された番号。手が震える。これがもし正当なものであれば、全てがひっくり返る。
依頼人に確認を求めたが、「覚えていない」としか返ってこなかった。嘘か真か、もう誰にも確かめることはできない。
それでも、この情報が決め手となり、私は登記申請を止めることにした。
名義は誰のものだったのか
登記上は依頼人の父の名義だが、実質的な管理は依頼人だった。しかし法的手続きが整っていなければ、それはただの占有に過ぎない。
「気持ちはわかるけど、登記は気持ちでは変わらないんです」私はそう言いながら、書類を返した。
依頼人は無言で立ち去った。振り返ることもなく。
故人の意志と現実
遺言があれば救われたのかもしれない。話し合いができていれば、こんなにこじれなかったかもしれない。
だが現実は、誰もが手続きを避け、感情で物事を処理しようとした結果だった。
その代償は、誰か一人がすべてを背負うことになる。
司法書士としての決断
私は登記の受任を断った。「抹消できないものもあるんです」そう告げて、深々と頭を下げた。
サトウさんがいつものように無言で頷いた。事務所に戻ると、電話が三件も鳴っていた。
やれやれ、、、こっちの方が事件だよ。
遺された者の責任
誰かが動かなければ、記録は永久に眠る。だがそれは司法書士の仕事ではない。人間としての良心が問われる領域だ。
私はそっと手帳に「受任不可」と記し、そのページを閉じた。
またひとつ、記憶の中にだけ残る事件が増えた。
名義を越えた想い
登記が消えても、想いは消えない。名義が誰のものであっても、そこに込められた感情は残り続ける。
法では裁けない部分が、人の人生には存在するのだと改めて思う。
そして私はまた、次の案件へと歩み出す。
最後に笑ったのは誰か
結局、誰も得をしなかった。ただ、サトウさんが一言だけ笑った。「今回はややこしい相続人がいなくてマシでしたね」
そう言って机に戻る姿に、ほんの少しだけ救われた気がした。
司法書士という職業が、どこか探偵に似ていると感じた瞬間だった。