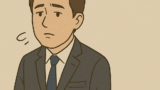不動産取引の相談に現れた男
昼下がりの事務所に、やたらと目立つアロハシャツの男が現れた。日焼けした肌にサングラス、まるで南の島から帰ってきたルパン三世のような風貌だ。男は不動産の名義変更について相談したいと言い出した。
「書面はないけど、ちゃんと約束はしてたんですよ」と言う男に、シンドウはすぐに眉をひそめた。司法書士にとって“書いてない”という言葉は、もはや戦争の火種だ。
一枚の契約書の不在
男が言うには、亡くなった母親が生前、「この土地はお前のものだよ」と言っていたという。しかし正式な遺言もなく、契約書もなし。つまり、証拠がない。
「うちはね、契約じゃなくて口約束を重んじる家なんですよ」と得意げに言う男に、サトウさんの塩対応スイッチが入った。
サトウさんの冷たい視線
「で、そのお母様のご発言は録音でもされてるんですか?」と、いつもより1.5倍低い声で問うサトウさん。男は「まさか」と笑う。
その瞬間、サトウさんが机の下でため息をついた音が聞こえた。シンドウもつられて肩を落とす。「やれやれ、、、またこれか」と心の中で呟いた。
忘れられた口約束
男はさらに続けた。「母は晩年、認知症っぽくてね。いろいろ曖昧だったかもしれないけど、あの時は正気だったはずだ」と。
その言葉に、シンドウはどこか既視感を覚えた。昔観た『名探偵コナン』のエピソードで、犯人が証拠もないアリバイを主張していた場面を思い出す。
十年前の話
その口約束が交わされたのは、なんと十年前だという。しかもその場には誰もいなかった。まさに“言ったもん勝ち”の世界だ。
司法書士として、法的根拠がないものに与するわけにはいかない。しかし、このまま断ってしまってよいのだろうか。
おばあちゃんの言葉を信じた理由
男は涙を浮かべながら語った。「あれだけ苦労して育ててくれた母が、俺に嘘をつくはずがない」。その姿に、シンドウはふと亡き母を思い出していた。
口約束。それは確かに、法では測れない重さを持つことがある。しかし現実は、言葉だけでは登記はできない。
登記申請前夜の異変
その日の夜、ふとした拍子に、男の名前をネットで検索してみた。すると、不動産トラブルのブログに、見覚えのある顔が出てきた。
「この人、過去に同じような手口で親族と揉めていたんだ」。サトウさんが資料を見ながらつぶやいた。予感が現実になる瞬間だった。
シンドウのうっかり
翌朝、目覚めたシンドウは大事なことを思い出した。「あ、あの土地、相続登記が未了じゃなかったか?」と。確認すると案の定、法務局のデータには一件の未処理案件があった。
「うっかりしていたが、これで詰んだな」と思いつつも、手がかりを掴んだことに一抹の満足感があった。
電話一本で狂った流れ
その情報を元に、親族に連絡を取ると、案の定「その土地は私のものだ」と主張する別の相続人が現れた。もはや完全に泥沼だ。
男に伝えると、彼は黙って席を立ち、無言で事務所を後にした。言葉だけの契約では、争いは避けられなかった。
書類にならない証拠
その後も、男からの連絡はなかった。サトウさんは「消えたルパンって感じですね」と冷静に言う。確かに、派手に登場し、静かに消えていった。
事件性はない。詐欺とまでは言えない。しかし司法書士の感覚としては、どこか後味が悪かった。
動き出す調査
シンドウは念のため、法務局の職員に過去の相談履歴を確認した。やはり、同様の相談が3年前にもあったことがわかった。
これで男の話が虚偽である可能性が高まった。だが決定打にはならない。契約書がなければ始まらない。それがこの世界の鉄則だ。
SNSと日記帳
最後の手段として、親族が提供してくれた日記帳を見た。そこには「今日、土地を誰にも渡さないと決めた」と書かれていた。
SNSの投稿も確認されたが、やはり男の話を裏付けるものはなかった。法的にも、そして感情的にも、彼は敗北していた。
サインを拒む男
土地の名義変更は、別の相続人の意向で進められることになった。申請書に男の名前はなかった。
契約書の代わりになるもの、それは信頼だ。しかし信頼は、裏切られた時に何より脆くなる。
契約書に書かれなかった名前
「もしあの時、一筆書いてもらっていれば」。男の呟きが耳に残った。だがそれは、既に遅すぎた“もしも”の世界だ。
言葉だけで成立する契約など、法律の世界では幻想に過ぎない。いや、幻想にしておくべきなのだ。
隠された過去の取引
登記簿を読み解いていくと、さらに数件、親族間での争いが記録されていた。いずれも、口約束が発端だった。
「法務局って、まるで墓場みたいですね」とサトウさんが言う。確かに、失われた信頼の記録が、そこには眠っていた。
サトウさんの直感
「この件、きっとまたどこかで再発しますよ」。そう言って、サトウさんはお茶をすする。淡々としたその表情に、妙な安心感があった。
ルパンのような男がまたやってくるかもしれないが、今度はもう少しうまく対応できる気がした。
喫茶店のレシート
後日、男が最後に立ち寄った喫茶店のレシートが見つかった。そこには「口約束ほど人を信じさせるものはない」と書かれた紙切れが挟まれていた。
「台詞まで残して去るなんて、まるで劇場型詐欺ですね」。サトウさんは皮肉を言いながら、その紙をゴミ箱に投げ捨てた。
手帳のすみに書かれたイニシャル
イニシャル「S.T.」が書かれた手帳が残されていたが、それ以上の手がかりは出てこなかった。まるでキャッツアイの予告状のようだ。
証拠にはならない、だが意味はある。そんな曖昧な“記憶”だけが残った。
言葉を信じた代償
結局、言葉を信じた男は、何も手に入れられなかった。だが、その執念だけは、シンドウの記憶に刻まれていた。
「契約って、冷たいようで優しいんですね」。不意にそんな言葉が浮かぶ。書かれた言葉は、人を守る。
約束と証拠の違い
約束とは、証拠があって初めて守られる。司法書士として、それは痛いほど分かっている。だが人は、それでも言葉を交わす。
証拠にならないものを、人は信じたがる。だからこそ、我々の仕事が必要なのだ。
それでも人は言葉で繋がる
「口約束でも信じたい」。それが人の本音だろう。だが、そこに法律という防波堤がなければ、きっと誰かが沈んでしまう。
シンドウは改めて、自分の役目を思い出していた。書くことで、人を守る。それが司法書士の務めだ。
そして誰も訴えなかった
不思議なことに、この一件において、誰も裁判を起こさなかった。口約束のまま、全員が折り合いをつけて終わったのだ。
ある意味、口約束が最後には効力を持ったのかもしれない。だが、それは偶然という名の奇跡だ。
民事不介入の境界線
シンドウは苦笑いしながら、閉じかけたファイルを手に取った。「民事不介入って、便利だけど残酷ですね」とぼやいた。
やれやれ、、、次の案件もまた、誰かの“言葉”から始まるのだろう。
裁かれなかった裏切り
嘘だったとしても、法が裁かなければ裏切りとはならない。だが、心にはきっと傷が残る。
それを癒すのは、契約書でも、登記簿でもない。人の理解と、少しの希望なのかもしれない。
サトウさんは今日も塩対応
「結局、口約束ってめんどくさいだけですね」。コーヒーを啜るサトウさんが、今日も静かに毒を吐く。
シンドウは、ただそれを聞きながら、黙って机の上を片付けた。次の依頼人がもうすぐ来る。書類の束と共に。
片付けられた茶碗と謎解きノート
昼食の後、茶碗を片付ける手つきまでシャープなサトウさん。その横には、事件メモがびっしり書かれたノートがある。
「どんなにうっかりしてても、最後は帳尻合わせますからね」と言いたげなその文字に、シンドウは少しだけ救われた。
明日もたぶん依頼は来る
世界は、今日も誰かが誰かと約束を交わしている。書いているか、書いていないか、それは時に問題にならない。
それでも、司法書士は書く。明日もまた、契約書の向こうに人間ドラマがあるのだから。